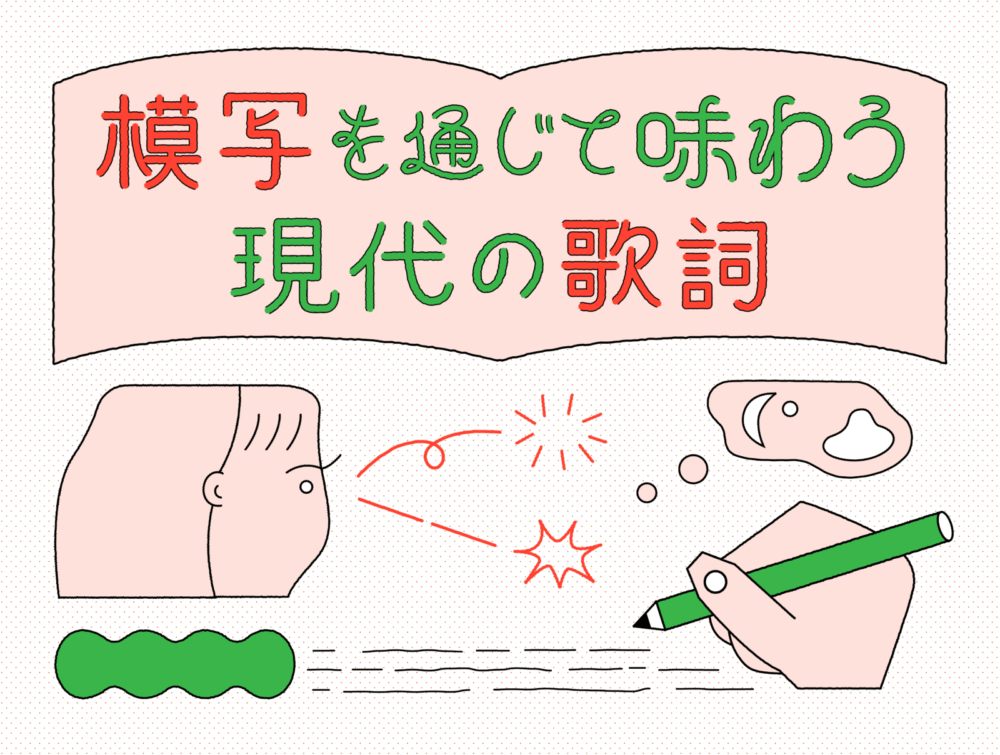「すでにそこにある」不気味さ—立花光による空間展示『壁抜け』【見て跳ぶための芸術 Vol.1】
『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭』と同時並行で開催された公募型アートフェスティバル『KG+』にて展示された立花光の作品『壁抜け』について、その鑑賞体験の「不気味さ」という観点からレビューする。写真を撮る/写真を観る体験そのものを揺さぶる立花の展示は、写真展全体へのひとつの批評たりえていた。
記事企画「見て跳ぶための芸術」は、京都で活動する批評家・森脇透青が、おもに関西を中心として、視覚的なアート表現をリサーチしレビューしていく連載です。このタイトルには「跳ぶ前に見ろ」(イソップ童話)でも「見る前に跳べ」(大江健三郎)でもなく、何かを〈見ること〉がすなわち〈跳ぶこと〉=驚きであり跳躍である、というコンセプトが込められています。
『KG+』で見た立花光の展示
日本でも最大規模の国際写真フェスティバル『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭』はよく知られている。『KG+』とは、このフェスティバルと連動して行われる公募型アートフェスティバルである。『KYOTOGRAPHIE』以上に幅広くジャンル横断的なこのフェスティバルの期間中は、これからの活躍が見込まれるアーティストやキュレーターの展示が京都の市街地のいたるところで展開される。
本編もさることながら、『KG+』に関して言えばその数はさらに膨大であり(その数は100を超える!)、そのすべてを見通す鑑賞者は稀だろう。私もほとんどの展示を見ることなく2024年度の会期を終えてしまったのだが、その中でもぜひ言葉にしたい展示をひとつ見ることができた。東山駅近くに位置する〈gallery16〉で公開された立花光『壁抜け』である。
『壁抜け』が切り取る、どこにでもある風景
1997年生まれの立花は、京都市立芸術大学の美術科構想設計専攻に在籍するアーティストであり、どこか殺風景で非人間的な空間に着目しつつも、独自の観点と工学的手法からそれに切り込むことで制作を展開してきた。『壁抜け』はそのなかでも、立花の空間へのアプローチがかなり純粋なかたちであらわれたものとなっていたように思われる。

展示空間に入ると、鑑賞者はまず異様な光景に出会う。この空間内には四角い箱がただ乱立しているのだ。鑑賞者はその箱に開いた穴から、窃視するようにその内部を覗き見るよう誘われる。その穴の先に鑑賞者が眺めることになるのはただただ、空間だ。それも、「どこにでもある空間」である。

それは、何でもないがゆえに不気味で空虚な空間のミニチュア的再現である。『KG+』の説明には、こう書かれている。「誰もいないホテルの廊下、窓のない地下のプール、レイトショーのあとのショッピングモール、ふと迷い込んでしまった巨大倉庫、開店前のゲームセンター。見る前からすでにあり、あとからあったと知る時空間。傍らにある密室のバックヤード。私たちはそれらへ壁抜けする」。
おそらく多くの読者は、これが近年「リミナル・スペース」と呼ばれ、ネット上で注目を集めてきた空間であることにすぐ気づくだろう。リミナル・スペースとは、特権的になにか目を惹くものがあるわけではない空間である。いやむしろ、見るべきものが不在であり場所が匿名的であることによって、それは居心地の悪さに直結する。どこにでも使いまわされている空間、移動途中の中途半端な場所性こそが、この空間の不気味さを演出しているのだ。
だが、リミナル・スペースへの着目そのものはそれほど珍しいことではない(むしろ、やや過ぎ去りつつある流行のひとつだと言える)。立花の作品の独自性はリミナル・スペースを主題としている点だけではなく、むしろ「写真撮影」という行為に鋭い問題提起を行なっている点にこそある(そもそも、この箱の形状からして、この展示はもっとも原始的なカメラ——カメラ・オブスキュラ——を真似ている)。立花の作品が『KG+』の一環として提示されたことには深い意義があるのだ。
以下ではこれを二点にわけて説明したい。
写真にまとわりつく不安:窃視から盗撮へ
第一に興味深いのは、こうした殺風景な空間をミニチュアで再現し、鑑賞者にそれを覗かせるという構図である。鑑賞者はこの装置を通じてリミナル・スペースを「盗み見る」。穴の向こうに広がる空間へと「壁抜け」するこの鑑賞行為は、「ふと見てしまった」という罪悪感と直結している。
ひとは何かを盗み見るとき、対象を純粋にまなざす「目」になる。しかし盗み見ている自分自身もまた「他人から見られているかもしれない」という不安に気づくとき、主体はおのれを反省し、おのれを客体化する他者のまなざしを意識することになる(哲学者サルトルが記述したように)。
だが、そうした窃視の構造が変容し、また極端になるのは、鑑賞者がこの作品をスマートフォンで撮影し、風景を写真に転じさせる時だろう。

鑑賞者が「窃視」から(いわば)「盗撮」の段階へ移行するとき、風景は「他人から見られているかもしれない」不安から離れ、物質化し、いくらでも個人的に見返すことができる私的所有物になるだろう。
しかし、実はここにも罠がある。この写真上で風景は距離感を失い、それが実際にあった空間なのか、ミニチュアで再現された偽の空間なのかが判別できなくなるのだ。
このことが伝えるのは、撮影の行為そのものに潜むひとつの魅惑的なリスクである。撮影は、ある風景を切り取り、保存し、証拠として残すアーカイブやエビデンスの機能だけをもっているのではない。むしろ写真撮影はその元々の遠近感を喪失させ、偽物と本物、ミニチュアとオリジナルの区別を曖昧にし、すべてを欺くかもしれないものなのだ。
ここには、「他人から見られているかもしれない」とは異なる不安がある。つまり写真にはあきらかにリアルな対象が写っているように見えるのに、それでも、そのイメージが何かの風景や出来事を証言しているとはかぎらない、という不安ないし不信である。
画像イメージがつねに改変され加工されているかもしれない、という不安は、画像生成AIの登場によってますます増しているだろう。この点で立花の作品は現代的なモチーフを扱っていると言えるのだが、同時に、そうした不安が拭い去られたことなど一度もなかったのではないか、とも思わせる。そもそも撮影技術というものが登場した時から、写真には遠近感を狂わせ、錯視させ、危険が伴っていたのではないだろうか。

「それは見る前からあった」?
二点目にとりあげたいのは、立花自身のいう「それは見る前からあった」の構造である。かつてフランスの批評家ロラン・バルトは、写真の本質を過去の光景の証言として語った。彼によれば撮影とは、その一瞬で奇跡のように生じた出来事、「それは・かつて・あった」(そこにひとつの光景が広がっていて、シャッターが押されたという、一瞬の確かさ)を証言するものである。
しかし立花の作品においては、この「それは・かつて・あった」の一回性につねに根本的な不安定さがつきまとっている。立花が切り取るのは、奇跡のような一瞬の光景ではなくむしろ、どこにでもある、いつでも立ち会えるような凡庸で匿名的な光景である。立花はこの既視感を(バルトをパロディする形で)「それは見る前からあった」と表現している(注1)。
この風景は、特権的な風景も瞬間も証言していない。撮影者がただ遅れてそこに到着しただけで、風景は前からあったし、これからもただ味気なく当然のように続いていく。ここにおいて撮影行為は、いつどこで撮っても同じであるような無名の凡庸さに足をとられてしまう。まるで人が、風景に対してなにも干渉できないかのようなのである。
(注1)イタリアの写真家ルイジ・ギッリもまた同様のことを述べている。この点について興味がある読者は、次の拙稿を参照してほしい。「地図の敷居をまたいで、——ルイジ・ギッリのフォトグラフ」『近代体操』創刊号、2022年(「左藤青」名義)。ここで私はギッリにおける「〈そこに−すでに−あった〉」「絶対的な遅刻の感覚」について書いた。

壁の向こうに広がる風景は、凡庸でどこにでもある、置き換え可能な風景である。しかし、「それは・かつて・あった」という確固たる証拠をもつことは禁じられている。何を見ても同じに見えるが、その「見た」という経験は不確かで、なにも確証してくれず、記憶にとどまらないのだ。しかしこの不定形な不気味さは、インターネット環境に取り囲まれた私たちにとってはどこか日常的なものでもある(注2)。実際、コロナ禍以降の立花の作品は、こうした不安定さを主題にしようと試みつつあるように思われる。
このように立花の展示はイメージそのものの不確かさを強調することになるだろう。こうした作品が『KG+』において取り上げられたことには、強い意義があったように思われる。私は正直、『KYOTOGRAPHIE』本編で展示されていたどの写真作品よりも、立花の展示のほうに驚き、関心を惹かれたのだった(撮影行為そのものをかくも複雑化した写真家が、『KYOTOGRAPHIE』本編にはたして存在していただろうか?)。
いずれにせよ私たちは、今後の立花の作品がどのように「見ること」の光学的経験を深めていくか、着目しなければならない。
(注2)宇野常寛は『ねじまき鳥クロニクル』を下敷きに村上春樹における「壁抜け」の問題を「インターネットを強く想起させる」としつつ批判的に取り上げた。おそらく立花はこのことを念頭においている。興味のある読者は以下を参照して欲しい。宇野常寛『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎、2011年)および『砂漠と異人たち』(朝日新聞出版、2022年)。
立花光
京都市立芸術大学大学院美術研究科構想設計専攻在籍中。モノが傍らに潜んで存在することや、時間が分岐したり引き伸ばされたりすることを、模型や複製の技法を用いて、思索的に工作する。表現ではなく、〈工作する〉ということに強い動機をもち、(1)手仕事としての工作、(2)目的遂行のための下準備としての工作の両方を重要視し、活動をおこなう。(立花光ポートフォリオより)
X(旧Twitter):https://x.com/tunis_211
Instagram:https://www.instagram.com/tunis_211/
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
1995年大阪生まれ・大阪在住。批評家。現代フランス哲学の研究者でもあり、現在博士論文執筆中。主に京都で活動しています。何か驚かせてくれるようなものに出会いたいというのが活動の基本的な動機です。
OTHER POSTS