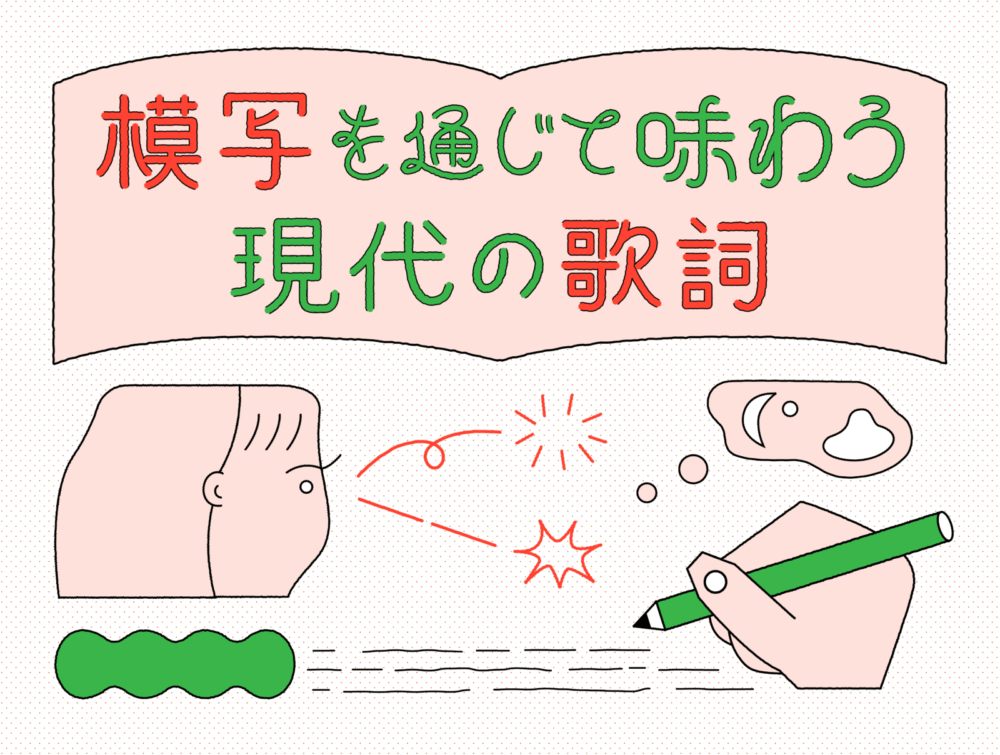【実は知らないお仕事図鑑 P4:小説家】 土門蘭
わたしたちは毎日、たくさんの言葉や文章、そして本に囲まれ生活している。そういった意味では、文筆家や小説家は非常に身近な職業であるはずだ。しかし、実際に「小説家」「文筆家」と聞くと、難しい顔をして頬杖をついている文豪や、締め切りに追われて机に向かってガリガリ手を動かしているような、ある種典型化された姿を思い描くのではないだろうか?
初めて土門蘭さんの文章を読んだとき、わたしは「この世のすべての文章は、ぜんぶ生身の人間が書いているんだ」という当たり前でいて、途方もない事実をあらためて突きつけられたような気がして震えてしまった。そんな生々しい文章を書く彼女は、一体どんな人生を歩み、何を考えて自分の仕事と向き合っているのだろうか? 一言ずつ丁寧に言葉を選びながら話す彼女の澄んだ眼差しを辿れば、その答えが見えてきた。
書いていたから死なずに済んだ
まず、土門さんの読書との出会いを教えてください。
小さい頃は絵本とか児童文学が読めなかったんです。自分の実生活と児童文学の世界がかけ離れているように感じてしまって、ファンタジー要素とかがあまりちゃんと理解ができなかった。こう言ったらなんなんですけど、読んでも自分の生活には”役に立たない”と思っていたんですね。
ご自身の実生活とのズレを感じていらっしゃったんですね。
母親が韓国人で、あまり言葉が上手く通じなかったんです。父親は仕事柄耳が悪かったので、家庭内で会話がうまく成り立たなかったんですね。不安や疑問を両親に話しても答えが返ってこなかったので、精神的に誰にも頼れない感じがありました。やっぱりそういう時に絵本とかを読んでも響かなかったんですよね。「いいなあ」って思う感じ。絵本の読み聞かせはされたことがなかったし、自分とは違う世界のことだと思っていたんです。
そうだったんですね。ではその頃どのような本を読まれていたんですか?
その頃に、それでもすごく好きだった作品が『小公女』と『若草物語』です。何故なら、それらの作品が、恵まれていた少女たちがいろんな事情で貧乏になってしまって、それでもどうにかやっていかなくちゃならない状況に陥る物語だったから。これを読んだ時に、これは”役に立つ”と。「ああ、こんな苦しい状況にあってもこれだけ気高く生きていられるんだな」というのを知ったのが、読書の始まりだったと思います。

児童文学にうまく馴染めない状況からどうやって「書くこと」に出会われたのですか?
小学校4年生の時に、初めて自分の生きづらさと向き合ったことがきっかけです。ある日の算数の授業で、私が風邪で学校を欠席している間にみんなが習った内容が突然出てきて、みんながわかっているものの概念が全くつかめない感覚がすごく怖くなってしまったんです。
そのとき「私にはこんな風にわからないことが多すぎる」と思いました。それまでも「友達とどうやって遊んでいいか」とか「どうやったら絵が描けるのか」とか、頭ではわかっていても身体的にわからないことがすごく多かったんですが、そのことがきっかけで「ああすごく生きにくいなあ、死んじゃいたいなあ」となってしまったんです。
なるほど。
当時私の学校には「4階の4年生の教室から女子生徒の自殺者が出る」っていう七不思議があったんですけど、それを思い出して「私のことだ。私が七不思議の中の、4年生で自殺する女の子なんだ」って思ったんですね。「その4年生の女の子がどうして死にたくなったか」とか「どのように窓から飛び降りて下に落ちていったのか」だったら自分でわかると思って、その算数の時間に物語を書き始めたんです。
それにすごく熱中しちゃって。そうしたら授業が終わるベルが鳴って「ああよかった、死なずに済んだな」と思いました。周りの人々にとっては当たり前のことが自分にはわからなくてその生きづらさに絶望したけれど、そんな自分にも七不思議の女の子の物語はわかる。物語を書いて絶望から避難していたから、押しつぶされずに済んだんだと思ったんです。それで「書くことって自分を生かしてくれるものなんだ、世界と自分をつなぎとめてくれるものなんだ」と感じたのが、書くことの始まりです。そこから手紙や日記をたくさん書くようになりました。
では純文学と出会う前から物語を書いてらっしゃったんですね。
私が初めて純文学と呼ばれるものと出会ったのは中学1年生の時です。江國香織の『きらきらひかる』を読んで…..アル中の女の人とゲイの旦那さんと彼の男性の恋人との三角関係と日々の暮らしについて綴った小説なんですけれど…..私以外にもいわば”アウトサイダー”の人、世界にちゃんと馴染めない、毎日生きる度に軋みを生じる人がいるんだというのを初めて感じて「文学って私の逃げ場だな」と思いました。そこから小説をたくさん読むようになって、ずっと本を読んでいたかったので大学も文学部の日本文学学科以外は受けない、という感じでしたね。
そこからたくさん本を読まれてきたと思いますが、好きな作家さんはいますか?
たくさんいるんですけど、私が卒論で取り上げたのは吉行淳之介で、第三の新人って呼ばれるグループにいる人でした。第三の新人というのは、第二次世界大戦の時に思春期を過ごして終戦の時にやっと社会人になった、つまり、思春期のときに「国と自分は別物なんだ」っていう、ある種の夢から醒める体験をした人たちです。
だから第三の新人は「私小説的だ」とか、国じゃなく自分の内面に迫るので「小さくまとまっている」と評されるんですが、その中でも特に吉行淳之介が好きだったのは、彼が”アウトサイダー”を描いていたから。彼は娼婦とか、レズビアンとか、子供を産むことをしない女性とかを突き詰めて書いている。多分私は、王道からずれる人たちにすごく共感してしまうんですね。
NEXT PAGE
「人生終わったな」って本当に思ったんです
WRITER

- ライター
-
1997年土曜日生まれ。結果オーライの申し子。言葉と、人々のそれぞれの暮らしを愛しています。
OTHER POSTS