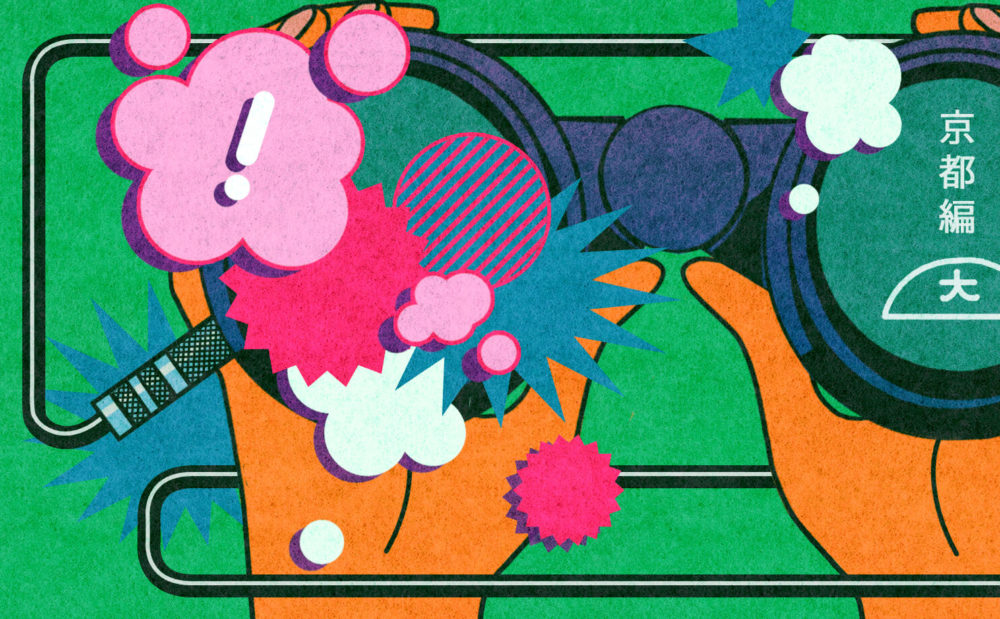「キテレツで王様になる」SuperBack『P wave』のキュートなダンディズムに震撼せよ
2017年に結成、京都に現れた異形の二人組ニューウェーブ・ダンスバンドSuperBack。1st アルバム『Pwave』は、80年代ニューウェーブ/ポストパンク的な捻りをとことん追求しながらも、タイムスリップしてきたかのようなそのアナクロニズムをものともせず、むしろその堂々たる無頓着によってクールな爽快さに到達した快作=怪作だ。
2000年代に勃興したポストパンク・リバイバル(The Rupture、LCD Soundsystem、国内ではPOLYSICS、The telephonesなど)の影響下から出発し、70年代後半の初期XTCやDEVO、Talking HeadsやGang of Fourといったニューウェーブの源流にまで遡ったSuperBack。他方で、80年代ジャパニーズ・ニューウェーブへの目配せも忘れない。一見無意味で不条理に見える代表曲“JADA”の歌詞のなかにも、ケラ率いる有頂天において度々登場したキーワード「カラフルメリィ」をさりげなく引用する余裕を見せる。
“JADA”のMVのキレたセンスに関してもいくらでも語りたいところだが、本稿でとくに注目したいのはこのアルバム全体に通底する、装飾を限りなく廃したそのシンプルな楽曲構成である。テクノ・ポップを思わせつつもシーケンサーは使わず生ベース+アナログシンセの手引きにこだわり、ライブでは毎回サポートベースを迎えた3ピース体制での演奏を披露している。ノイジーでひねくれているが歯切れの良いギター、素っ頓狂だが心地いいフレーズを連呼するボーカル、禁欲的にエイトビートを刻み続ける生ドラム、うねるシンセベースの反復——いずれも、どこまでもシンプルに「肉体を刺激する」ために構成されている。
ここにあるのはパンクの精神を突き詰めた先に現れた、あのポストパンクの殺風景さである。一聴すればわかるように、歌詞においてSuperBackが重視しているのも、意味や情感ではなくあくまで音の響き、フレーズの連なりの奇妙さである。ニューウェーブの伝統に即して、彼らは言葉を伝達手段としてではなく徹底的に「モノ」として扱うのだ。
だが、叙情性も意味も徹底的に突き放すようなこの唯物的なストイックさが、リスナーを不条理な不安に突き落とすかと言えばむしろ逆である。SuperBackのダンディズムは、興味深いことにむしろ吹き出すくらいにポップなシュールさ、一種の親しみやすい「かわいげ」につながっているのだ。たとえば丹野のティアドロップ・サングラスを見さえすれば、誰でもこのキュートさを理解できるだろう。

この奇跡的なバランス感覚から、どこまでも殺伐としながら、その冗談のような男臭さによって逆にシュールなポップネスにまで突き抜けるドイツの肉体派インダストリアル・ユニットDAFを想起する向きもあるかもしれない。実際次のような楽曲は、DAFのパロディのようにさえ聞こえる。
さて、このように反叙情的なひねりを加えながらもユーモアを保持する希少なバンドSuperBackだが、今後の彼らは京都ないし日本のライブ・シーンのなかでどのように活躍していくのだろうか。ライブに出演すれば熱狂必至のバンドとはいえ、とりわけ京都で同系統のバンドはほとんど見当たらず、その行く道はともすれば孤独な歩みにもなりうる。
だが、そのキラーチューン”キテレツバイソン”で、彼らはすでに自身の目指す道筋を歌っているのではなかっただろうか。つまり、「キテレツで王様になる」のだと。迷わず行けよ、行けばわかるさ。
SuperBack

2017年に結成、ニューウェイブ・ポストパンクの要素を持ち合わせていながら、ブラッシュアップを経てディスコパンクバンドへと変貌。現メンバーは丹野と小椋の二人。シンセベースを駆使し、ヒリヒリしたギターカッティングとビートを極限ミニマルに仕上げパッケージされた楽曲群。ダンサブル且つパンキッシュでしかもユーモラス。まさにGang of Four⇔The Rapture⇔XTCといった派生を縦横無尽に駆けめぐる面白いバンドです。 2023/4/1に新EP『Dance from JA/DA』をリリース、関西・京都を中心に活動中
X(旧Twitter):@superback_band
Instagram:@superback_band
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
1995年大阪生まれ・大阪在住。批評家。現代フランス哲学の研究者でもあり、現在博士論文執筆中。主に京都で活動しています。何か驚かせてくれるようなものに出会いたいというのが活動の基本的な動機です。
OTHER POSTS