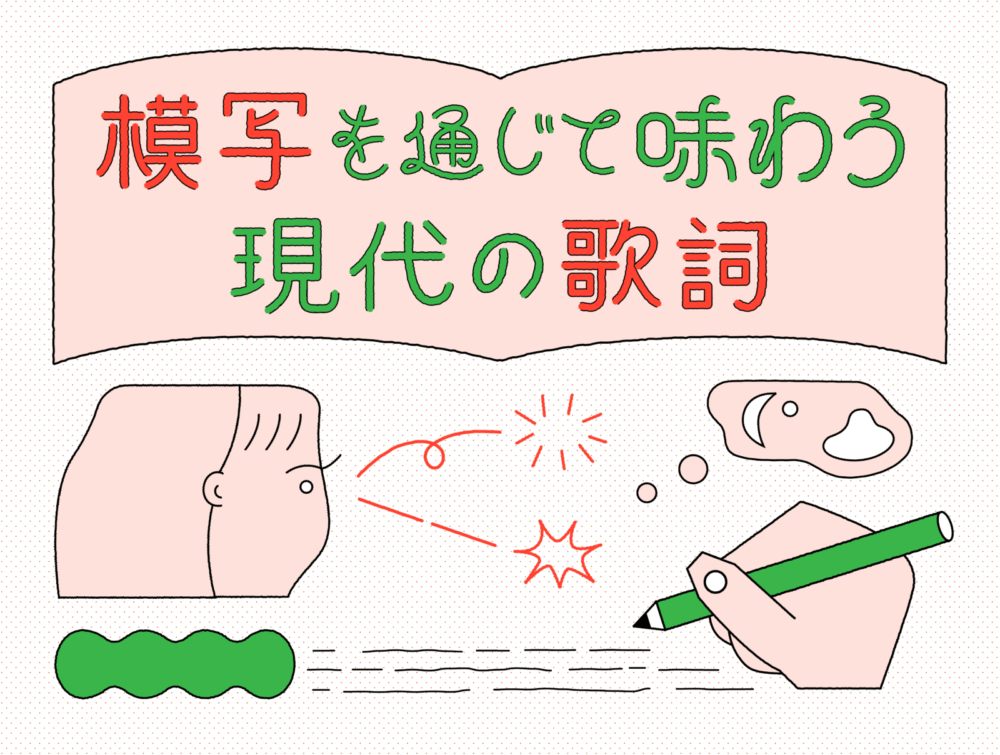Vol.1 Sovietwave 時代の移り変わりでねじれるソ連のノスタルジー
わたしたち自身の持つ価値観や、世界や周りの環境が絶えず変化し続けることで、カルチャーに対する眼差しが移り変わる。カルチャーが持つ従来の評価と、それを取り巻く人々の目線の間にねじれが生じて、新たに生まれたアイデンティティ。そんな「アイデンティティのねじれ」からカルチャーに対する解釈が生まれ変わる文脈を追う。本記事では、ソ連のカルチャーが時間を経て再解釈された結果生まれた音楽ムーブメントSovietwave(ソヴィエトウェイヴ)が強烈なノスタルジーを放つ理由を紐解いていく。
カルチャーは多様な側面を持ち、楽しむ人々はそれぞれの視点から価値を引き出している。時代や環境、言語や国が変われば、その視点も変化し、今まで見えなかった新しくて面白い側面を再発見できる。例えば、竹内まりやの“プラスティック・ラブ”をはじめとする70~80年代のシティ・ポップは時代を超えて楽しまれているカルチャーと言えるだろう。
YouTubeが持つアルゴリズムのレコメンドの偶然性とノスタルジーを求める時代性が交差した結果、日本のリスナーを超えてた広がりを見せている。Tyler, The Creator(タイラー・ザ・クリエイター)の“GONE,GONE / THANK YOU”では山下達郎の“Fragile”をサンプリングしたり、 Saint Pepsi(セイント・ペプシ)は同じく山下達郎の“Love Talkin”の一節を大胆に取り入れたことでシティ・ポップはフューチャーファンクのシーンに欠かせない「元ネタ」となった。
このわたしたち自身の持つ価値観や、世界や周りの環境が絶えず変化し続けることで、カルチャーに対する眼差しが移り変わる。カルチャーが本来持っていた評価とそれを取り巻く人々の目線の間にねじれが生じて、カルチャーに新しいアイデンティティが立ち上がってくる。そして、新たに生まれたアイデンティティは当初の文脈から飛び出して、新しい文脈に織り込まれていく。本連載ではそんな「アイデンティティのねじれ」を紐解き、カルチャーに対する解釈が生まれ変わる文脈を追う。
Vol.1 Sovietwave(ソヴィエトウェイヴ)
Sovietwave(ソヴィエトウェイヴ)と呼ばれる音楽ジャンルをご存知だろうか。元来ロシア語圏で楽しまれているアンダーグラウンドな音楽であるため、決して大衆の注目を得るようなジャンルではない。しかし、その起源を辿っていくとアイデンティティのねじれを感じる音楽ジャンルだと思わされた。
Sovietwaveはその名前の通り、ソビエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連)のカルチャーに端を発する。2010年代前半からロシア語圏のアーティストにより音楽ジャンルとして形を取り始め、2020年現在その影響は非ロシア語圏まで広がり、ニッチながらも一つの音楽的ムーブメントとして認知されている。特徴を挙げるとすると、ソ連から独立した東ヨーロッパやロシアなどの国々をベースとする現代のロシア語圏のアーティストが、音楽を通してソ連の郷愁を表現している。サウンドとしてはソ連時代に放映されていたプロパガンダ的ラジオの音声のサンプリングや、シンセサイザーで表現されたしんとした空虚な静けさ、低音が少なく空間の広がりを感じさせる浮遊感の余韻を残しているのが大きな特徴である。
代表的なアーティストとしてはウクライナ出身のМаяк(マヤーク)が挙げられる。2013年にリリースされたアルバム『Река』(リカー)は荘厳なシンセサイザーの音色から始まり、雪国を思わせる静けさが漂う掴みどころのないサウンドスケープを生み出している。
Маяк - Peka
また、直接的な影響でないものの、80年代のソ連の音楽シーンで活躍したバンドもSovietwaveのレファレンスとなっている。80年代のソ連ではニューウェーブやポストパンク・バンドが隆盛を誇っていたが、その中で登場した、Alyans(アリヤーンス)の“На заре”(ナ・ザレ)は1987年のリリース以降、現在のロシアにまで語り継がれている。2001年にはロシアのロックバンドMad Dog(マッド・ドッグ)に、また2019年にはラッパーであるBasta(バスタ)によってカバーされるなど、時代を超えて愛され続けている。
Alyans - Na Zare
また、Alyansと同じ時期に活躍し、ソ連のYMOと呼ばれたラトビアのZodiac(ゾディアック)などもSovietwaveに大きく影響を与えた存在だ。
Zodiac - Disco Alliance
また、近しい音楽的ムーブメントとしてSynthwaveと対比されることも多い。Synthwaveは80年代の資本主義側のゲームや映画、グラフィックなどのカルチャーを引用してる。ロサンゼルスやマイアミなどの西海岸の都会的なムードとヤシの木がモチーフとして多用されており、ブレードランナー的なサイバーパンクを思わせるSF的価値観がミックスされているのが特徴だ。一方Sovietwaveはそのインスピレーションが全てソ連の共産主義的なカルチャーに置き換わっている。ウクライナのアーティストProton-4(プロトン4)による2015年のアルバム『Далекая Звезда』(デレカヤ・ズヴェズダ)では冷戦下プロパガンダとして機能した宇宙での成功を連想させるヴィジュアルが使われている。
Proton-4 - Далекая Звезда
また、2020年にリリースされたPluto(134340)(プルート(134340))の 『Улица моих городов』(ウーリッツァ・モイーフ・ゴロドフ)ではブルータリズムの静的ながら荘厳な造りの旧ソ連時代の建築物がアートワークとして採用された。どちらも現代の経済や政治の停滞から逃げるように、ノスタルジーを80年代へ追い求めた結果生まれたムーブメントであるものの、その引用元となるカルチャーの毛色が全く性質が異なる。
Pluto(134340) - Улица моих городов
極端に言えば、Sovietwaveは政治的、文化的、言語的にも資本主義が当たり前になった日本で暮らすわたしたちの対岸にあるような音楽ジャンルである。しかし、ソ連崩壊後、資本主義経済に切り替わったロシアでは格差が拡大、ベラルーシやブルガリアなどソ連の「衛星国」と呼ばれた国々でも独立後、政治の混乱や独裁により経済が低迷する状態が続いている。Sovietwaveはロシア語圏の国々が抱えている現代社会の行き詰まりが生み出したノスタルジーへの逃亡の産物と捉えるのであれば、日本でもアメリカでも同様に似た現象を見て取れる。「事実」と「記憶」をノスタルジーという感情に繋がれたカルチャーといえるだろう。
資本主義の停滞
Sovietwaveが持つ「アイデンティティのねじれ」は、当時の史実と現在の解釈の間で生まれている。言い換えるなら「共産主義の負の側面を持った史実としての80年代ソ連」と「現在の視点で旧ソ連を回顧したユートピアへのノスタルジー」の間に生まれたギャップだ。そのねじれの間には、当時のソ連を経験していない世代が立っている。彼らは現代社会への行き詰まりから、ノスタルジーを求めて「過去が描いていた明るい未来」へ潜っていったのだ。
ソ連解体後に経済的に苦境に立たされたロシア語圏の人々は、崩壊した共産主義の夢に拠り所を求めた。旧ソ連が描いたユートピアは叶うこともなかったが、ゆえに強烈なノスタルジーを喚起する。政治的なイデオロギーが根を張ったソ連の記憶は、時間の経過とともに徐々に政治的な匂いが失われ「やってこなかった世界線」への空想が膨らみ次世代のアーティストへ影響を与えたと言えるだろう。
例えて言うなら、現代のロシアの人々が在りし日のソ連へ抱く感情は、日本人が昭和という時代に持つノスタルジー似ているのかもしれない。経済的に恵まれた時代でもなかったし、犯罪の数も今よりも多かった時代だ。しかし、当時を経験していない現代の日本人の多くが持つ昭和のイメージは”Always 三丁目の夕日”で描かれたような温かな世界観なのかもしれない。これも時間の経過と共にポジティブな記憶が強化されたことによる、見え方の変化だ。わたしはもちろんソ連も昭和も経験していないが、美化された記憶のイメージに「あの頃はよかった」という感情を持つ気持ちは理解ができる。時間の経過は「よかったこと」だけを残してノスタルジーを強化し、もし「よかった時代」の延長線上に立っていたら見れたであろうユートピアへの空想を駆り立てる。
80年代におけるソ連は、公にリリースされる音楽も検閲され、国営のレコード会社〈メロディア〉からリリースされたアーティストのみプロとして活動が許された時代だ。決して表現の自由が保証されていたとも言えないし、アンダーグラウンドな活動を余儀なくされたバンドがいたことからも、自由な創作活動を行う上では恵まれた環境とも言えない。ソ連崩壊後に立ち上がったロシア連邦は資本主義に移行し、共産主義の負の側面が徐々に歴史となり人々が捉えるソ連の記憶が形を変えていった。その後2010年代に入ったあたりから、世界的に資本主義の停滞や、大量生産・大量消費への疑問など、現代に不信感や閉塞感を持つ人々は少なくない。
アメリカを中心とした資本主義下の西側諸国は80〜90年代のポップカルチャーにノスタルジーを求め、Synthwaveとして表現したり、Vaporwaveを生み出した。当時の生活を知る人間はどう感じるか定かではないが、現代のアーティストたちは、当時テクノロジーや経済が上向きで様々なカルチャーが生まれた時代を「発展するフロンティアが広がっていた時代」と解釈し、過去に未来の発展の展望を見た。同じように現代のソ連諸国のロシア語圏の人々は経済不況に対峙した時に、ソ連の宇宙開発やブルータリズム的建築物、共産主義下のラジオや映画、音楽にノスタルジーを求めたのだ。
僕らが経験し得ない想像上の旧ソ連
Sovietwaveのインスピレーション源であるソ連のカルチャー。それを通すノスタルジーというフィルターがなければ、当時を経験した人たちの中でただ「過去を懐かしむ」卒業アルバムみたいな限定的な音楽だっただろう。しかし実際のソ連から共産主義性やプロパガンダ、当時の政治色が時間の経過とともに徐々に薄まっていったことで、ノスタルジーをキーに「経験し得ない架空のユートピア」に入り込めたのだ。
Sovietwaveの中心となるアーティストはソ連圏のロシア語話者である一方で、彼ら自身もソ連崩壊前後に生まれた世代であるため、実際にその時代を経験をした世代ではない。彼らは後から振り返ったソ連のカルチャーから自身の想像力と2020年時点の視点で眺めた時に生まれるSovietwaveは、実際のソ連を描写するドキュメンタリーではなく、いわば現実をベースに書き上げられたファンタジーなのだ。過去と現代の解釈の間でアイデンティティのねじれが生まれたSovietwaveに、ノスタルジーを感じるまでの流れを見ることができるのかもしれない。
アイデンティティのねじれ Vol.3 Sovietaweトラックガイドでは、本記事で取り扱ったアーティストやSovietwaveを理解する上で重要なバンドを紹介している。ぜひこちらの記事も併せて読んでいただきたい。
https://antenna-mag.com/post-50546/
WRITER

- ライター
-
奈良県生まれで東京在住のライター。普段はSleepyhead_blogというインディーロックを中心に扱う音楽ブログを運営しています。Tame ImpalaとLostageが好きです。
OTHER POSTS