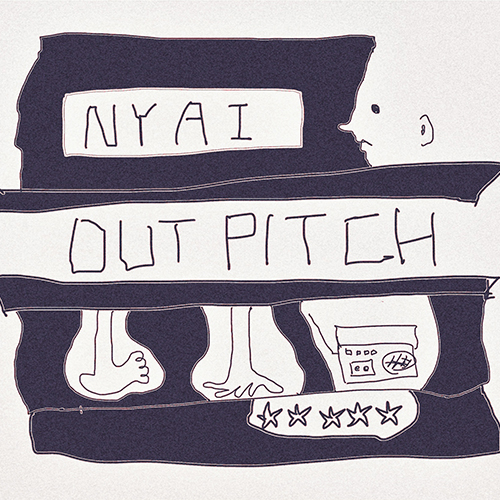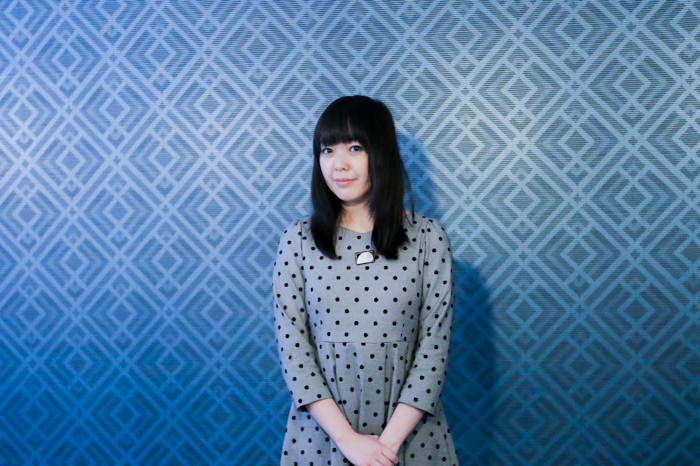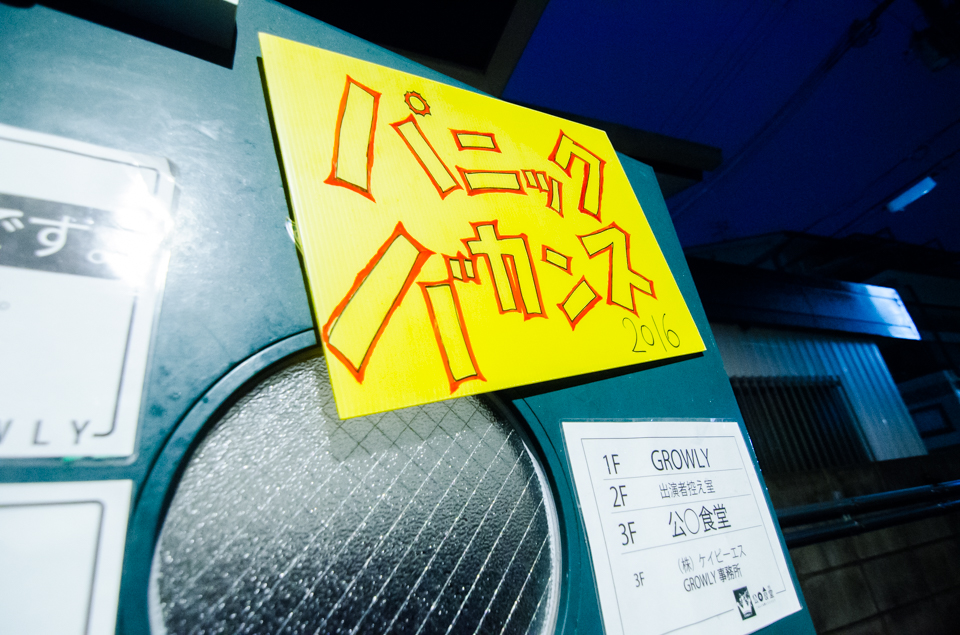みんなの劇場が無い‼ 私たちが自分の言葉で語るための場所づくりを〈THEATRE E9 KYOTO〉あごうさとしさんに聞く
特集『文化の床』の企画「#無い!!」では、満たされているはずの都市や生活の中で「なにかが無い」ことに気がついた人々へインタビューし、どんな「無さ」に向き合っているのかを伺った。2019年にオープンした〈THEATRE E9 KYOTO〉で芸術監督を務めるあごうさとしさんは、私的で先駆的な表現をそのままに尊重し育む小劇場という場所がこの街で100年続くために、「みんなの劇場」とは何なのかを様々な角度から問い続けている。

小劇場〈アトリエ劇研〉の閉館と〈THEATRE E9 KYOTO〉の開館に関わり、あらゆる「無さ」に向き合ってきたあごうさん。それは欲しても直ちに満たされない国策レベルのものから、街の人との関係性まで様々だ。しかしお話を伺って感じるのは、ないものに途方に暮れながらも、あるはずのものに向かって突き進む果敢さのようなものだった。
それは、舞台芸術の力を信じている、あるいは知っているとも言える。
オンラインでの繋がり、SNSの発達によって、私たちは自分が自分でないまま、借り物の言葉を語ることにいつの間にか抵抗がなくなり、もしくはある種の快感を覚えるうちに、とある場所や人、ものを「自分に関係のあるものだ」と感じる力を失ってはいないか。そんな昨今、何かと自分の関係を取り戻せる場所のひとつが小劇場なのではないかと感じた。そもそも人は望むとも望まざるとも「私」を表現している、とあごうさんは言う。あらためて自覚的に、自分の言葉でものを感じ表明していくことで、その外側にある他人との関係性が耕され、「私たち」という感覚が立ち現れる。それがこれからの公、つまり「みんなの」を考えるひとつのヒントになるのではないか。
全国に支援してくれる人はいるのに、すぐ隣の人にとっては関係のない場所だった
まず〈THEATRE E9 KYOTO(以下:E9)〉開館のきっかけとも言える、2017年の〈アトリエ劇研(以下:劇研)〉閉館についてお伺いしたいのですが、あらためて小劇場が続いていくために、どういったことが「無かった」と言えるのでしょうか?
演劇の歴史が仮に2500年あると考えたときに、「京都の老舗劇場、アトリエ劇研」と言われながらも33年で幕を閉じた、ということは民間小劇場は本当に短命なんだなということを改めて思ったんです。〈劇研〉はフランス文学者の波多野茂彌さんという館主が私財を投じて、若い舞台芸術家に33年間解放し続けたのですが、一個人の崇高な志によってようやくできた劇場だったんですよ。〈劇研〉と同時期に閉館になった京都市内の他の小劇場も、おおむね同じく個人の志で成り立っていて。一時代の、ある人間の、ある才覚によって何かが勃興することが時折あり得るわけですが、文化として定着するまで続かない。個人のものを引き継ぐ、つまり相続とか、企業で言えば事業継承という問題があって構造的に難しい。

しかし〈E9〉設立の際にはプロジェクトメンバーに直接面識のない方々、つまり〈劇研〉の歴史に携わってきた人たちからのご支援があったのですから、〈劇研〉の33年がこの〈E9〉を作らせてくれたという言い方もあると思います。大衆性重視でない先駆的な表現というのか、歴史的に見ても小劇場はそういう表現を追求する場所としての役割を担ってきたと感じますが、新しい表現が必要とされて、次の時代へと引き継がれるエネルギーは、確実にその33年間にあったんですね。
個人的な志によってできた劇場に、先駆的な表現が集まるという閉じた魅力がある一方で、それを続けていくために広く開いていく難しさというのはありますよね。
愛好者だけの為の場所、というレベルからもう一段引き上げていきたいとは考えています。そうすると、劇場がみんなのものになっていくし、一番は地域のみなさんに「我が街の劇場」という感覚を持ってもらえるのがいいかなと思っていますけど。だからといってアーティストに対しては間口を広げるような作品をつくってくれとは絶対に言わないですけどね。尖りたかったらどんどん尖って下さい、いや尖る必要もなくて、基本的にはとにかくやりたい表現をやっていただくということなんですけど、その上でそのままに受け入れられることが理想ですね。閉じている部分と開く部分を、力学として同時に駆動していかないと、とは思っています。
〈E9〉のキャッチコピーには「作品をつくる・地域をつくる劇場」とありますから、「我が街の劇場」と思ってもらうための地域との関わりが非常に大きなテーマになっているんですね。
〈劇研〉は周辺住民の方から頻繁にお叱りを受けていたんです。劇場という場所は、常にお客様に「集まって下さい」と声をかけている場所なのに、すぐ隣の人にとっては関係のない場所というのが大きな矛盾なんですね。街の人が日常的に劇場に通う風土のことを劇場文化だとするなら、劇場文化は地域に根ざしているとは言い難いでしょう。小劇場が地域のみなさんに親しんでもらえるほどに、文化として成熟していないというのが現状かなと思います。
今、現代舞台芸術専門館としての小劇場が100年続くということが本当にあり得るのかということを、〈E9〉を通じてあらためて考えたりみなさんに問いかけさせてもらっている感じですね。
よく分からないけど一緒にいる、というのが街の在り方のヒント
実際に〈E9〉を東九条という街に開いていく際に、街の中の「無さ」のようなものは何か感じられていたのでしょうか?
〈E9〉という劇場の活動についてちょっと勘違いされることもあったんですけど、税金は入っていなくて完全に民間で開設されているんですね。というのもそもそも制度として、民間の文化施設を建設する際に公的資金を投入する仕組みが「無い‼」からなんですけど。
先日、兵庫県豊岡市に平田オリザさんが開校する演劇と観光の大学に認可がおりましたけど、それまで国公立の芸術大学の中に舞台芸術学部というものはなかったんです。意外と知られていない事実なんですけど、演劇やコンテンポラリーダンスは、国策として教育の分野では採用されていなかったんですね。
もっと言えば法律の上でも位置付けが違っていて、例えば博物館法といって美術館や博物館を設置するための趣旨を明確にするための法律があるんですけど、これは文化芸術や教育目的の施設を管理する法律、というたてつけなんですよ。一方劇場は、興行場法という法律で位置付けられているんですが、つまり法律上は文化芸術・教育を目的とした施設として見られていない、ということになります。
そういった構造の問題があって、舞台芸術は長らく民間で培ってこざるを得なかったという歴史があるんです。
国公立の芸術大学に舞台芸術を学べるところがなかったというのは、言われてみればという感じで気付きませんでした。
東九条の街の人たちに少しずつご挨拶して、少しずつ交流していくというスタートのタイミングで、京都市主催の2件のアートプログラムのコーディネーター役を承ったんですよ。それは、京都市さんや企画制作をされたHAPS(東山アーティスツ・プレイスメント・サービス)さんからの、小劇場をつくろうと言っている我々をなんとか間接的にでもサポートしてあげよう、という心配りも強くあったと思っているんです。しかし、公的な税金が投入されてアートイベントをやるということに関して、最初は反発がありましたよね。それよりも大切な社会課題があるのではないかと。
そんな中、どうしたらこの街の人たちにこの劇場が親しんでもらえるかなということを色々考えていて、僕の契機として一番良かったのが2017年8月の東九条夏祭りです。そのときの出し物に、〈E9〉館長の茂山あきらさんと、ご子息の茂山千之丞さん(※当時、茂山童司)親子で『柿山伏』という狂言をやっていただきました。上演場所が舞台もないようなほぼ野外という厳しい環境だったんですが、そこで上演可能で、かつちゃんと舞台芸術の魅力が伝わるもの、となれば「これしかない!」という感じで。
それが、お祭りのがちゃがちゃした中でもちゃんと届いて、すごく盛り上がったんです。大人も子ども笑ってくれて。僕の個人的な感覚では、あの場で初めていわゆる舞台芸術・芸能を通じて街の人と交流して、親しくなるきっかけになったかなと思いました。舞台芸術のパワーというか、原風景を見た気がして感動したんですね。
それは作品を作る際の「大衆性」みたいなものを見くびらないというか、これまで閉じた劇場の中で全身全霊でやってこられたものを市民のみなさんと共有できたというのが意義深いのではないでしょうか?
そうかもしれないですね。もちろん作り手はいつでもどこでも全身全霊でやってるんですけど、とりわけ劇場の「表現をやってもいいよ」という、仕組みが色々整って守られた場所の中ではなく、丸裸でぶつかったのが良かったのだろうと。そういうところで作品をつくってお見せすることで関係をつくるっていうのは、シビアだし、でも面白くなる。

夏祭りという状況がそうさせてくれたのでしょうが、街に開けた瞬間でもあるんですね。
先ほどの2つのアートプロジェクトも、それぞれ振付家の倉田翠さんときたまりさんのダンス作品を、街の人や高齢者福祉施設を利用されている方と一緒につくったんですけど。いずれの作品もそれぞれの形で、別の場所でも再演されて。街に開きつつ、作品として芸術的評価もお2人とも得ていた感じがありましたね。それは、作る過程でも発表の場でも、街のリアルみたいなものを全身で受け止めていたところがあったのではないかと思います。そのことが作品の魅力や強さに繋がったんじゃないかなぁ。そういう意味では街の人に作らせてもらったと言ってもいいのかなと思うんですよね。
そうして交流した街の人が、実際に舞台芸術に興味を持って〈E9〉に足を運ぶということには繋がっているのでしょうか。
〈劇研〉でやりたかった支援会員制度を導入しているのですが、周辺住民や周辺にお勤めの方は、年間の全プログラムを観られる会員価格を一般より安く設定しています。去年だけでも50人くらいは会員に入っていただきました。
50人はすごいですね!
今年の鑑賞人数はさすがに少ないんですけど、去年だったら例えばこれまで本当に演劇を観たことがなかったというご夫婦が頻繁に足を運んで下さったりとか。それで、「面白かった」とか「よう分からんかった」とか、一言声をかけて下さる。近所にお住まいで同じくよく来て下さる方がいらっしゃるんですけど、「なんでこんなに劇場に足を運んでいただけるんですか?」って、そんなこと聞くのも変なんですけど聞いてみたんです。すると「作品が毎回面白いわけでもないし、毎回分かるというわけでもないけど、劇場に来ること自体が面白いんだなと思ったんです」とおっしゃって。そういう反応が嬉しくて、そういう方が増えると劇場が100年続くんじゃないかって。
確かに「よう分からんけどまた来たい」と思えることは、今すごく大事なんじゃないかと思います。私たちはすぐ分かるもの、あまり考えなくても理解が及ぶものを選びがちですものね。
「よう分からんけど一緒にいる」という感じが、街の在り方としてはヒントになりそうですよね。分かり合えなければ一緒にいられない、ではなく。分かり合うなんて、なかなかないですから。
ええ、そう思います。
東九条という街は、多様な背景を持った人たちが共に暮らしていけるようにということで、多文化共生という言葉がキーワードになっているんですけど。多文化共生って「共に生きる」ということでもあるんだけど、なんだろう、共に生きているのではないけど、一緒に居てもいいんじゃない?って。そういう「共にいるための居方」というんですかね。そういう感じに可能性があると感じました。
表現することは生きていることと同義で、私たちはすでに表現者である
そうして、能動的に劇場に興味を持つ方が増えることは希望ですが、一方でこれまでそうであったように、なかなか街の人は小劇場が自分と関係のある場所であると感じにくいと思うんです。鑑賞制度の他に、街の人の関わり方として工夫されている部分はありますか?
街の人がいつも「鑑賞者」であるとは限らなくて、最初の取り組みとしては2階にあるコワーキングスペースを利用している一般の方々と一緒に作品を作って発表するということを、コロナ禍以前にはやっていました。

「誰かが舞台に現れて、何かを語って、語り終えたら去っていく」というのが誰もが納得する演劇の一番シンプルな形で、実は古代から人間がやっていることだと思うんです。それならいろんな人によるいろんな語りがあってもいいのかなという中で、働いている人・街で暮らしている人・子どもたちが表現者となって、これから本格的にやるというつもりじゃなくても舞台に立つことがあってもいいんじゃないかって。そういう人たちにプロとして表現してもらう。新しい芸術の可能性があるかもしれない人、そういう人たちと何かしていくことは続けていきたいですね。
「プロとして表現する」とは、どういうことを意味しますか?
一番分かりやすいのは、発表する作品に対してチケット代を支払っていただくことですよね。アマチュアの発表会としてではなく、通常の演劇とかダンスの公演と同じように、鑑賞される方からお金をいただく。だからシビアな部分も出てくると思うんですけど、それが楽しさにも繋がると思っていて。普段舞台に立たない人に経験してもらえると、劇場ってどういうところなのか、自分に関係のあることとして考えてくれるんじゃないかとも思いますし。閉じていた個人を作品として舞台芸術の中で表現すると、その人の存在が開かれていく、つまりパブリックになっていく。そういうことが民間の小さい劇場にできる「パブリック」を作るということで、それがとても大事なんだろうなと思っているんです。
表現をしていく、個を開いてパブリックをつくっていくということは、今いろんな文献でも触れてみて非常に共感するのですが、あごうさんが演劇というものと長く関わってこられたご経験から、なぜそれを演劇を通じて実践すると良いのか教えていただけませんか?
演劇は稽古の過程でも本番でも、必ず他者とのやりとりの中から「私」というものが立ち上がってくるんですよね。それで、「私」というものが実感として開かれていくこともあるし、その人があらためて「私」を捉え直すことにもなるんですけど。あるいは「私」を切り離すことができる。
例えば全然違うバックグラウンドを持った人たち同士が一緒に居てもいいよねって言い合える状態になるというのは、私たちの街にいる人たちが「彼ら」ではなく「私たち」という概念に含まれた瞬間なのかなって思うんですよ。この「私たち」を生み出すためには「私」がないとそもそも生まれなくて、この「私」を拡張していくために表現というものがあるのかなと考えていたんです。
表現ってそうかもしれませんよね。舞台に立ってしまうと、準備していようがしていまいがとにかく「私」をさらされてしまうというか、見ていたらやっぱりその人の本質みたいなものを感じるんですよ。言葉を発しても、伝えたいと思っていることが違う形で伝わることもありますよね。舞台上ではそのくらい個がさらされてしまう。
表現したいことって本当にその人が理解できていなかったら、多分一歩も動けないんですよ。腹落ちしている部分があるといいと思うんですけど、そのときに向き合う時間がもしかしたらない、あるいは自分の言葉で話す機会が与えられていない人、あるいは与えられても模範解答的な言わなきゃいけない設定になっちゃっている人が結構いるんだろうな。日常の仕事で忙殺されている人たちは、そういう時間を持てないと聞きますから。

この国では、個というのがなじみにくいカルチャーなのかもしれませんけど、日本の憲法で一番大事にしている価値って実は「個の尊厳」なんですよね。これは無限じゃなくて、公共の福祉とのバランスの中にある。
個をさらすということは、怖いことでもありますよね。
でも、みんな絶対嬉しいんですよ、「私」の言葉を聞いてくれる人がいたら。絶対なんて言ったらだめかな。
演劇の授業をいくつかやらせてもらっているんですけど、今年は大学の授業でも基本的にZOOMを使うことが多かったので、ZOOM上で「私とは何かを語って下さい」という授業なんかをやっていました。最後の発表の時に、あの小さな画面の中でも衣装を着たり工夫してみんなが「私」を表現しようとする。今年の閉塞している空気を、画面越しに乗り越えてくるパワーを感じたんです。それぞれ私の心の何かをみんなで共有するということに、始めは怖さがあって、段々と安心感になって。私というものを表現していいんだって、最終的にはちょっとした自信になっていく。そうなってくると例えば、「私の身体の傷を順番に紹介していきます」とか(笑)そこには歴史があってリアルがあって、そうすると明らかに学生たちの表情が良くなっていくんですね。面白くなってくるんです、彼らの表現が。
なるほど、「開いてくる」のが見えるんですね。
だから、私たちが生きていくということと表現するということは、ほとんど同じ意味だなと思っています。引きこもったって表現から離れられないですもんね。むしろ表現が強くなっちゃってる。寝てても無理でしょ?表現しちゃってるでしょ?だから無理なんですよ。表現することは、生きることとか存在することから、構造的に切り離せない。
そしておそらく、経済的な活動や、日常の暮らしの営みの中でも、どんな局面でもそのとき向き合っていることやその相手が「私」と繋がっていたら、障害が出てもなんとかしようとする力が働くんじゃないかって。「私」と繋がっていない人の営みはしんどくなる可能性が高いから。
誰もがやりたいことを出来る街のひとつに
今おっしゃったような、個から派生するパブリックというのは小劇場だからこそできるという部分なんだと思いました。
税金を投入したハードが「公共」という意味ですか?って、公共とは何かっていうことを問い直した方がいい時期にきているのかなとは思いますよね。
こういう状況下ではありますけど、これからあごうさんが実践していきたい取り組みというのはどういうものですか?
劇場に来たことのある人の方が多い街にしたいだけなんですけどね。だから、ロームシアター京都とか他のいろんな劇場とか、劇場じゃないオルタナティブなスペースでもいろんな表現がありますし、もちろんライブハウスとかジャンルが違っても。映画館に行ったことのない人はさすがに少ないと思うんですけど、小劇場がそれぐらいになるといいなと思うんですよね。
こういう小さな劇場だから、元々持っているキャパシティが少なくて、私たちひとつで出来ることは本当に小さいんですよ。だけど全国を見渡してみると、地方にも同じような志の小劇場があって、そういう地域のみなさんとも連携してやっていけるようにと思っています。3年前に民間小劇場の全国的なネットワークができて、殊更このコロナ禍ではどこもダメージを受けていましたが、だからこそみんなで知恵出し合おうよと機運が高まった部分もあります。
最後に、あごうさん自身は作り手でもいらっしゃって、京都に劇場をつくることに注力しなくても、例えば既に小劇場のある地域に移ることも出来たと思うのですが、京都に作ろうとされたのはなぜだったんでしょうか?
おそらく、なくなった劇場が〈劇研〉だけだったらやらなかったと思うんですよね。たまたまくじ運がいいのか悪いのか、京都中の小劇場が閉館するタイミングでそのうちのひとつに関わっていて、これどうするのかな?って自問自答しますよね。ただ、やはり先輩たちが切り開いて育んできた環境の中で自分はここまでやらせてもらっていて、そういう月並みなことも考えるわけです。劇場に出入りしていた若いスタッフたちが、京都に見切りをつけて東京に行くのを見て、これはますますこの街で舞台芸術が育まれる機会は加速して失われていく一方になるなと思ったわけです。
でも、僕自身はずっと勝手に演劇をやってきただけなんですけどね。誰から頼まれることもなく、演劇が好きだからやってきた。過去から受け継いで、未来に繋いで、ってそんなに崇高なことをやっていますという感じではなくて(笑)でも京都は、そうして勝手にやることをアリにしてくれた街だと思っているんですよ。みんなが、好きなことをやったらいいって思っています。
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
滋賀生まれ。西日本と韓国のインディーズ音楽を好んで追う。文章を書くことは世界をよく知り深く愛するための営みです。夏はジンジャーエール、冬はマサラチャイを嗜む下戸。セカンド俗名は“家ガール“。
OTHER POSTS