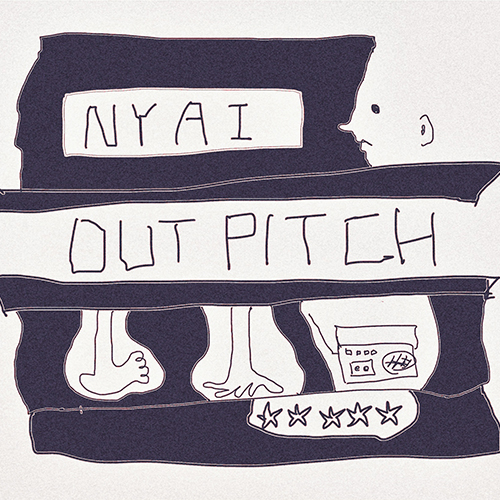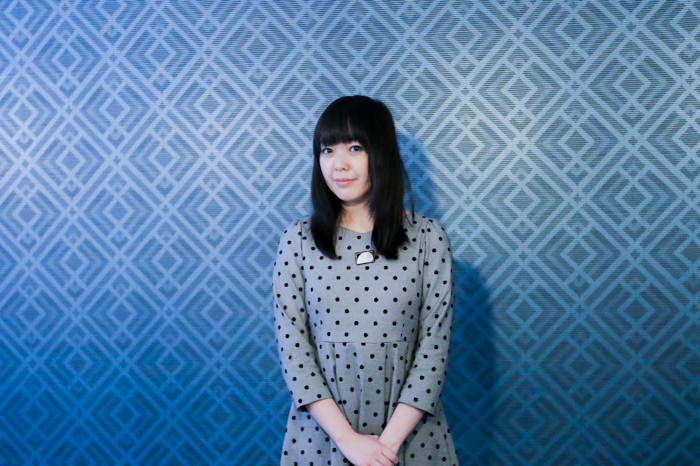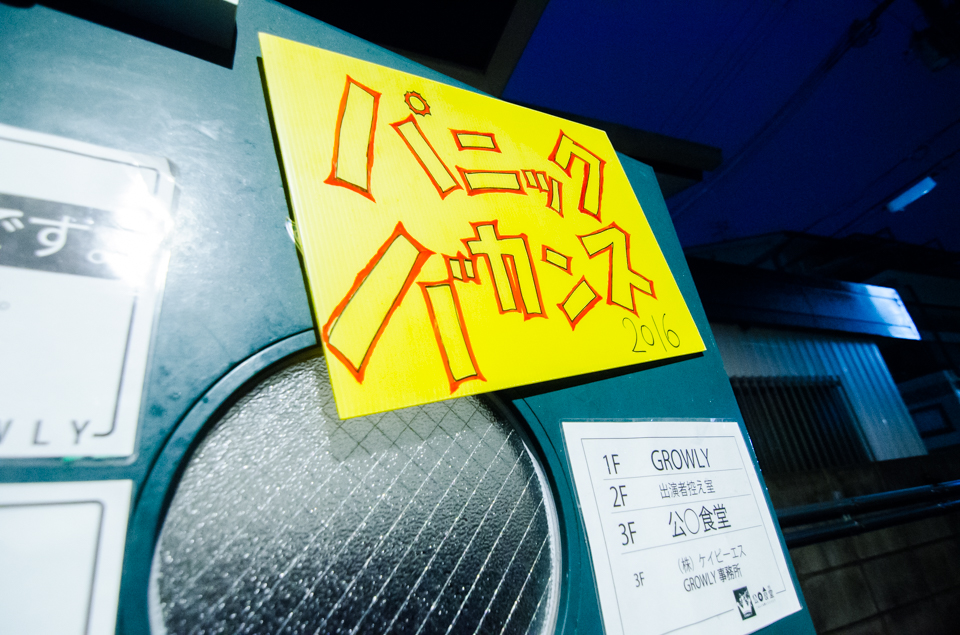流れる日々の中で生まれる、渚のベートーベンズの音楽
全員がソングライター、それぞれがメインボーカリストのバンド、渚のベートーベンズ。そんなコピーを見れば、各々の個性が粒立ったカラフルでテンションの高い作品群を思い浮かべるのは私だけだろうか。そのイメージに近い濃厚なアルバムが前作『Oyster』だとすると、3rdアルバム『AFRICA』は少し様子が違う。バラエティ豊かな楽曲が並んでいるには違いないが、作品全体を覆っているのは凪のような穏やかさと、時折心を打つさざ波のような味わい。
そんな音楽の成り立ちには、彼らがバンド活動だけではなく全員で釣りに出掛けるなど常にゆるやかに友人として関わっていることが前提にある気がする。それぞれが音楽制作のオーナーとして自立していることとのバランスは、一体どこで取っているのだろう。そんなことがどうしても気になり話を聞いてみた。
前作『Oyster』(2017年)がリリースされた後、2018年にオリジナルメンバーの麻生達也がバンドを離れ、高木ぼらが加入し、おのしほうは住居を東京に移す。そして2020年にガルシアが加入して、『AFRICA』が完成を迎える……これがここ4年のベートーベンズのトピックスだ。『AFRICA』には未収録だが、同時期に制作された楽曲“love song”を今回のインタビュー後に聴き返していた。これは元々バンドメンバーと「飲み仲間」であったガルシアが、初めて江添恵介の家に集まってメンバーと飲んでいたときに、一夜であらかた完成したものだそう。〈今日をおいかけて 暮れるような ひびをすごしていけるかな ながるまま〉と締めくくられるように、彼らの音楽は生活の延長線上というより生活そのものの中でつくられる営みなのだとあらためて思った。
今回のインタビューでは、京都にて生活をしている江添恵介、西村中毒、高木ぼら、ガルシアの4人に、3rdアルバム『AFRICA』の制作をあらためて振り返りながら、渚のベートーベンズというチームの話を伺った。また東京のおのしほうからもテキストで事前質問に回答してもらっている。取材場所は江添がブッキングマネージャーやPAも務めており、それぞれの出会いの場所でもある〈西院ネガポジ〉。
3月21日(月・祝)には初めてメンバー5人揃ってのワンマンライブが磔磔にて行われる。

遊んでいる中で、さりげなく音楽をつくりたい
前作まではそれぞれが書いてこられた楽曲を制作されていましたが、今回は作詞や作曲に複数人の名前がクレジットされていたり、共同作業が多かったのですね。つくり方が変わったのにはどういう経緯があったのでしょうか?
以前は個々にやりたい曲が溜まって、それを持ち寄ってスタジオでアレンジしていく作り方だったんですけど、高木の加入以降は江添さんの家に集まって、ゼロから曲をつくる機会が多くなったんです。その頃江添さんが引っ越したのも大きかったですかね。
しほう以外の京都にいるメンバーで「今日飲もうや」って集まって、お酒を飲みながら曲づくりをしていました。
江添さんのお家にひと通りの楽器や機材と録音環境が揃っているので、お酒飲んだりご飯食べたりした流れで曲づくりが始められるんですよね。
気分が乗ってきたから歌を歌いましょう、って感じで。
その変化は、コロナ禍による影響もあったんでしょうか?
いえ、コロナ前からでした。もうベートーベンズではスタジオに入るより江添さんの家に行ってる回数の方が多い。
3倍ぐらい(笑)
誰かが歌いだしたり、歌詞を書き出したり、その場の雰囲気で遊びながらつくるやり方は、以前もやったことはあると思いますが、そんなに頻度は高くなかったですよね。
ゼロからつくることはあんまりなかったな。
そもそも2018年に高木さんが加入されたのはどういった経緯だったんですか?
以前からネガポジにも無線っていうバンドとして出てくれたり、ライブを観に来てくれてたので知った仲ではあったんですけど。ちょうど無線が解散するということなので、そのタイミングで誘いました。歌詞に重きを置いたソングライターっていうのは、脱退した麻生(達也)くんもそんなタイプだったんですけど、あとの3人はどちらかと言えばメロディーから書くので、そこを補ってくれるかなと。
どんな楽曲をつくるかももちろん知っていたし、つくり手としての感覚が江添さん、しほうさん、僕の3人とは違うなと何となく感じていたので、加入してくれたら面白そうやなとすぐ思いました。
タイプの違いで言えば、みんなコードの理解が早いから音を聴いたらすぐコードを拾ってやりとりが始まるんですけど、僕はそこが苦手でずっと苦労していますね。

そして2020年にはガルシアさんも加入されるんですね。
ガルシアはメンバーになる前から僕の家で一緒に交じって飲んでたんです。いつもいるから、いつの間にかメンバーみたいな意識に勝手になってきちゃってて。
ガルシアさんがいないとさみしいっていう時期がありましたよね。
俺はいないけどガルシアさんはいるって日もあって、そうなるともう感覚としてはメンバーですよ。
だから2020年12月にベートーベンズがネガポジでライブする時に、ガルシアにサポートでギターを弾いてもらうことにして、そのタイミングで正式にメンバーに誘いました。
本当にただ飲み仲間として遊びに行って、ついでにベートーベンズの楽曲制作を手伝えて楽しいなっていう距離感で関わっていたので、メンバーにって言われたときは晴天の霹靂でした。

それで現在の5人が揃ったんですね。飲み会のように集まって、どんな風に制作していくのですか?
僕は歌詞を書き上げる初動だけは早いので、俳句の会みたいにお題を出してもらって、その場で歌詞を書くんです。にっしゃん(西村)もメロディをつけるのがめちゃくちゃ早いので、それで“ブルーチーズ”が一瞬で出来たりとか。
配信シングル“Natural Hiking”のカップリングに入ってる“love song”は、僕が初めて江添さんの家に飲みに行ったときにみんなでつくったんですけど、10分ぐらいで原型になるメロディのコード進行が出来て、高木くんが5分ぐらいで歌詞を書いてました。
つくっている途中でにっしゃんが一回寝たんですけど、起きたら大体出来ていて「めちゃくちゃいい曲出来てるやん!」って驚いてた。
寝て起きたら曲が出来てる飲み会。
今作は奇をてらわず、さりげなくつくりたいとは思っていたんですよ。僕は一緒に飲んだり遊んだりできる人と、バンドがしたいと思っているのもあって、高木が入ったこともガルシアが入ったことも流れのままなんですよね。遊んでいたら結果、音楽になっちゃったっていうのが僕の理想の形だから、その流れで『AFRICA』は出来たと思います。
『AFRICA』制作からみる、渚のベートーベンズのクリエイト
4人が自然に集まり制作する一方で、時勢はコロナ禍であったり、おのしほうとは東京と京都という遠距離での制作となった『AFRICA』。「ベートーベンズが遠距離でも制作が可能だと分かった作品と言えます」とおのからの回答にはあったが、そんな全ての環境の変化が新しいベートーベンズの色として顕著に現れた作品であるようだ。

前作までは混沌とし過ぎてるところもあったんですけど、高木とガルシアさんが入って、バンドサウンドとして聴きやすくまとまったなと思います。
例えば江添さんはギタリストでもあるんですけどアレンジャー寄りなので、音を重ねたり展開で色をつけることが多かったんです。一方ガルシアさんはギター一本のいい音でいいフレーズを弾く。ギタリストらしいサウンドだからすごくキャッチーなんです。高木は軸になる歌詞を書いてくれてる。特に“アメリカ”はガルシアのギターと高木の歌詞に江添さんの歌がしっくりきて、聴きやすい形に落とし込めたと感じています。
僕は『フルーツパーラーミュージック』(1stアルバム / 2015年)の頃から渚のベートーベンズのファンでずっと観ていたので、僕が入る前の方が凝ってたけど、今はそんなテンションでもないから大丈夫かなと、過去の作品を聴き直しながら制作してた時期がありました。これまではしほうさんがずっと京都にいて、バキバキにアレンジに参加してたけど、今回は遠距離でやりとりをしていたことも影響していると思うし、そうやって変化していけるバンドなんやっていうのが発見でした。
江添さんはそもそもエンジニアでもあるからもちろんなんですけど、僕としほうさんもアレンジをしっかりして、マニアックにつくり込んでいくクセがあると思うんです。だから、楽曲の味付けがどんどん濃くなっていくんですけど、高木とガルシアさんという素材を活かす方向の2人が入ったことによって、これ以上コテコテに味付けせんでもいいやんって認識がメンバーの中に生まれた気がします。その結果聴きやすいものになったと思いますね。あと遊びの延長でライトに制作してるから、僕らのアレンジの濃度で丁度いい塩梅になったかな。
でも遠距離とは言えしほうさんの柔軟性は大きいです。データを一回送ってくれて、もうちょっとこんな感じって伝えると、即座に違うアイデアを出してくれるんです。
共作することって、誰がどこまで手を出すのか、出さないのかのせめぎ合いが難しいんじゃないかなと思うんですが、どうまとめていくかはスムーズだったんですか?
全員が曲をつくるバンドってことで、加入当時はさぞかし色々言い合いとかするものなのかなぁってビクビクしてたんですけど、全く揉めることもなく仲良くやってるんで、それが一番ベートーベンズのすごいところだなって思います。
それは結局、面白く遊んでいいものつくろうとしているだけやから、揉める必要がないんやろうね。
自分の色が出したいんだったら、各々自分のバンドだったり別のところでやるんだと思うんですよ。他の人の意見を尊重できなかったら、ベートーベンズでやる面白みがないですよね。

自分らしさって出そうとするものじゃなくておのずと出るもんやから、主張が戦ってるのはしんどいんですよね。強烈なフロントマンの一人がいて、ついていく感じのバンドにしたいわけではないので。5人全員がそれやったら逆に面白いかもしれへんけど、多分バンドが2週間ももたない(笑)。5人がつくる全然違う曲をひとつの作品にまとめていく工夫として、今回で言えば極端にでも決まりごとを設定しました。
どういう決まりごとでしょうか。
3分前後の曲だけを入れるって途中から決めたんです。あとはアナログライクな音にしたかったので、そこに合う曲。だからアルバムの流れや音に合うかという考えはありましたけど、ベートーベンズらしさというテイストは考えてないですね。
むしろ定まったジャンルがなくてどんな曲が飛び出してくるか分からないのがベートーベンズらしさなんじゃないでしょうか。
バンドの基準やアルバムのコンセプトはあらかじめあるわけではないんですね。
アルバムの全貌が見えてからは、それ以降に持って行く曲は流れにハマるかは考えていました。あと個人的にはワードがいなたすぎないようにしてますけど、最終的にどんな曲を採用するのかはまだ分かってないです。
そこは江添さんがジャッジするんですか?
今回に関してはそうですね。
江添さんは人に対して大きく指示するのがめっちゃうまいんですよ。細かいことを全然言わないのに、右か左か悩んでる人に「右やで」って言うのがすごくうまい。その後の細かいことを言うのは僕とかしほうさんの役割になってます。そこが結構重要なんかな。
僕がこうして欲しいというんじゃなく、制約によっておのずと個性が引き出されて、でもまとまりがあるのが理想ですね。今後はもっと制約をつけてもいいかなと思っています。コード3つしか使わへんとか、歌詞に「あいうえお」しか使わへんとか(笑)
実力が試されますね(笑)。でも作品は洗練されていくと思います。
今回、しほうさんが離れているのもあって、自宅で録ったもののファイルを共有して、江添さんにミックス・マスタリングしてもらう形式でやってたんですけど、そうするとオムニバス盤を聴いてるような感じがなくもなかったんです。そういう面白さももちろんありますけど、次は全員でスタジオに入って、似たような音でせーので録音したら、コード進行やメロディにそれぞれの個性が出ても、バンドの個性をサウンドでつくれるんじゃないかって、高木くんとは話していました。
サウンドにも制約を持たせるっていうことやね。
持つギターが変われば出来る曲も変わるし、全員が同じ音をお題にして楽曲をつくれば確かにまとまるのかなと。自分ひとりでつくっていたら出ない発想ですね。
自分一人では想像に及ばなかった音楽が、生まれる過程が楽しい
「全員がソングライター」という枕詞は渚のベートーベンズのお馴染みになったが、おのしほうの言葉を借りるなら「ライティングだけではなく、曲を幅広く受容して自分の持ち味を出していく、アレンジャーとしての才気が全員にある」というのが彼らをたらしめている稀有な魅力なのかもしれない。

音楽だけではないんですけど、何かをつくることって時として一人でした方が早かったり、思った通りに出来たりするじゃないですか。そんな中でバンドとして集まって音楽をすることの最大の魅力って、みなさんにとってどんなところですか?
展開はこの方がいいんじゃないかってみんながアレンジしてくれることだったり、しかもそのスピードがめっちゃ早いのも楽しいポイントですね。初めてベートーベンズ用に作った曲が“冷たい夏のグラス”と“Natural Hiking”なんですが、しほうさんに渡したときに、初手のフィードバックが予想だにしなかった最高のフレーズだったんですよ。やっぱり他の人が思いもしないアイデアを出してくれるので、話し合いながらつくることは楽しいです。
最終的にどんなものが出来るか、分からないままつくる過程を楽しみたいんですよね。そもそも僕は友達とバンドがやりたくて、音楽だけの付き合いで、スタジオだけで会うのではなく、やっぱり音楽も遊びだと思いながらつくっていたいです。
よくみなさんで釣りにも行かれていますけど、それも同じような感覚なのでしょうか?
そうですね。みんなが釣りに興味持ってくれたので、メンバーで行くようになりましたね。みんな凝り性やから、ちょっとハマり過ぎてます(笑)
単純に「お前こんなデカいの釣ったん!?」って喜び合えるのが嬉しいですね。一人で行ったら写真撮ってくれる人もいないし。「あのときに釣ったあれがさ」っていう話をまた酒の肴にしたり。
みんな遊ぶことも好きやから、あんまり真面目に考えると音楽もよくもならへん、って考えは共通認識の中にありますね。
みんなで集まるだけじゃなく、個別に飲みにいったりもしますし。ガルシアさんに大宮のお店を紹介してもらったのが楽しかった。教えてもらったバーに、次はにっしゃんと行ったり。
みんなで遊び続けられるっていうのは、バンドをやっていく上でサステナブルでもありますよね。江添さんがセルフレビューの中で“アメリカ”を「おっさんがやりそうな曲」って形容されてたのは、年を重ねても長くやれる曲っていう意味もあったのですか?
それは「おっさんが好みそうなロック」って意味だったんですけど(笑)。そうですね、楽しんでやり続けるっていうのは大事にしたいです。いつまでやろうとかは何も決めてないけど、今だけじゃなくて、10年後聴いてもいいなって思える曲をつくりたいっていう意識はありますね。
“アメリカ”に限らず、10〜20年経っても聴ける、それでいて単純なグッドミュージックに収まらない音楽ばかりだと思います。

live information
| 公演タイトル | 渚のベートーベンズ・磔磔ワンマン |
|---|---|
| 日時 | 2022年3月21日(月・祝)OPEN:17:00 / START:18:00 |
| 会場 |
京都府京都市下京区筋屋町139−4 |
| チケット | 前売:2,500円 当日:3,000円 学生:1,500円 |
| 予約 | nagisa.no.beethovens@gmail.com |
AFRICA

アーティスト:渚のベートーベンズ
仕様:デジタル / CD
発売:2021年10月20日
価格:¥2,200(税込)
収録曲
1.DEAD
2.名画
3.22世紀の唄
4.砂の男
5.ブルーチーズ
6.Windom Age
7.Knock Knock
8.海を見た日
9.街にヤバい奴らが増えた
10.Beautiful
11.記憶のラプラス
12.戯言
13.アメリカ
14.アフリカ
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
滋賀生まれ。西日本と韓国のインディーズ音楽を好んで追う。文章を書くことは世界をよく知り深く愛するための営みです。夏はジンジャーエール、冬はマサラチャイを嗜む下戸。セカンド俗名は“家ガール“。
OTHER POSTS