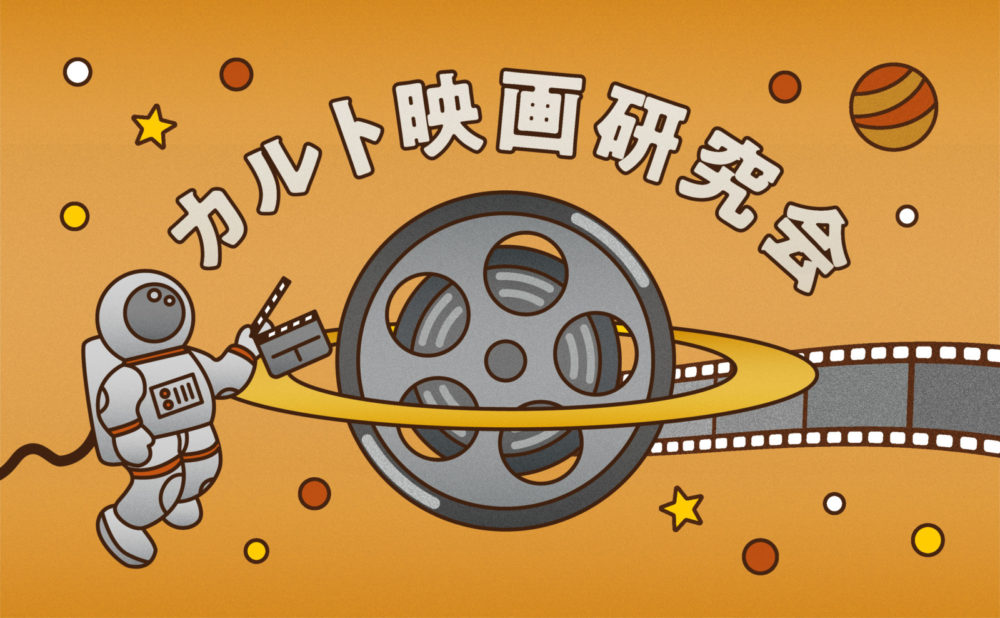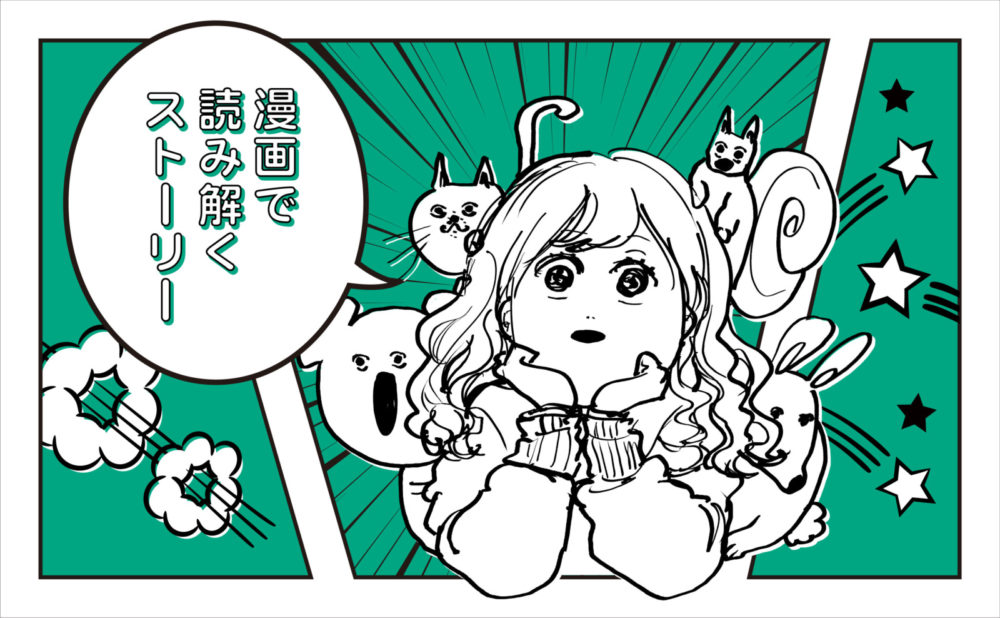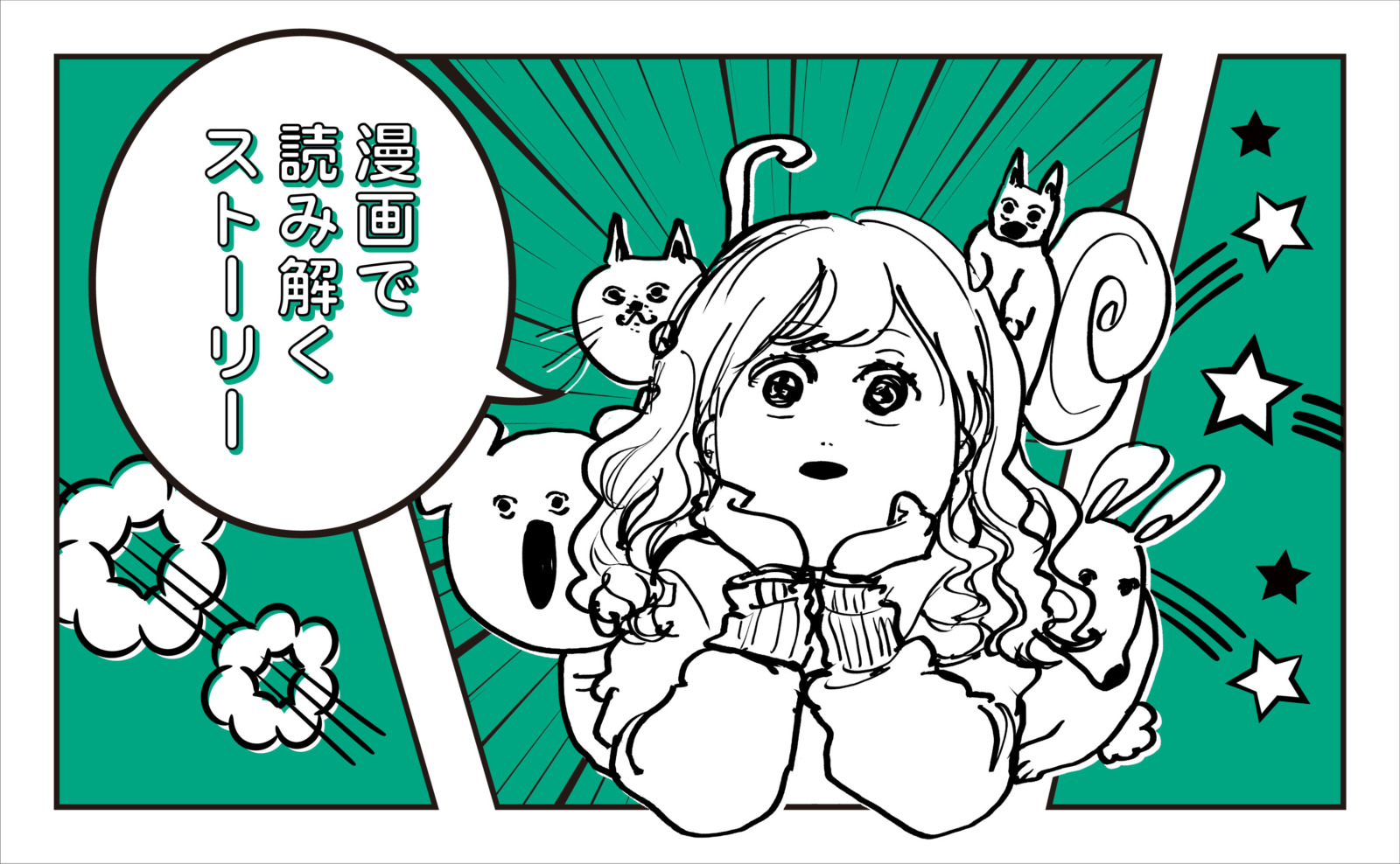
【漫画で読み解くストーリー:第9話】『最後の遊覧船』に見るマンガと映画の関係性
イラスト提供:中田アミノ
マンガ家はみんな映画が好き
1947年に手塚治虫先生が『新宝島』を発表して以来、マンガ家は実写映画に憧れ続け、嫉妬を原動力にしてきました。マンガは、映画が持つダイナミズムをなんとか取り入れようと進化してきたメディアと言っても過言ではありません。
紙に絵を描く。それは「書きたいものがそこに在る」という情報です。それが写真になると「写したいものがそこに在る」だけではなく、被写体自身が持つリアリティ、写り込んだ背景などが情報として含まれます。さらに映画になると全ての存在に動きが加わることに。「立体」としての三次元情報に時間軸が加わることで、その膨大な情報量を演出・構成していく映画には自ずと相応のダイナミズムが必要になってくるのです。
あくまでマンガは二次元の表現。動画である映画には情報量の多さではかないません。そこでマンガは読者にキャラクターの動きを脳内補完させる「コマ割り」という技術を使って、時に映画以上の臨場感と迫力を表現する独自の手法を確立するに至りました。
しかし、マンガが映画から受けた影響は必ずしも「動き(アクション)」だけではなかったのです。すぎむらしんいち先生は1987年講談社「ヤングマガジン」で『サムライダー』を連載して以来、その作風には常に映画への愛がありました。キャラクターの表情やセリフやアクション、画面の構図やコマ割りにおける間の取り方。さらに破天荒でありながらどこかリアリティのあるストーリーは、まるで映画のような印象を受けます。そのように感じさせるのは、僕は「役者(キャラクター)の生身感」と「ストーリーの映画的まとまり、及びスケール感」がポイントだと思っています。
主人公の選択が関わる人に影響を受け、目まぐるしく変化する
そのことがよくわかる作品が、2020年から小学館「ビッグコミックスペリオール」で始まった4年ぶりの連載、『最後の遊覧船』(現在は連載終了、2巻で完結)。本作のストーリーは、月9ドラマでかつて一世を風靡したシナリオライター湖尻洋子(すぐに実在の脚本家であるあの方が思い浮かびますね)がスランプから故郷へ帰るものの、そこで出会った遊覧船の船長が気になって一向に仕事が進まず……という一見地味な設定。ですが、次から次へと現れる曲者の登場人物、全く先の読めない展開は最終的に天変地異のスペクタクルに至り、まさに「面白い映画を観た!」という読後感です。
最後の遊覧船

作者:すぎむらしんいち
連載: 2020年
掲載誌:ビッグコミックス
そもそもすぎむら先生の作風は(原作付き連載はともかく)地味で小さなところから次々と状況が転がり続け、ラストシーンに至ってストーリーの全体像がわかるというもの。『最後の遊覧船』もまた同様に、キャラクターの行動や思惑が同時進行で並走しながらドラマを作り出していきます。連載作品によくある主人公の主観で話が進むのではなく、主人公の洋子と関わった様々なキャラクターが持っている事情や行動が洋子に影響を与え、それによって洋子がまた行動を選択する。そのことで洋子を中心とした人間関係が、一つの大きなストーリーの「うねり」をつくりだします。
まるで映画のような「一つの物語」を生み出す肝がそこにあります。言い換えれば、連載であってもすぎむら先生は「読み切り」並の切れ目のないドライヴ感を持ってストーリーを転がし続ける事が出来る。これはマンガを描く方ならわかると思うのですが、とてつもない構成力とキャラクター造形力のなせる技なんですよ!なんせ脇役がいないんだから!
なぜそんなことが出来るのでしょうか?すぎむら先生が各方面から絶賛される天才だからなのは間違いないのですが、僕はその秘密が「映画」にあると思っています。
『最後の遊覧船』に出てくるクセのあるキャラクターたち。船長、売店の祐子、ホテルマンの吉田、劇団の網走さん、島の管理人の本橋、もぎりのおじさん、その他全ての登場人物はこの物語の中で生きており、マンガで描かれていない人生さえも読者に印象付けます。
そこまで全員のキャラを立たせると主人公のドラマじゃなくなっちゃう?そうならないのは彼らが皆「生身の役者」みたいだからなんですね。脚本を理解した上で自分の持ち味を最大限アピールしようとする役者だからアドリヴもあるし、監督はそこから展開のアイデアを拾う。ストーリーを考えてキャラクターに役割を与えるのではなく、クセの強い役者に脚本を渡して演技させる。そこからインスピレーションを受けた監督(すぎむら先生)が役者に合わせた展開を作っていく。そんな感じなんですよ!
マンガのキャラクターを役者に押し上げる映画への愛
マンガは二次元でストーリーを語るメディアです。表現方法は進化してきたとはいえ限られたページ数で読者に物語を伝えるためには、無駄を省いてキャラクターの演技を厳選し、わかりやすい構成にする必要があります。そうしないと読者がストーリーを掴みきれずに迷ってしまう。そこにはキャラクターをリアルにすればするほど、ストーリーを語る上ではリアリティがノイズとなってしまうジレンマがあります。マンガのキャラクターは生身の役者と違って限定されたリアリティの中で生きる記号的な存在だからです。
しかし、すぎむら先生のマンガではそのキャラクターのノイズも拾ってストーリーを構成していきます。繰り返しになりますがすぎむら先生のキャラクターたちは、それぞれに人生を生きています。だから誰も都合よくは動いてはくれない。その状況を監督はなんとかまとめなくてはならない。そんな先の読めない話がつまらないわけないじゃないですか!
しかも『最後の遊覧船』の主人公・洋子はドラマの脚本家。物語自体が主人公の書く脚本とメタ構造になっていて、執筆でアイデアに詰まった主人公が自ら行動して状況を動かそうとする展開そのものが、すぎむらマンガのメタ構造ともなっていて凄い!
『最後の遊覧船』という物語が映画のようなリアリティとカタルシスを持っているのは、すぎむら先生の映画への愛があるからなんだと思います。登場人物が物語の中で生き、そこでそれぞれの人生のニュアンスを残し、それらがさらに舞台のグルーヴを生み出し、状況が変化してその状況にまたキャラクター達が飲み込まれる。そんな物語の行き着くところにあるのは、人間のどうしようもなくバカで、エネルギッシュで、愛おしくて切ない姿なんですね。
それはマンガが映画から受けたもう一つの影響の最高の形なんだと思います。
「物語とはあたりまえの日常を壊すところから生まれる…つまりそれは俺たち脚本家の性(さが)なのさ……」 by本橋信夫
You May Also Like
WRITER

-
石川俊樹プロフィール:1962年東京生まれ 大学卒業後浦沢直樹先生のアシスタントを2年勤めた後、マンガ家兼アシスタントとして業界で働く。現在名古屋造形大学造形学科マンガコース准教授。バンド「フラットライナーズ」Ba/Vo
OTHER POSTS
【名古屋造形大学】
http://www.nzu.ac.jp/index.php
【マンガコースブログ】
http://www.nzu.ac.jp/blog/manga/
【フラットライナーズ】
http://isosounds.com/flat.html