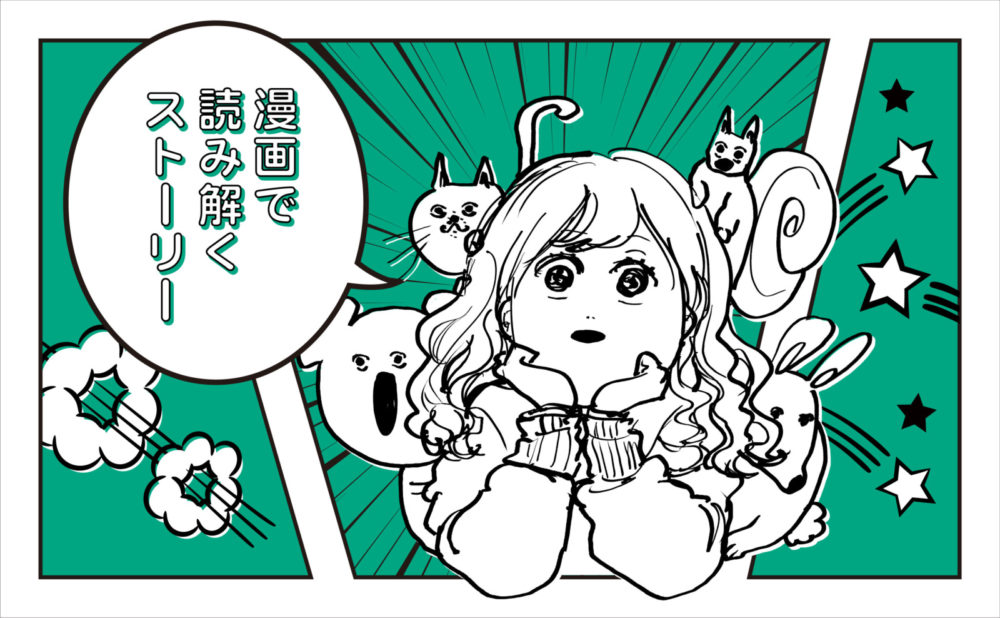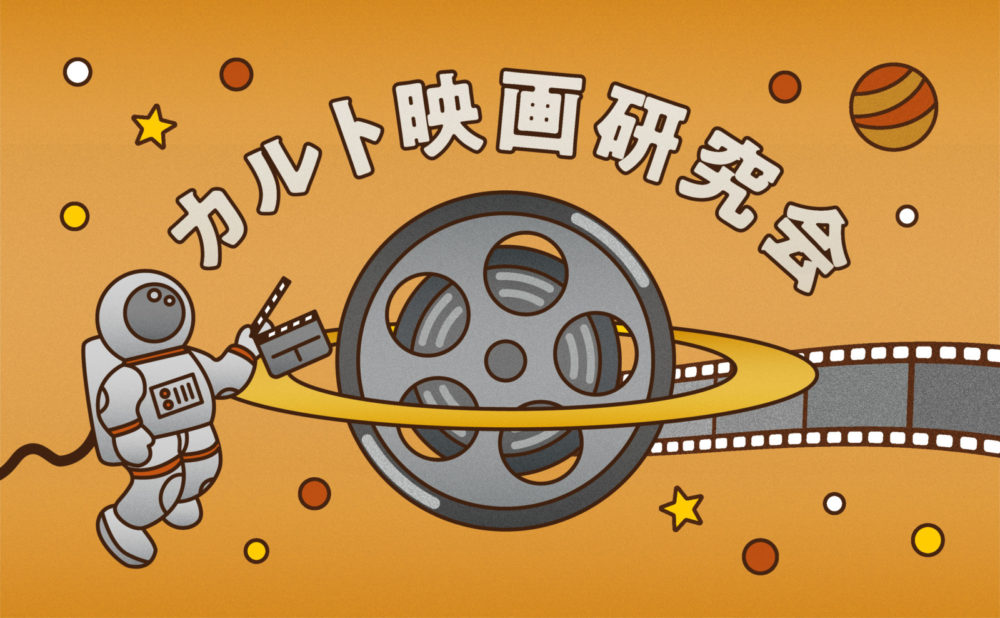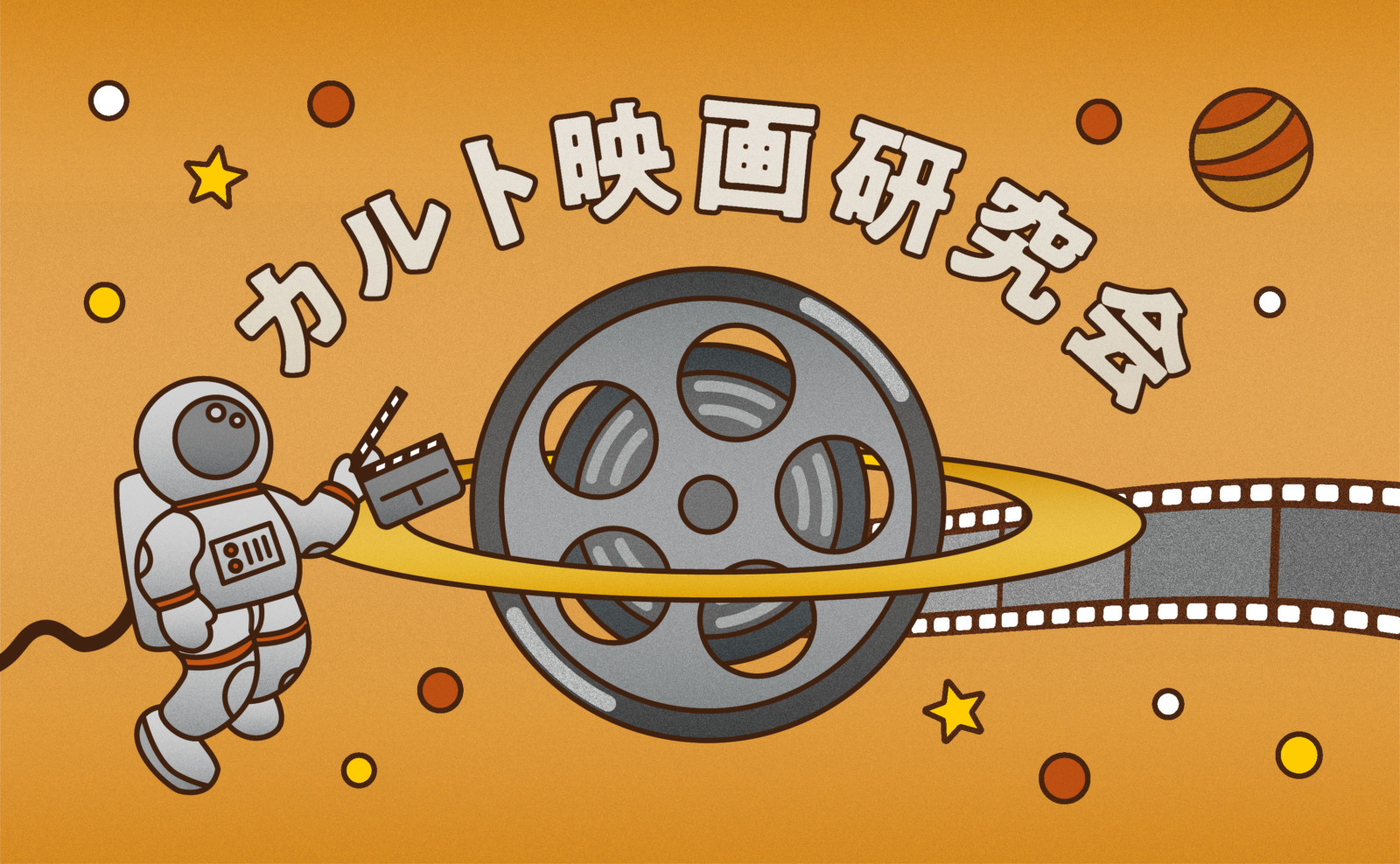
【カルト映画研究会:第10回】ブリグズビー・ベアー(Brigsby Bear)
現在コロナ禍で全国の大学生はいわゆるキャンパスライフを謳歌できない状況である。自分が勤務する大学でも授業がリモートになり大学へ登校できず、同期や先輩と知り合う機会がなくなったり、クラブ活動が制限されたり、その結果「キャンパスライフ」が失われた世代として不満や嘆きの声も大きい。これではなんのために大学へ来たのかわからない、学費を減額しろ、という主張も無理からぬ話だが、それはまた別の問題としてここでは「いわゆるキャンパスライフ」とは何か?を考えてみたい。
許されざる犯罪行為と、感動作としてのストーリー
キャンパスライフは10代20代の多感な年頃に勉学だけではなく恋や友情やなんやかやを通じて人間的成長を育む、人生においても特別なモラトリアムというイメージがある。「青春そのもの」と言ってもいい。だが実際のところその「青春」は最も景気の良かった80年代バブルの頃の自由奔放な大学生のイメージをいまだにベースにしており、そもそも大学生活は自由で楽しくあるべき……とは限らないのだ。
デイヴ・マッカリー2017年監督作『ブリグズビー・ベアー』の主人公ジェームズは幼少期に誘拐され25歳に至るまで外界と遮断された環境で独自の教育を受けていたという設定である。誘拐犯であるテッド(マーク・ハミル!)とエイプリルは偽の両親を演じ続け、彼ら以外の人間を知らないジェームズは従順に彼らの教育を受けて成長するが、彼らがジェームズのために作ったハンドメイドな教育プログラム番組が「ブリグズビー・ベアー」という連続冒険ドラマなのだ。しかしそんな日々もいつまで続くわけもなく、ある日警察が来てジェームズを解放しジェームズは初めてリアルな外界を知る事になる。
誘拐、監禁は犯罪である。そこは間違いのないところとして、もし誘拐犯が物心つかない子供を誘拐して25年間愛情かけて独自の教育をしていたら?その教育や犯人の愛情もまた断罪されるべきものなのだろうか?……問答無用で「当たり前だ!」と考える人の目にはこの『ブリグズビー・ベア」』という映画は偽善的で犯罪行為を美談にすり替えようとする不愉快な産物のようにも映る。しかし果たして本当にそうなのだろうか?この『ブリグズビー・ベア』という映画はそんな感情におけるグレーゾーンに切り込んだ意欲作とも言えるかもしれない。
とは言えこの映画はそんなに小難しい映画ではない。ノリはオフビートでハートフルなコメディなので誰にでもとっつきはいい感じである。クライマックスにはベタな感動シーンもあって、一見すると「優しさと勇気を与えてくれる」感動作みたいなつくりでもある。確かにジェームズの本当の両親や本当の妹のオーブリーと友人達、元演劇部の刑事などちょっとみんな単純でいい人すぎる感じはある。気になるのは誘拐犯のテッドとエイプリルがなぜそのようなことをしたのかのバックボーンがあまり語られていないところだが、虐待や性犯罪ではなく一種のニューエイジ思想にかぶれた終末思想的ヒッピーのようなもので、イかれてはいるがジェームズに注いだ愛情は本物のように見える。
ただそんな優しい世界のドラマもベースには許されざる犯罪行為がある、というアイデアそのものが挑戦的で簡単に感動作として飲み込んでしまうのは危険だと自分は判断した。……その上であえて言うとこの映画はやはり「感動作」なのだと思う。
最悪の青春の中から最良の部分を探すという、主人公の肯定的な態度
誰でも人生は一度きりだし、より良く生きたいと思うのは皆同じである。そのために我々は法律を遵守し他人に迷惑をかけずに生きようと努力する。ただ同時に過ちを犯すのもまた人生である。そんな正しさと過ちの凸凹模様の中でより良く生きるのは大変な事だし、だからこそドラマがそこに生まれるとも言える。この映画を観て感じるのは、そんな凸凹模様の人生でより良く生きようとするのには指針が必要であるし、夢中である事、許すことがヒントであると教えてくれる。ありていにいえばそれは「愛」であり、この映画は愛に小綺麗な形ばかり求めず、不細工だったり不器用だったりするところにも愛はあるのではないか、という事が言いたかったりするのではないだろうか?
もちろん現実はもっと複雑だしこの映画のようにハートフルな展開はそれこそファンタジーなのかもしれない。しかしそれを伝えることができるのがフィクションであり、映画の良さであると自分は考える。
「自分の人生かくあるべき」という考え方には多分にイメージが関係している。冒頭の今の大学生もそういったイメージと比較して自分達は損をしていると考えるのだろう。だがあらゆる人にとって20代の大学時代は一度きりだし、一つとして同じものはないはずだ。思い出したくもない学生時代を過ごした人も少なくないだろうし、人生最高の時期と言い切る人もいるだろう。
この映画は最悪の青春を過ごしたジェームズが、それでも肯定的にその中から最良の部分を抽出し、なんとか立て直そうと奮闘するそのポジティヴな姿勢によって人々との愛を見つけ出すという寓話である。
もちろん個人の犯罪と現在のコロナ禍の状況を並列で語ることには無理があるしコロナの状況は個人を超えた政治的レベルでの問題でもあるのだが、少なくともコロナ以前のイメージを追い続けいつまでも「失われた青春」を嘆いていては、それこそたった一度の人生、もったいない気もするのである。
映画の出演者であった薄幸そうなウェイトレスに主人公が会いにいくシーン、マーク・ハミル演じる偽の親父が刑務所で主人公に誘拐した懺悔をするシーンは、いろいろな人生があり、全ての人生は肯定されるべきという感じがしてとても好きだ。
企画趣旨とその他の掲載作品一覧
You May Also Like
WRITER

-
石川俊樹プロフィール:1962年東京生まれ 大学卒業後浦沢直樹先生のアシスタントを2年勤めた後、マンガ家兼アシスタントとして業界で働く。現在名古屋造形大学造形学科マンガコース准教授。バンド「フラットライナーズ」Ba/Vo
OTHER POSTS
【名古屋造形大学】
http://www.nzu.ac.jp/index.php
【マンガコースブログ】
http://www.nzu.ac.jp/blog/manga/
【フラットライナーズ】
http://isosounds.com/flat.html