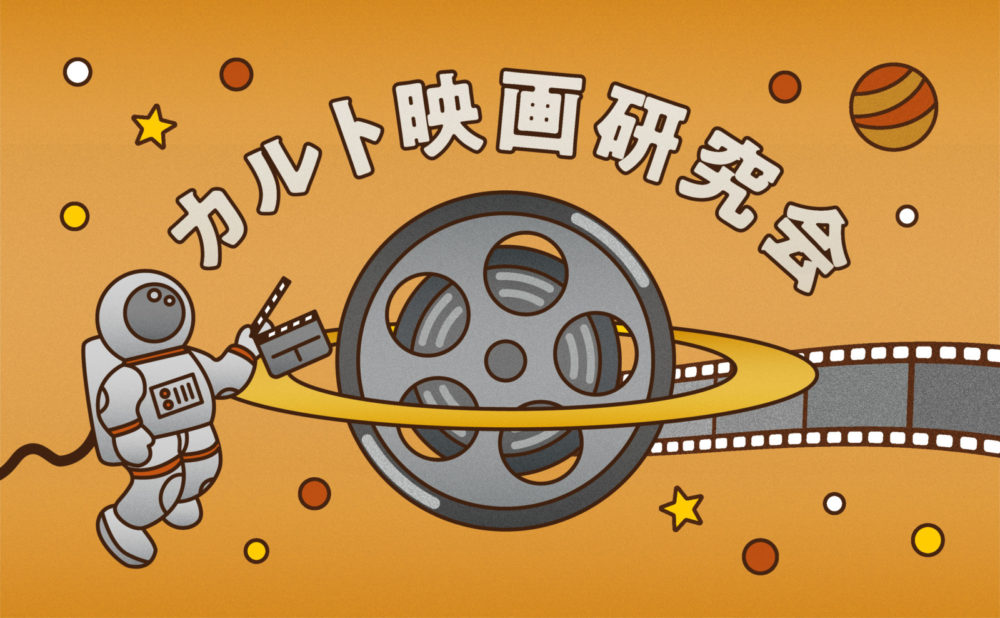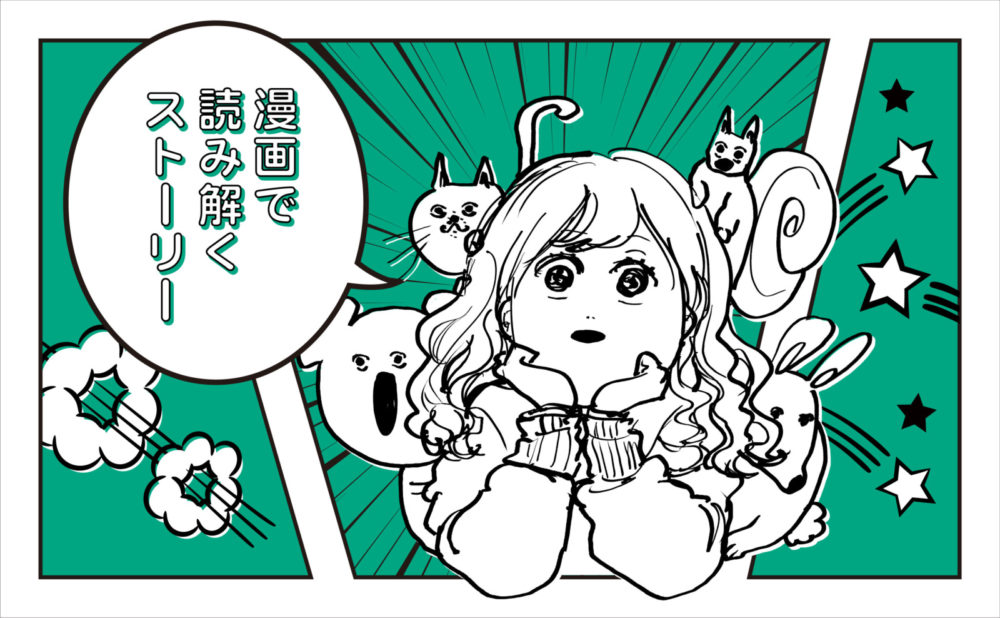『ブレードランナー』解析講座:過去からの影響と、未来への影響を8本の映画から探る – 中編 –
©2017 Alcon Entertainment, LLC All Rights Reserved
4作品目:新しい未来イメージの誕生『ブレードランナー』

『デュエリスト』『エイリアン』と基本1対1の対決をモチーフにした非常にシンプルなプロットを手がけてきたリドリー・スコット監督は、ついに後に様々な解釈を生み出すようなスケールの大きい複雑な映画に挑戦する。それが後のSF映画のマスターピースとなる『ブレードランナー』(1982年)である。
もともとSFに大した興味のなかったリドリー・スコットだが、数々のCFを手がけた映像畑の人間らしく『エイリアン』の成功によってSF映画は先進的映像技術や先進的イメージの追求をするのにうってつけのジャンルである事がわかり、自信をつけたのは間違いない。そして少々傲慢でもあった。
前述した通り『ブレードランナー』は77年に脚本家ハンプトン・ファンチャーがフィリップ・K・ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』の映画化権を獲得したところから始まっているが、そもそもファンチャーが原作を大幅にチャンドラーテイストのハードボイルド調SFに改変しているところから始まり、最終的にリドリー・スコットは『ブレードランナー』を作るにあたってディックの原作小説を全く読んでいなかった事を後年告白している。にもかかわらず(映画化のプロセスには懐疑的だった)ディックは完成した『ブレードランナー』のラッシュを観て「まさに私の想像した通りだ」と感嘆したというエピソードは興味深い。それほどまでに『ブレードランナー』で描かれた未来のビジュアルはユニークかつリアルだったという事だろう。
ファンチャー(後に脚本はデヴィット・ピープルズに交代)とスコットが映像化にあたって大いに参考にしたコミック(バンド・デ・シネ)にメビウス・ジャン・ジロー作画の『ロング・トゥモロー』(1976)という作品があり、その原作はダン・オバノンであった。漫画家メビウスと脚本家オバノンはともにホドロフスキー監督の『デューン』プロジェクトに参加しており、後にメビウスはホドロフスキー原作の『アンカル3部作』を発表し、日本でも大友克洋を始め多くの漫画家に影響を与えている。
『ロング・トゥモロー』は荒廃した未来都市の探偵の元に謎の美女(異星人)が依頼に来るところから始まるハードボイルドタッチの短編コミックだが、地球の表層から掘り下げられた雑多な未来都市の中をエアカーが飛び交う”絵”は『ブレードランナー』において2019年のロサンゼルスをスピナー(エアカー)が飛ぶシーンに確実に影響を与えている。『ロング・トゥモロー』がいかにしてスコットの元に渡ったかは不明だが、『エイリアン』で招集されたチームにオバノンとメビウスがいた事も関係ないとは言えないだろう。
さて、『エイリアン』の強烈なキービジュアルを作りエイリアンを体現するアーティストにもなったのがギーガーその人だったが、『ブレードランナー』においてそのビジュアルデザインを担い未来を体現するアーティストにもなったのがシド・ミードである。
ミードはもともと工業デザイナー(主にカーデザイン)であり、未来のコンセプトカーを描いた画集『センチネル』(1979)が注目を集め、スコット監督に『ブレードランナー』における未来の車両デザインを依頼されるが、やがてスコットはミードがデザインした車両が素晴らしいだけでなく、その背景に描かれた未来都市そのものに自分のイメージを見い出し、全面的にプロダクションデザインを任せる事となる。ロン・コッブの合理的で無駄のない無骨なデザインはいかにも深宇宙を旅する宇宙貨物船にふさわしかったが、それとは対照的にミードのデザインには優雅さとシャープな冷淡さがあり、それが使い古されたウェザリング(汚し)を施される事で一種独特な”ポスト産業化社会”のイメージが創出された。一種のディストピアとも言える混沌した未来像は資本主義の悪夢であり、消費社会の彼岸をも予感させ、当時新宿歌舞伎町の映画館で『ブレードランナー』を観た自分としては、映画館を出てそのあまりに地続きなイメージにクラクラした事を覚えている。
もう一つ、『ブレードランナー』の創出した強烈なイメージが”レプリカント”と呼ばれる人造人間。それまでSF映画に出てくるアンドロイド(人造人間)といえば、ロボットのより人間に近い姿バージョンが主流であり、人間が演じる場合でもどこか無表情で無機質な演出が為されていたように思う。”レプリカント”は生身の臓器と感情を持ち、見た目、立ち振る舞い、話し方、考え方、全てにおいて人間と区別がつかないばかりか、作った人間以上の知性と体力を持っているという設定だ。その唯一の弱点(?)が意図的に設定された4年間という寿命であり、その事をめぐるレプリカントの実存的葛藤と闘いがこのドラマの主軸となっている。人間に似せて造られた無表情で無機質なアンドロイドではなく、4年間の寿命と人間以上の能力以外は人間と同じ感情を持つレプリカントという存在を演じる難しさはこのテーマにおける大きなポイントだったと思うが、レプリカントのリーダー、ロイ・バッティ役のルトガー・ハウアーは見事にキャラクターを作り出し、主役のデッカードより明らかに魅力的だ。当時ハリソン・フォードが主役にもかかわらず役に不満を持っていたのもわかる気がする。
リアルな未来都市とレプリカントという哲学的な存在を扱いながら、70年代のディストピア映画やダークヒーローを擁したSF映画にならなかったのは、ひとえに物語がリック・デッカードというキャラクターの主観を中心に進むからであり、同時にそのデッカード自身が広大な物語のありふれた存在であるというハードボイルドにおける”自主性”と”客観性”を持っていたからに他ならない。この物語では主人公が地球の危機を救うわけでもなく、社会構造に影響を与えるわけでもなく、広大な(そして殺伐とした)世界の中の一人の男が体験した事件であり、彼自身がそこで悟った真実と、そこからジャッジした小さな決断を描いている。デッカードは無力な存在であり、時に自分の人生に自嘲と自己嫌悪を覚えているような(未来の)ありふれた人間だが、レプリカントのロイと死闘を繰り広げる過程において”生”に執着するレプリカントの怒りと諦観から、自らの人生における”生”の意味を見出す点にこの映画の最大の感動がある。ヴァンゲリスのシンセサイザーを基調とした未来的ながら哀愁を誘うブルージーなスコアは、この映画のそんなテーマを見事に演出している。
しかし、前作『エイリアン』のヒットに対し、『ブレードランナー』は公開当時全く振るわず早々に上映が打ち切られてしまう不人気ぶりだった。何故か?簡単に述べれば『早すぎた』作品だったと言えよう。同じ先進的イメージをありったけぶち込んだ『エイリアン』と『ブレードランナー』を比較すると、前者はプロットが単純であり観客はそのイメージに惑わされずとも十分に理解できるストーリーと作り込みと関係なくドキドキできる古典的スリラーな演出があったが、『ブレードランナー』を理解するにはその舞台となる世界観とそこに生きるキャラクターをまず理解する必要があり、展開も観客が期待するような勧善懲悪SFアクションではないため、観客は一体この物語における善玉と悪玉はどれなのか次第にわからなくなるようなプロットについていけなかったのであろう。もちろん当時でもグレーゾーンを描く映画は数多くあったが、不評の原因の多くはビッグバジェットの『SF映画』に対するエンターテイメントとしての要求を満たしていないと判断された事のように思う。後年の高評価はご存知の通りだが、かくして時代を変えるエポックメイキングな表現は得てして苦難のスタート切る事が世の常なのである。
NEXT PAGE
5作品目:サイボーグは電気羊の夢を見るか『攻殻機動隊』
You May Also Like
WRITER

-
石川俊樹プロフィール:1962年東京生まれ 大学卒業後浦沢直樹先生のアシスタントを2年勤めた後、マンガ家兼アシスタントとして業界で働く。現在名古屋造形大学造形学科マンガコース准教授。バンド「フラットライナーズ」Ba/Vo
OTHER POSTS
【名古屋造形大学】
http://www.nzu.ac.jp/index.php
【マンガコースブログ】
http://www.nzu.ac.jp/blog/manga/
【フラットライナーズ】
http://isosounds.com/flat.html