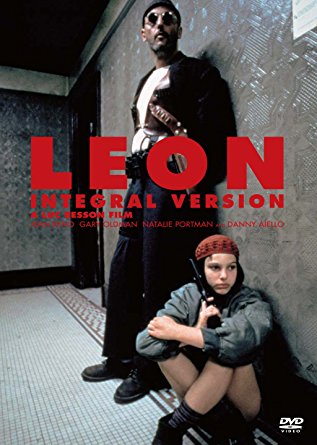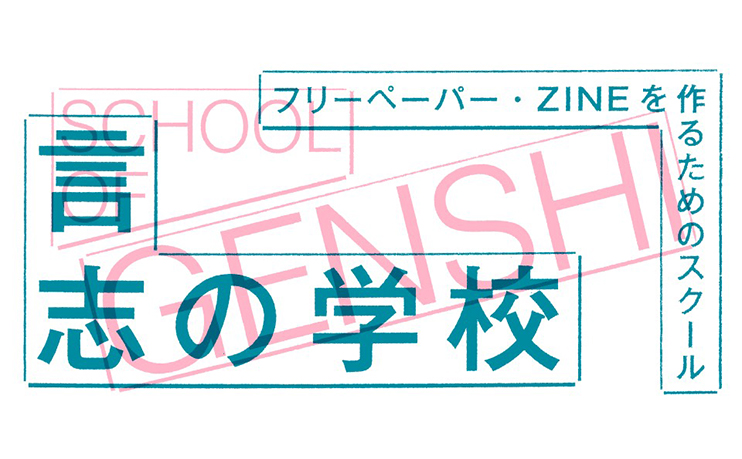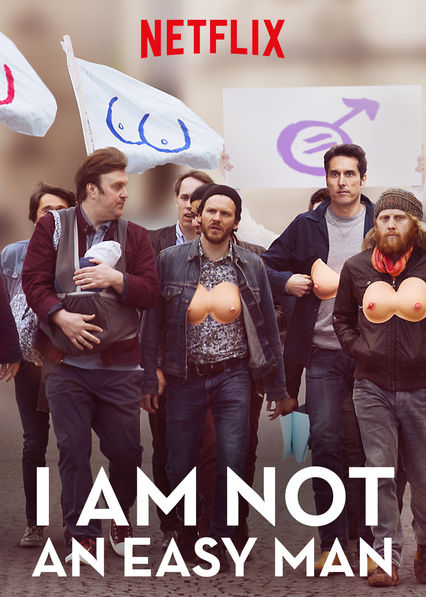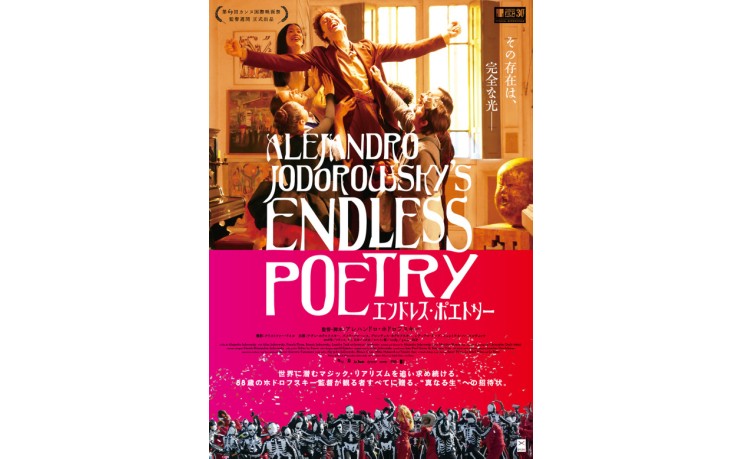【脇役で見る映画】『愛がなんだ』 テルコより大切なのは仲原くん。赤いメガネのボスによろしく
(C)2019「愛がなんだ」製作委員会
上映がはじまってからもう2カ月近くも経っているというのに、その日のテアトル梅田は平日の昼間だというのにほぼ満員でした。上映を知らせるチャイムが響いて、会場内にクスりと微かな笑いが漏れる。学校みたいだね、と黄色くか細い声が後ろから聞こえる。
そう、普段映画を見ないような人がミニシアターに足を運んでいる。微笑ましい光景だ。
頬を緩めると同時に僕は意地悪に鼻を鳴らしたくなった。ほんと、気を付けてね。共感しようがしまいが絶対この映画しんどいから、と。上映後、案の定の空気で観客(筆者を含む)が劇場を後にすることになります。
つい甘えさせちゃう
まだ作品を見ていない人のためにも、あらすじ紹介がてら冒頭のシーンを振り返ってみましょう。
風邪で動けないから、もし仕事帰りで時間があったら何か買ってきてほしい。田中マモルからのそんな電話を受けて、山田テルコは颯爽と支度をして自宅を飛び出す。マモルからの電話を待ちわびていたことなど、微塵も匂わせることなく、あたかもまさに残業中のようなフリをして。彼の自宅で頼まれていないのに鍋焼きうどんを振る舞い、さらに鼻歌交じりに掃除をしていると突然彼は「帰って」と冷たく促してくる。突然の状況を呑み込めないまま身支度も半ばドアの外に追いやられ、しかたなしに車の行きかう七号線をとぼとぼと歩きながら金麦を呷る。
もし原作を知らなくたって、このシーケンスさえ見れば予想がつく。ああ、これは生傷を負うタイプの映画だ。このようないびつで非対称な男女関係をまざまざと見せつけられるのが『愛がなんだ』という物語です。
この偏愛は、自己表現とアイデンティティだ

主人公のテルコは、恋人という関係が叶わなくてもそれでもマモルと繋がることにしがみつく。「たぶん恋ではない。きっと愛でもない」この「執着」の正体がわからない。わからないけれど、もう逃れられない。しかし、意地悪な僕はこう考えてしまいました。
テルコのこれは、「唯一の趣味としての性愛」なんじゃないか。
山田テルコという女性には何もありません。仕事に精を出しているわけでなければ、クリエイティブな趣味や活動をしているわけでもない。原作小説や映画の描写を読む限り、おそらくは学歴もない。岸井ゆきのは美人だけれど、テルコという人物自体は決して美人ではない。(意地悪な言い方になってしまったけれど、非実在の人物が相手だから許してほしい)
そんな彼女が自分を自分だと強く認識する唯一の手段が、マモちゃんへの執着を実感することだったのでは? 少なくとも僕はそう思わずにはいられませんでした。
だからテルコはどうでもいいけど

いるよね、こういう人。だから見透かされるし、マモちゃんくらいの頭の人には無意識に利用される。
人間は好きなことや嫌いなことを共有して親密度が深まると思うんですよ。それがないと何も生まれないとすら信じています。でもテルコには好きなことが何もない。これまでいい加減に生きてきたから。
けれど性愛は生まれつきインストールされた唯一のセンサーです。例外はあるかもしれないけれど、誰しもに備わっているセンス。たとえばスポーツでも文学でも、なんだって娯楽を楽しむには努力してルールやコードを覚えたり、技術を染み込ませたり時間を費やす必要があるじゃないですか。
それを怠った人間でも、努力せずとも「好き!」を公言できるのが性愛です。この物語の中での描写で言えば、たまたまお互い手持ち無沙汰だった時に会話した、優しい、手がキレイ……。ほら、どれも深いコンテクストの前提は必要ないでしょ?
だから僕はテルコのことは正直どうでも良いんです。他人に依存するような自己表現なんかはやく卒業できればいいねと思うけど、まあ本人が納得しているなら水はさせないですよ。
ただ、僕の心配は別のキャラクターにあります。こいつ、まじで放っておけない。
どうした仲原

僕が心を痛めながら見つめていたのが、若葉竜也の演じる仲原くんという男の子。彼もまた非対称の人間関係に苦しんでいたのです。
深川麻衣の演じる葉子という女性に想いを寄せ、「付き合う」のような形のある関係を作ることができなくたって構わないと彼は語ります。覚えていてもらえるだけでも良いんだ、と。左側の口角の上にある小さなホクロがチャーミングだ。葉子(というか深川麻衣)はたしかに可愛い。気持ちはわかる。彼は葉子のために愛玩動物を演じる。構いたいときにだけ構い、あげたいときにだけ餌をあげるような無邪気で無責任な飼い主に忠誠を尽くすのです。
でも、君は写真家じゃないか。テルコなんかと違って、そこまですがりつくことないじゃん。アイデンティティはハッキリしてるじゃん!
しんどい思いをしなくたって……待てよ?あれ?もしかして。
拝啓、赤眼鏡のアーティスト

最後に彼の撮った写真がスクリーンに登場するのですが、そのほとんどがポートレイトでした。もしかして、仲原の自己表現は身の周りの人間関係から感じとった機微をアウトプットすることだったのかもしれない。
だとすれば。
それなら納得がいく。葉子のことが好きという感情や、にも関わらず成就しないというアンビバレントな心境は、彼の芸に直結する。それは彼の心臓だ。
それがなくなってしまうかもしれない。この関係は心を滅ぼすけれど、だけど傷ついた心こそが自分なのだ。そんな自分を失うのは怖い。自分の表現がなくなってしまったら、それは自分ではないから。
なんだか最近、聴いたことある。あの日の水曜日の深夜3時だ。自身のラジオ番組「不毛な議論」(TBSラジオ)の終盤、蒼井優と結婚したら自分の芸が壊れてしまうのではないかと逡巡する胸の内を打ち明けて涙を流した山里亮太と同じなのかもしれない。「わかる」なんて到底口が裂けても言えない。僕はそんな神の領域には達していないのですから。でも「わかる気がする」。
もう会うのやめるっす。そう決意して葉子との関係を絶ってから開いた彼の個展にも、やはり彼女の写真はあります。つらいことであっても蓋をして埋めるのではなく、表現に昇華しないと気が済まないのです。彼は表現という悪魔と握手をしてしまったのですから。この個展を最期に彼女のことは一切忘れてしまおう。そう考えていたのではないでしょうか。その個展の名は「一瞬の夢」と題されていました。
それでもカメラマンとして個展を開くのは、そんな一瞬の夢がさめてしまった後でも自分は写真で表現を続けるのだという宣言だったのではと僕は信じています。
自分の表現の手段は、必ずしもひとつじゃない。
表現の源泉を、どこに求めるべきか。まさか角田光代と今泉力哉が、そんな角度で揺さぶってくるとは想像だにしなかったと俯きながら帰路につくのでした。
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
95年生。映画ライター。最近大人になって手土産をおぼえました。
OTHER POSTS
「フラスコ飯店」というwebの店長をしています。