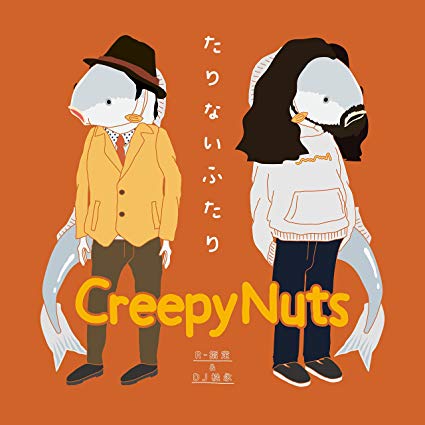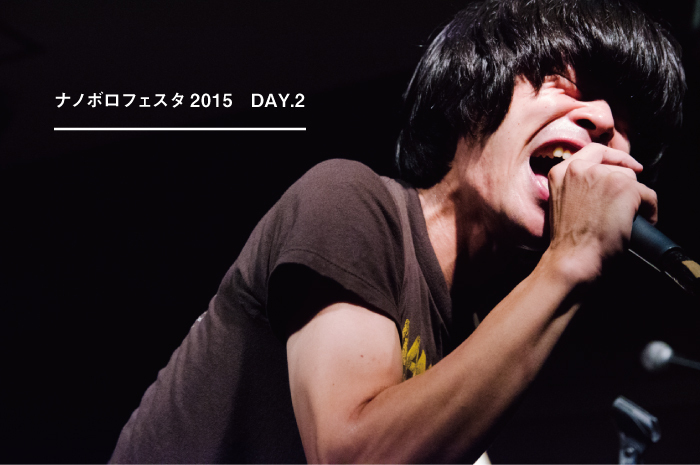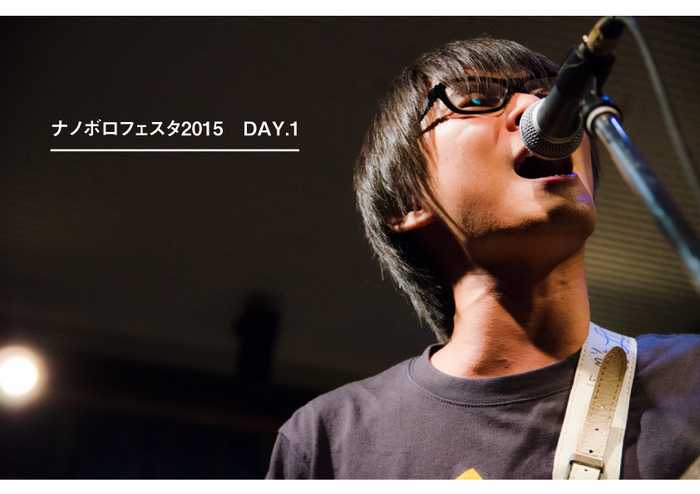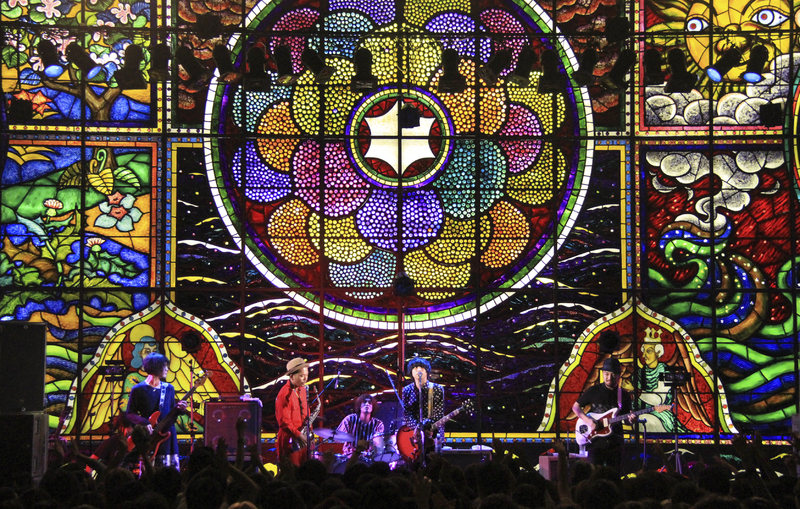中村佳穂、1年9か月ぶりの新曲“アイミル”。主人公・すず/ベル役の声優を務める細田守監督の最新作『竜とそばかすの姫』も7月16日に公開を控えており、まさしく第二章の幕開けを告げるこの楽曲を、編集部員7名で総力合評します。
Apple Musicはこちら
“AINOU” =(I know)から“AIMIRU”=(I 見る)へ(峯 大貴)
2010年代を代表するポップ・アルバムとなった『AINOU』(2018年)で放った矢が2020年代の幕をぶち破り、時流の風によって軌道を変えながら、2021年という的のど真ん中を射抜くような。中村佳穂1年9か月ぶりの新曲“アイミル”は、それまでと地続きなメッセージを持ちながら、ビビットな変化を遂げた楽曲だ。
ベーシックな進行のトラックとハンドクラップが延々と続いていくシンプルな構成。やけに硬質で艶を消したようなサウンドには今回中村・荒木正比呂(レミ街)と共に、作曲でクレジットされている西田修大の寄与が大きいだろう。そこにひらひらと歌い舞う中村佳穂が表明するのは〈つまりもっと単純に「すき」は「すき!」と言ってちょうだい〉と自分の感情を言語化し、そして伝えていくことの提唱だ。これは〈知らない方が近いんだよ〉と、形にしなくてもあなたの想いはわかってるから!と歌い切った“AINOU”と相反するようにも見える。
しかし他者との繋がりを求める根源は変わらない。この曲は時代が変わったことで見えにくくなってしまった他者との歩み寄りを促す号令なのだ。“AINOU” =(I know)とはもう言いがたいから、より能動的な“AIMIRU”=(I見る)へ。人との繋がり方をアップデートするところから着手した、中村佳穂・新シリーズの導入にまんまと惹きつけられている。(峯 大貴)
人生のステージに合わせた示唆をくれる、未来のスタンダード・ナンバー(柴田 真希)
音楽は「聴く」ものだが、タイトルでも歌詞でも「見る」ことに注目している本楽曲。ジャケット、リリックビデオを紐解くと、楽曲が「子ども」と「親」、そしてかつて「子ども」だった人やこれから「親」になる全ての人に向けられていることに気がつく。
加瀬透がアートディレクションを担当したジャケットはカラフルで、一見何が写っているのか分からない。だけど眩しくて水の流れに動きがある映像のような一枚は、曖昧で、何を見ても驚きと感動があった幼少期の記憶を思い起こした。kazuo が手がけたリリックビデオでは、卵の形に分断されたジャケットの写真が曲に合わせて動く。そして最後にやっと見える写真の全体像には鳥が映っている。卵はじきに鳥になるのだ。そう思うと〈好きは浴びるとなんと 空も飛べちゃうのさ〉というのは子どもに沢山「好き」と言って育てて欲しいという、全ての親へのメッセージのようにも聞こえてくる。
〈大人だってしょうもないんよ〉と子どもに話しかけるような歌詞もあり、誰もが簡単に楽曲に参加できるハンドクラップが1曲を通して鳴り続けていることも助け、全ての世代に向けたポップソングとして完成している本楽曲。人生のステージに合わせた示唆を与えてくれそうで、長く大切に聴いていきたい一曲だ。(柴田 真希)
まなざしの変化 ビートから客観視へ(マーガレット安井)
中村佳穂の新曲“アイミル”は「音楽をどう観客に聴かせるか」に興味が移行した作品だ。2ndフルアルバム『AINOU』では「ビート」という部分に興味を持ち、打ち込みも使用し、トラップ以降のラップにも通じるリズム、南米音楽、クロスリズム、など多種多様なビートをアルバムに取り入れた。本作においてもビートの主張は強い。ミニマルミュージックのように、同じ動きをするクラップとベースラインはどの音にも埋もれることなく力強く、楽曲の軸となっている。
また本作は主旋律の引き立て方がうまい。伴奏やコーラスの入れ方を小節単位で変え、メロディと違う動きを見せる部分も多い。ともすれば情報量の整理がつかず、音楽が破綻しかねないが、歌やギターソロなどその場面に応じて、音量・音圧をコントロールし、交通整備の行き届いた楽曲に仕上がっている。ビート、伴奏、コーラスに共通しているのは「複雑なものをシンプルに聴かせる」ことだ。それは「リスナーに対して、自分の音楽どう思われたいか」という点に着地する。細田守監督のアニメ映画『竜とそばかすの姫』に出演し、今後ますます注目を浴びるであろう中村佳穂。より多くの人に自分の音楽を伝える、その結論こそ“アイミル”での「シンプルに見せる」部分に集約されているのではないか。(マーガレット安井)
あなたもわたしも主人公の、ネクストストーリー(小倉 陽子)
中村佳穂の作品は常に「私」を力強く歌う物語である。と同時に彼女からみた、リスナーである「あなた」を同等に尊重するパワーがある。
『AINOU』(2018年)収録の“アイアム主人公”では、他人に期待することへの諦めのような気持ちを滲ませながら、自分の人生の主人公は自分でしかないことを高らかに歌った。本作は同様のエネルギッシュなリズムにその続きが感じられ、複雑な悩みの先に見つけた、シンプルで明快な答えを提示するような楽曲になっている。そして、自分が主人公の世界に対して、楽曲前半では〈世界は言ったもんで作られていくわ〉と示し、後半では〈世界は見たもんで作られていくわ〉とも言い切る。
ブレイクで現れる「スーハースーハー」という呼吸のモチーフも、世界はアウトプットとインプットでつくられていることを象徴しているみたいだ。表現する自分と、世の中の表現を受け取る自分。どちらも等しく並べることは、どちらも自分をつくるのに大切な要素であると同時に、表現者である中村の人生も、受け取るリスナーの人生も脇役にしないという、彼女の音楽の魅力そのものようだ。
それにしても中村が提示する「インプット」が「聴く」じゃなくて「見る」なのは、彼女のフィジカルなパフォーマンスゆえという気がするし、映画という観る世界で主人公の声をつとめるネクストストーリーにも通じていた……というのは考え過ぎだろうか。(小倉 陽子)
What a Wonderful World!(阿部 仁知)
中村佳穂の1年9ヶ月ぶりの新曲“アイミル”には、純粋無垢な感情が溢れんばかりに表現されている。それは未知なる世界と対峙しながら自ら切り開いていく喜び、つまり〈世界は言ったもんで作られていく〉あの眩い感覚のことだ。センス・オブ・ワンダーともいえるその感覚は、彼女のクリエイティビティの範疇を飛び越え聴いている僕らまで広がっていく。
熱心なリスナーならサビの“LINDY”の引用はすぐにわかるだろうが、終始楽曲を貫いていたギターリフと比べて、本曲で通底するのはハンドクラップ。誰にだって鳴らせる最もプリミティブなその音色が、歌やピアノと絡み合いながら本作を緩やかにドライヴさせていく。とりわけ西田修大のギターソロに感化され不意に刻みを遊ばせるようなブリッジから終盤にかけては、喜びがお互いを刺激して新たな表現が生まれていくようだ。
〈世界は見たもんで作られていく〉という主題は、ともすれば「世界は自分の認識したものでしかない」なんてニヒリズムに陥りそうなものだが、彼女の歌唱からそんなニュアンスはまったく感じられない。広い世界に飛び込んで、たくさん出会って、表現して、変化していく自分に驚いて。そんな彼女が〈世界はイメージ通り作られていくわ わ わ〉と3度繰り返す語尾の“わ”が、僕には「What a Wonderful World!」に聞こえてくるのだ。(阿部 仁知)
彼女の歌声をアップデートさせた、誰かと音楽をつくる喜び(乾 和代)
現実があまりにも理不尽に、自分を蹂躙していくんだ。誰もがそんなことを感じずにはいられなかった2020。このコロナ禍という今を経て、1年9か月ぶりにリリースされた中村佳穂の“アイミル”を歌う彼女の声は、肩の力がふっと抜けるような空気感をまとっていた。
彼女が音楽を始めた頃の、鍵盤を叩けば話言葉すら歌へと変換していた圧倒的な存在感はそこにはない。アルバム『AINOU』(2018年)でもお馴染みの荒木正比呂や西田修大と共に制作された本作だが、アルバムの頃の歌い方とも違う。コロナ禍の今、何を歌うことができるのかそんな模索の先に見つけた答えのような新しさを感じる歌声なのだ。
〈否定じゃない選んでるだけさ 君が君がつくるのさ〉
スポーツ選手でもこれまでのフォームを変えるのは難しい。ノリにのっている選手なら尚のこと。今回、それを歌声で彼女がやってみせたように思えてならない。そして、そんな彼女の進化に応えるように、間奏ではギターの西田がエフェクトで歪がみに歪ませた渾身のソロをきかせている。これも、誰かと共に音楽を作ることを選んだからこそ生まれたフレーズなのではなかろうか。友と音楽を作る喜びを知った彼女の見つめる先には、まだまだ新しい世界が広がっているにちがいない。(乾 和代)
歌詞に書かれなかった「ずっと傍で」。そこに込めた肯定する意思(出原 真子)
自己肯定感を持つことができない。無理に見つけようとしても、こぎつけみたいでなんだか虚しい。しかし、「ずっと傍で」肯定してくれる存在に気づいた時に、自分自身を受け入れられるのかもしれない。そんなメッセージをサビの歌詞に書かれなかったコーラスから感じ、ハッとしてしまった。
<つまり 世界は言ったもんで作られていくわ 沢山“言うのだ”>
その裏で、空耳かと思うほどさりげなく “ずっと傍で” と流れてくるのだ。しかも、あえて歌詞に書かないことによって、その存在感がより一層引き立つように感じる。同じフレーズが“LINDY”(2019)にも存在するが、こちらは歌詞にも明記されている点に注目したい。中村は“LINDY”にまつわるCINRA.NETのインタビューで、肯定される不安が歌詞に出ていると吐露した上で、「自分が自分のままでいて、そのまま愛されるって、奇跡的なことだと思うんです」と語った。この言葉を引き継ぐように、本作では私たちが私たちであることを全力で肯定し、ありのままに生きるように導いている。
しかし、<沢山“言うのだ”><沢山“見るのだ”><沢山“知るのだ”>と最後の一歩を私たちの意思に委ねているのは、中村自身が音楽活動を通じてバンドメンバーに肯定される喜びを享受してきたからではないだろうか。仲間の存在が今では当たり前になったから、もう確かめなくても大丈夫だから、本作の歌詞では「ずっと傍で」をあえて明記しなかった。そして、今後も新たなつながりを求めつつ、私たちに “応援をあげる” 存在であり続けたい。彼女のそんな強い意思が宿っている気がしてならないのだ。(出原 真子)
You May Also Like
WRITER

-
地域に根ざした世界中のインディペンデントな「人・もの・こと・場所」をおもしろがり、文化が持つ可能性を模索するためのメディアANTENNAです。
OTHER POSTS