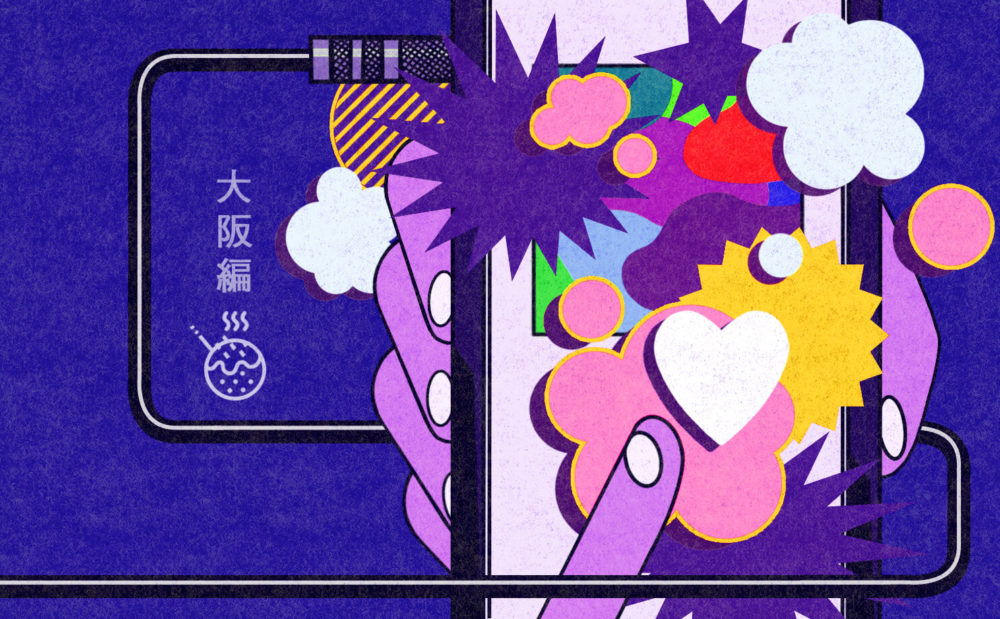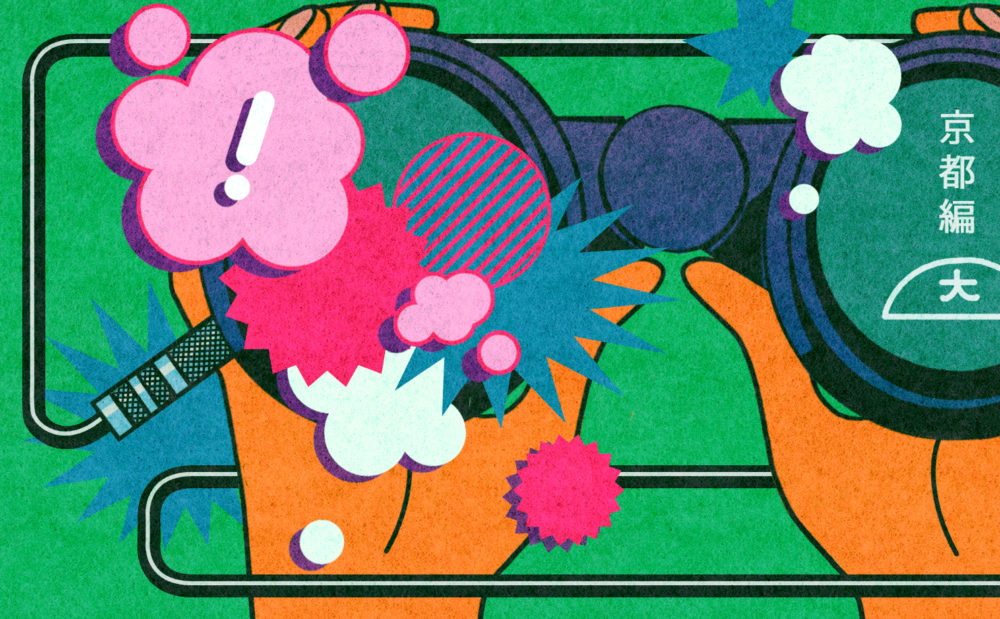【東日本編】ライブハウス・クラブでの思い出のエピソード
募集の経緯
こんにちは、編集長の堤です。
2ヶ月前、コロナウィルスが中国で発症したとのニュースを見た時に、ここまで大きな火の粉が自分たちに降りかかることを予測した人がどれくらいいたでしょうか。僕自身、かなり甘くみていた節がありますし、のんきに3月の旅行のことを考えていました。その状況が大きく変わるのにたいして時間がかからなかったことは、みなさんもご存知の通りです。
今、多様な人を受け入れ、また人間としての豊かな営みを生み出してきた多くの場所が存続の危機に瀕しています。ライブハウス・クラブ・映画館・ギャラリー、文化的な場に限らずバーやカフェも似たような状況でしょう。なによりも厳しいのは政府や行政に自粛は求められるが、補償も給付も約束されていないこと。
私たちはインディーのメディアです。今できることは多くないかもしれません。なにができるかを悩んだ末に、まずは「少しでも文化的なものを身近に感じてもらえないか」という考えにいたりました。先日、実施された「Save Our Space」という自粛要請に伴う助成金交付のための署名活動では、予想を上回る30万もの賛同が集まりました。こういった活動をもっと後押ししたい。そのために「暮らしの中にある文化や芸術、それを一人ひとりのエピソードを通じて伝える」ことで、社会の中での文化・芸術のあり方を可視化したいと思ったのが、今回の募集の経緯です。
映画館やギャラリー、イベントなど多くのものごとをテーマに公募したいと感じてはいるのですが、まずは「ライブハウス・クラブでのエピソード」からスタートさせていただけますと幸いです。ぜひみなさんがそれぞれの場所で、どのような体験をされてきたのか、そしてあなたをどのように形づくっているのか、その声を聞かせてください。
北海道:札幌 KLUB COUNTER ACTION
寄稿者:Cossackさん
漠然と何かのクリエイターになりたいと思い、ロクに学校行かずにバイトしながら週5で通い詰めたライブハウス。気づけばそこでバイトしていた。
クラブに来る外人と毎回のように喧嘩していたらスタッフになった先輩1。会話のほとんどがラップになっている先輩2。そしてすごい才能溢れてかっこよかったけど、結果的に墨汁やボンドをよく口から吹き出していた先輩3。
3人にだいぶ雑に教えてもらいながら1年ちょっと働いた。13人でパグパイプを演奏する屈強なガテン系スコットランド好きバンドと角煮を振る舞うバンド、寺山修司について熱すぎるくらい語る、元暴走族の特攻隊長がボーカルで、入場曲がなぜか白鳥の湖のバンド。これまでインストだった曲にボーカルが何かを思い、「となりの海のワカメは青い」と歌ったあのバンドは、解散してもずっと忘れることがない。
ちょっと極端な世界観もあったけども、あの場所があったから、世界の広さとか人の違いを楽しむことができています。
東京:TSUTAYA O-Crest(渋谷ON AIR)
寄稿者:75さん
ライブハウスと音楽が繋いでくれた嘘みたいな本当の話。
2018年3月、渋谷のTSUTAYA O-Crestで開催されたハンブレッダーズのレコ発を観に行った。対バンはナードマグネット。私は当時21歳。熱くぶつかり合う2バンドがあまりにもかっこよくて、胸がいっぱいになりながら道玄坂を下った帰り道を今でも覚えています。
それからハンブレやナードを好きなったおかげで「パワーポップ」に出会い、聴き漁って偶然辿り着いたJellyfishというアメリカのバンド。サイケデリックなジャケ写が目に止まり、再生してみるとどこかで聴いたことがある気がした。そういえばこのジャケ写も見たことある。
そんな曖昧な記憶の正体は中学生の頃の自分にあった。音楽に興味を持ち始めたばかりの私は、母からJellyfishのCDを譲り受けていたのであった。思わぬ繋がりが嬉しくてすぐにCDを取りに実家に帰ると、母はJellyfishの来日ライブを渋谷の<ON AIR>というライブハウスで見たと教えてくれた。そんな名前のライブハウスあったっけ、と思い調べてみると<TSUTAYA O-EAST>の前身となる箱らしいことがわかった。そして、1993年に<ON AIR>でJellyfishの来日ライブを観た母も当時21歳だった。
21歳の母と、21歳の私。同じライブハウスで大好きなパワーポップスターを観て、余韻に浸りながら道玄坂を歩いた夜があったなんて。名称や形態が変わっても20年以上の時を経て繋がった奇跡みたいな偶然は、歴史があるからこそ起きたこと。音楽好きにとって何よりも大切なライブハウスを守って、これからも沢山のドラマで歴史を紡いでいけますように!
東京:下北沢Club Queでのエピソード
寄稿者:村田タケル(SCHOOL IN LONDON)さん
2012年。深夜の下北沢Club Que。10人にも満たないお客さん。その一人こそおれ。
就職に伴う上京。ロックが好きだったからロックのパーティーに行きたかった。ライブの折込フライヤーで知ったパーティー。行ってみて、お客さんが少ないことなんて自分には関係無かった。
自分が知らないカッコいい音楽。新しいものも古いものも。自分が知っている音楽。しかし、DJが作る曲の流れで自分が知らない良さに気付く。興奮した曲の繋ぎを思い出しては、買ったばかりのDJプレイヤーで真似してみる。そんな日々をずっと過ごした。
いつの日か自分自身もDJになっていた。今では中規模イベントにも出演できる機会がたまにあるけど、あの日の10人にも満たないアンダーグラウンドで起きていたことが礎としてあることは確か。小さなものでもプライオリティな価値観として実践できるインディペンデントな場所がそこにはある。人との出会いに価値を置く人も多いけど、自分の中ではクラブとはそんな場所。
東京:新宿Nine Spicesでのエピソード
寄稿者:貧乏暇なしさん
岡安嬢(アンテナ副編集長)にはお世話になったり、少しの嫉妬心を抱きながら関東で活動しているカメラマンです。
昔、ずっと好きだった人といろんなライブに一緒に行ったり、 好きな音楽や色んな趣味を共有していたけど色々タイミングが合わず付き合うという事はなく、ただ仲のいい友達という感じでそれ以上は近づきもせず離れるもしない感じで過ごしていて、僕から海外のバンドKittyhawkを勧めたら相手もとても気に入ってくれて、お互い来日を楽しみにしていたけど、いつの間にかそのバンドは解散してしまって一度も見れずに終わっちゃたなぁと残念な気持ちとちゃんと大人にならなきゃいけない年代(未だにちゃんとした大人になってないけど)というのもあり、お互い連絡もあまり取らなくなってしまい、SNSとかで何しているかを知る程度になってしまって数年。
僕が敬愛して聞いているmalegoat・The Firewood Projectのベーシストの岸野一氏が今年の1月にthe lost boysという名義でまさかの解散したKittyhawkのJapan tourを組んでくれて、真っ先に連絡をしようと思ったけど相手は結婚もして生活も変わっただろうと思い、直前で思いとどまり連絡する事なく来日公演最終日の新宿<Nine Spices>に行くと、その子が旦那さんとライブに来ていて色々思い出しちゃったのとずっと見たかったバンドを見れたので複雑な感情になってしばらくはポカーンとしちゃってたけど、いつまたこんな出来事があるか分からないからしっかりフンドシ締め直してかっこ悪いところ見せられないなと自分に一喝。
音以外にもいろんな出会いや感情が渦巻くライブハウス。 今は大変な時期だけれどもまた素敵な出会いやドラマを作ってくれる日がまたすぐ訪れますように。 僕が勧めた音楽をずっと好きでいてくれてありがとう!
神奈川:F.A.D yokohama
寄稿者:Yukiさん
11月中旬。寒気が街を覆い始めた頃、クリスマスの訪れをちらつかせる横浜の街並みを、僕は一人歩いていた。OGRE YOU ASSHOLEの新譜『フォグランプ』のツアーに参加すべく、F.A.Dという初めてのライブハウスへ向かっていた。
大人の入り口に差し掛かった年齢の僕が一人で来る、ほとんど初めての横浜。テレビで見ていたおしゃれな街を、ちょっとドキドキしながら歩く自分が少しイケてる男になれたかも、と錯覚していたのは、自分だけが知っている素晴らしい音楽を楽しみに行くんだ、というインディーキッズ特有の若気の至りもあったと思う。
店名のネオンが光り、様々なバンドのポスターが貼られているウインドウ。ちょっと怪しげな空気に、背徳感に似たわくわくを感じる。到着までの道すがらに中華街で買った肉まんなんかほおばってみたりして、白い息を吐きながら開場を待った。派手なことはなかったけど、この日の様子はなぜだかはっきりと覚えている。
対バンのおとぎ話のステージに飾られた、儚げなイルミネーションと多幸感のある演奏。MCもほとんどなく、淡々と演奏をするオウガの面々。大歓声が沸くわけでもなく、一心にステージへ腕を振る様な場面もなかった。だけれども、グラスを片手に、ほほえみをたたえながら、それぞれが気持ちよさそうに揺れる。終演後のフロアは一人ひとりの充実感で満たされていたように思う。
一人で来た僕も誰と話すわけでもなく、冷たさの強まった横浜の街を駅へと早々に引き返していった。自分だけの充実感を胸に。こころなしか、街の灯りが来たときよりきらめいて見えたような気もする。
ただライブハウスへ行き、音楽を聴いて、家路につくという、言葉にすればささやかな一日。けれど10年経った今でも、そのささやかな一日のほのかな温かさがこうして胸に残っているのは、街々にあるあの空間での体験があったからこそだと思う。
こうした何気ない日常への喜びを、これからも感じられる世界が続けられますように。
You May Also Like
WRITER

- 編集長
-
26歳で自我が芽生え、とうとう10歳に。「関西にこんなメディアがあればいいのに」でANTENNAをスタート。2021年からはPORTLA/OUT OF SIGHT!!!の編集長を務める。最近ようやく自分が持てる荷物の量を自覚した。自身のバンドAmia CalvaではGt/Voを担当。
OTHER POSTS