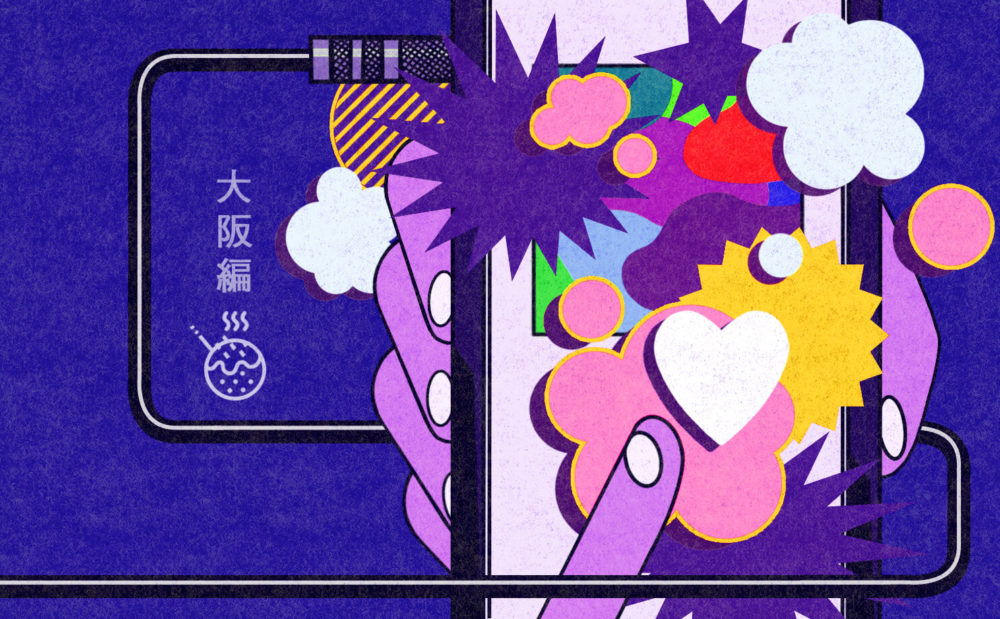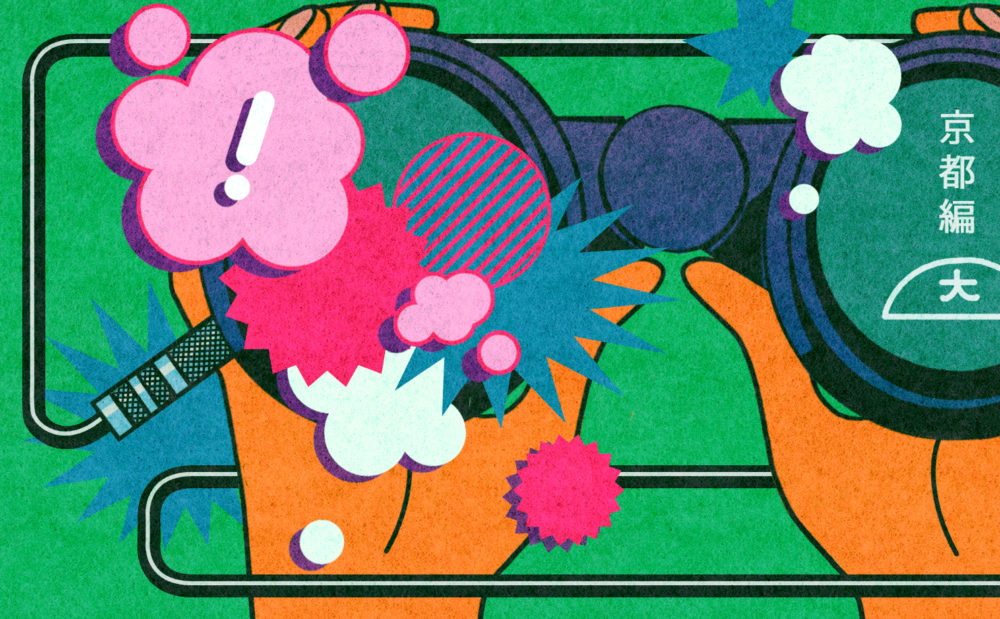【SXSW2022】地元に根付いたバカ騒ぎの種火たち、3年ぶりのオースティン探訪
COVID-19が世界的な問題となり、国境が封鎖されていった2020年の春。SXSWは1987年以降の歴史で初めてイベントを中止した。2021年度はオンライン開催のみだったので、僕がオースティンへ訪問できたのは3年振り。今回で計4度目のSXSW参加となった。久しぶりに訪れたオースティンは「相変わらず」だったとも思うし、その一方で「随分と変わった」と感じることもある。そんな「街の変化」をベースに、2022年のSXSWの出来事を振り返っていきたい。
パンデミックの傷跡残る街の中心地
3月のオースティンは、陽が登るまでは随分と冷える。その後、太陽が登ると同時に街が温まり、そして夜はまだ熱が街に留まっていて随分と過ごしやすい。そう、オースティンは夕方から夜にかけての時間が気持ちよく過ごせる街だ。だから、26時まで野外でライブが行われるのが当たり前になるのかもしれない。今回初めて時差ボケになり、朝の6時頃に目が覚めるようになってそんな気候のことを知った。これはSXSWの盛り上がりに関しても同じことが言える。カフェでPCや本を広げて過ごすなど、朝はどこかのんびりとした空気が漂うオースティン。街が温まっていくにつれて、人々のテンションも盛り上がっていく。
そんなSXSWの「賑わい」を象徴するのが6thストリートだ。オースティンの繁華街を東西に走る、中心となる通りのひとつ。イベント期間中は4車線分の道路がホコ天になってあちらこちらにパフォーマーや流しのミュージシャンが現れる。またストリートの南北に面したレストランの(ほぼ)すべてがライブハウスやクラブと化し、若い男女はもちろんインタラクティブへの出展など日中の責務から解放されたビジネスマンたちが思い思いに身体を揺らして夜を楽しむ。
毎年、このストリートへ足を運ぶと「SXSWに来たな」という感覚があるのだが、今年に限っては「騒ぎの中心」がこの場所ではなくなってしまったように感じた。特に、ミュージックフェスティバルが始まるまでの期間は、昼も夜もひっそりとしていて寂しさを覚えるほど。それもそのはず。COVID-19の影響を受けていて、まだいくつかのテナントが「FOR RENT(賃貸用)」の張り紙を出している。特に残念だったのはアメリカでは貴重なクオリティの高いラーメンとおにぎりが食べられる〈Daruma Ramen〉や、毎年勢いのあるイギリスのアーティストが目白押しとなる『British Music Embassy』の会場〈Latitude 30〉がクローズしてしまっていたことだ。

〈Latitude 30〉では2018年にはIdlesやSuperorganism、2019年にはblack midiなど、今や世界を代表するイベントに出演を重ねるアーティストを目と鼻の先という距離で見てきた。それが今年は〈Cedar Street Courtyard〉という6thストリートからは少しだけ外れた、ダウンタウンでは比較的大きめの会場へ移動。キャパは250人→700人まで増加したらしいが、ほとんど同じ目線の高さで、アーティストの汗やツバが飛んでくるほどの距離で音を浴びる熱を帯びる体験は少し遠のいた印象があった。

そういった変化は残念だったが、ポジティブな側面もある。『British Music Embassy』は毎年連日満員で、必ず入場制限がかかっていたからだ。COVID-19をきっかけに注目度に合わせた適切な会場に移動したと見ることもできる。ただ、会場のキャパが3倍近くになった今年ですら、Yard Actの出演時には身動きができないくらいにオーディエンスで一杯になっていたし、今年の最注目アクトのWet Legが出演する時間は会場に入場できないほど行列ができていた。今後、イベントの規模をどのように保つのかは、UKミュージックの存在感を見極める一つの指標となるかもしれない。
街は今、その熱を周縁に宿している
『British Music Embassy』のベニューの変更で語るべきことがもう一つあるとすれば、コンベンションセンターや6thストリートなどの繁華街を中心に形成されていたSXSWの熱が、オースティンの街中から外側に拡散していっていることだ。変化を進める要因としては土地の高騰が大きいという。端的に言えば、ジェントリフィケーションだ。その2019年以前からその傾向はあったが、決定打はきっとCOVID-19だったのだろう。
オースティンで、ライター兼フォトグラファーとして活動しているブライアンという友人がいる。彼から聞いたのは、ここ2,3年で僕たちが想像できないほどのスピードでオースティンの土地が高騰しているとのことだった(アメリカでも抜きん出て!)。街中の家賃は2,3年の間で倍近くになってきていて、そのため、多くの人が郊外や他の街に家を構えるようになっている。ダウンタウンのマンションはワンルームで1億を超えるらしい。郊外の一軒家では3LDKで5000万となる。近くにある同規模の都市、サンアントニオに行けば似た条件の家が2000万程度で買えるらしく、オースティンの土地の高騰ぶりが伺える(書いていて思ったが、日本の土地も相当に高い)。
COVID-19に加え、土地の高騰によって中心部での商売が困難極まることは想像にかたくない。世界のいずれの都市と同様に開発は周縁化し、今オースティンではその波が街の東側に伸びている。以前は、東端にあり、また夜中に行き来をするには道が暗くて少し怖かった〈Hotel Vegas〉周辺も随分と拓かれてきた印象があった。周辺や通りを行き交う人が増えたことで、比較的足を運びやすい環境になっている。〈Hotel Vegas〉が賑わっていたことは言わずもがな、ダウンタウンから南に歩いて小一時間も離れた〈Hotel San José〉なども観客の出入りが絶えなかった印象だ。

オースティンが「音楽の街」たる所以は、地元アーティストの地道な活動の延長にある
〈Hotel Vegas〉の話を続けると、好きなところは、野外のステージが気持ちいいことや、さらに屋内にも2つステージがあって様々なジャンルのバンドが同時に楽しめること。そしてなにより「地元のバンド」と出会いやすいことにある。自分が観に行く日は、インディーやパンクのイベントが多いが、ほとんど必ずと言っていいほどゲストに加えてオースティンやテキサスのアーティストが出演している。そして、概ね地元のオーディエンスに深く愛されていて、その熱狂ぶりには観ているこちらも心が躍った。今年は、そんな地元バンドの存在感を強く感じた年でもある。
中でも印象に残ったと言えば、オースティンを代表するパンクロックバンドA Giant Dogはそのひとつ。ライブスタート時は大人しくマイクスタンド前からあまり動かず、ロックバンド然としたパフォーマンスが目立った彼ら。ライブの前半はVoのSabrina Ellisのハスキーな歌声に魅了され、観客の熱に呼応し、徐々にタガが外れ、激しくなるパフォーマンスに後半は目が釘付けになった。練り上げられたパフォーマンスだけでなく、それを支える歌唱力や演奏力はこれまでに立ったステージの数を否応にも想像させる。そして、ライブの盛り上がりを見ているとパンデミックの中でもオーディエンスの熱を消さずにいられたのは、彼らのような存在があったからだと感じさせられた。
SXSWはお祭りであり、多くのイベントやアーティストがその熱狂に身を投じるべく外の世界からやってくる。しかし、オースティンを「音楽の街」たらしめている理由は彼らではない。地元のアーティストがSXSW中も変わらずステージに立ち続けることで、オースティンを外のシーンとつなぎ、きっと文化を地続きなものにしているのだ。

Smells Like 90th Spirit
その他のトピックとして、自分が見ていた範囲で今年の出演アーティスト全体の傾向をあげるなら「女性によるオルタナティブ・ガレージロックの復権」だろう。「インディー・オルタナティブミュージックの主権」が女性に移ってきていることは、各メディアでも取りざたされているし、2019年までのSXSWでもStella Donnellyや、Snail Mailなど、毎年のようにインディーシーンを軽やかに塗り替えていくフィメールシンガーが注目を浴びてきた。こういった、アーバンでインディーな雰囲気をまとったシーンからまた少し変化があったようにもう。


その変化はサウンド面はもちろんだが、わかりやすくファッションにも見出すことができる。女性アーティスの服装が、これまでと違い「ゴシック」で「黒く」、「ハード」なテイストのフィジカル的に強いものへ変化している。それはSASAMIのような2018年前後に登場したアーティストに加え、ニューヨークのSunflower BeanのVo / BaのJulia Cummingなどにも見て取れた。その変化に比例して、サウンドも歪んでいく。
率直にThe Smashing Pumpkinsを思い出したし、今年妙にいろいろなところでNirvanaの楽曲を耳にしたことは無関係ではないのかもしれない。こうした90年代のオルタナティブ・ガレージロックがライオットガール的文脈と融合しながら、女性のものとなっていく兆しは、The Linda LindasやSorry momなどの世界的な潮流に加え、日本でもMs.Machineなどのアーティストが出てきていることが証明している。SXSWでもそういった盛り上がりが見られた年であった。
今年のSXSWでの再開は喜びもひとしお

SXSWに通うことによって楽しめることも増えた。それは、これまでに語ってきたような会場やイベントごとのカラーの変化を感じられるようになったことや、アーティストの成長を追いかけられるようになったことだ。今年で言えば、2019年頃まではインディーアーティストとしての評価に留まっていたJapanese Breakfastがいい例だろう。VoのMichelle Zauner単体でのSXSWのKeynoteの参加もさることながら、2021年にリリースされた『Jubilee』で第64回グラミー賞でベストオルタナティヴミュージックアルバムとしてノミネートされ、一躍活躍の幅を広げた彼女の凱旋ライブとなった今回。相当早くから会場に並ばなければ入場ができないくらい、オーディエンスに熱狂的に迎えられていた。
それはまた日本のCHAIでも同じことが言える。SXSWへは3度目の出演となった彼女たちだが、年々オーディエンスの歓声はパフォーマンスを心の底から待ち望んでいたことがわかるようなオーセンティックな熱を帯びてきている。「アジアルーツであること」は今や、取りざたされる特徴ですらない。ごく一般的に欧米のアーティストと並べられるフラットな環境が整えられつつあることを、アーティストの成長とともに思うのだ。同時期に北米ツアーを予定していたおとぼけビ〜バ〜が、もしSXSWに今年出演していたらどのような盛り上がりを持って迎えられていただろうか、と思いを馳せざるをえなかった。
バカ騒ぎをするには、バカが必要なのだ
MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)シリーズのスティーブン・ロジャースと、親友であるバッキー・バーンズが行うやり取りがある。
「Don’t do anything stupid till I get back.(留守中、バカをするなよ)」
「How can I? You’re taking all the stupid with you.(バカがいないと、できないだろ)」
非常にウィットがきいていて好きなセリフなのだが、この掛け合いは「バカはバカがいないと始まらない」というシンプルな事実を思いださせてくれる。このオースティンで年に一度のバカ騒ぎをするにも、同じことが言えるはずだ。ではこのバカは一体どこから生まれてくるのか?
それはきっと、日々たった$5のチケットで最高のパフォーマンスを発揮している地元のバンドたちだし、その場を必死に維持してきたベニューのオーナーやオーガナイザーたちのはずである。私たちの「楽しい」は彼らが築いてきた土台なしには成立しえない。では自分は、自分の街で、地域で、場所で「リスクを引き受け、種火を燃やし続けるバカになれているだろうか?」そんなことを考えざるを得ない一週間であった。

レポートというものは本当に難しい。最近、特にそう感じるようになった。事実として、行われていたことがどうであったかを伝えることは非常に容易だ。だが、それだけでは面白くないし、「その場の出来事がどのような意味を持つのかはその場ではわからない」と節に思う。
今、この場で育まれている文化がどのようなものであるのかは、数年後に振り返ってみることで初めてわかる。そしてそのために必要なのは出来事にどのような意義を見出すのか、という能動的な態度に他ならない。オースティンが「音楽の街」と呼ばれるきっかけをつくったSXSWも、始まったときには、誰もどのような意義を持っているかは正確には評価ができなかったはずだ。後に、僕たちが勝手に意義を見出しているだけに過ぎない。
でもだからこそ、イベントは継続させることに価値があるし、自分自身はこれからも毎年オースティンを訪れ「今ここで起こっていること」を書き残していく必要性を感じている。今年のイベントの良し悪しを語るには、まだ少し時期尚早だ。そして、いろいろと書いてきたが、僕が観測できるものはたったこれだけ。僕一人では観測できる範囲には限界があるからこそ、今こうして自分が感じたことを、どこまでが届くかわからない中であなたに共有しているのだ。

You May Also Like
WRITER

- 編集長
-
26歳で自我が芽生え、とうとう10歳に。「関西にこんなメディアがあればいいのに」でANTENNAをスタート。2021年からはPORTLA/OUT OF SIGHT!!!の編集長を務める。最近ようやく自分が持てる荷物の量を自覚した。自身のバンドAmia CalvaではGt/Voを担当。
OTHER POSTS