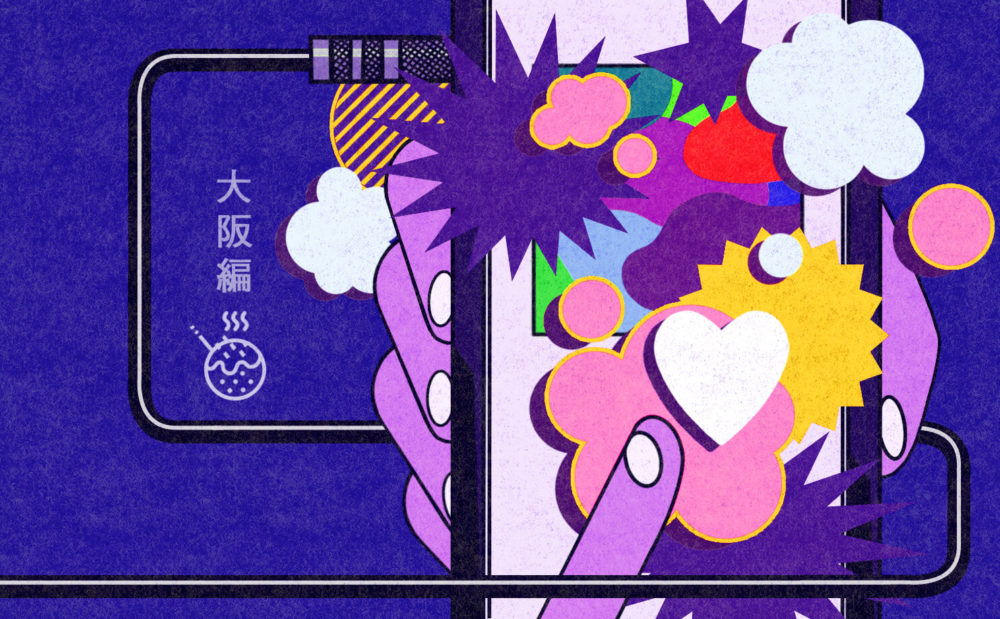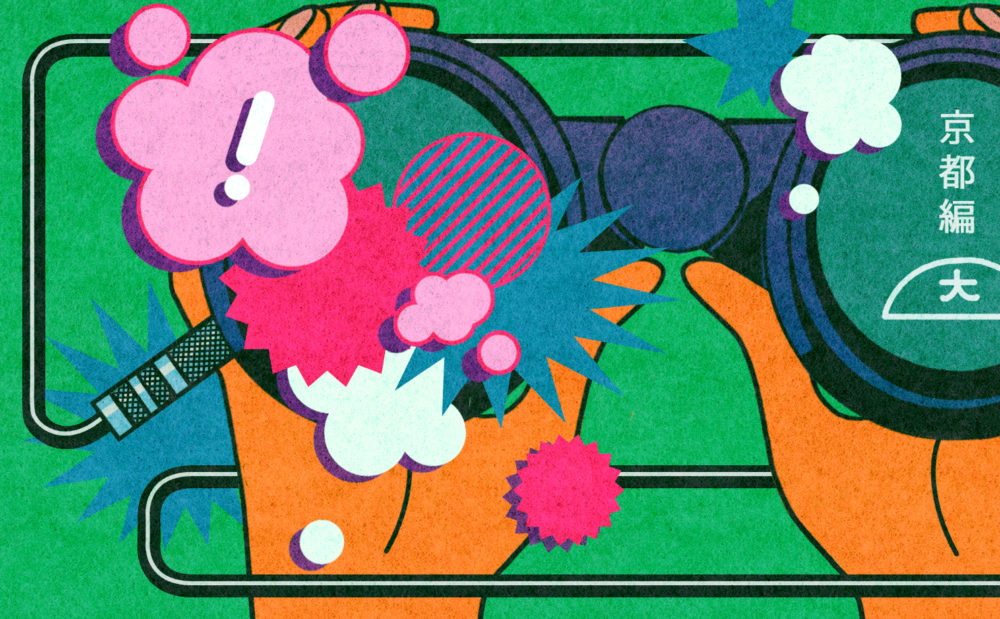【SXSW2023】移りゆくアジアの重心と、裏庭に集う名もなき音楽ラバーたち
2年ぶりとなった昨年のSXSWに引き続き、今年も3月に2023年もオースティンでイベントを楽しむことができた。アメリカへの入国にも、日本への帰国にもPCR検査は不要で、参加に向けて不安になるようなことはもうない。10時間ちょっとのフライトももう随分と慣れたもので、そうしたスムーズさにパンデミック前と変わらない状態が戻りつつあることを感じる。そうした中で、今年のSXSWはどのような様相だったのか?巨大なイベントゆえ、その全容とはとても言えたものではないが、見られる範囲で感じたポイントを今年もレポートしていきたい。
大規模な音楽フェスより、SXSWの方がずっと気楽に楽しめている自分に気がついた

数えてみると、2017年に初めてSXSWに参加してからというものすでに計5回、パンデミックを挟んで7年もの間オースティンに通っていることになる。(2022年の7月に居を京都から台北に移したこともあり)台湾以外で、これだけの期間を過ごした国外の地域は他になく、さすがに街での過ごし方にも熟れてきたところがあるし、お気に入りのカフェもあれば、馴染みの顔もいる。どうすれば快適に過ごせるかは身体が覚えているようだった。
それでもやはり、SXSWの会期中にこの街を訪れることは特別で、浮足立った雰囲気にこちらの気持ちも引っ張り上げられる。さらに、今年は気候もよく過ごしやすい日が続いた。以前に比べて、街中にカフェや(ビールの)タップルームが増えてきており、そうした場所は大概テラス席がついている。そうした場所で、行き交うバッジホルダー(SXSWの参加者)を眺めながらカフェやビールをお供に一日の予定を整理したり、感じたことをゆったりとまとめる時間は格別だ。

日本の数多くのサーキットイベントでレファレンスとして名前のあがることも多いSXSWだが、通っているとサーキットイベントと称すにはちょっとした違和感がある。そうしたものの正体を、これまでいまいち掴みきれなかったところがあるのだが、今年ようやく少し言葉にできそうだ。そのヒントのひとつは「都市全体の空間的余裕とライブ会場の散らばり」であり、そのことにより副次的に発生する「過ごし方の選択肢の豊かさ」である。まずは、そのことから話していこう。
SXSWには非日常も日常も、その間のグラデーションもある、それもたっぷりと

SXSW中はよく歩く。
遠い会場への移動はタクシーや電動スクーターを利用することが多いものの(電動スクーターの値段は本当に高くなった……)、iPhoneの記録を見返すと少なくとも毎日2-3万歩程度は歩いているようだ。初めてアメリカに来たときに驚いたのだが、Google Mapsを見て日本と同じ感覚で移動しようとすると大きな後悔をするはめになる。車での移動が前提となる都市設計、そのため施設の大きさや道路の距離感が日本とは全く違う(初年度に確保したホテルから会場まで歩けると思っていたものの、遮蔽物のない道路、連続する真夏日に1時間以上も歩く必要があるとわかりすぐに断念したことを思い出す)。
オースティンは、その中でも比較的歩くことにも向いた都市だとは思う。SXSWの中心となるコンベンションセンターを中心にダウンタウンが広がっており、その周辺に主要なライブハウスが多い。イベント会場になる飲食店もたくさんある。しかし、どこまでがSXSWのイベントの範囲なのか、その祭りの端をとらえることは困難だ。下手をすれば、車で40,50分ほど走った場所ですら(オフィシャルか、アンオフィシャルかはさておき)SXSW関連のイベントが行われていたりするからである。

進むジェントリフィケーションの影響はもちろんあるものの、例えば、〈The Hole in the Wall〉や〈 Spiderhouse〉などがある少し北側、ノース・ユニバーシティ周辺は元々今の中心部が盛り上がる以前より盛り上がっていたエリアだったらしい。そうした「小さな繁華街」や、「名物スポット」が街の至るところに点在しており、そうした場所は今でも地元民に愛され、会場として用いられながら祭りはその周縁を広げていくのである。
そんなエリアやスポットがいくつもあると、毎日、いくつものイベントを追いかけて街の端から端までを移動することになる。そして、雰囲気の違う各エリアの中から自分のお気に入りのお店や、場所などを見つけていく。今年でいえば、南のエリアにできていたクラフトビールや、日本酒(!)を醸造している工場街でのイベントなどは初訪問で楽しむことができた。


そもそも、クラフトビールの醸造所や、カフェ、本屋にショップなど、チェーン店ではない個性豊かな独立系のお店が多い。こうした活動はおそらく、土地の広さ、都市の空間的余裕などが後押しをしているはずであり、この場所で、SXSWのようなイベントのあり方が育まれてきたことは必然だろう。そして、そうしたお店をイベントの合間に覗いてみたり、ちょっとした休憩に使ったりできることは、間違いなく楽しみの一つとなっている。


また、これが一つの「空間的余裕と、過ごし方の豊かさ」だとすれば、もうひとつ別角度からも語れるものがある。オースティンの地価は随分と上がったとはいえ、そもそも一般的な家も日本と比べると基本的に大きく、庭付きで広い(もちろん、全てとは言わない)。となると、やはりここもまたライブ会場として使われることがあるのだ。
SXSW中は自然と「イベント会場」的なものに足を運ぶことが多いが、今年は最終日に民家の裏庭で行われているイベントにも足を運ぶ機会があった。ブラジルのレジェンド、Os Mutantes(ムタンチス)が出演するという情報がSNSを駆け巡っていたからだが(結果、デマだった)、その時に、その裏庭でのライブをとても「いい」と感じたのだ。

主催はおそらく家主で、いわゆる一般の方だ。入り口には手書きのセットリストがあり、受付に置かれたカンパ箱には1ドル札が何枚も入っている。そして子どもから老人まで幅広い層のお客さんが遊びに来ていて、身体をゆったりと揺らして熱心に聴いている人もいれば、奥でおしゃべりに夢中な人もいるし、チェアでゆっくりとビールを飲む人もいた。誰しもがリラックスしていることが伝わってきたし、そうした中で聴く、地元のフォークシンガーがカバーする楽曲は夕陽も相まって妙に沁みる。その小さな庭には純粋に「歌うこと」とか、「みんなで音楽を楽しむこと」へのプリミティブな喜びが宿っているような気がした。
次々に生まれる新しい音楽と、その潮流や変化を追うことのおもしろさは間違いなくある。それを世界規模でやっているのがSXSWなわけだが、そうしたイベントを許し、下支えしているのは小さくともこうした地域に広がる音楽と過ごす時間への素朴な愛であってほしい。そしてそれを生み出しているのは、こうした都市に広がる空間的な余裕であることを強く感じるのであった。
インディペンデントには、ある種のビジネス的強かさも必要になってきているかも

さて、肝心の今年のショーケースについてである。
毎年、気になるアーティストを見つけては「好み」を軸に追いかけていたのだが、今年は明確に「アジア」の動きを気にかけて回ることにしていた。その背景として、前述の通り、自身が台湾へ移住をしたこともあるし、近年のシーンを追うのに「アジア」という括りで比較をすることが最も今の日本のアーティストやシーンの現在地を確かめられるような気がしたからだ。

まずは、出演者をチェックするためにSXSWの公式Webサイトでアジアの国名を検索して、アーティストを片っ端からお気に入りにいれる。そうした中でまず見えてきたのは、(わかってはいたことだが)現在アジアで音楽の輸出に力を入れているのは日本・韓国・台湾の3国(地域)であるということ。この3国(地域)に関しては、出演するアーティストも、インディーのバンドから、ラッパー、R&Bシンガー、エレクトロ系のDJなど幅の出し方も似ているような印象があった。欧米のマーケットへの売り込みを考えると、どうしても似るのだろうか。
少し台湾について触れておくと、ここ数年国策としてもインディーカルチャーを用いた国際社会でのプレゼンスの向上に力を入れている。今年の出演者を眺めていると、新進気鋭のR&Bシンガー9m88(ジョウ・エム・バーバー)や、会期中にTシャツを着ている人も多く見かけたElephant Gym(エレファント・ジム)、羊文学とのコラボレーションで日本でも話題となったLÜCY(ルーシー)が出演するなど、その本気度が伺えた。


なんと初めて雷雨によりステージが中止で、観れなかった
実際、オースティンで音楽ライターをやっている友人のブライアンも、パンデミックでオンライン開催となった2021年にSXSWに向けて制作された台湾のライブ動画の完成度を褒めていたり、台湾のカルチャーにフォーカスしたプラットフォーム『Taiwan Beats』のショーケースではオープン前から行列ができるなど、着実にその成果が出つつあることを感じた(日本のショーケースよりお客さんが多かったような印象がある)。

アジアのアーティストが出演するイベントを見比べていく中で、特に気になったのが韓国のBalming Tigerで、結果として期間中に2度見ることとなった。

他のアジアのアーティストにはあまりなかった特徴として、 『British Music Embassy』という基本的にUKのアーティストが出演するイベントにも出演していたことが一点。更に、『Tiger Den』という各国のアーティストが出演し、まさにアジアを包括するようなイベントの主催も(Jadedというアメリカ拠点のアジアのユースカルチャーを推進する企業との共催とはいえ)行っていた(スポンサーには彼らのバンド名の元ネタであるタイガーバームまで巻き込んでいるのがチャームだ)。

そもそも、『Japan Night』や、『Taiwan Beats』と名乗る国や行政を単位としたショーケースは毎年見かけるものの、アジアという地域でくくられたショーケースは珍しい(アジアに限らず数は少なく、他にあるとすればアフリカ系のイベントくらいか?)。共催のJadedは昨年もCHAIや、韓国のCIFIKAを招待し、「東・東南アジアを中心に」アジアというくくりでのショーケースを開催していたものの、今年はアーティストとの共催という形を取っていることとなるとさらに稀有だ。
このイベントは、Balming Tigerを始め韓国のアーティストを中心に据えつつも、近年インディーカルチャーの国際的評価が高まる東アジアの日本・台湾のアーティストはもちろんのこと、インドネシアのYacko & Tuanや、フィリピンのEna Moriなど東南アジアの各国にも目配せがきいているのが印象的だった。そうした動きも加味されてか、今年、結果としてBalming TigerはSXSWの音楽部門の賞である「Developing Non-U.S. Act」を受賞している。

Balming Tigerのライブの所感はというと、自称「オルタナティブK−POPバンド」ということや、 BTSのRMをフィーチャリングした “SEXY NUKIM “などの印象も手伝って、Hava a Nice Day!を中心として盛り上がったスカムパークに出演するような、アングラさとカオスさを持ち合わせたコレクティブのイメージを持っていた。しかしステージングは想像と大きく異なり、どちらかといえばポップさの方が(どこか可愛げがある)印象に残るものだった。
自分が観た2回とも、マイクの音量調整がうまくいっておらず本調子とは言い難いところがあったが、ライブではそうしたアクシデントに左右されずにやり切る強度のあるステージングを見せてくれたし、振り幅のある楽曲郡はどれも一度聴くと癖になる中毒性がある。
特に、シンガーであるsogummの艶のある声がピカイチで、リーダーのSan Yawnが積極的にスカウトしたというのには深く頷ける。彼女はBalming Tigerでのパフォーマンスに加え、別日にもソロでのステージがいくつかあり、そちらにも足を運ぶほどには夢中になった。Hope Sandoval(ホープ・サヴァンドル)のような、ハスキーだがどこか幼さをもはらんだ声は、背徳感を覚える色気がある。

また、強く印象に残っていることは『Tiger Den』で日本のTohjiがライブを行なっている時に、Balming Tigerのメンバーのほとんどがステージの横に集まって盛り上がっていたことである。心底、音楽が好きであることが伝わるのと同時に、彼らの人の良さと、「自分たち自身でイベントを盛り上げる」という強い意志が伺えた。こうした部分も含めて、テキサス、オースティンという遠征先のアウェイに自分たちの力でホームを作り上げていったように思う。もちろん、この日の大トリのステージが盛り上がったことは言うまでもない。

こうしたレペゼン的な「意志」は、イベントに限定せずとも「韓国」という言葉に置き換えても、「アジア」と置き換えても通ずるような強さを感じられた。このマインドは、今まで何度かSXSWに通う中でも、どの地域・ステージにも見られなかったものであり、新鮮に感じられると同時に、アジアのポップカルチャーのシーンが韓国にその重心を移す兆しにも感じられたのであった。来年、この勢力図がどのように書き換えられるか、楽しみに待ちたい。
年々、SXSWに行くのが楽しみになってきている

最後に、その他にパフォーマンスを見ることができたアーティストを音源の紹介がてら軽く言及しておきたい。
〈Central Presbyterian Church〉で見たIndigo De Souza(インディゴ・デ・ソウザ)はただただ贅沢の一言であったし、近年のポストパンク的な文脈を引き受けたサウス・ロンドンのFolly Group(フォリー・グループ)も見ごたえのあるライブだった(本人たちはそこじゃないと否定しているっぽいが)。そして北アイルランドのRobocobra Quartetを見逃したことだけはとても後悔している。
今年出演した日本のアーティストでいえば、最も印象に残っているのはTHEティバだ。東京のサーキットイベントである『TOKYO CALLING』主催のイベント、〈Elysium〉に出演した際のパフォーマンスを観ることができた。曲がいいのはもちろんのこと、2人組ユニットにしては十分すぎる音の大きさと圧は、「また見たい」と思わせる力があり、フロアにもその熱は伝わっていたように感じる。
通常の音楽フェスでも、大小様々、出演者のカラーにあわせたステージは用意されているし、その中で自分の好きな場所を気分にあわせて選ぶことはできる。しかし、SXSWのおもしろいところは、一般的なフェス以上にその幅が広いところだ。なにせ、ただの住宅地の一軒の裏庭や、10km以上も離れた空き地ですら何かが蠢いている。
そして、このイベントは非日常な祝祭なんかではなく、日常の延長にもあるからこそ、過ごし方のバリエーションも自然と肥える。それが、人々を容易に主催者、ミュージシャン、お客さんといった役割の垣根をも飛び越えさせるのだろう。
そうした各々の関心が自由に反映されるこのイベントは、ありのまま現在の音楽文化の縮図を見渡せる場所となっている。これを求めて、多くの人が世界中からここでしか得難い最前線にいる体感を求めて毎年オースティンに吸い寄せられるのだ。
You May Also Like
WRITER

- 編集長
-
26歳で自我が芽生え、とうとう10歳に。「関西にこんなメディアがあればいいのに」でANTENNAをスタート。2021年からはPORTLA/OUT OF SIGHT!!!の編集長を務める。最近ようやく自分が持てる荷物の量を自覚した。自身のバンドAmia CalvaではGt/Voを担当。
OTHER POSTS