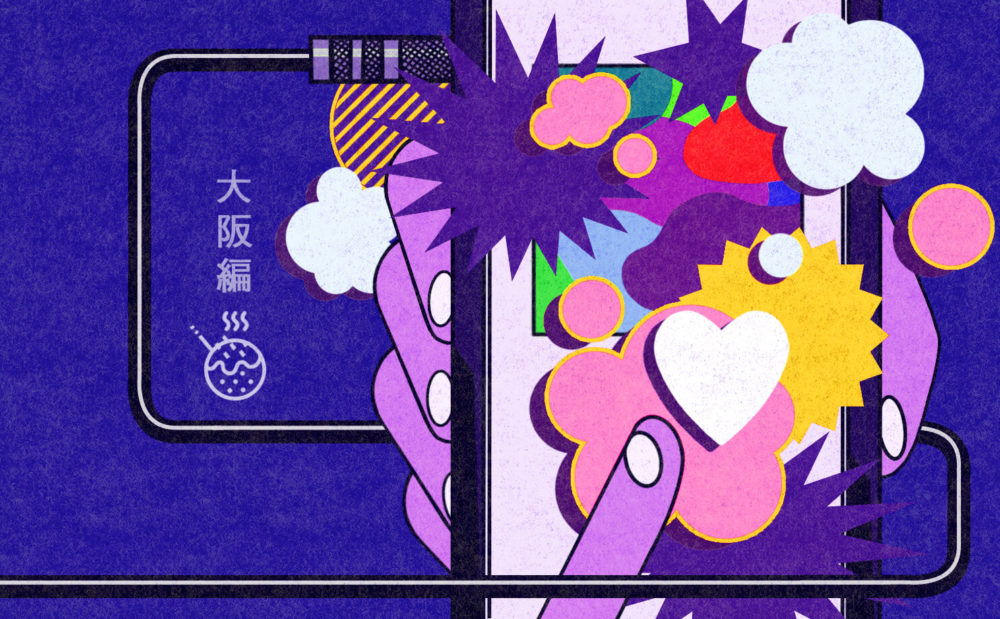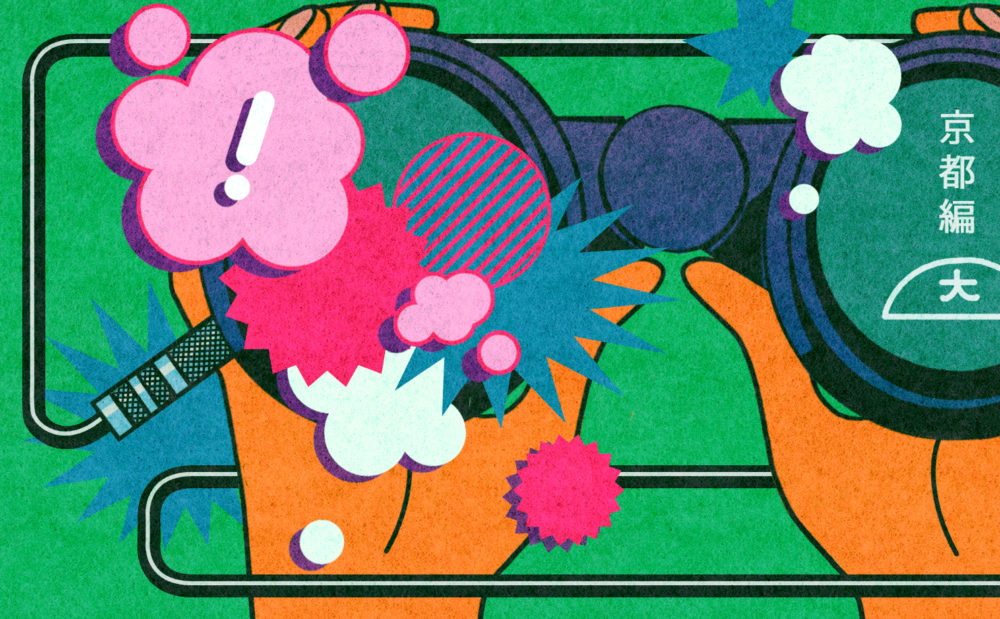【SXSW2024】再起や復活とは距離をおく、中堅バンドと継続のすごみ
毎年、アメリカのテキサス州・オースティンで行われる世界最大の音楽・映画・ITの祭典SXSW。恒例となった毎年の取材だが、今年は円安に震え続けるものとなった。それだけでなく、米軍がイベントの公式スポンサーとなり、SNSも大荒れ。結果、100近いアーティストがボイコットすることに。そんなイベント全体を振り返りつつ、今年特に気になったアーティスト4つを写真とともに振り返る。
「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)には1999年から来てる」
というのは、SXSWのイベント中でもひときわ目立つ風貌のイエローさんが率いるPeelander-Z(ピーランダー-Z)でギターを弾いてきた、ブラックさんの言葉だ。その話を聞いたのは、2024年のSXSWが最終日を迎えた次の日。3月17日の日曜日に晩ご飯の卓を囲んでいる時だった。その日は、Peelander-Zのメンバーであるイエローさんとピンクさん、ブラックさんに加えて、フォトグラファーの森リョータさんも帰国する前の最後のご飯ということで、おいしいと噂のベトナム料理屋にみんなで出かけていた。1999年、もはや前世紀末ではないか。
イエローさんとピンクさんは30年以上アメリカに暮らしていて、長い。SXSWにおいても20年以上参加している最古参の一人だとは思っていたが、それよりも前からブラックさんはこのオースティンにずっと通っているのだという。森さんもまた、2004年からオースティンを訪れ続けている猛者だ。いつかイエローさんが「SXSWは一回だけ来るやつの方が多い。二回以上来るやつは少ない」と少し寂しそうに口にしていたのを覚えていた。初年度の参加から数えて8年目ともなれば、この年に一度の同窓会ともいえる場も混ざってもいいだろうとは思えるようにはなった。
こうしてSXSWは開催初年である1987年以降、国や言葉を超えて人々を惹きつけてきたわけだが、積み上げた長い歴史の中でも今年は今後の行く先を問われる分水嶺になっていたのかもしれない。米軍や、イスラエルに武器や兵器を供与してきた企業を公式スポンサーとしたことで、100に近いアーティストのボイコットが起こったのだ。
すでにSXSWはオースティンの市をあげての巨大なイベントになっているとはいえ、既存のエコシステムや、産業のあり方に一石を投じるといったインディペンデントな精神がこのイベントの根幹にあった、はずなのにである。自分自身、ITのショーケースの会場の端でアーミーの人員募集が行われているのを見つけた時、かなりドキッとした。2020年のパンデミックによるイベントそのものの中止も相当なインパクトがあったが、それ以上にショッキングな光景ではある。

出演したバンドの中にも異議を唱えたいアーティストはたくさんいただろう。レーベルとの関係性、アーティストとしてのキャリアのこと、今回のイベントに投じた手間、費用のことを思えば、(遠方であればあるほど)ボイコットも簡単なものではない。そうした中でアメリカのアーティストが率先して、ボイコットで中指を立てていたことはまだ救いがあるように思う。
彼らはキャンセルだけする場合もあれば、Reyna Tropical(レイナ・トロピカル)などアンオフィシャルのイベントに限って出演を行うといった対応をするケースもあった。中には、「アンチSXSW」と銘打ったイベントが多数あったし、デモなどの抗議活動もあった。また、こうした動きの背景には、ここ数年アーティストたちからあがっていたSXSWの出演料への不満も、下地にはあると推察する。拡大・拡張を続けてきた巨大イベントのSXSWのあり方は、「今後どうするの?」と身のふり方を問われている。

ここからは音楽部門での体験に話を移そう。例年、SXSWは多くのアーティストを好きになる機会となるが、今年は妙に「中堅バンド」の活躍に意識が向いた。中堅バンドと言えば聞こえはいいかもしれないが、「音楽フェスティバルではなく、あくまでショーケース」であるSXSWへの出演が意味するのは、「まだ(もしくは再度)知ってもらいたい立場にある」ということ。同時に、音楽業界で一定期間の活動を経て中堅にまでなっているということは、確かな音楽で一定のファンをしっかりと掴んでいることを意味する。また、中には自分たちの生活と音楽の天秤を上手に取れていてマイペースに活動を重ねているバンドも少なくない。
こうしたアーティストに意識が向いたのは、そうした地に足のついた態度。言うなれば、船は小さくても、凪も荒波の中だろうと自らがハンドルを握って行き先を決める彼らの姿が、SXSWという巨大な船が時代のうねりに大きく揺られている光景と対象的に映ったからかもしれない。
スペインのHinds、メンバーの脱退と自分たちのアイデンティティを見つめ直すことについて

今年、最もSXSWでライブを行ったバンドの一つは、スペインを拠点にするHinds(ハインズ)だろう。
SXSWにおける「出演数」はわかりやすい注目度のバロメーターだが、日によっては3つも4つもステージにあがらなければならないハードさには舌を巻く。彼女たちを初めて観たのは2018年、よく晴れて光の差し方まで完璧な〈Cheer Up Charlies〉のお昼の屋外ステージだった。
パフォーマンスもキュートながら、楽曲のキャッチーさにすぐに虜になった(そして後日レコードを買った)。その年パフォーマンスが話題となり、それからすぐに大きなフェスへの出演などを重ねていたが、パンデミック前後で少しずつ活動が落ち着き、そしてとうとう2023年にはリズム隊の2人が脱退したというニュースが流れた。そんな彼女たちの新体制のお披露目が今年のSXSWだったのである。
観る機会はたくさんあるし、と思っているとSXSWの音楽のショーケース期間はあっという間に過ぎる。他の観たいアーティストと時間がかぶって思っていたより観に行くチャンスが少ないなんてこともあるが、それ以上にどうせ観るなら好きなベニュー、良い音で聴きたいという思いをみんな抱えている。どこで観るかを考えるのはSXSWの楽しみの一つだが、往々にして人気のベニューに多くの人が詰めかける。ヘタをすると入れないこともザラだ。
そうこうして序盤はいくつかHindsを観る機会を見逃しつつ、ようやくライブを観れたのは3月15日(木)に行なわれた人気のベニュー〈Mohawk〉のデイパーティのステージだった。忘れ物をして引き返したため途中からのステージとはなったが、並んでいる間も昼のステージによくあうカラリとした陽気なサウンドが壁越しに聞こえてくる。
以前観たときのHindsは4人のメンバーがそれぞれの個性をぶつけ合う、エネルギー溢れるステージが何よりも印象的だった。それがどういう形に変わっているのか、それが一番の見どころだとは思っていたが、実際にライブでの印象は随分と変わっていて、ギター・ボーカルのCarlotta Cosials(カルロッタ・コシアルス)と、ギターのAna García Perrote(アナ・ガルシア・ペロッテ)のジュブナイルなコーラスワークはそのままに、以前より更に歌とメロディが前に立つような楽曲とセットリストになっていた。
ちょうど会場に入れた際に演奏していた新体制での楽曲“Coffee”(2024)はそうしたコーラスワークを活かした一曲だ。音数は多いものの、少し引っ込みがちのヘタった音質で歌を立たせてきた過去の楽曲と比較するとリズムそのものに隙間が多い。その分メロディとのかみ合わせで、ノれるし聴きごたえがある。
その後の新曲2つも、カルロッタのギターのみをバックに歌う弾き語りと言えるようなものが一つあり、歌を聴かせることを意識した音数を控えた楽曲だった。この日の最後に演奏した曲は、4人体制での最終アルバムとなった『The Prettiest Curse』の代表曲、“Good Bad Time”。
Hindsの魅力は陽気なサウンドやメロディに対する、憂いを帯びた歌詞にあると思っている。この曲は他の楽曲と比較してサウンドも全体的におセンチで、そうした意味では異質な一曲なのだが、この日の演奏を聴いていると過去のメンバーの脱退と、喪失に向き合っていたことが歌詞も相まってにじみ出てくるようであった。同時に、そうした過去もバンドや自分たちのあり方を再構築する機会としてカラッと受け止める度量のようなものを感じたのである。そうした意味でも、人気曲である以上に、この曲を最後に持ってきた意味が見えてくるような気がする。

カナダのCorridor、地元で地道に改善を重ねる職人的アーティストの姿勢

その他、中堅のバンドで印象に残ったショーをしていたのがモントリオール出身のCorridor(コリドール)だ。2013年にEP『Un magicien en toi』でデビュー、《Sub Pop》と契約した初のフランス語圏のアーティストとして話題になっているが、日本での認知度でいえばHindsと比較すると大きな隔たりがあるかもしれない。しかし、彼らはすでに4枚のアルバムをつくり、精力的な活動を継続している。2024年の今年は、最新アルバム『Mimi』をリリースしており、そのツアーの一環としてSXSWに出演しているのだろう。
事前に音源を聴いていた印象と、ライブのパフォーマンスが大きく違っていて驚いた。ライブを観たのは〈Swan Dive〉という、カナダのショーケースがよく行われているベニューのパティオ(野外のステージ)。今まで、音が良いといった印象のないステージだったのだが、まずは出音が圧倒的に良い。
新メンバーであるSamuel Gougoux(サミュエル・グーグー)を加えた4人に加えて、サポートメンバーとの5人編成でのステージだったが、音がきれいに分離していて、ギターやキーボードの上モノからリズム隊も含めてサウンドが渾然一体となっている。00年代のインディーや、ポスト・ロックを思わせる単音ギターの絡みを聴いているだけで、気持ちがいい。そして、そこに素晴らしいコーラスワークが重なってくる。ただ、編曲はポストロックっぽさはあるものの、インダストリアルな印象は薄く、同じくカナダのBroken Social Scene(ブロークン・ソーシャル・シーン)などを抱える《Arts and Crafts》のバンドを彷彿とさせるところがある。
楽曲そのもののキャッチーさが飛び抜けているとは言い難い。しかし、パフォーマンスの精度が圧倒的に高い。職人的な楽曲の構築とライブでの演奏を聴くのはそれだけで「彼らのライブへ足を運ぶ満足感」を与えてくれる。まごうことなきライブバンドだと感じた。
音源よりアップテンポで駆け抜けたこの日のパフォーマンスは、最新のアルバムに加えて3枚目、2枚目、はたまたその間にリリースしていたEPまでの楽曲をもバランスよく含めた全9曲。初見だが、昨今の楽曲が過去の楽曲の延長線上にあることが伝わってくるものだった。それは決して「焼きまし」と言われるものではなく、新しいアルバムの楽曲である “Phase Ⅳ”や、“Jump Cut”が、それぞれ一曲目や後半戦の皮切りとなる楽曲として、セットリストのスパイスとして機能していることが何よりの証拠だ。
彼らはこうした楽曲の変化は「パンデミックとメンバーのライフステージの変化が大きい」と地元のカルチャーメディアに語っているが、この「変化に耐えうる根」は今でも地元モントリオールで音楽に向き合い続ける「継続性」によって、育まれた気がするのである。

ブラジルのGlue Trip、過去への期待を振り払う「今」の示し方

個人的に、今回最も楽しみにしていたバンドの一つがGlue Trip(グルー・トリップ)だ。彼らもまた2013年に活動をスタートさせた中堅と言える。元はブラジルのパライバ州に住んでいたLucas Moura(ルーカス・モウラ)が首謀者の宅録ユニットで、現在では4人組のバンドになっている。2015年にリリースしたセルフタイトルの1stアルバム『Glue Trip』がBandcampの年間ベストにも入り、一挙に名前が広がった。サイケデリックでチル、そしてもちろんブラジリアン・ミュージックの要素がたっぷりと取り入れられた楽曲は、トロピカルで毒々しく、中毒性が高い。今はサンパウロに拠点を移しているようだが、とはいえまさか観れるとは思っていなかったのだ。
SXSWに足を運ぶアーティストは、オフィシャルのショーケースの出演に加えて、前後にツアーをいれるか、アンオフィシャルのショーに出演をすることが多い。遠方から来る交通費のことを思えば当然だ。Glue Tripはブラジルから来るにも関わらず、オフィシャルのショーはなんと〈Hotel Vegas〉の一本。SNSを見てみるとオースティン滞在中に、他にアンオフィシャルのイベントへの出演をいくつか予定しているようだった。〈Hotel Vegas〉のライブは絶対に盛り上がることがわかっていたが、どんな塩梅かその前に一度ライブを観ておきたい、そんな想いで〈Outer Heaven Disco Club〉という少し離れた名前を聞いたこともないベニューにまで足を運んだ。

ダウンタウンから歩けば30-40分くらいの距離だろうか、バッジ(SXSWにおける参加証)を付けて歩いている人がいない、どころかほとんど歩行者がいない。この一帯はSXSWの狂騒の外にはあるとはいえ行ってみると驚いた。客が自分一人しかいなかったのだ。黙々とセッティングをしている(ようには見える)メンバーだったが、演奏を始めていいものかどうか迷っているようにも見えた(実際に、ルーカスとは何度か目があった)。が、さすがに厳しい環境の海外遠征にも慣れているのか、吹っ切るようにライブはスタート。
夜の海をコンセプトに作ったという2ndアルバムの『Sea at Night』の“Fancy”でフロアを一瞬で乾いた北米から、ジメッとした南米へと我々を連れていき、最初からフロアを踊らせにかかる。アメリカのベニューは音がだだ漏れなわけだが、そうした音に釣られたのか、それとも最初からGlue Tripを目的としていたのかはわからないが3曲目に代表曲である“Elbow Pain”をする頃にはフロアにも多くの人が集まっていて、大きな歓声があがるような状態となっていた。
作品がいわゆるベッドルームミュージックにも分類されるGlue Trip。最初から、小綺麗なライブをするとは思っていなかったが、ライブの体験はカオスそのもの。全楽器の音が大きく、よい意味での荒さを残していて、ブラジルの地方の州都でどのようなステージが求められているかを伝えるようなものだったと思う(出演したベニューの環境が悪かったのもあると思うが)。
結局、後日〈Hotel Vegas〉の屋外ステージでのショーも観に行ったのだが、出演は25時とトリの時間だったことも相まってお酒を片手に大勢の人が楽しそうに踊っているのを見た。代表作である一作目『Glue Trip』が強すぎた故に、その後のアルバム制作は大変だっただろう。ライブパフォーマンスでの振り切りも含めて、過度な過去への期待を振り払うようなステージで、リスナーへの期待には応えつつ、伸び伸びと今自分がやりたいことをやっているように見えた。

イギリスのDivorce、積み上げたキャリアを存分に発揮するこれからの4人

今年、最も良かったアーティストは誰か、と聞かれれば彼らを推す。
00年代、シアトルで同名のバンドが活動していたが、それとは別だ。今年SXSWに出演していたDivorce(ディボース)はノッティンガム出身の4人組のバンドで、結成は2021年と若い。アルバムもまだ出していない中で、BBCに取り上げられ、SXSWに出演しているところは「最近の流れっぽい」とも言える。
とはいえ、同じシーンで活動していたメンバーが集まってできたバンドらしく、全員が地道にキャリアを重ねてきたことはライブの強度を見ればわかる。British Music Embassyというイギリスのメディア(BBCやカルチャーメディアなど)が各日の昼と夜がキュレーションしているステージにおいて2つ、SXSW全体では4つのステージをこなしていて、推されていることも伝わってくる。3月13日(月)に早々に観ることができ、とても気に入ってもう一度観たいと思って最終日のショーとの二回足を運んだ。
オルタナティブ・カントリーバンドと称する彼らは、自分たちの音楽をABBA+Wilcoと例えている(それで言えばかなりWilco寄りなのではなかろうか?)。ライブを観たいずれの日も、曲順こそ違えど演奏する楽曲は概ね似たようなセットリストだったが、妙な切実さみたいなものが籠もることが特徴に思えた。
加えて、ライブでは真っ直ぐに歌い上げるベース・ボーカルのTiger Cohen-Towell(タイガー・コーヘン・トウェル)と、素朴で少しよれた声のギター・ボーカルのFelix Mackenzie-Barrow(フェリックス・マッケンジー・バロウ)の掛け合いが、よりメロディの輪郭を引き立てる。歌詞の世界を立体的に想像させるのは、一つの関係性の終わりを前提としたDivorce(離婚)というバンド名のなせる技だろうか。同じ歌詞でも、他のバンドではこうは聞こえないのではないか。彼らの楽曲には「終わりを始まりに変える力」がある。

また、これだけは書いておかねばなるまい。自分が観たアーティストの中で、唯一彼らだけが今年のSXSWのスポンサーの問題に触れていた。いずれのライブでも、タイガーが演奏直後に、「これだけ言っていいかな?軍のお金の元に生まれたものを芸術だなんて信じないで」ということを言い放っていた。
音楽性としてアメリカ発祥のカントリーを掲げ、そのサウンドからイギリスのメディアには「当初アメリカのバンド」とも思われていたDivorce。そもそもオースティンが「ライブ音楽の都市」としてその地位を獲得するきっかけとなったのは、ナッシュビルを中心とした音楽産業に嫌気がさしたカントリーのミュージシャンたちが新天地を求めて、移住を始めたことが一つのきっかけとされている。そのカントリーは、アメリカ国内では随分と保守層に響く音楽であることも指摘されているわけだが、ちょうどタイムリーに発売されたBeyoncéの『Cowboy Carter』はもちろんのこと、そうした現況を純粋に音楽で更新しようとするDivorceのようなバンドがいることもまた、勇気の出る話ではないか。
タイガーはまた、最後のライブでこうも言っていた。
「これ以上、この地球で、軍事にお金が使われるべきではないと私たちは考えてる。インディペンデントな人も、街も、まだ元気じゃないか(だからできることがある)」

音楽を消費するものにするか、文化にするかは私たちが決める

今年は、このトピックに触れずにレポートを書くことは不可能だと思っていたし、正直な話「SXSWに参加している」ということですら、SNSでは言い難かった。気が重いに決まっている。イベントに参加している以上、軍が公式なスポンサーである以上、そのことに加担していることには変わりがない。行っていいものかどうか、何を書くべきか、正直に言えば悩んだ。
SXSWにはこれまでにも多くの紆余曲折はあっただろうし、その中でイベントを大きく左右する出来事もあったはずだ。長く続けて、変節を続ける中で清濁併せ呑むことが必要な場面があることもわかる。ただ、願わくばただの音楽フェスティバルではなく、街を舞台とし、文化と技術の融合と発展を掲げるSXSWであるからこそ、人々を熱狂したり興奮させるだけでなく、それらを支えている市井の生活そのものに寄り添ったものであってほしい。このイベントを唯一無二にしているのは、そうした市井の人々あってこそだからだ(2022年のレポート参照)。
そうしたマインドに通ずるものを、今年は中堅のバンドに見たのだ。Kelly Reichardt(ケリー・ライカート)は『First Cow』のインタビューの中で、「昨今の映画のスピードの速さ」について語っていた。トレンドとは真逆、長回しで身の回りの手入れをじっくりと撮る彼女の映画は、なんでもない生活そのものに光をあてる。
再起でもない。華々しい復活のようなドラマでもない。素晴らしい解決方法なんてこの世界にないし、なにかを劇的に改善できることも、夢物語だと知っている。それをわかっているからこそ「懐かしいわ〜」なんて心ない人に言われながらも、彼らはできることを積み重ねている。
もちろん、今回レポートでは取り上げられなかった心に残ったバンドもたくさんいた(アメリカの若手のChinese American Bearや台湾のMong Tongの話とか、FRIKOを見損ねたこととか)。レポートを書くのは大変だが、一週間の滞在を振り返りながら今年出会った音楽を聞き返しているだけでも、随分と楽しい。来年は「めっちゃおもしろい」と気持ちよく言いたい。

You May Also Like
WRITER

- 編集長
-
26歳で自我が芽生え、とうとう10歳に。「関西にこんなメディアがあればいいのに」でANTENNAをスタート。2021年からはPORTLA/OUT OF SIGHT!!!の編集長を務める。最近ようやく自分が持てる荷物の量を自覚した。自身のバンドAmia CalvaではGt/Voを担当。
OTHER POSTS