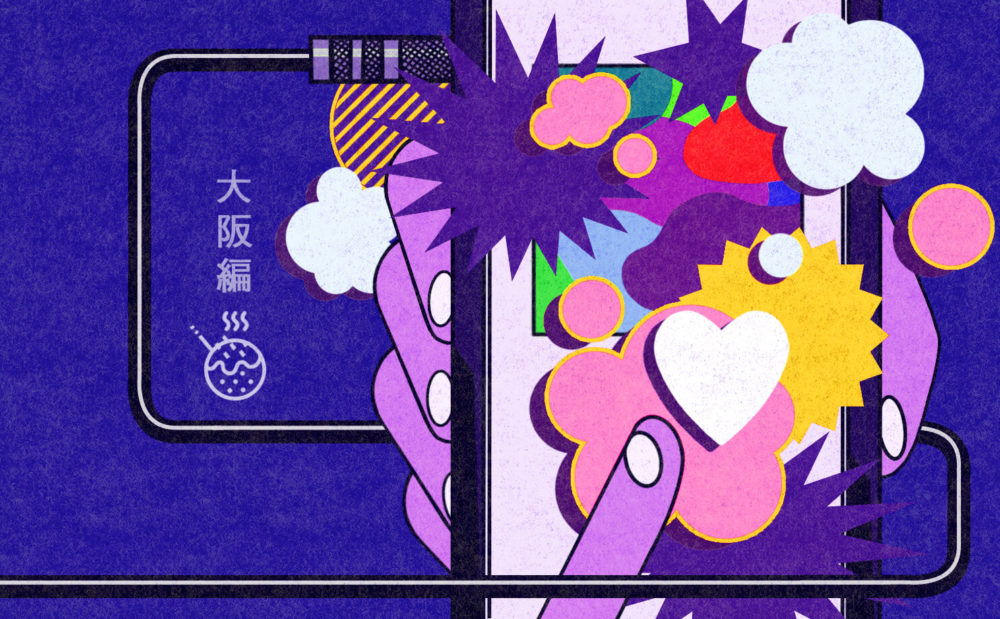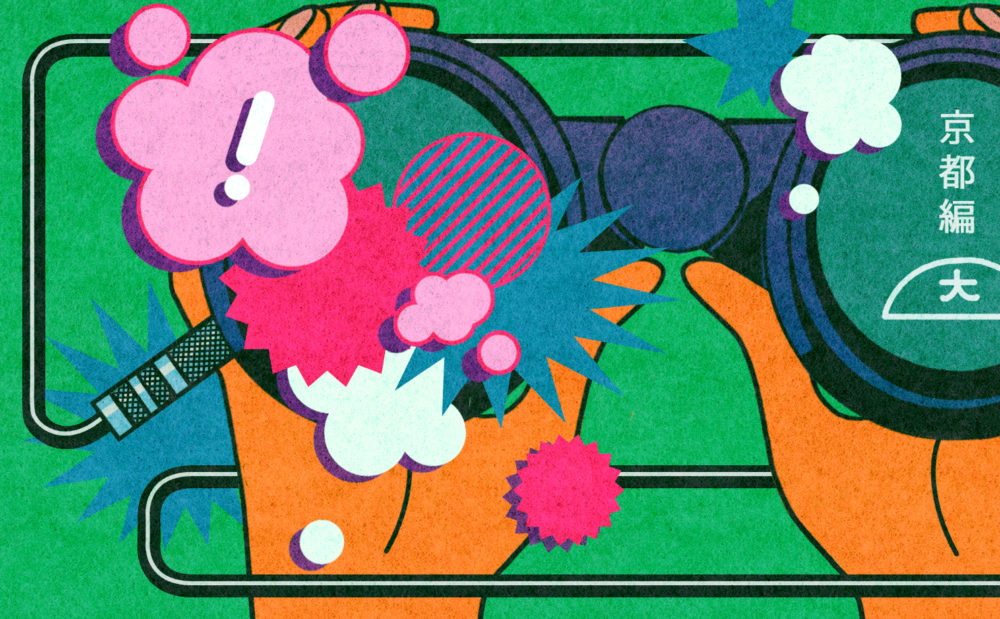キャリアゼロから写真の怖さに向き合って15年。 写真家・吉田亮人が考える「しぼまない」人生
「誰からも依頼がない中で作品を作ってきた」という言葉に、「それでも続けてきた、これからもそうする」という覚悟と矜持がにじむ。そのことを真っ直ぐも、暑苦しくないカラリとしたトーンで話すのが写真家・吉田亮人の魅力だ。小学校の教師を天職だとまで思っていた彼は、30歳を過ぎてからキャリアが一つもない状態で写真の世界に飛び込んだ。そこから15年、自身と社会の「働くこと」、そして「生きること」をレンズを通してどのように見てきたのだろうか。
吉田のことを知ったのは、2017年でのKYOTO GRAPHYでのこと。吉田の祖母と、いとこの大輝、2人の日常とその結末を作品として発表した『The Absence of Two』(発表時のタイトルは『Falling Leaves』)に強く感情を揺さぶられた人は少なくないはずだ。かくいう筆者もそんな一人だった。
その後も展示会をひらき、写真家として自身の作品を発表し続けるだけでなく、いわゆるクライアントワークに加え、2023年には東京在住のヴィジュアルアーティストの鈴木萌とと共同で写真集に特化した出版社「Three Books」を立ち上げた。同時に、京都在住の装丁家・画家の矢萩多聞とは「写真絵本 はたらく」シリーズを刊行。図書館や、動物病院、中華料理屋など「身近にある営み」に静かにその目を向け続けている。
30歳で写真家へ転身し、キャリアとしては15年目となった。そうした意味では、今が脂ののったタイミングなのかもしれない。精力的に活動を続ける吉田のエネルギーの源泉と、赤裸々なお仕事事情について話を聞いた。
吉田亮人

写真家。写真集出版社「Three Books」共同ディレクター
1980年宮崎県生まれ。京都市在住。
滋賀大学教育学部卒業後、タイで日本語教師として1年間勤務。
帰国後小学校教員として6年間勤務し退職。
2010年より写真家として活動開始。
個人的な問題や原体験から出発した作品を多数制作。その作品は国内外で展覧会が開催されるとともに、多くの出版物が刊行されている。
2023年に写真集出版社「Three Books」をヴィジュアルアーティストの鈴木萌と設立し共同ディレクターを務める。
受賞歴多数。
行けば撮れる写真ってある

今回、お話をさせていただくにあたりキャリアを振り返る一冊として出された『しゃにむに写真家』(亜紀書房 2021)も改めて読ませていただきました。フォトグラファーではなくて、写真家という言葉が選ばれていることがまず吉田さんの「自身のキャリアとしてのあり方」を表しているなと感じます。
写真を撮るにしても、いわゆる商業カメラマンとか、フォトグラファーとして生計を立てていくことは当初から考えてなかったんです。その頭が全くなかったというか。
イメージすることができなかったのか、それとも自分は生き方が違うと感じていたのかでいえばどちらなんでしょうか。
ジャンルというか、自分は違うと思っていたんです。同じ写真というフィールドの中にはいるかもしれないけど、種目が全く違うって捉え方をしてたんですよね。僕はどちらかといえば、ぼんやりとだけど、自分が何か心が動かされるものを撮って、それで写真展をしたり、写真集を作ったり、雑誌に掲載してもらったり。 お金のことは差し置いて、社会という大海に「作品」という小石を放り込んで、誰かの心に波紋が広がるような写真家になろうという話を妻と最初にしていたので。(※1)
※1 『しゃにむに写真家』でも語られているが、吉田が写真家の道を歩むきっかけになったのは同じく教員をしている吉田の妻の「この家に公務員は二人要らん。〜中略〜だから亮人、先生やめて。」というある日の一言だった。
でも、最初はそのために何を撮ったらいいのかまったくわからない。「作品」を作ったこともなかったので。お金を稼ぐのはバイトでいいと思ってバイトして。写真の学校に行くとか、アシスタントについて師匠から技術的なことを学ぶとかっていうのは、もう論外というか。時間的にも、金銭的にもその余裕がなかった。
お子さんもいる状態で、じっくりゆっくりというわけにもいかないですよね。
多分、僕、人から教わるのがすごく苦手なのもあって。自分で本を読んだり、グーっと一人で掘っていくのが好きなんです。 それで3年ぐらいかな。バイトでお金を貯めたら海外に写真を撮りに行って、雑誌社に持ち込んで、それが運よく全て掲載されたので、その原稿料とまたバイトで稼いだお金を次の作品制作に投入してみたいなのを繰り返していました。 やらないとわからないし、動いたことで、何かこう結果が出ていくだろうって風には思っていたので、それを信じて写真家としての活動をやり始めた感じです。

その辺りは『しゃにむに写真家』でも描かれていましたね。その中で、チベットでの撮影に関するやり取りがとても印象に残っています。
辛辣ですよね、あれ(笑)。今でも妻とその話をするんですけど、あれはね、辛辣な話であると同時に本質なんです。チベットへ行ったのが写真を始めて1年経ったくらいで。ちょっと写真の撮り方がわかってきたので、1ヶ月半ぐらいチベットへ行きました。高山病になったり、それでも頑張って撮影してきたんですが、それを妻に見せたら「1ヶ月半、チベットで何してたん?」みたいな。「こんなん、この場所へ行くことさえできたら私でも撮れるやん」って言われて。
強烈なフィードバックです。自分が言われたらすごく落ち込む自信があります(笑)
その時は僕もすっごいムカついて、もう話もしなかったんですけど、数年経った時にわかったんですよね。そこに行くことさえできれば誰にでも撮れる写真って確かにあるよなって。でも本当に心が動かされる写真っていうのはわざわざ秘境に行かなくても、絶景の地に行かなくても、テクニックとかそういうものを超えてあるんですよ。誰でも撮れる写真と誰も撮れない写真がある。それが写真のある種の怖さでもあるというか、すごいところなんです。(人の心や、社会に)波紋を投げかけられるような写真には、マジックがある。
ただ一つ、美しさがそこに宿っているってことは確実に言える

マジックですか。
人それぞれあると思うんですよ。 写真家によってマジックの調合の仕方というか、作り方みたいなものが。 時間に漂白されずに歴史に残ってきた写真ってあるじゃないですか。 そういう写真家の作品を見ると、共通性はあるんです。一つは、時間なんですよね。
時間。
ある対象物に単純に長く取り組めばいいってわけじゃなくて、撮影していない時間も含めて深くコミットできているかどうかです。 例えばその現場にいなくても、自宅だったり、日々の中で考えている時間の積み上げ。いかにコミットして深くグーッと入れるかです。人が相手ならコミュニケーションを取って信頼してもらいながら、自分が空気のような存在になれるかどうか。自然とか山が相手なら、いかに山と対話できるかとか、あるじゃないですか。 その深さだと思うんです。
被写体への関心をどれくらい日々向けられるかということですね。
もう一つは写真家が持っている視点ですね。 その人の生まれ育った環境とか、今まで育まれてきた周りとの人間関係とか、もともと持ってる性格とか、一言で言えばその人の人間力そのものだと僕は思ってて。 それが写真の場合はだいぶ出るなって。こういったものをどう調合するかで、他の人には撮れない写真っていうものが撮れるんじゃないかなあと。
写真に限らずあらゆる「つくる」に該当しそうな話ですよね。
何気なくただ単純にその辺をパッて撮った写真でも、なんかめっちゃいいやつってありますよね。 ロバート・フランクって写真家がいて、彼が撮影した作品の中に、地平線に走る一本の道を写した写真があるんです。 なんでもない写真じゃないですか。 それがね、もう本当に超美しいんですよ。それが何なのかっていうのを言語化するのはすごく難しいけど、ただ一つ、美しさがそこに宿っているってことは確実に言える。その美しさに僕はすごく心打たれたし、心に残り続けてきた。
編集者の後藤繁雄さんが名だたる写真家と対話している『現代写真』(リトルモア 2023)という書籍があるんですが、そこでいい写真について「タイミングとは『決定的瞬間』と思われがちだが、そうではない。実はタイミングとは。世界が最もイメージのポテンシャルを高くした時のことを言うのだと思う」と言っていたことを思い出しました。
おっしゃる通りだと思います。人が一生懸命仕事をしている場面に僕はときめいたりするんです。(世界の)解像度が上がる瞬間っていうのが、確かに自分の中の感覚としてもあって、それがなにかわかったことがあったんですよ。 そういう人の姿を見た時に、自分の両親の姿とガーって重なる瞬間があって、そういう時にシャッターを切った写真は、やっぱり力がある(※2)。自分が写真を撮る原動力が明確にわかったというか。
※2 吉田の両親は宮崎で中華料理屋を2019年まで営んでいて、吉田が幼い頃はおんぶ紐に抱えられながら厨房を眺めていたという。

そうした自身の感覚と世界が重なる瞬間がポテンシャルが高まるってことですよね。
そのためにも面白い瞬間に感応する媒体に、自分がなっていくというか。 面白いかどうかを考えるのは、もうその後の編集の段階ですね。 撮影する時はもうただの感覚であることがすごく大事で。撮ったことすらも忘れているのが一番いいんですよね。 後で、「えっ、こんな写真撮ったっけ」みたいな。
結局一人じゃ何もできないってことが、この15年間でめっちゃ分かった

今、日々の中で写真のお仕事ってどんな配分でされているんですか?作品づくりに、クライアントワーク、最近はパブリッシャーとしても活動されていますよね。
生活の中でやるべき4本の柱があって。1つはクライアントワークですね。もう1つが出版社のThree Booksとしての活動。 今年の11月にある韓国人写真家の写真集をうちから出すんですけど、そのためにこの前も韓国へ行って、現地の作家さんとやり取りをしてきました。それでもう1つが自分の作品づくり。自分の作品づくりが今、一番時間の割合が少なくなってきてるから、よくないなって思ってるんですけど……、次の準備はしてますね。 それで、最後の1つが家事です。この4本の柱で、一日のサイクルをやってるんです。
それを毎日やっていると、あっという間に24時間経ちそうです。
出版社は法人化してるんです。すごくお金もかかるし、自分たちで方針を決めてどこのブックフェアに出るかとか、次はどういう企画にするかとか、作家さんや書店さんとのやりとりどうするかとか、法人税どうするかとか……、今、立ち上げて3年目なんですけど、次は5年、そして10年を目指してやっていこうと思っています。
本を作るのって時間もですけど、下手したら車買えたりするくらいお金はかかっちゃうこともありますからね(笑)。しかも、それを売っていくために、また自分の身体や時間を持っていかれて……。
ただ、写真家としての自分だけだったらわからなかったことが、いわゆるパブリッシャーとしての自分を体験することで、見える世界が変わってきてるのは確かなんです。他の作家さんの作品を出すために、ああしようこうしようなんて今まで一切興味がなかったけど、勉強になるし、それによって広がる世界がある。なにより、出版社というプラットフォームを作ったことで海外とつながれたり。いち写真家だったら、多分、この辺で終わってたかなっていうのはありますね。

それはどうしてそう思うんですか?
結局一人じゃ何もできないっていうことが、この15年間でめっちゃわかったんです。 一人でやってきているように思ってたんだけど、本一冊作るにも一人じゃ何もできなかった。いろんな人の支えがなかったらできないってことがよくわかりました。だったらこれはもう人に頼って、いつか身体が動かなくなっても誰かが助けてくれるように、そんな自分を作り上げとかなきゃいけないと思って。だから今動けるうちに、ちゃんと水をあげて、良い土壌を作って、ちゃんと(周囲との関係性や信頼を)育て上げないと、(写真家としても)死ぬまではやれないなって。30代の時にそんなこと思わなかったんですけど、40代になってリアルにそう感じるようになりましたね。
言葉にすると軽いんですが、死ぬまで続けるって改めて冷静に考えると相当ハードルが高いですよね。
続けている人を見たら、やっぱりみんな気力が充実してますよね。70,80歳になっても、写真撮ってるような人っているじゃないですか。 アマチュアでも、プロでも、ああいう人たちを見ているとやっぱり全然気力が衰えてないんですよね。 しぼんでない。 むしろ充実していく感じがする。映画監督とかにもそういうパターンの人多いんですよね。リドリー・スコットとか、マーティン・スコセッシ、クリント・イーストウッドとか、山田洋次とか。年を重ねれば重ねるほど、どんどん作って、どんどん自分の世界を追求していって、面白いみたいみたいな。 経済的な面で成功できるかはわからないですけど、あれが目標なんです。
10万とか20万って金額が大金って感覚が僕、どうしても抜けなくて

「経済的な面でも」とのことですが、お仕事、いわゆるクライアントワークも順調なのではと感じているのですが。
実は最近、広告代理店の方に「ギャラの金額を安く設定しすぎじゃない?」言われたことがあって。正直まだ、感覚がよくわからないですね。
自分の仕事の値付けって、誰かに教えてもらえるわけじゃないから難しいですよね。金額が大きくなると発注側と、受注側にパワーバランスも発生してきますし。
金額を安く設定することで、自分の仕事に対する価値とか、何を提供できるかっていうハードルを上げなくて済む感じもあるじゃないですか。 だからこそ、仕事のクオリティの担保を上げていく、責任をきちんと持つことをやっていった方がいいんじゃないかというアドバイスで、「ほんまそうやな」とは思いましたね。
今、吉田さんって売上の比率は作家としての活動とクライアントワークでどんな塩梅なんでしょうか?
お金の面で言ったら6割クライアントワーク、4割が作家としての活動ですね。出版社も自主プロジェクトもお金はかかるんですが、自分が好きでやり始めたことだし、これが自分の活動の軸でもあるので目標を決めてやっていきたいなとは思っています。
自分の時間の半分を自主プロジェクトに使えているのは、とてもいいバランスですよね。ある種、師匠もいない、キャリアもない野良としてこの15年を過ごされてきたわけですが、自身はプロになったと感じる瞬間はありますか?写真の世界には資格もないですし、「食える=プロ」ではない難しさがあると思うんですが。
作品に関してはもう本当に、お金をいくら積まれてもやりたくないことは絶対やりたくないので、そういう意味では完全にアマチュアかもしれないです。ただ、クライアントワークに関しては、当たり前ですがプロとして臨んでいます。 というのも、クライアントワークの時にプロって意識を自分の中に持っておかないと、頼んでくれている人に失礼ですし、クライアントが想像していていた以上の結果を出して喜んでもらいたい。そのためにプロであろうという気持ちがすごくあります。
作家としては、プロになったと感じる瞬間はくると思いますか。
京都の祇園にある〈何必館・京都現代美術館〉の館長と以前2人で話したことがあって。その館長が言っていたのが、「広くやっちゃあかん」ってことだったんですね。「とにかく狭く、深く、ずーっと掘り続けられるやつが、本当の作家になる」って言ってて。 人って、飽きてくるじゃないですか、ずっと同じことをするのって。でも同じことをやるにしても、手を替え、品を替え、なんとか別の方法で同じことをやり続けることはできるわけですよね。 自分を飽きさせないようにするための工夫をして、一つのことを掘り続けていく。それを本気で長い時間、人生をかけてもしやれたら、きっとそれは写真でも、会社でも、なんでも作品になるんですよね。
なるほど。飽きることや、一つのアプローチを突き詰めることをそんなかたちで肯定されたのは初めてかもしれません。
万人には受けないかもしれない。でも、そうした作品が人の心を動かしたり、未来の人たちの心を捉える可能性は十分あると思います。だから、今、自分はこれがやりたいとか、これが好きなんだよなぁっていうことを自覚できている時点で、僕はすごく強いと思ってます。それが趣味じゃなくて、仕事としてやっているのであれば、それはなおさらです。趣味では到達できない深さに、仕事だったら深く潜れる可能性もある。僕はそれを目指しているんです。
「車輪の再発明」という言葉がある。「すでに誰かが確立した有用な技術ややり方を再発明をする」という意味だが、どちらかといえば現在ではムダな行為としてネガティブな文脈で使われることの多い言葉だ。しかし、吉田の話を聞いていて思ったのは、五感と心をフルに使って、いちから積み上げてきた人間が持つ言葉の泥臭さと力強さだ。「車輪の再発明もいとわない」自身の血肉の通った経験は、吉田の写真家としてのキャリアを押し広げ、自分一人のものではなくしていった。しゃにむに迷い、道のりが吉田を唯一無二の真似できない写真家として今、かたちづくっている。

You May Also Like
WRITER

- 編集長
-
26歳で自我が芽生え、とうとう10歳に。「関西にこんなメディアがあればいいのに」でANTENNAをスタート。2021年からはPORTLA/OUT OF SIGHT!!!の編集長を務める。最近ようやく自分が持てる荷物の量を自覚した。自身のバンドAmia CalvaではGt/Voを担当。
OTHER POSTS