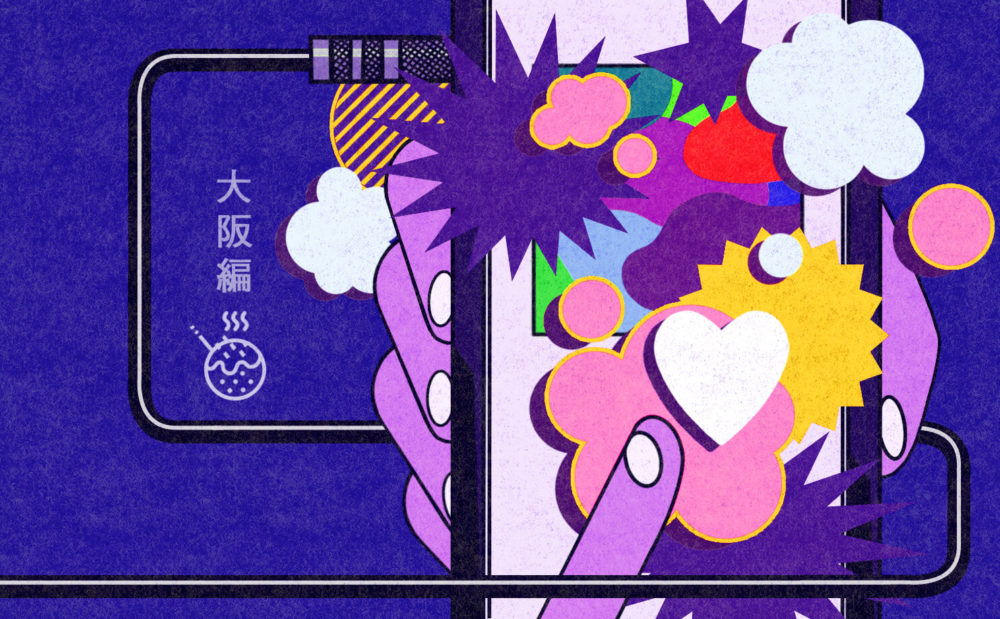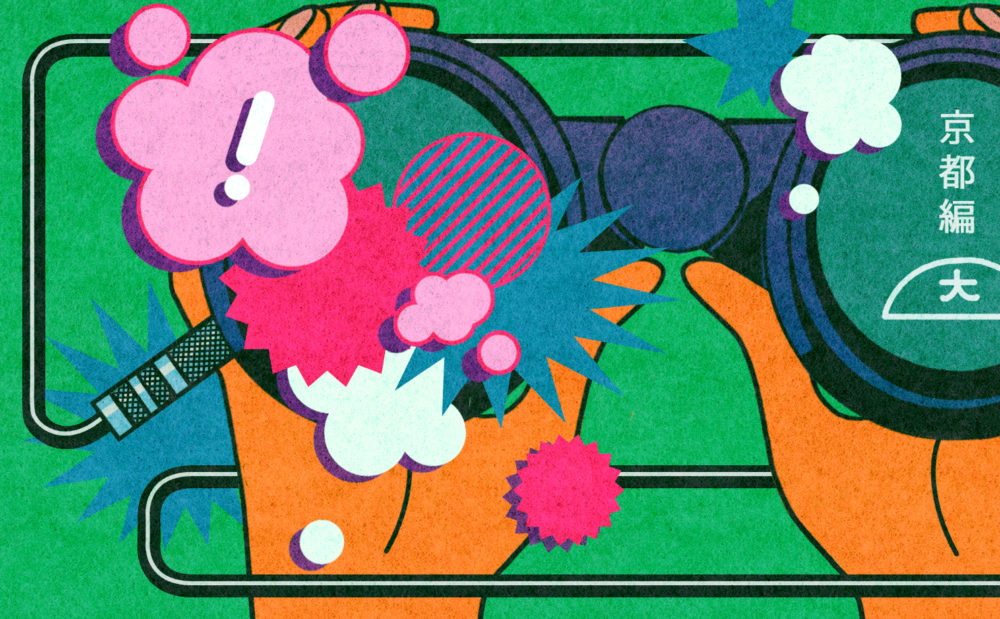コラボレーションのはじまりは「市場の交差」か「アーティストの交わり」か。TAIPEI MUSIC EXPO / JAM JAM AISA 2025レポート
「音楽はアーティストからはじまる」という、幾何学模様のGO KUROSAWAの発言が印象に残った『TAIPEI MUSIC EXPO 2025』。非常にシンプルで当たり前ながら、こと増加傾向にある音楽フェスや、レーベルとの力関係を鑑みると、キーノートでわざわざ発言をしないといけないくらいには見落とされがちなことなのだとも思い知らされる。アジアのメジャーなシーンと、インディーシーンが交差する『TAIPEI MUSIC EXPO 2025』、及びあわせて開催された『JAM JAM AISA 2025』の模様を今年もレポートする。
鴨出汁のヌードルを夜ご飯に食べていると、横からボソッと「好吃(おいしいぞ)」と聞こえてくる。こちらを見るでもなく、薬味の瓶だけを指さして言う店員のおじさんは、すぐにカウンターに戻りやりかけのスマートフォンのゲームに目を落とした。無愛想である、だが不親切ではない。日本ではそんな印象を受けることはあまりないが、一体なんの差であろうか。こうした接客を受けていると、「ああ、久しぶりに台湾に来たのだ」という感覚になる。
2025年8月30日、31日に開催された『TAIPEI MUSIC EXPO 2025』は、2020年に竣工されたコンサートホール〈Taipei Music Center〉が主体となって行う、東・東南アジアのレーベル、ライブベニュー、イベントオーガナイザー、ミュージシャンが集まって行われるイベントだ。主に2つのプログラムで構成されていて、事業の規模を問わず音楽産業の関係者が集まり、テーマに沿って事例などを共有するキーノートと、国や地域を超えて、互いの音楽産業を発展させるためのマッチングが一つ。そのタイミングにあわせて、Taipei Music Centerと同エリアにあわせて作られた大小4つのライブベニューと野外ステージを使って行われるショーケースイベントが『JAM JAM AISA 2025』となる。
台湾が音楽を主要産業として育てていこうとする気概が今年はアジア各国だけでなく、ヨーロッパのオーガナイザーまで参加していることからも見て取れる。ANTENNAは昨年度から主催のチームに“インディー側”として声をかけてもらっており、今年もその双方への取材とレポートを行うこととなった。
「ミュージシャン」という生き物は、誰かとなにかを作り上げることに喜びを覚える「コンヴィヴィアリティ」が天然で備わっているのかもしれない。そう思わされたのが今年のイベントの総括だ。
音楽はいかにして言葉の壁を超えるのか

近年はジャンルを超えたコラボレーションがシーンの大小に問わず増加傾向にあるが、そうした動きは日本だけに限ったものではない。数あるキーノートの中にも、「A Successful Cross Cultureal Music Collaboration(異文化の音楽コラボレーションの成功)」という企画があったことからも、各国の音楽関係者が他国や他地域とのコラボレーションに高い関心を寄せていることがわかる。K-Popが、各国のマーケットに切り込んだのは、市場の拡大を見越してのことだが、「他国、他地域とのコラボレーション」は言葉の壁を乗り越えるための一助となる。そうした可能性の模索を台湾の音楽関係者も意識していると、タイトルから伺える。
このキーノートの登壇者は、台湾の9m88と韓国のMAMAMOOのSolarとのコラボレーションを手掛けたFLUXUS INC. (ContentsX)のJameson Le (韓国)、GYMV (ex. Gym and Swim)とSunset Rollercoaster(落日飛車)のツアーなどをオーガナイズしたタイのLemmy(タイ)、そしてバンド・幾何学模様のリーダーであり、運営するレーベル・GURUGURU BRAINで様々な国や地域のアーティストコラボレーションを実現させてきたGo Kurosawa(日本)、そしてモデレーターのJohn Huang(台湾)という4名だった。
この投稿をInstagramで見る
この登壇者でいえば、まずJameson Leと、Lemmy、Go Kurosawaでは大きくコラボレーションの意図するものが違うことがわかる。話の口火を切ったJameson Leはマネージャーという立場から、「アーティストの寿命を伸ばすためにコラボレーションが必要だ」と話す。Solarの台湾アルバムの制作とリリースを参考に、台湾のリスナーをどのように獲得できたのかを「献身性」をヒントに語った。
中でも、やはり最も大きな障壁となったのは「言語」であるという。リスナーに歌われる、愛される楽曲があるのだとすれば、それは歌詞として意味がわかる、メロディとして美しいというだけでなく、リスナーの文化や生活と響きあうものである必要がある。そのための準備として、Solarがまずは2か月ほど台湾に滞在し、中国語を学んだというエピソードを聞かせてくれた。言語を学ぶにあたり2ヶ月という期間が決して長いとは思わないが、多忙を極めるアーティストがその時間を費やしたこと自体が、ストーリーを生み、プロモーションとしても成功を引き寄せた要因にもなっていると推察する。その結果は、中国語・韓国語の双方からポジティブなコメントが集まったYouTubeのコメントを見ていてもよく伝わってくる。
上記が、レーベルがアーティストをリードした成功例だとすれば、実にインディペンデントにアーティスト主導でのコラボレーションをサポートしてきたのがLemmyとGo Kurosawaの二人だった。共通している姿勢は、「じっくりとコラボレーションを成熟させていく」こと、そして「市場ではなく、音楽を主体にコラボレーションを行っていく」こと。二人の話を聞いていると、当日集まっている音楽関係者に「そもそも音楽を売ること以上に、コラボレーションをする喜びや目的があるのか?」という本質的な問いを投げかけているように感じられた。
特に、Go Kurosawaは《GURUGURU BRAIN》というレーベルを運営する立場にありながらも、自身がミュージシャンであるということは、忘れてはいけないポイントだ。Netflixのオリジナルドラマ『ザ・プレイリスト』(2022年)はSpotifyが立ち上がり、またサービスが音楽業界を大きく変えていく様をいくつかの立場からオムニバス形式で描いた作品だが、「ミュージシャン」、中でもインディーのミュージシャンがストリーミングサービスが台頭する中で置かれた厳しい状況にスポットライトがあたっていたことが記憶に新しい。一括りにメジャー、インディーの違いとして語ってしまうことは乱暴ではあるが、「市場がより大きく、資本との距離の近いメジャーシーン」において、無軌道で安易なコラボレーションはミュージシャンや音楽そのものをより「ただの商品」として扱ってしまう可能性をはらんでいることをLemmyとGoは示唆している。
そうした話の中で、さまざまな地域で親交を深めているキーとなるアーティストが台湾にいることが自然と伝わってきたことはおもしろかった。それが、各国の事例に名前があがっていたMONG TONGである。東洋のオリエンタルなあやしさをデジタルなサウンドを交えながら表現しているインストゥルメンタルな楽曲として昇華している兄弟ユニットなのだが、ビートを武器とするアーティストは「越境的なコラボレーションのハードルが低い」のかもしれないとも感じさせた。
Solarの事例が「言葉」を軸に文化的背景を乗り越えようとした話と対比するカタチで、ビートを軸として身体的なコラボレーションを行ってきたという話は、インディペンデントなアーティストの今後のやりようの糸口になっているように感じるのであった。
ミュージシャンは、今あなたと交信したい
次に、『TAIPEI MUSIC EXPO 2025』の後日に行われた『JAM JAM ASIA 2025』についても触れていきたい。
まず、昨年度の『JAM JAM ASIA 2024』と比較して随分とお客さんが増えているような印象を受けた。前日に運営チームのメンバーに、「今年のチケットの売れ具合がよくない」と不安を聞いていたのだが、メインとなるホールの〈Taipei Music Center〉だけでなくどこの会場もお客さんがパンパンで、2番目の大きさを誇る〈TERA〉(1,600~2,000人規模)も、3番目の〈SUB〉(800人規模)も、朝から晩まで取材のパスがなければ会場に入るには列に並ばないといけないほど賑わっていた。
そうした光景を見て、感じたことは台湾音楽シーンの成熟である。〈TERA〉には、Solarとのコラボレーションが紹介されていた9m88がトップバッターとしてステージに立った。台湾だけでなく日本を含めアジアの中でもより高めていることが想像にかたくなく、もちろん集客もばっちりで会場に入るのも一苦労である。
また、それ以上に寡作なバンドでインディペンデントなあり方に軸足を置くI’m difficultが(大きめなイベントなのでお客さんそのものが多い部分があるとはいえ)同じトップバッターとして会場を埋めていたことが少々驚いた。演奏のレベルが高く、ライブ巧者ではある。代表曲である“Last Summer”や“Half-Full”あたりを楽曲の序盤と、終盤に持ってくることでしっとりとしたラインナップでもしっかりと盛り上がりを作ってくるあたり、そのことにも納得ではあるのだが。
台湾外のアーティストでぜひ触れておきたいのが、インドネシアのバンドン拠点のダブバンドRub of Rubだ。
今回は、8月30日(土)に最も小さな会場となる〈Live House D〉に出演していたのだが、楽曲が始まった瞬間に踊りだす人で前方に小さな輪ができあがるほどにピースフルで、ダンサブルなムードがパフォーマンスによって一瞬で生み出された。演奏中Rizwan(Gt / Vo)は終始ニコニコしており、広がりのあるギターサウンドとベースのうねり、軽くても締まりのある心地よいハットの音が絡み合い自然と身体が揺らされる。この日はお酒を我慢していたのだが、飲んでいないことを後悔するくらいには身体を横に揺らされるサウンドだった。
ここで思ったのは、リスナーとアーティストの関係性についてである。『JAM JAM ASIA』は出演者にアジア各国のアーティストが名を連ねてはいるものの、お客さんは台湾に在住している台湾華語の話者が基本ではある。そうした意味で、「歌詞」の意味が伝わらないRub of Rubが集客面で苦戦することは自然といえば自然なのだが、初めてリスナーが耳にする楽曲であっても自然と身体が動き、踊ることができるビートを彼らは持っている。
もちろん、踊り方はその日会場に来ている人たちそれぞれなので、前述のように輪になって踊る人もいれば、一人でゆったりと踊る人もいるが、会場にいる一人ひとりがバンドのビートを受け取って一つのアンサンブルを構成しているように思えた。これもまた、ミュージシャンが行うコラボレーションの一つだと感じたし、そうした交信を求めるステージは、商業的に音楽を “歌詞によって届ける” ということとは、やはり少し意味が違ってくると思うのである。

二日目のトリを飾ったバンドは、なんと9年ぶりとなる2ndフルアルバム『QUIT QUIELTY』をリリースしたばかりのSunset Rollercoaster(落日飛車)だ。近年はアジアの枠を超えて活躍するバンドとなり、また韓国のHYUKOHとのコラボレーションも記憶に新しい。この日は台湾の俳優であるGreg Hanとの共演を行っていた。
彼らとGreg Hanとの関係は深く、MVへの出演に加え、パンデミックの際に彼らが始めたVR空間に作った架空の街での音楽イベント『Sunset Town Festival』にも出演者としてその名を連ねている。この日は、終盤にGreg Hanが登場すると新作のアルバム人気曲「bluebird」を含む3曲ほどを一緒に演奏していた。
加えて、この日は舞台演出に新田幸生が参加。照明やVJも彼らがチームとして作り込んだものになっていた。VJの映像は2つのビルを背景に、近づいたり離れたりスケール感を変えながら、エフェクトが重なるというもの。新田を含め、この照明やVJとの連携はSunset Rollercoasterが中国ツアーをした際のチームであり、そうした意味で、この日は国内外でいろいろと試してきた「音楽、演出」をそれぞれ一つのパフォーマンスとしてかけ合わせるようなものになっていたのである。
そうして作られた世界に呑まれ、大きなホール、一時間ほどのショーにもかかわらず、ほとんどの人がゆっくりと座り込みその場を動けなくなっていたことに気づいたのは僕自身ライブ終演後であった。

あっという間にイベントが行われた4日が過ぎ、またすぐに台湾を離れることになった。今はずうっと住んでいるわけでもないし、シーンにコミットしているわけでもないからこそ、定期的に訪れることでどんな音楽産業が盛り上がってきたかとか、ムードの変化がなんとなく伝わるものがある。
アメリカや日本の市場を求めた韓国同様、台湾もマーケットは小さく今後もそうした外へ向かう意識は継続していくだろうとは感じている。願わくば、そうしたコラボレーションが「市場から届けられるもの」だけではなく、「アーティストの生活から交わっていくもの」であることを楽しみにしている。もちろん、そこにコンヴィヴィアリティが宿るからである。
You May Also Like
WRITER

- 編集長
-
26歳で自我が芽生え、とうとう10歳に。「関西にこんなメディアがあればいいのに」でANTENNAをスタート。2021年からはPORTLA/OUT OF SIGHT!!!の編集長を務める。最近ようやく自分が持てる荷物の量を自覚した。自身のバンドAmia CalvaではGt/Voを担当。
OTHER POSTS