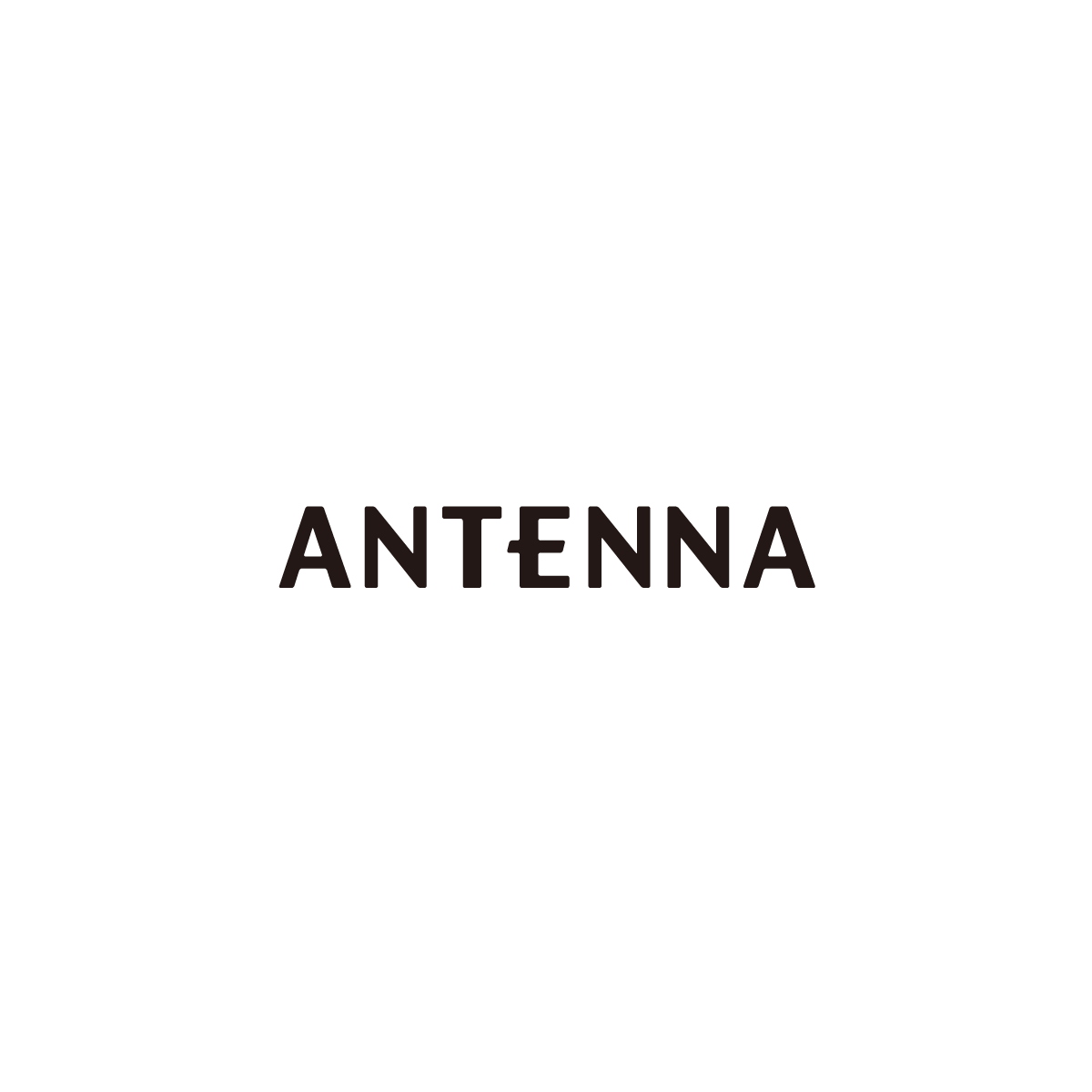【阿部仁知の見たボロフェスタ2018 / Day2】ギャーギャーズ / 2 / 踊ってばかりの国 / toe / tofubeats
ボロフェスタの良さとはなんだろうか。前日の興奮を引きずりぼんやりしながら歩くKBSホールへの道すがら、僕はそんなことを考えていた。
語り尽くされているかもしれないが、まず一つ挙げるならそれはやはり手作り感であろう。入口前のタイムテーブルひとつとってもペンキまみれで汗水垂らした奮闘の過程が見えてくる。それはプロのデザイナーの仕事であろう大規模フェスからは感じにくいもので、親しみと暖かさを持って僕らを迎え入れてくれる。
そしてそれを作っているのがボロフェスタを支えるボランティアスタッフだ。当日も動線管理や呼び込み、速報レポートの作成からアーティストのケアまであらゆるところを奔走する彼らだが、単なる提供者ではなく俺たちがこのフェスを一番楽しんでやるんだという気概と誇りが参加者の立場からも見えてきて、一緒に作り上げようという気持ちになってくる。いろんなフェスに行ったが、そういう気持ちをスッと持てるのはこのフェス特有のものではないかと思う。
さて、そんな風に気持ちを新たにしたところで、2日目スタートだ。
ギャーギャーズ
MC土龍の「最初からアゲてくぞ!」という紹介から現れたのはfrom 大阪、ギャーギャーズだ。「入口の人混みに巻き込まれて俺以外のメンバー死んでしもた」と1人でステージに上がる蛭田マサヤ(Gt. / Vo.)。「お前らの叫びで復活やー」みたいに煽ってくるのかと思っていたら特にそんなことももなくあっさり4人揃ってしまった。かたや京都を代表するバンドHomecomingsがメインステージを彩っている裏にあからさまな大阪ノリを持ち込む彼らの印象は掴みから強烈だ。
いきなりフロアに飛び込みギターをかき鳴らすハイテンションな蛭田。若干戸惑いつつも湧き上がるオーディエンス。バンド名の通りギャーギャーうるさい直情的なパンクなのだが、町内会のお祭りのような野暮ったくもどこか懐かしいパフォーマンスに自然と笑みがこぼれる。ピッチが不明瞭だったり、もたったりはしったり、荒っぽくはあるがその雑味がたまらなくいい味を出している彼ら。後半の“さざ波”や“映画を観た日”ではたまを思わせるアンニュイな感じで脱力しながらゆらゆら揺れ、最後は再び盛り上げナンバー“チャリンチャリン”。「ボロフェスタは主催者の顔が見えるフェスだ」と語った蛭田だが、このフェスにしてこのバンドありとでも言ってしまいたくなるような泥臭くて生活感がある近所の兄ちゃんみたいな彼らのロック。そんな姿を見ているとなんだか僕もお酒でも飲みたくなってきて、いい気分で地上へとあがった。
Photo:ヤマモト タイスケ
2
古舘佑太郎(Gt. / Vo.)と加藤綾太(Gt.)がそれぞれのバンドを休止させるもやっぱりバンドがしたいと邂逅したのがこの2(ツー)だ。京都初ライブということもあって彼らを一目見ようとサウンドチェックから期待感が高まる中、カラッとしたギターが鳴り響いた。初っ端から疾走感溢れる曲の応酬でフロアも跳ねたり踊ったりどんどん盛り上がっていく。飾り気のないシンプルなギターロックサウンドながらも、バンドで音を鳴らす喜びを噛みしめるようなプレイに胸が熱くなる。1×4が10にも100にもなるだとか、そんなクサいことも言いたくなる。これぞバンド音楽だ。
yucco(Dr.)のパワフルなドラムに走らされ熱を帯びるパフォーマンスの中でも、古舘のどこか子どもっぽく青臭い歌声にあてられてなんだかセンチメンタルな気分。みんな汗だくだけど、先ほどのギャーギャーズのような酒臭くて脂っこい汗(それもまたいいものだが)とは違い、まるでスポーツマンみたいな清涼感あふれる汗だ。
そして終盤に入り、家族への愛をざっくばらんな古舘節で歌った“Family”へと続く。かつてのバンドTHE SALOVERSではひたすら前のめりに消え入りそうな衝動を歌っていた古舘だが、2の音楽はあらゆる層へ向けられた普遍的なものへと広がりを見せている。そして銀河の果てから目の前の彼女へ一直線に向かう代表曲“ケプラー”で完全燃焼。バンドのダイナミズムに巻き込まれ全速力で走りきった30分間。青春時代はとうに過ぎ去り、かつてのようなキラキラは消え去ってしまったとしても、この4人の第2章はまだまだ始まったばかりだ。
Photo:岡安いつ美
踊ってばかりの国
神戸から飛び出し今や全国を席巻する踊ってばかりの国が今年もボロフェスタにやってきた。今年は兵庫県伊丹市のフリーフェス『Itami Green Jam』や先日大阪府堺市で行われたGEZAN主催の『全感覚祭』にも出演し、全国区のバンドながらもライブの度に地元関西への愛着を語る彼らは、ここ京都でも凱旋とばかりに一曲目の“ほんとごめんね”から轟音ギターを鳴り響かせる。「いっぱい踊れ〜!」と身体をくねらせながら叫ぶ下津光史(Gt. / Vo.)の言葉は音楽を奏でる純粋な喜びに溢れていて、そんな姿を見ると堅苦しいことなど考えなくとも音楽に身を委ねるだけでいいという気持ちになってくる。
幾多のメンバー交代を経て進化と変化を繰り返してきた彼らだが、現在は初期からのサイケサウンドを貫きつつもシンプルに下津の歌が輝く。<ときめく心は大切に ずっと 心を大切に>と歌う“evergreen”だが、こんな素朴でありふれたフレーズにここまで真に迫る説得力を与えられるシンガーがどれほどいるだろうか。自由奔放に動き回る下津をよそに他のメンバー4人は表情も変えずクレバーに演奏に徹する。
「ロックンロールしにきた全員に捧げて帰ります」と言い始まったのは最新作『君のために生きていくね』のリードトラック“boy”。3本のギターが絡み合いいつまでも終わらないかのようなリフレインの中、感極まった下津は何度も「ロックンロール!」と叫ぶ。拳を突き立てる人、フラフラ揺れる人、圧倒され立ち尽す人、それぞれ色んな反応を示すこの空間がただただ美しい。彼らの音楽には形式や作法なんてものはなく、ただただ自由な解放なのだ。下津が語った「音楽は無限大なり」。そのことに立ち返れたような素晴らしい時間だった。
Photo:ヤマモト タイスケ
ムツムロアキラ・下津光史

「チルな時間もいいけどできるだけ盛り上がる時間だらけにしたい」と語るMC土龍は会場で参加者と同じように楽しんでいた2人のフロントマンを飛び入りで連れてきた。このリアルタイム感もボロフェスタなのであろう。まず現れたのはハンブレッダーズからムツムロアキラ。「お父さんは嬉しいよ」と息子ほど年が離れたムツムロに話すMC土龍の表情はとても穏やかだ。「Live House nanoからの帰り道で作った」と感慨深そうに話す“口笛を吹くように”など、彼にとっての京都の思い出を噛み締めながら歌うステージはとても和やかな雰囲気で、お客さんもゆらゆら揺れていたり座ってぼーっと眺めていたり思い思いに過ごしている。結果的にチルな時間にはなったが、これも音楽が作り出すの一つのかたちだろう。
そして「毎度恒例ボロフェスタのむちゃぶり!」とおどけてみせる下津光史 (踊ってばかりの国)。彼の歌には先ほど圧倒されたばかりだが、一つ一つの言葉を噛みしめるように丁寧に丁寧に歌うこのステージはまさに弾き語りという言葉そのもののようで、みんな静かに彼の歌声に耳を傾けていた。ハイライトは「音楽を愛してる全員の歌」と語る“唄の命”。遠い国の戦争をモチーフにしたこの曲で下津は<僕が歌ってるという事 今を生きているという事 それを君が聴くという事 唄の命が生まれるのよ>と歌う。これは彼自身の、歌うことの、或いはこのボロフェスタという試みの本質を射抜いた一節だと思った。歌うことしかできない表現者という孤独は僕らがこうして観ることで少しだけでも救われる。そこに生命が宿る。歌いきった彼を僕らは鳴り止まぬ拍手と歓声で迎え入れた。
toe
2012年の初出演以降世界中に活動の幅を広げてきたtoeの6年ぶりのボロフェスタ。今回はなんといっても今夏にリリースされた最新作『Our Latest Number』からの曲が印象的だ。“レイテストナンバー”では彼らの楽曲では珍しいヴォーカルを山嵜廣和(Gt. / Vo.)が務める。彼の気だるい歌声が加わることで生まれた浮遊感はこれまでのtoeにはない新境地を見せてくれた。
そしてサポートメンバーを加えた5人が有機的に絡み合うことで生み出されるグルーヴはエレクトロミュージックのような麻薬的な陶酔感を醸し出し、僕らはこの空間に溶け込んでいく。シリアスで狂気的ともいえるサウンドは、リズムという概念を超え僕らの身体に直接訴えかける。周りを見渡してみれば本当に多種多様な揺れ方・ノリ方の人々がいて、拳を挙げるタイミングもバラバラ、みんな思い思いの空間だ。この不揃いがなんとも気持ちいい。みんなが揃っていることで生まれる一体感とは違う、誰も一緒じゃないことによる不思議な一体感。再び山嵜が歌う“F_A_R”が鳴り止んだ時、僕たちにはもう恐れることなんて何もなかった。
tofubeats
ダンスミュージックとJ-POPの接合点を模索し続ける神戸在住のトラックメーカーtofubeats。数々のコラボレーションとともに時代を切り開いてきた彼が一人で挑んだ意欲作『RUN』をひっさげて2年ぶりのボロフェスタ登場だ。
DJプレイならではの抑揚をコントロールしながらシームレスに場を作り上げていくスタイルはやはりポップミュージックとの相性抜群。一度聴いただけで耳に残るキャッチーなフックの数々が直接感性に訴えかけ、僕らは身体の反応のまま踊る。ここはパーティーナイトだ。
その中でも特に印象的だったのが初期の代表曲“Don’t Stop The Music”。どんどん閉塞感を増してきているような感じがする2018年の現在、もはやこの曲は無邪気に未来を夢見ていられた当時のようには響かない。だがそれでも<Don’t Stop The Music>と高らかに宣言する姿に彼の強い決意を感じるのと同時に、真横に掲げられたボロフェスタ2018のスローガン「音楽を止めるな!」に込められた意志をまざまざと実感させられて胸が熱くなった。そんな姿をみると“Lonely Nights”のやりきれない焦燥感も受け入れられる。僕らには“ふめつのこころ”があるから大丈夫だとばかりに彼は力強く歌い続ける。
そんな楽しいパーティーもそろそろおしまい。この刹那的な今を名残惜しく愛しむアンセム“水星”ではフロアを埋め尽くす観客が左右に手を振る。そして言葉にすると消えてしまいそうな深い深い愛を歌った“RIVER”。どんな愛に想いを馳せるかはここにいる人の数だけあっても、感じている気持ちはみんな同じだ。
迷い苦しみながら時代とともに歩んできた彼の物語が凝縮された30分間を通して、同じように試行錯誤を生きてきたボロフェスタに想いを馳せる。まるでクラブでの一夜のように様々な感情が詰まった濃密な時間は、外に出て夜が明けていないことに違和感を覚えるほどで、名残惜しさと余韻に浸りながら僕はしばらく佇んでいた。
Photo:齋藤真吾
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
はろーべいべーあべです。フェスティバルとクラブカルチャーとウイスキーで日々をやり過ごしてます。fujirockers.orgでも活動中。興味本位でふらふらしてるんでどっかで乾杯しましょ。hitoshiabe329@gmail.com
OTHER POSTS