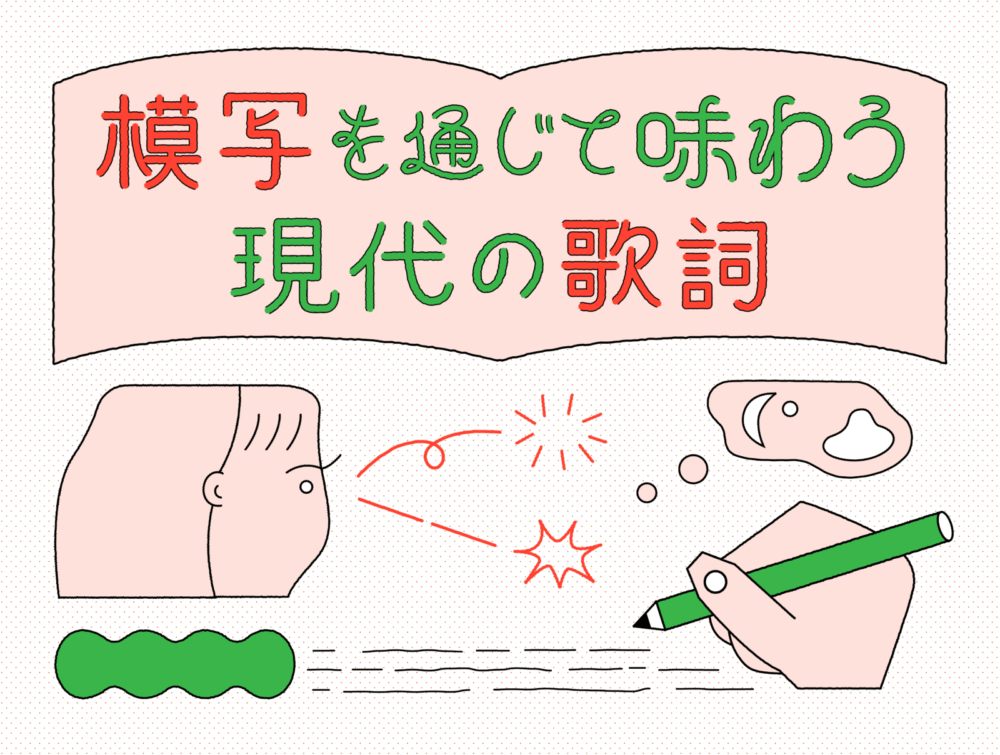阿部仁知が見たナノボロフェスタ 2020
来年もこの場所で会おう。ボロフェスタ2019のライブレポートを僕はこう締めたが、まさかこういうかたちでこの場所に来るとは思ってもいなかった。そう、誰ひとり想像していたはずもない。新型コロナウイルスの影響で多くの音楽フェスティバルが中止・延期となった2020年の夏。8/29(土)と8/30(日)の2日間、例年のLive House nanoを中心としたサーキットフェスからボロの本尊KBSホールに場所を移し、ナノボロフェスタ2020は開催された。
行かないほうが賢明、行くなら自己責任。自粛ムードが日本中を覆った3月以降、まるで「あまり楽しそうにしてはいけない」とでも言われているかのように、僕は外出した際もどこか後ろめたい気持ちを抱えざるを得なかった。しかし、この2日間は少し違っていた。会場の至るところで徹底的な感染症対策を施し、パーティーナビゲーター土龍を中心に密にならないよう呼び掛ける姿も、真摯ながらも決してものものしくはない。せわしなく動くスタッフ一同の「絶対にいい日にしよう」という思いが伝播し、僕らも自然と「この場所をつくるのは僕たちだ」という気持ちになったのだ。だから何も後ろめたくなかったのだろう。

「これがリアルや!」と開幕を飾ったアフターアワーズ(1日目 / Forever Live STAGE)が小気味よくギターを掻き鳴らしながら、丁寧に響きを確かめるようにライブをする喜びを噛みしめる表情に僕らもグッとくる。密こそが彼らのアイデンティティのように思っていたULTRA CUB(1日目 / Never Die STAGE)も、ライブハウス然とした前のめりの熱情を徐々にホール規模に広げながら、僕らもゆったりとしたフロアで思い思いの感情をぶつける。はたまた常にシャウトで全力全開、愚直にパワーコードでひた走るワッツーシゾンビ(2日目 / Forever Live STAGE)の極限まで削ぎ落とされたステージングに、洗練された美学を垣間見る。「我々はもみくちゃを信じてるのではなく音楽を信じている」と語ったのはボロフェスタ代表の飯田仁一郎。そう、もちろんぐっちゃぐちゃのモッシュもいいものだが、決してそれだけが音楽の楽しみ方ではない。



例えば須田亮太(1日目 / どすこいSTAGE)の弾き語りに溢れた、決して色あせない音楽への愛。苦難に晒されながらもなお、初めてギターを鳴らした時のような純粋な輝きをまとう彼の歌に、聴衆は誰からともなく座って耳を澄ませる。そしてごくシンプルに弾き語る長谷川健一(2日目 / どすこいSTAGE)の、強靭な歌の力。この場で培われてきたものを媒介としながらただひたむきに歌に乗せるその姿は、ボロフェスタの精神そのもののようで、僕はただただ圧倒される。ここに共通するのは、どんな苦難に晒されようと自分の信じた自由を歌う、その気概と覚悟だろう。10周年のエンドロールで流れたという“夜明け前”は、その場に居合わせなかった僕にも東日本大震災で傷ついたこの国を優しくもたくましく鼓舞したのであろう、当時のボロフェスタの姿がありありと浮かんできたのだ。


そんな精神を脈々と受け継ぐナノボロフェスタ 2020には、METROを中心に京都アングラシーンを彩る気鋭のトラックメイカーたちも集結。トラックメイカーとバンド、クラブの情感とライブハウスの熱狂が、KBSホールに入り乱れていた。本レポートでは2日間を使った壮大な取り組みをそれぞれのシーンから紐解くことで、この場所に流れていた大きな精神の脈動の記録としたい。
2020年の京都の夏にはナノボロフェスタがあった。もし数年後に振り返って「何を大袈裟な」と思われようとも、これは偉大な足跡であり金字塔なのだ。
ゆとりのあるフロアで各々の身体の鼓動に没入する、トラックメイカーたちの共演
3月に取材をした際にアリムラ(in the blue shirt)は「今トラックメイカーたちは引きこもってひたすら曲を作っている」と語っていたが、ダンスフロアが失われた状況下でも虎視眈々とクラブの情景を描いてきたトラックメイカーたちの共演が見られた。例えばCeeeSTee(2日目 / Forever Live STAGE)。各々の精神世界に深く没入するような音像に目を閉じ揺れる中で、グルーヴとはリズムでも音の大きさでもなく、自分の身体が一番気持ちのいいフィーリングのことなのだと実感した。コンピューターのバグのような、抽象的ながら脳内世界を刺激するヴィジュアライズとともに展開するSNJO(2日目 / Never Die STAGE)のステージでも、タイトなビートとメロウな歌の情感を縦横無尽に行き来するパフォーマンスに僕らの感覚は開かれていく。これを意図したわけではないだろうが、ソーシャルディスタンシングなゆったりとしたフロアの中、僕らはなんの雑念もなく各々の揺れに意識を集中させていた。

そして極めつけはピアノ男(2日目 / Forever Live STAGE)だろう。広末涼子のパネルとともにインドネシア語の“恋のマイアヒ”でフロアを高揚させたと思ったらMay J.の“少年時代”が醸し出す夏の情感をマシンガンのようなガバサウンドでぶち壊し、パラパラを踊りながらの浜崎あゆみの“SEASONS”もビートの重量で即座に台無しに。「何が起こってるんだ!?」の応酬に、理解するというフェイズをすっ飛ばしながら感応していくオーディエンス。2月のPotluck Lab.でも、周りにどう思われようとも自らの「おもしろい」を探究する姿勢を示してくれたピアノ男だが、まさに“よくできた量産品より唯一無二のクソ”の精神がKBSホールの隅々まで波及した瞬間だった。
彼と同様にマスクとサングラスで表情が見えなかった佐伯誠之助(1日目 / どすこいSTAGE)のステージでも、サンプラーとカオスパッドが内蔵された特注ギターを駆使しながら卑猥極まりない言葉がフロアに刻まれていく様に当惑したが、共通しているのは堂々たる佇まい。徹底的なディグに裏打ちされたダンスフロアへの哲学と矜持をぶちまける姿に、僕らも爆笑しながら拳を握るしかなかった。ステージを降りてホールで見かけた彼が着ていたのはMETROのドネーションTシャツ。とぼけたMCを聞いていても佐伯の本心はまるで掴めなかったが、その胸に刻まれた「UNDERGROUND KYOTO」の魂を体現したステージは、京都アングラシーンの真髄を雄弁に語りかけていた。


フェスの現場だからこそ表出する、破壊と再構築の流動
フェスティバルの醍醐味のひとつにタイムテーブルの流れがある。とりわけボロフェスタはそこに込められた思想を強く感じるフェスだ。そしてナノボロフェスタ2020で特異点、いや劇薬のように僕を殴りつけたのはおとぼけビ〜バ〜(2日目 / Never Die STAGE)だ。
CeeeSTeeで深い内省に投げ込まれ、SNJOがその感覚を拡張し、ピアノ男で大いに開かれた僕に飛び込んできたのは、以前METROで観た時よりも遥かにたくましいパフォーマンス。ウィットに富んだ言動で笑いを誘いつつも、あくまで真摯に激情をバンドサウンドにぶつける姿に、僕は彼女たちが嫌悪する“理解のある風の”男性でしかないことを嫌でも痛感させられてなんだか心がザワザワする。でも目の前で繰り広げられるバンドの躍動から目を逸らせない。「イロモノ」や「声を上げる女性」というバイアスを乗り越えたおとぼけビ〜バ〜が僕に与えてくれたのは、どうしようもない混沌と自己変革への渇望だったのだ。

そんな僕に投げかけられたのはLaxenanchaos(2日目 / Forever Live STAGE)のサウンド。性別も年齢も人種も見て取れない眼前のトラックメイカーが繰り出す、細胞から宇宙までダイレクトにつながるようなスケールの大きなサウンドに身を委ねるにつれ、僕の混沌は瓦解し再構築されていく。後ろのPAスタッフは引いていたかもしれないが、そんなことは気にならない。多分近くにいた他のオーディエンスも同じ気持ちだったんじゃないだろうか。僕はここで何か生まれ変わったような気持ちになった。
そして、ステージはKONCOS(2日目 / Never Die STAGE)に引き継がれる。彼らが暮らす下北沢が置かれたライブ・エンターテインメントの状況を語りながらも、それでもなお音楽を生かそうとする古川太一(Key / Ba / Vo)の熱情と矜恃はシンプルに核心だけを射抜いていく。ここに集まれた喜び、音楽の素晴らしさ。それがここまで素直に僕の胸に届くのは、彼らの生き様が刻まれたような熱いパフォーマンスによるものなのは確かだが、CeeeSTee、SNJO、ピアノ男の流れが根底から感性を開ききってからおとぼけビ〜バ〜に揺さぶられ、Laxenanchaosで再構築する大きな流れがあったこその、このKONCOSの昇華だったのではないだろうか。僕はここに、ジャンルに捉われず「音楽の力」をただひたむきに信じ続ける、ナノボロフェスタの精神を見たのだ。


バラバラな出自を飛び越えて混ざり合っていくKBSホールの情景
ホール正面の大ステージを2分割して設置されたNever Die STAGE / Forever Live STAGE。このステージ形式はほとんどの人にとっておそらく初めての体験だっただろうが、バンドの正面でライブハウスのようにガンガン熱狂したり、斜め後方で佇みながらホールの響きを感じたりと実に多種多様な楽しみ方があらわれていた。ソーシャルディスタンシングなまま熱狂をというナノボロフェスタの想いを汲みながら、自分たちの表現を追求するミュージシャンたちの姿。ここに散りばめられた素晴らしき音楽の協奏をさらに掘り下げてみよう。
誰もが度肝を抜かれたのは家主(1日目 / Forever Live STAGE)のパフォーマンスだろう。昨年のアルバム『生活の礎』に表現されたぬるい日常の情感はそのままに、田中ヤコブ(Gt / Vo)のつんざくようなギターを中心に生々しいバンドサウンドが展開される様子に、僕はホール全体で音を感じたいと少し後退していた。しかしそれでもなお狭く感じる歌と弦と打音のせめぎ合いを、彼らはラフなセッションのようなゆるさのまま紡ぎ出す。オールディーズへの憧憬と古き良き哀愁を感じさせる恍惚のギターサウンドに、僕はひたすら唸るばかりだった。

家主同様に深いルーツを感じさせたのはCuBerry(2日目 / Forever Live STAGE)。カラッとしたガレージサウンドをポップに昇華する姿は愛らしくも力強い。だが単純明快なポップソングではなく、少しモヤっとした空気を切り裂くようにKanaco(Gt / Vo)のギターが飛び出してくる様はとてもスリリングだ。そんなバンドサウンドの中でも、、意識すらできないレベルの男性優位が根づいたこの社会を浮かび上がらせる歌詞が突き刺さる。女性だからという安直なラベリングではない、女性であることも踏まえてCuBerryだからできる表現を追求する姿勢に、HAIMやStella Donnelyの姿が重なったのは僕だけではないだろう。
一方で僕がおおいに注目していたthe McFaddin(1日目 / Forever Live STAGE)のステージ。よくゲスト出演しているDJイベント『SCHOOL IN LONDON』が東京で行われているまさに真裏で、トラップビートのチルな情感とThe 1975を彷彿とさせる情動の緩急がKBSホールに刻まれる。VJとしてサポートするryoma matsumotoの映像はとてもきらびやかで洒脱な雰囲気を醸し出しているが、どことなく野暮ったさも持っていて、そこにryosei yamada(Gt / Vo)のシャウトが飛び込んでくるKBSのフロア。クールでスタイリッシュ、だが激情も併せ持つ彼らの冷たくも熱いステージは、トラックメイカーとバンド、クラブの情感とライブハウスの熱狂が入り乱れたナノボロフェスタの楔となっていたように思う。


例年のKBSホールをもみくちゃにしてきた街の底STAGEは密対策のためか今回は設置されなかったが、そこから這い上がってきたバンドが多くラインナップされた1日目。想像していたかたちとは違っても、広いホールで音を鳴らす喜びを噛みしめるバンドとその姿を愛しむ人々のあたたかいコミュニケーションがあった。
そのトリに満を辞して登場したのが浪漫革命(1日目 / Never Die STAGE)。他愛のない日常を噛みしめるような彼らのバンドサウンドは、高出力ながらもどこか気だるげな雑味がありあたたかい。人でごった返した祇園祭、ビール片手にふらふらと歩いた木屋町、鴨川、METROまでの道。今年は失われてしまったこの街の日常が愛おしく思い返され、それぞれ思い思いの感傷に浸る。土龍から浪漫革命へのサプライズというステンドグラスはメンバーもびっくりしていたが、失われた祝祭が華やぐ様子に、レリーフの天使たちも心なしか微笑んでいるように見えた。

明快で清々しいエンドロール、これからを生きていく僕たち
アーティストと観客の垣根も越えた数ヶ月ぶりの再会がそこかしこで見られ、失われつつあったこの夏を全身全霊で躍動させるナノボロフェスタ。2日目の最終幕には、過ぎ去ってしまうこの儚い一瞬を永遠に刻みつけんとするアーティストと僕らの煌めきがあった。さとうもか(2日目 / Forever Live STAGE)のバンドセットでは、気心の知れたメンバーたちが彼女のトラックメイカー気質の遊び心をさりげなくも確実に引き立てホールを包み込む。話し言葉のような息遣いで屈折した感情ごと等身大に表現する彼女の姿はとてもキャッチーでポップだが、たまらなく切なくもなる。今、ここに集った偶然を奇跡のように輝かせる“Glints”でステンドグラスがあらわになり、誰もが残りわずかなこの夏を名残惜しくも愛おしく思っただろう。
そしてこの夏の最終幕を託されたのはマンチェスタースクール≡(2日目 / Never Die STAGE)。名前の通り明快で清々しいUKガレージサウンドをかき鳴らす彼らの姿は、この2日間を締めくくり明日からも過ごしていくためのエンドロールのようにも思えた。マイクを高々投げたり、ドラムに登ったり、最後には終演後のForever Live STAGEを駆け巡るハルロヲ(Gt / Vo)。なんていい顔をしているんだ。自粛を余儀なくされたこの半年を思い返しながら、この瞬間に全て吐き出すような彼らのパフォーマンス。いつものような歓声はあげられなくとも、誰もが心の中で歌い騒いでいたことは、ここにいた全員が感じたはずだ。


全力で駆け抜けたナノボロフェスタは終幕を迎え、ステージにあらわれる土龍、飯田、そしてナノボロフェスタ運営チーム代表のミノウラヒロキ。「ここにいる人に真っ先に伝えたかった」と10月に予定されていたボロフェスタ 2020の中止が発表されるが、思いの外悲壮感はなかった。もちろん悔しい。僕はもとより、ステージの3人の想いはなおのことだろう。だがこの2日間、リアルタイムで試行錯誤しながらナノボロフェスタがこの時世でできる最善を尽くし切ったことは、ここに残った全員が肌で感じ取っていた。だからこそ不思議と清々しい納得感があったのだ。
思い返せば1日目の最後に掲げられた垂れ幕には「コロナに負けるな」と掲げられていた。これは決して感染することでもイベントを中止することでもなく、避けようがない大きな流れに絡め取られて僕らの精神性、「ライブが、フェスが、音楽が大好きだ」という気持ちを殺してしまうことなんじゃないか。ステージに冠されたNever Die / Forever Liveもきっとそういうことだ。
ボロフェスタが脈々と育んできたひたむきに音楽を、そして自分自身の可能性を信じていく精神。僕は今回その真価を見た気がした。多くの変革が迫られたナノボロフェスタだったが、まったく揺らがないその根底があるからこそ誰もが清々しく過ごせたのだろう。どんな苦境でも、思いやりと敬意を持ちながら、自分自身が楽しいと思った感覚を信じていく。エンドロールで流れていた“Baby, Stay Home”も、そんな気持ちがSNSを通じて結晶となった曲。想像の垣根を越えて僕らはなんだってできる。2日間で体感したそんな確信が、曲に乗せて終演後のKBSホールを気持ちよく包んでいた。
今年のボロフェスタは中止となったが、来年は20周年の2週連続開催。ボロフェスタはただでは転ばない。その日まで各々の日々を生き抜いて、来年もこの場所で会おう。

You May Also Like
WRITER

- ライター
-
はろーべいべーあべです。フェスティバルとクラブカルチャーとウイスキーで日々をやり過ごしてます。fujirockers.orgでも活動中。興味本位でふらふらしてるんでどっかで乾杯しましょ。hitoshiabe329@gmail.com
OTHER POSTS