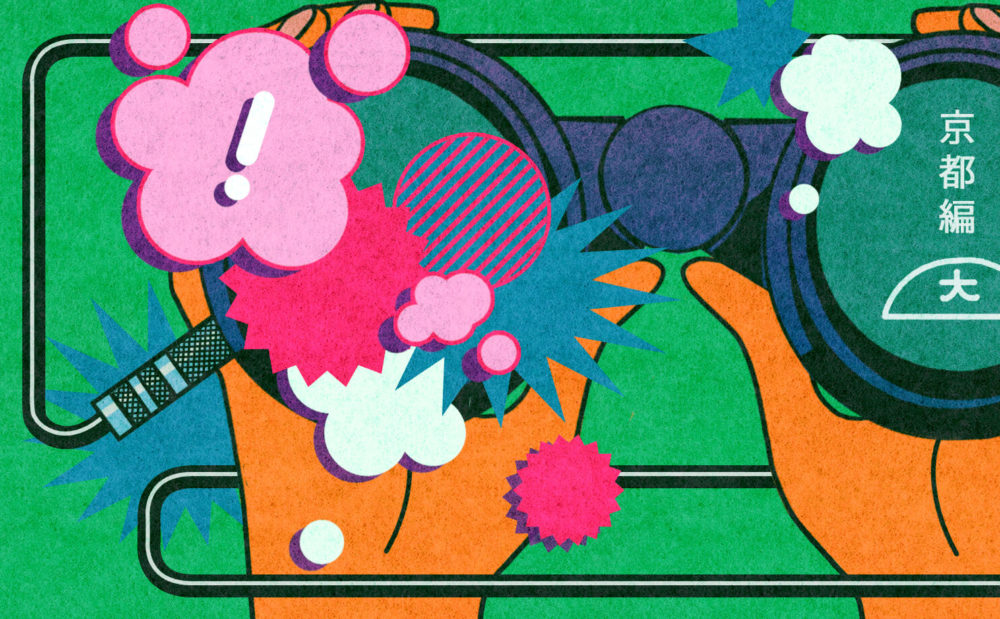『Fight Club vol.1』- ぶつかり合う、拳の先に見えたもの
4組の演奏が終わった時の不思議な感覚はなんだか忘れがたい。‟アンダー25”というテーマにそって編集部のメンバーがそれぞれに推しアーティストをブッキングしたわけだが、互いの音楽性は違うもアンソロジーのようにつながり、一つの物語になっていたような、そんな夜だった。
映画フリークならすぐにデヴィッド・フィンチャーの名が頭によぎるだろう、その夜のイベントの名は『Fight Club』。ここに集まってくれたアーティストは、あの街の水色、Akane Streaking Crowd、音楽かいと、コロブチカだ。‟アンダー25”以外に‟関西のアーティスト”というしばりもあったが、図らずとも京都を拠点として活動する4組がこの場に集った。
それぞれが『Fight Club』という言葉を咀嚼し、思い思いにステージ上から音楽として解き放つ。彼、彼女から放たれた音楽という拳が私たちのカラダに反射し、ぶつかり合うことではじめて、確かな輪郭が姿を表したのだ。きっと目撃した人の数だけ、その輪郭は異なり、それぞれの物語が生まれていたのではないだろうか。私たちのイベントへの思惑というパンチに対して、4組から放たれたカウンターパンチを受けてそんなことを思った6月22日の土曜日の夜。京都〈livehouse nano〉にてANNTENA主催で行われた初のライブイベント『Fight Club vol.1』の模様をレポートしたい。
“Why we do Fight Club?”
京都を拠点としたメディアとしてフリーペーパーの発刊をスタート地点に、Webサイトを運営し、今年10年目を迎えるANNTENA。そんな私たちがなぜイベントをするのか。その理由については、当日、入場時に配られたリーフレットにて編集長の堤が‟開会宣言”として次のように綴っている。
Fight Club 開催宣言
「野暮だ、野暮だ」と思いながらも「競う」という魔力に抗えない自分もいる。
我々はゆとり世代に分類されるらしく、小さな頃から「自分らしくさえあればよい」という教育を受けてきた。だが、いくら自分の内を掘っても「らしさ」というものは顔を出さない。そもそも人は他者との摩擦がなければ、自身の輪郭をとらえることができないと知ったのは随分と後のことだ。
このイベントは、アーティストの優劣を競うものではない。もちろん、音楽には勝ち負けもない。わかりやすい二項に物事を貶める態度には明確にNoを突きつける。ただ、普段身を削り音楽をつくるアーティストが、本気で鎬を削れる場所があればよいとこのタイトルを付けた。
今日はシンプルに音楽そのものがあなたにどのように響いたのか、イベントが終わってから話したいのである。
あなたの目的のアーティストは今日は誰だっただろうか?
音楽の好き嫌いはあると思う。でもそれは、これまでの人生の中で、今日のバイオリズムの中で変わってもいいはずだ。シャツと靴は脱いで、そんな話をしよう。
ANTENNA 編集長 堤大樹
このステートメント以外に、各アーティストを推した4組のレビューを加えると用意されたリーフレットは5種類。それぞれ、入場者にランダムに配られるという、全部読みたい人にとってはちょっと意地悪に思える仕組みだったかもしれない。しかし、持ってないリーフレットを互いに見せ合ったり、交換したり、知らない人同士でもこの『Fight Club』に入会してこの場に集まってくれた人同士が会話という拳を交えることができるような仕組みとなっていた。かくいう私も、準備に必死でまさか、そんな粋な計らいがされているとはつゆ知らず、フロアで「どれ持ってるんですか」なんて声が飛び交う様子に心が踊った。


最新の魔法をかける、あの街の水色
freefall / あの街の水色【MV】
照明が落とされ、小さな光がステージを照らす。暗闇の中に流れる幻想的なギターのアルペジオが会場の空気を変えていく。1組目に登場したのはスリーピース・ロックバンドあの街の水色だ。
まずフロアに放たれたのは、リリースを控えた2nd EP『drop in the sea』から先行配信されたばかりのミディアムバラード‟freefall”。らう(Gt / Vo)の透明感のある歌声に、もこ(Dr / Cho)のコーラスが重なり美しいハーモニーがフロアを満たす。そんな彼女たちの歌を時にマイクオフで口ずさみながら、たがみ(Ba)は歌の世界にどっぷりはまり込み情緒的なベースラインを弾く。5弦ベースということもあり深いところから沸き立つように奏でられるベースは、歌やギターのメロディに合わせて表情豊かにタッチを変え、あの街の水色の音楽に深みを与えているようだった。
途中のMCでは、もこがまっすぐ前を見据えて「私たちは、戦闘タイプでいうと魔法系だと思います。言葉より音楽で戦っていこうと思います」と言っていたが、この日のセットリストは‟letters”、”Kamogawa fighters”、”眩暈”とリリース直前の新曲が中心で、慣れ親しんだ曲よりもバンドとして今、一番聴いてほしい曲を惜しげもなく披露していた。
彼女らの楽曲の面白さはポップなメロディーに滲む不協和音の美しさとロックサウンドとの絶妙なバランスだが、圧巻だったのは、ラストに演奏された”眩暈”だ。気持ちよく轟音と高音の波に飲み込まれていたと思ったのだが、後奏ではらうのギターリフにのってベースも向かい合いながらジャムセッション。徐々にテンポアップしていきながら、ギターのリフもベースラインも目まぐるしく変化していき、最後には強い光のようにノイジーな音像とともに観客を飲み込み、しっかりと放った音楽で私たちの心を掴んでいった。
翻弄されて、Akane Streaking Crowd
Akane Streaking Crowd - 新快速【MV】
開口一番、淡々と「昨日は夏至だった」という話しから、「夏よりも次の冬が待ち遠しい」と吐露する北里(B / Vo)。前口上じみたその言いっぷりに、ちょっと向井秀徳が頭をよぎる。同期のリズムにのって語るように言葉を放つ北里は‟夏の思い出、海見ようぜって / やっぱり夏はサイコー! / 転じて隙間から流れ込む / 冷たい季節 / やっぱり冬はすきになれねー”と歌う。前口上と真逆の歌詞からはじまる‟噴水”から1曲目をスタート。
天邪鬼とも言える真逆な感じは、この楽曲の中にもしっかりと顕在化されていて途中のサビでは、声音をガラリと変えてバラードを歌うように艶のある声音で魅せる。もちろん、彼が流暢に歌っていないときには、ベースが自分の番ともいうように指板を駆け巡るので、目が放せない。場面が展開するように変化する北里と同じく、ドラムセットを細かく使い分けこちらも変幻自在にリズムをつくり出してくのがドラムの立本だ。サポートだというCity Lizard(from 街蜥蜴塾)のギターも彼らの目まぐるしく変わる音楽の変化を加速させる。
1曲目からその音楽性の振れ幅に翻弄されたが、それで終わりではなかった。アップテンポでギターのリフが曲調の転換をどんどん後押ししていく‟さよならハングオーバー!”、ポップな曲調が印象的な‟それだけだった”、高速で繰り出されるヒリヒリとしたビートに乗って「時間が足りない」と繰り返される‟KARATE!”、キャッチーなのに捉えどころのない音楽たちがすり抜けていく。それに翻弄されるのがこのバンドの醍醐味なのだろう。ドラムがリズムを刻みはじめると、メガネをさっとグラサンにかけ替えた北里がラストの1曲に選んだのは‟PLS”。鍵盤のフックのあるメロディと、自身が自在に奏でるベースラインで観客をしっかりと揺さぶりAkane Streaking Crowdという存在をしっかりと示していた。
圧倒的な音楽の没入感、音楽かいと
音楽かいと/「キラメクメロディー」Music Video
今回、ブッキングされた4組の中で「唯一バンドではない」という意味で異質な存在だったのが音楽かいとだ。私も音源で彼のことを知っていたが、パフォーマンスを観るのは今回が初めてだ。
セッティングはラップトップに鍵盤というシンプルなもの。彼が機材のつまみを回すと、「これから音楽かいとのライブをはじめます」といろんな声音で鳴り響き、ポップで軽快なビートとともに彼の音楽の世界へとチャンネルが切り替わる。映像では彼の歌詞の世界を画とリンクさせることで耳で、目で魅せてくれる彼の音楽だが、ライブでは体を心地よく揺らしながら、歌の世界を身振り、手振りでリンクさせる。その姿を見ていると、耳へと飛び込んだ歌詞がカラダに浸透していくよう。彼の代表曲の一つ‟キラメクメロディー”では映像がないことで、ビートだけでなく、彼の言葉で軽やかに踏んでゆく韻の心地よさにも改めて気づかされた。
ダイレクトに彼の楽曲に没入させてくれるようなライブパフォーマンスには驚かされたが、それ以上に驚かされたのは彼のミュージシャンとしてのパッションだ。このイベントでどうしても新曲がやりたいという気持ちになり、なんと、当日の朝までかかって身を削って1曲仕上げてきたというのだ。曲目は“歌って”。「緊張する」と言いながらも、かなりアップテンポで早口なポップチューンを見事に歌い切り、次の楽曲‟Tears”へと楽曲をつなげ、彼のメロディアスで繊細な曲の世界へとまた舞い戻る。
持ち時間35分の中で、今回のイベントの趣旨までしっかり咀嚼し、彼の音楽の世界をしっかりと組み込ませてエンターテインメント化させる手腕は素晴らしく、まさにアーティストとしてだけでなくプロデューサー的な視点で映像を投影させることなく、立体的に音楽を見せてくれたように思う。
ライブを続けるのは理屈じゃない、コロブチカ
コロブチカ / ユーズド・ユース (Music Video)
「Fight Club、俺たちがラスボス、コロブチカですよろしく!」と北原圭悟(Gt / Vo)はマイクを掴むと高らかに叫ぶ。それぞれが、バンドをはじめたルーツであるアーティストTシャツ(北原はサカナクション、平田歩(Ba)はUNISON SQUARE GARDEN)を身に着け、臨戦態勢万全という面持ち。サポートメンバーはドラムはさなこ、そして彼らが所属するサークル〈ロックコミューン〉の先輩であるサブマリンのギタリストであるタカノという面々だ。ギターリフが鳴っただけでわかる、彼らがバンドで音を鳴らすのが好きだということを。彼らがストレートに拳に込めて振り鳴らされる音は、それくらい純度が高く、何度も振り下ろされるたびに帯びた熱は熱さを増し、渾身のギターロックでフロアの熱を上昇させていく。
‟夜のせい”、“ボーイフッド”、‟アドリビトゥム”と3曲続けたところで、汗だくの北原の口から飛び出したのは「弦が切れました。それでもライブは続きます」という言葉だ。これは後から聞いたのだが、実は1曲目から切れていたらしい。しかし、まったくそれを感じさせない熱演に驚かされた。もぐらさんの「誰か、ギター貸したって」の一言で、場はすぐ動き、Akane Streaking CrowdのサポートギタリストCity Lizardのギターが彼の手によってすっと差し出された。北原は握手をするかのように笑顔でギターを受け取り、早速チューニングをはじめ、何事もなかったように予定通りに次の曲に挑む。いろんな夜を乗りこなしてきたこの場所だからこその連携プレイに、フロアの熱は冷めることも、覚めることもなく、このライブの行く末をさらに熱を持って見守り、ギターが変わったことぐらいでは何ら変わらない彼らの熱量に、時に声を上げ、時に拳を掲げて応える。
「ライブを続ける」という言葉通りに、迸る汗も気にすることなく4曲を完走。その熱演を目撃した観客から飛び交うアンコールの声に、最後の最後の1曲に選んだのは、先ほど演奏したばかりの‟Teenage Riot”。音が鳴った瞬間の温度が、さっきよりもさらに上がっていることが体感でわかる。北原も汗だけじゃなく、メガネも飛ばして、すべての音楽をはじめたときの初期衝動ともいえる熱をその拳に込め、惜しげなくフロアに放ち続ける。最後にギターを高らかと掲げた様は、彼なりのラスボスとしての矜持を見せつけたようにも見え、音が鳴りやむやいなや、フロアには拍手の波が広がった。
“ナンバーガールが / 今も僕を突き動かして / 鳴り止まないのはなぜ”
‟Teenage Riot”の印象的な歌詞のように、音楽がこの胸に飛び込んでくる瞬間はいつも突然だ。今回、この4組がドアをノックした人もいれば、もしかしたら、自身の過去の初期衝動となったルーツミュージックを思い出した人もいるかもしれない。きっと、人が鳴らす音楽に共鳴した先に、物語が生まれるのだから。そして、このイベントの場が、その思いのたけを話せるような踊り場であれば、そんなふうに思った1回目の私の『Fight Club』。あなたには、どう響きましたか?
イベントの果てに
さて最後に、ぶつかり合った拳の先に一体何が見えたのか。関西の音楽シーンのこれからが見えるのでは。そんな目論見もあった。そんなこのイベントで、彼らがステージ上で発した言葉の中で一番心に残っているのは、アンコールを前に北原が話していたことだ。
「僕たち、京都のシーンのこととか考えてなくて。僕、ただ普通にやっているのというが一番に頭にある」
点で見てみるとそうかもしれない。しかし、例えば今回の会場となった今年20周年を迎えた〈nano〉のような箱があれば、比較的新しい西院〈SUBMARINE〉、老舗の〈拾得〉や〈磔磔〉などの数々のライブハウスが営業を続けていること。そして、コロブチカのサポートをサブマリンが行うような光景が見ることが出来たように、コロナ禍の停滞期を乗り越えて京都の大学生のサークルが途切れることなく続いていること。さらには、今日ここに集まってくれた4組を筆頭に、いろいろな面白い音楽が生まれ続けていること。音楽シーンが生まれる場がしっかりと機能しているからこそ、シーンという輪郭が見えてくるのではないだろうか。そう、これからも拳を交えることが必要なのだ。次回、『Fight Club』にもご期待あれ。
編集部メンバーによる推しアーティストレビュー
あの街の水色

透明感のある歌声が、バンドサウンドに飲み込まれ揺蕩いながら染まってゆく。それは透明な水に色がついていくよう。羊文学を思わせるような退廃的な音像も魅力的なバンド、それがあの街は水色だ。
メンバーは、らう(Gt / Vo)、たがみ(Ba)、もこ(Dr / Cho)の3人。2022 年にとある京都の大学で結成されたという。らう・もこのコーラスワークは心地よく響き合い、その合間を縫うようにたがみがベースラインを紡ぐ。ポップでありながら、どこか哀しげでそのバランス感覚に惹きつけられた。あの街の水色というとスピッツの“水色の街” を思い出す。なんだか、あの楽曲にも通じるような捉えどころのない儚さも内包しているような気がするのだ。
2023 年7 月に1st EP『bloom in the pity』をリリース。京都を中心にライブ活動をしながら、来月2024 年7 月12 日には2nd EP『drop in the sea』のリリースが決定している。今、伸び盛りのバンドだ。海、川、湖と水面はその時々によって、私たちに違う水色を見せる。昨年から気になっていたバンドが、このイベントでどんな水色を見せてくれるか、とても楽しみだ。
書き手:乾和代
Akane Streaking Crowd

2020 年、北里(B / Vo)と立本(Dr)の京大生二人組によって結成。確信をもって人に薦められるものの、実際に紹介の言葉を語り出そうとするとなんだか困惑してしまうバンドだ。たしかにAkane っぽさと呼びうるスタイルは存在しているが、それは不定形で、どのような言葉で語ればよいのかが難しい。
この不定形さは北里の作詞にも表れる。基本的には私小説的に見えるが、そうかと思えば毒のように突飛な描写が滑り込んでくる。たとえ”Entertainment” における「つまるとこ/つまんないものが/つまってしまって困る!」といったような言葉遊び。最新リリースの『ASK(C?)3』収録の「KARATE!」の意表をつくふざけっぷり(「空手を習って/空手を習って僕ら強くなろう」)。彼らの音楽性と同じく、歌詞もまたひとつの意味やコンセプトによって理解されることを拒んでいるのだ。しかしその拒絶はしばしば吹き出すような、余裕あるユーモアとして現れる。
夏への憧憬や慣れ親しんだ街からの別離といった、どこか終末を匂わせるような二枚のEP『ASK(C?)2』・『ASK(C?)3』を立て続けに発表したAkane は、すでに円熟期といった。風格だ(とりわけこの二枚では録音技術の向上に伴って、リズム隊の動きがはっきりと聴き取れるようになった)。聞いたところによれば、来年度からのAkane は進路選択の関係で関西・関東に分かれてしまうらしい。リスナーの一人としては、活動頻度が下がってしまうのだろうかという心配がないわけではない。しかし同時に、北里という男が諸々の生活の変化をどう楽曲に落とし込んでいくのか、それを楽しみにしまう自分もたしかにいるのだ。彼らの人生と同期しつつ変化していくAkane は、今後も不定形な輝きを放ちつづけるだろう。
書き手:森脇透青
音楽かいと

自分が学生の頃を思えば隔世の感がある。音楽かいとのことだ。今回のイベントに向けて、編集部のメンバーと西日本のバンドやSSW など、多くの音源を聴いた。その中で音楽かいとの楽曲の完成度の高さには舌を巻いた。しかも、群を抜いて若い。聞けば、現役の大学生だという。さらに高校生の頃には、ビクターエンターテイメントの《CONNECTUNE》から1st アルバム『僕は音楽に照らされて』(2020 年)をリリースしているというのだから、怠惰に怠惰を重ねていた大学生の自分に爪の垢を煎じて飲ませてやりたいくらいである。
サウンドのことに話を移せば、彼は自分の音楽をダンスポップと標榜し、最新のシングル『ソラナミダ』(2024 年)や、ERA との楽曲『Planet』(2021 年)では小気味よいビートを軸としたチルなビートメイカー的なアプローチが際立つ。しかし、1st EP『君は音楽で泣いた』(2021 年)のラストナンバー “春の前に” などではしっとりとピアノと歌だけのシンプルな編曲もまた光らせている。
こうした二面性は彼のプロフィールにあるSSW という言葉に矜持として表れている気がしてならない。星野源を代表に、一人のアーティストが抱える多面性を表現することがポジティブに需要されてきたのがこの10 年ほどの受け手の変化の一つだった。音楽かいとは、自分たちの世代が想像する引き出しとは違った側面を持ち合わせた存在として映る。少なからず自分が持っているSSW という言葉は、彼によってアップデートされるという予感めいたものを抱いている。
作詞作曲からトラックメイキング、ミックスまでのすべてを自分で手がけているのも彼の大きな特徴だ。自身の音楽の主戦場をSNS やネット上に後押ししてきたのも、音楽を一人で完結させられる能力によるところが大きいだろう(パンデミックの影響もあっただろうことは書くまでもない)。アーティストだけでなくプロデューサーにまでまたがる両手いっぱいのこの才を、ライブハウスという場でどのようにぶちまけるか楽しみである。
書き手:堤大樹
コロブチカ

くるり、おとぼけビ~バ~などを輩出した立命館大学の名門軽音サークル『ロックコミューン』に在籍中で、結成してまだ1年足らず。音源も今夏にEP『ワンダーアラウンド』をリリースする予定だが、現時点ではシングル『ユーズド・ユース』1枚のみ。
今回出演するアーティストの中では最もキャリアの浅いバンドだが、ライブで見せてくれるほとばしる熱量、バラエティーに富んだ楽曲の魅力は全くひけをとらない。さらに思わず口ずさみたくなるような良質なメロディー、等身大で背伸びをせずに自分の人生を歌にできる胆力、その生き様をエモーショナルに表現する歌声。そのすべてが「本当に1年目なのか?」と驚くくらいに素晴らしい。
近年京都では、サブマリン、THE HAMIDA SHE’S、オートコード、そして本日の出演者であるAkane Streaking Crowd など若いバンドが次々と生まれ、シーンがより一層面白くなってきている。もちろんコロブチカもその筆頭だ。今はまだ関西の中だけの話なのかもしれないが、いずれ全国で「今の京都のバンドはヤバい」と言われる時代が近い将来待っているはずだ。
夢物語で終わるのかもしれないが、そんな未来をこのバンドに託してみてもいいのではないだろうか。
書き手:マーガレット安井
You May Also Like
WRITER

- 編集者 / ライター
-
奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。
OTHER POSTS