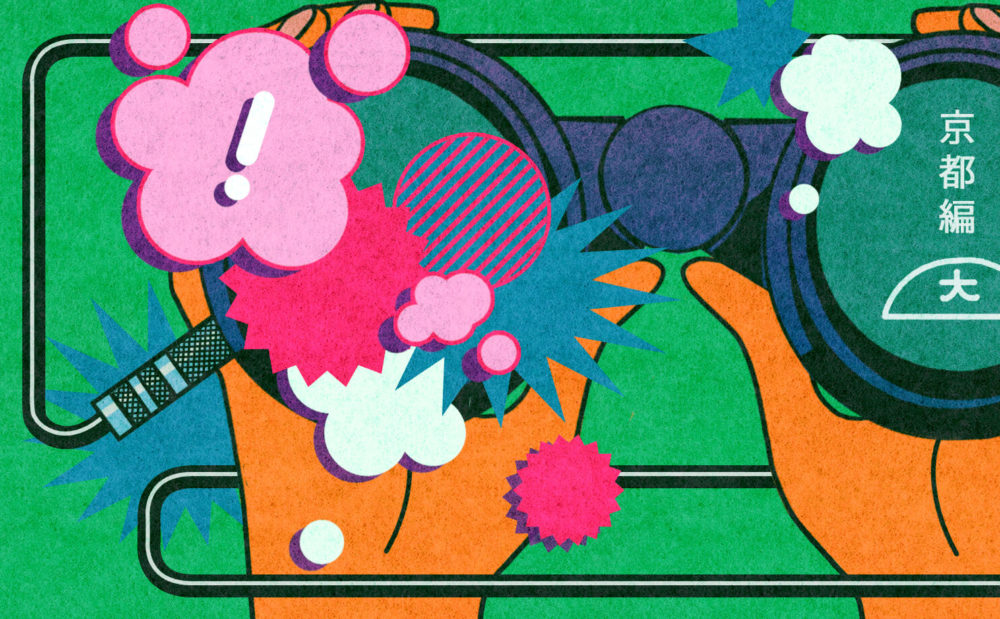ボロフェスタ2022 Day1(11/3)-帰ってきた、ライブハウスと地続きの“日常”
今年21年目の開催を迎えた、京都のフェスティバル『ボロフェスタ』。今年は11月3日~11月6日の4日間に渡って〈KBSホール〉で、また4日の夜には〈CLUB METRO〉で開催されました。2014年から毎年ライブレポートを掲載してきたANTENNAでは今年も編集部あげての総力取材!各日1名のライターによる独自の目線でボロフェスタを綴っていく、全4記事のクロスレポートをお届けします。本記事では初日の11月3日の模様をハイライト。
帰ってきたと言わんばかりに、オープニングで〈KBSホール〉内の空を見事に舞ったのはウルトラマン。ボランティアスタッフによるDIYの良さが滲み出る手づくりのモニュメントが、ワイヤーに吊り下げられてステージに向かって飛んでくるという演出でこの日の幕が開ける。その年を象徴するテーマを音楽以外でも提示するのはこのフェスの特徴の一つ。コロナの影響で、昨年はクローズしていたホール内の地下に設置された〈街の底 STAGE〉とロビーの〈どすこい STAGE〉も復活を遂げた。ここからはじまる4日間への意気込みを感じる演出に沸いた1日目。この日、印象的だった言葉が「街のライブハウスとの地続き感があるイベント」だ。ライブ中にナードマグネットの須田亮太がそう話していたが、今、振り返るとまさにこの日を象徴していたように思う。21年目に突入した『ボロフェスタ』1日目は、ライブハウスで積み重なった日常がこの特別な一日を生み出しているのだと改めて思える、そんなシーンが繰り広げられていた。
日和ってなんかいられない、真剣な遊び場
この日は、はじまりから何かが起こりそうな空気があった。トップバッターとして登場したのは夏の『ナノボロ2022』にも登場したthe McFaddin。前回も、いかにこの瞬間をフロア全体で楽しむかに終始していたように感じたが、この日もその姿勢は変わらない。Ryosei Yamada(Vo)の「遊ぼうぜ、よろしく」から始まった1曲目の“idly(L.H)”ではバックのVJとも連動し解像度をあげていくように徐々にフロアの温度をあげていき、3曲目の“DRAW IN A HEAD”ですっかりと観客を彼らの音の波へと引き込んだ。
完璧ともいえるステージで観客を魅了する彼らにアクシデントが起こったのが4曲目。Taito Katahira(Gt / Composer)に起こった機材トラブルだ。限られた時間、自分たちのパフォーマンスをやり遂げたい。そんな想いが交錯しているように見えたステージ上で、Ryoseiは先を見据え、彼らが出演する4日のボロフェスタ夜の部で演奏しようと思っている新曲の話をし「このトラブルを乗り切った俺たちの顔を見て」と言い放つ。その言葉通りに、最後にはトラブルを乗り切り、Taitoも気持ちよさそうに音に身を委ねながらギターを奏でる。オープニングで東京リベンジャーズのキャラに扮したこのフェスの主催者である土龍が名台詞を引用し「日和ってるやついる?いねえよな」と言っていたが、いるわけがない。ライブハウスで育ってきた彼らにとってどんなステージも真剣な遊び場なのだ、そんなことを思わせる一幕であった。
バンドを続けているからこそ、見える景色
土龍が店主を務める〈livehouse nano〉を筆頭に、京都界隈のライブハウスに学生の頃から出演経験があるバンドもたくさん集まるボロフェスタ。社会人になってもバンドを続けている人を京都のライブハウスでよく見かけるのも、この街が培ったライブハウスをはじめとする音楽を鳴らし続ける場所があるからだろう。「久しぶりにボロフェスタに呼んでもらった」と須田亮太(Gt / Vo)がMCで話していたナードマグネットもそんなバンドの一つだろう。いつもは小さいライブハウスに出演することが多いなんて発言もあったが、1曲目の“アップサイドダウン”から彼らの鳴らす音に、観客が高らかに拳を突き上げて応える様子は、〈KBSホール〉をいつものライブハウスで見る光景へと変える。2021年に新規加入したベースのさえこは、今回が初のボロフェスタ。彼女はステージから見える景色に「すごーい」と言葉を発していたが、気負いなど感じさせない。“C.S.L.”では、イントロからゴリッと力強い低音が光るベースを聴かせてくれた。
2019年はアルバムをリリースし主催フェスを開催するなど精力的に活動を続けていたが、コロナの影響や2020年10月に前ベーシストの前川知子が脱退などもあり、「もうバンドを続けていくのはいよいよ無理やな」と思ったと、当サイトのインタビューで須田が話ていたが、そこには確かにバンドを続けるという日常を選んだからこそ見える景色があるように見えた。
このフェスの主催者の一人、飯田仁一郎もOTOTOY、SCRAPの取締役などいろいろな顔を持ちながら、Limited Express (has gone?)のリーダーとしてバンド活動を続けている。メンバーそれぞれが音に没頭し、この場でしか味わえない音楽体験を全身全霊で体現するのがこのバンドのスタイル。特にYUKARI(Vo)はステージという箱に納まりきれないバンドの熱量を体に宿し、〈KBSホール〉のすべてがステージだと言わんばかりに力強い歌声を放ちながら縦横無尽に動き続ける。『ボロフェスタ』の10回目から土龍に止められているというステージ上のやぐらにも登らずにはいられない。その熱量はフロアにも伝播し、ステージ上ではYUKARI以上に、JJこと飯田仁一郎(Gt)、谷ぐち順(Ba)、YASUNORI MONDEN(Dr)、KOMADORI(Sax)が渾身の音をぶっ放す。そんな彼らの音に呼応し激しくヘッドバンキングする観客は、マスクを付けているがこれまでのように全身で音の波に身をゆだねていた。ルール無用なわけではない、そこにはせめぎ合いがある。
YUKARIが恒例となった脚立に登り、力強く歌う。コロナにコンプライアンス、なにかと縛られがちな日常からどのように解き放たれるか問いかけているように思えた。これも、バンドがそしてボロフェスタが、そして何よりフェスを楽しめる平和な日常が続いているから見ることができる、貴重な景色なのだ。
可視化されるブッキングライブの楽しみ
京都のライブハウスに通うようになって知った楽しみは、ブッキングライブだろう。メジャーのアーティストライブでも対バン形式はあるが、1回のライブに複数のアーティストが出演する小規模なライブハウスは、毎日がフェスのように、思いもよらない音楽に出会える機会で溢れている。そしてこの『ボロフェスタ』という形態が、さらにその枠組みを広げているように思う。
京都のライブハウスでも、東京のアーティストとのブッキングも多い。今回登場したKOTORIは以前〈livehouse nano〉に出演経験があり、ミツメも〈京都MOJO〉の周年企画に招聘されるなどこの地とつながりがあるバンドだ。ぐっと明かりを落としたステージに登場したのはミツメ。1曲目は“睡魔”。彼らの音像に寄り添った柔らかな照明に彩られ、軽やかなドラムのビートと爪弾かれるギターの音色、川辺素(Vo / Gt)のあわいを感じる歌声が響く。最後のエフェクトがかかった「溶けそうな」というフレーズでフロアをいっきに微睡みの渦へ。最後に演奏された代表曲“エスパー”まで彼らの描く音の世界に観客は魅了されていた。
まばゆい黄色の照明に照らされて登場したのがKOTORI。1曲目は“YELLOW”。4人の息の合った音が会場を埋め尽くし、横山優也(Vo /Gt)が高らかに歌い上げる。“トーキョーナイトダイブ”では、以前東京で彼ら主催のライブで見たような観客の盛り上がりで、彼らを初めて観た人も多いだろうがアウェイを感じさせない。最後に演奏された“GOLD”では、存分に彼らの音で観客の心を高めた後にギターのアルペジオだけが響き、ゆるりスピードを緩めたかと思ったが、4人の音が一気に重なり音の波が充満していく、まるで天高く羽ばたくような光景であった。
京都の枠に納まりきらない、音楽の振り幅の面白さ
いろいろな文化が交じり合う街、京都。それは音楽の世界も同じ。京都という土壌が生み出したバンドの振り幅の広さを1日で体感できるのも『ボロフェスタ』らしさ。ワールドワイドに活躍し京都アンダーグラウンドの一角を担うのがおとぼけビ~バ~だ。あっこりんりん(Vo)がキレのあるマイクパフォーマンスを披露しながら“ヤキトリ”、“ハートに火をつけたならばちゃんと消して帰って”、“シルブプレ”と息つく間もなく演奏し、観客の心に火をつける。あっこりんりんが「知らない曲で踊るっていうのが京都の文化」と話していたが、自然と彼女たちの空気に飲まれ、思い思いに音を楽しんでいた。アメリカツアーから戻ってきたばかりという彼女たち、これぞショータイムと言わんばかりの完璧なステージを観客の目に焼き付け、ステージを颯爽と後にした。
ANTENNA編集部の中でも、今年彼らが出演したイベントでひと際盛り上がっていたと話題に上がっていたのが京都のバンド浪漫革命だ。リハーサルでまるっと“KYOTO”を披露。1曲目の“ラブストーリー”から観客は気持ちよく体を揺らし、時にリズムに合わせて拳をあげる。全員がアイドルのようにマイクを片手に歌う“月9”で観客を沸かせたあとに、藤澤信次郎(Vo / Gt)が「よかったら歌ってください」とフロアに向かって声をかけはじめたのは“あんなつぁ”。その呼びかけに応え「あんなつぁ」のフレーズではフロアの人たちの手がメロディに合わせて揺れた。最後には特別ゲストとしてYouTuberの岡田康太が登場し、“優しいウソで feat. 岡田康太”を京都で初披露。サプライズをプラスして、観客をさらに盛り上げ、この日のトリを飾るハンブレッダーズにバトンを渡した。
音楽との偶然の出会いを演出するレイヤー
『ボロフェスタ』で、知らない音楽との偶発的な出会いの発火装置となっているのが、地下にある〈街の底 STAGE〉と〈どすこい STAGE〉だ。〈街の底 STAGE〉はトイレ、〈どすこい STAGE〉はメインホールの入口という導線上に設けられているので、何気ない移動の瞬間に知らない音楽が耳に飛び込んでくることがある。この日、私が注目したのは京都を拠点に活動しているトラックメイカー・DJのE.O.Uと東京を拠点に活動するシンガー・ソングライター宗藤竜太だ。
まずは、〈街の底 STAGE〉に登場したE.O.U。集まった人たちの数は、入場規制一歩手前という感じ。E.O.Uの手から生み出される、ゆったりとした音の波が次第に広がり、人を揺らす。音の波の上にリズムを落としてグルーヴが生み出されていく感覚はまるでオイルペインティングのよう。それは、耳だけでなく体全体で感じるからこそ生まれる感覚のように思えた。次は〈どすこい STAGE〉に一人、ギターを抱えて登場した宗藤竜太。鴨川で練習をしてきたという彼が生み出す音楽は、音源で聴いていた以上に繊細だが、人肌のような温かみを感じるもの。焚火が揺らめくように抑揚をつけて歌った、ドラマ『モアザンワーズ』主題歌の“ライムライト”は、聴き知った曲がなんだか知らない曲のようにも思えた。この二つの場所は、音楽配信サービスでは得られない、音楽との出会いをつなげてくれる場所なのだと改めて感じた。
ライブハウスとバンドをつなぐ、二つのステンドグラス
周年やメンバーの誕生日などなど、何かの門出にショットグラスで乾杯する姿というのはライブハウスでよく見る光景の一つ。ちょっと特別なときに、そっと背中を押してくれるようなサプライズ的なシーンを私も目撃したことがある。そんなサプライズに遭遇したのが、今年の12月をもってライブ活動休止を宣言したD.A.N.のステージだ。大悟(Gt / Vo / Syn)、市川仁也(Ba)、川上輝(Dr)の3人に、サポートの小林うてな(Steelpan / Syn)が登場。川上がスティックでカウントを入れて、始めたのは“Sundance”。鍵盤、ベース、ハープと音が重なり合い、刻まれるリズムに合わせて表情が変わる。さらに、たゆたうように歌う櫻木の声も合わさり、彼らの音楽で〈KBSホール〉を染め上げていく。“No Moon”の赤が印象的だったが、楽曲ごとに変わる音の世界を光でも再現する照明も相まって、フロアの熱気も上がっていく。でもなんといっても、ハイライトは最後の“Anthem”だ。彼らの後に演者が2組が控える中、トリで開くのが定石と思われた幕がスッと開き、ステンドグラスの煌めきにD.A.N.のメンバーが染められていく。その光景を目の当たりにした観客も、冷静に演奏をしていたように見えた彼らも、その粋な計らいに会場の熱気はさらに上がる。セオリーなんかない、この瞬間に見合った最高の演出を、そんな心意気を感じずにはいられなかった。
波乱万丈の1日目のトリを務めたのは、これまで何度も『ボロフェスタ』に出演しているハンブレッダーズ。この10月にサポートをしていたukicaster(Gt)が正式加入し、新しい体制になってから京都では初のライブという彼ら。ステージに登場すると木島(Dr)を中心にムツムロ アキラ(Vo / G)、でらし(B / Cho)、ukicasterが目を合わせたのを合図に“フェイバリットソング”を演奏。ukicasterとでらしは照明のついていない隣の〈GREEN SIDE STAGE〉まで駆けていく。大きなホールでも広さを感じさせない、彼ららしい振舞いは、この場所でライブができるのがうれしいという気持ちの現れだったように思う。
MCでムツムロの口からこぼれるのも、ボロフェスタへの思いや土龍との思い出話。そして、コロナで自分たちの居場所でもあったライブハウスが営業停止になっていることに、何かしたいと思って曲をつくったという話をし「そのCDのジャケット写真にもなっている、nanoに愛を込めて」と言うとギターをかき鳴らし、件の曲”ライブハウスで会おうぜ”を歌う。彼らの気持ちに応えるように、キラキラのステンドグラスがまた顔を出す。そう、ライブハウスで会おうぜ。エンドロールではない、今日開いた二つのステンドグラスは、また音楽が鳴り響くライブハウスで会おうという気持ちが込められていたのではなかろうか。そして、こんな光景に出会ってしまうから、ライブハウスへと地続きの日常という名の『ボロフェスタ』に足を踏み入れてしまうのだ。
You May Also Like
WRITER

- 編集者 / ライター
-
奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。好きなものは、くじらとベース。
OTHER POSTS