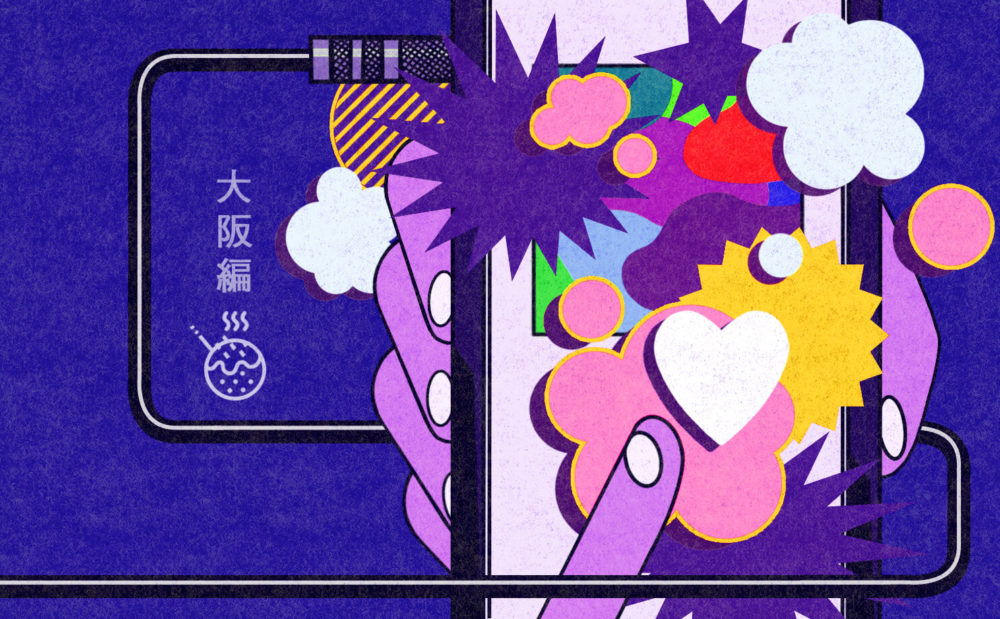映画が「作る人」をもう一踏ん張りさせてくれる -〈日田リベルテ〉原さんが映画館をやる理由
映画館というにはあまりにも多様で、ギャラリー併設のシアターと言うだけでは何かがこぼれ落ちてしまいそうな場所。それが、大分県日田(ひた)市にあるミニシアター〈日田リベルテ(以下、リベルテ)〉だ。映画の上映やトークイベントの他、haruka nakamuraさんや青葉市子さんなどの人気ミュージシャンがプライベートで訪れたり、ライブをしたり、カフェスペースの壁にはミロコマチコさんや牧野伊三夫さんの絵が描かれていたり、数々の雑貨やレコードも並ぶ。そこに集まっているのは、日々の心の奥にある祈りを表現したものが作品となり、いろんな人の心をゆらめかせているような人たちの生きている軌跡。素敵な人たちが日々支流から流れ着くように集まってはまた大海原へと旅立つ宿場町のような〈リベルテ〉は、どんな人がどんな気持ちで作っている場所なのか、興味を惹かれた。
〈リベルテ〉は、神社のように「自分に向き合う」場所
この場所を作っているのはオーナーの原茂樹さん。日田出身で、2009年から個人事業としてこの場所を運営している。会社員をしながら時々手伝いをする距離感だった時に、前オーナーからの直々の頼みがあり、自由にさせてくれることを条件として引き受けた。そんな〈リベルテ〉について、原さんは神社のような場所だと話してくれた。
「神社には、鏡があるんですよ。鏡って、“かみ”と響きが一緒。その昔は、鏡を“神”だと言っているわけです。手を合わせて祈ることは、鏡に映る自分自身と向き合うことでもある。そうやって自分の中に神様をつくることができたら、謙虚でいられますよね。昔は教会や寺に行けば、宗教画があって、音楽もあった。つまり庶民でも文化に気軽に触れられるアートスペースだったわけです。しかも苦しいときに行く場所。〈リベルテ〉は、そういう場所に近い。立ち止まって、自分の現状に向き合う場所です。映画を見たら、何か感情が出てくるでしょ。そこを見るわけです」
前職では御守りのデザインもしていたことがある原さんの言葉だからか、納得させられる。これまでをさかのぼると、日田で過ごした学生時代は、野球に没頭しひとつ下の世代が甲子園にも出場するなど活躍。さらには福岡でバンド活動に勤しみながらTSUTAYAで映画と音楽を浴びるように体験し、大手カメラ屋さんでカメラのことを学び、御守りのデザインの職に就く。そこで〈リベルテ〉を継ぐことになるのだ。スポーツにも音楽にも触れたが、たどり着いたのは映画だった。
「映画と音楽が僕の基準です。この二つは、大体値段が一緒なんです。CDを買うのも、映画を観るのも数千円。貧乏でも、お金持ちでも、手に届く値段ですよね。それに、いい音楽でもそうでもない音楽でも、人生を変えるような映画でもそうでもない映画でも、値段が一緒という世界が、誰でもフラットに楽しめるという点で好きなのかもしれないです」
そんな原さんはこの日、ハル・ハートリー監督の映画『トラスト(邦題:トラスト・ミー)』(1990年)の自作Tシャツを着ていた。

「レオス・カラックス(監督)もすごく好きで、『汚れた血』(1986年)のTシャツも自分で作りました。カッコ悪い男の恋の話に共感して、青春時代からずっと1位かなぁ。なかなか想いは届かないんだけど、死んだ後に届いたりするんですよ。当時のカラックスの恋人ジュリエット・ビノシュが主演で、恋人だからすごく美しく撮るわけ。この映画の成功をきっかけに彼女がハリウッドに行き、大成するが、別れが訪れる。そんなエピソードも含めて、映画っぽくていいんですよね」
好きな映画をTシャツにしてしまう愛情が、チャーミングだ。取材中にふと耳に入ってくる音楽は、音楽家の宮内優里さんと現在制作中の音楽作品『日田』の第2弾のデモテープだし、いただいたアイスコーヒーは〈リベルテ〉の開店当初からワークショップも行っていた豆香洞コーヒーとともに作った映画館ブレンドだという。この場所に足を踏み入れてから、ずっと五感で原さんの愛情が紡いできたものを受け取っている。その温かさに包まれて、気づいたら好きな作家や映画など、自分のことも話していた。原さんと話していると、自分のことが分かる気がするのが不思議で、それはまるで映画を観て自分の心の動きを観察しているときのよう。
「なんか、話していると“原さんが映画みたいですね”とよく言われます。それは多分、相手が何を思っているかということに、興味があるからでしょう。そこを隠そうとする人も、そういう人だから、それはそれでその人だし面白いんですけど、やっぱり、わっと出した方がいいな、と思っていて。ここは大分県。源泉掛け流しのお風呂に浸かりたいでしょ。どうしても好きなものって、あったりするじゃない。だからそれを掛け流して生きていけたら、幸せなのかもしれないよね。それは生まれ持ったもの。星の流れみたいなものだから、ある意味仕方ないんです」
この日、原さんが度々口にした「仕方ない」という言葉は、これまで聞いてきた、後ろ向きな意味を孕む言葉とは違って聞こえた。まるで、運命を受け入れる、前向きな諦めのように原さんはその言葉を使う。自分が何かに惹かれる気持ちを「仕方ない」ものと思うと、確かに思っていることを外に出せるようになるのかもしれない。

好きな人と、好きなことについて話すだけでいい
「好きなことをやっている時って、夢中になって雑念とか雑音が入りにくいんですよ。この状態が一番良くて、僕はこの状態で生まれたものを見たい。たとえば〈リベルテ〉で展示をやった靴職人:uzüra(ウズラ)の宏美さんは、靴を作る過程でどうしても“かたまり”を作らないと仕方がなくなると言うんですね。たとえ利益にならなくても、それを出さないと押しつぶされてしまいそうだし、社会がそういう部分を受け入れていくことが、より良い未来に繋がってゆくのだろうなと、思っています」
原さんの着ていたオリジナルTシャツもそうだし、好きが高じると、何かを作ってしまうことには心当たりがある。好きこそものの上手なれ。
「ちょうど『放浪の画家、ピロスマニ』(1969年)というグルジア(ジョージア)を代表する画家ニコ・ピロスマニの半生を描いた伝記映画があって。それを観るとわかるんですが、彼の人生自体が素敵なんですよね。だから“ピロスマニ”というワインの名前にもなっているし、加藤登紀子さんの“百万本のバラ”もピロスマニの恋の歌を歌っていて、生きている時には貧乏でも、今ではワインにも歌にもなって受け継がれている。文化の時を超える素晴らしさを感じます。」
生前には有名だったとは言えないながらも、自分の信じる絵を描き続け、後世に多大な影響を残したピロスマニ。原さんは、彼のどんなところに一番惹かれているんだろうか。
「紅茶を囲んで、芸術について話すだけでいいとピロスマニが言ってるんです。その感覚が、すごく分かる。彼もお店を開くんだけど、金持ちが来たら追い払うのに、貧しい人たちが来たら受け入れるんです(笑)。だからお店は続かないけれど、なんか分かる。彼が、僕の中にもいる感じかな。かといって僕は区別しないけれど、みんなに公平な機会があればと思うきっかけになっているんです。好きな映画を観て、映画を好きな人に会って話す。それを日々本気で、純粋な気持ちでやっています。それなら誰にでもできるでしょ」
何かを作らざるを得ない、「仕方ない」人たちの表現を愛する原さんの下にたくさんの人が集まってくる。ピロスマニとも通じる原さんの根底にある芸術そのもの、そして芸術について語る時間への愛情は、誰かの表現を否定しないから、安心して集まれるのだ。だから〈リベルテ〉は、多くの「仕方ない人」に対して開かれた場所となっている。

自分が好きなものを、“伝える”ことが重要
原さんは、牧野伊三夫さんが中心となって日田の林業を盛り上げるために集まっている集団「ヤブクグリ」の宣伝担当でもある。他にも絵描きのミロコマチコさんや豆香洞コーヒー、独立して世界で活躍する青葉市子さんなど、原さんや〈リベルテ〉ですでに出会っていて、その後に活躍の幅を広げたアーティストは後を絶たない。
「純粋にいいと思ったものを信じて、伝える。それが大事なんです。信じるも、伝えるも、人偏に“いう”って書くんですよ。用意された尺度で考えてものを作るんじゃなく、いいものだと信じて、それを伝える。それだけ。例えば高校生に“日田といえば”と聞くと、豆田町!と一般的に観光地とされている場所を挙げたりするんですけど、それよりも、自分の好きな川に連れて行けばいいじゃないですか。それで自分の好きな場所が盛り上がっていけば、たくさんのスポットが生まれる。今までの概念を飛び出て、それらを受け入れる場所を新しく作ることで、落ちていた人が落ちなくなると思うんです」

落ちていた人とは、これまで多くの人に評価はされなかった人だ。それでも、“好き”な場所やアーティストや作品を、自分で盛り上げることが重要だと原さんは語る。
「人類の歴史を考えると、“伝える”ことが一番大事なんですよ。僕らより大きくて強い動物がなぜ滅びて、僕らが生き残ったのか、『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著)に書いてあります。集団で敵の情報を伝え合っていたからなんです。ノアの方舟の話でも、第四の世界に行けたのは“伝えようとした人”だけです。絵本で言うと、『フレデリック』(レオ・レオニ著)。フレデリックは、周りから働いてないと思われている。でも実際は、“伝える”っていう大事な働きをするわけです。〈リベルテ〉でやっていることは、そういうことの体言化ですね。できているかは分からないけれど」と笑って話す。
絵本を読みながら、自身がやっていることをフレデリックのようだと話してくれた原さんは、どこかフレデリックのようにも見えてくる。伝え方には、工夫が必要だ。
“ブリコラージュ”の考え方で、田舎にいても仕事を作る

例えば、原さんが仕掛け人となって、エルメスのドキュメンタリー映画『HUMAN ODYSSEY ―それは、創造を巡る旅。―/DIRECTOR’S CUT』(2021年)を全国の地域に根差した映画館で一斉上映した企画。これは、映画館は映画をプレゼントできないという制約の中で生まれたアイデアだ。エルメスに劇場の上映権を宣伝費から買ってもらい、関係者やこれからお世話になりたい人も含めたお客さんを呼んで、映画をプレゼントするという画期的な内容だった。原さんはアイデアを生み出すことで、都市部から離れた日田に居ながらも仕事を作っている。
「どうしても田舎というと、農業とか古民家とかのイメージがあるかもしれないけど、そうでもなくて。田舎の方が、アイデア次第でぽんっと全世界とつながれたりもするんですよ。『サーミの血』(2016年)という映画があって。サーミ族が劣っていると思われている西洋的な考え方がある一方で、呪術やお祭りといった、彼らなりの知的体系もあるわけですよ。それこそ都会と田舎も同じで、どちらも、それぞれ良いところがあるはずなんです」
取材後「僕の考えはレヴィ・ストロースの“ブリコラージュ”っていうのに近いと思ったよ」と連絡をいただいたことも相まって、原さんがアイデアを重視することに合点がいった。“ブリコラージュ”とは文化人類学者のレヴィ・ストロースが自身の著書『野性の思考』の中で取り上げた概念で、今あるものを生かして新しい価値をつくる考え方。そして原さんの周りには、たしかにブリコラージュ的な考え方で、作品を生み出す人が集まって来ている気がする。
「最近では、ヤブクグリが日田杉で作った『おふろのフタ』もすでに大きな話題になっています。〈リベルテ〉をオープンした時期と同じ頃にオープンした豆香洞コーヒーは、今では焙煎の初代世界チャンピオンになりました。そこまでやる手前で諦めちゃう人が多いんですけど、そこでもっと何かできないのかと、背中を押すのが、映画やこの映画館の仕事なのかもしれないですね」
身の回りにあるものを生かして、アイデアをプラスすることで新しいものを生み出す。そんな根気がいることを次々と成功まで導いている〈リベルテ〉が、ギャラリーやカフェである以前に、映画館であることは、必然だ。
「ここに集まっているのは、みんな映画が好きな作家たち。自分の中だけで考えていると、スパイラルみたいに落ちていってしまう時があって。でも映画を観るとそこに他人の人生があって、ちょっと引っ張り上げてもらえるんです。そうすると、“いっちょやってみようか”と、もう一踏ん張りできるんです」
孤独は誰もが感じることだが、それを感じる機会が多いのが、何かを作ることに一人で向き合っている人。だから〈リベルテ〉には、映画を好きなアーティストや作家が集まるのだ。

無料で映画が見られる、公共の映画館を作りたい!
そうして〈リベルテ〉に集まったものたちには、関連があるようにも見えるし、時に唐突にも見える。原さんの空間作りは、誰の影響が大きいのだろうか。
「僕は『relax』編集長だった岡本仁さんの、どこに何があるか予想できないようなカッコいい編集と、牧野伊三夫さんの『雲のうえ』のような、普段メディアに出ないような人たちをカッコよく取り上げる編集が好きなんです。二人の編集を合わせた編集が、僕の、この映画館の基本だなと思っています」
そう聞いてからリベルテのカフェスペースを眺めると、レコードが置いてあったかと思いきや、器が置いてあったり、はたまた五島うどんが登場したりするのにも納得だ。それぞれに納得できる由縁がある。そして岡本仁さんと牧野伊三夫さんの影響については、度々話題に上がった。
「お金がなくても手に取れる、カッコいいもの。そういうのが一番好きかもしれないです。岡本仁さんも『relax』の人気コラム『ART FOR ALL』で無料のタブロイド版を出していたり、牧野さんが手掛ける『雲のうえ』もフリーペーパーを出しています。若い時はお金がなくて、欲しくても買えないからフリーならその世界をこんな僕でもしっかり感じられるのです。そういう意味では無料って、いいですよね。しかも今でも続けているその優しさに心打たれるのです」
そんな原さんにこれからやりたいことを伺うと、「公立の映画館作り」という話が出た。
「日田市立映画館を作りたいんです。日本では映画は商業的なものとされていて、文化として取り扱われてない。市立図書館や美術館は至る所にあるし、市立博物館もあるのに、市立映画館は全国的になぜかないんですね。もし市立映画館を作れば、歴代の文科省選定作品だけでも相当の数を上映できる。学校に行かない子が増えている状況で、映画を観たら出席にできるようにできればいいですね。映画を観ることで、いろんな世界があると気づく子もいると思います。そういうコミュニティスペースとしての映画館を作りたいです」
映画は他人の人生を見せてくれるから、映画を観る人が増えると、今よりちょっと多様な社会に近づくと原さんは思っている。
「映画を通して闇を見ることで、今まで世間の基準から落ちていた人の存在に気が付く人が、増えると思うんです。だから映画の世界に本気で入って、闇を疑似体験して欲しい。例えばユダヤの戦争の映画を見たら、本当に自分がユダヤ人で、ナチスに殺されるかもしれない、という感覚で見ることが大事なんですよ」
芸能人の不倫スキャンダルにSNSで自分本位な感想を述べるような言葉が蔓延している世の中を打破する一つの選択肢が、映画なのだ。
「映画には、例えば結婚という制度があっても別の人を本当に好きになってしまう世界が描かれているわけじゃないですか。そういう世界を知ることで、いろんな状況を想像できるようになります。だから当事者の気持ちを理解できないで弾劾している人の行動をみると、僕は“映画を観ていないんだろうなぁ”という結論に達するんです」
他人の人生を見せてくれる映画だが、ただ傍観者として観ることも出来てしまうだろう。鑑賞者は、どうすれば本気で映画の中に入っていくことができるのだろうか。その手がかりとなる映画として原さんが口にしたのは、映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』(2022年)にも登場する、白鳥建二さんだ。
「白鳥さんは全盲なので、一緒に絵を観る人に、目の前の絵のことを説明してもらうんです。そうすると、目が見えてた人が初めて見え始める世界がある。それが面白い。ということは、目が見えている人の方が、実は本当の意味で見てなかったんですよね。だから、“伝えよう”として鑑賞すると、ただインプットするだけとは違う世界が広がります。これが本当の鑑賞だと思うのです」
原さんがいろいろなことを実現できている理由は、「映画を真剣に観て、実生活で生かそうとしている」だけだという。これまで自分は真剣に映画を観れてきただろうか、自省してしまった。
4時間以上に渡る取材の中で印象的だったのは、原さんがどんな話をするのにも、映画のタイトルを上げて「〜でも言っている通り」とお話してくれたことだ。原さん自身が、映画から人生の指針を得ているからだろう。映画館の扉を開けると、誰かが本気で作ったものを観ることができ、それによって動く自分の心を、自分で感じることができる。スマホをすぐ手に取れる現代で、数時間、自分の心に向き合う時間を手にいれることはなかなか難しい。だから配信で映画を観ることができるようになっても、いつでも対話できるこんな映画館に通いたいと思うのではないだろうか。
山と川のすぐ近くに佇む〈リベルテ〉は、映画というフィルターを通して他人の人生を覗くことで、心を育てていく場所。そして育った苗の元に鳥や虫が集まり、雨が降り、新たな植物が咲く、生命の循環が垣間見える、まるでプランターのような場所だった。“日田の地形も盆地で子宮みたいでしょ、だからいろいろ生まれるんです”と、土地の話にまで及んだが、今回は時間切れに。また訪れて聞こうと思う。きっとこうやっていろんな人が定期的に訪れる場所なのだろう。「1日でも長く存続して欲しい」映画館を立ち去る頃には、そう願う自分がいた。

You May Also Like
WRITER

- ライター
-
1997年生まれ、みずがめ座。西荻窪|成城|祖師ヶ谷大蔵
OTHER POSTS
カルチャーWEBメディア NiEW(ニュー)、Musicman、ANTENNA等で執筆。