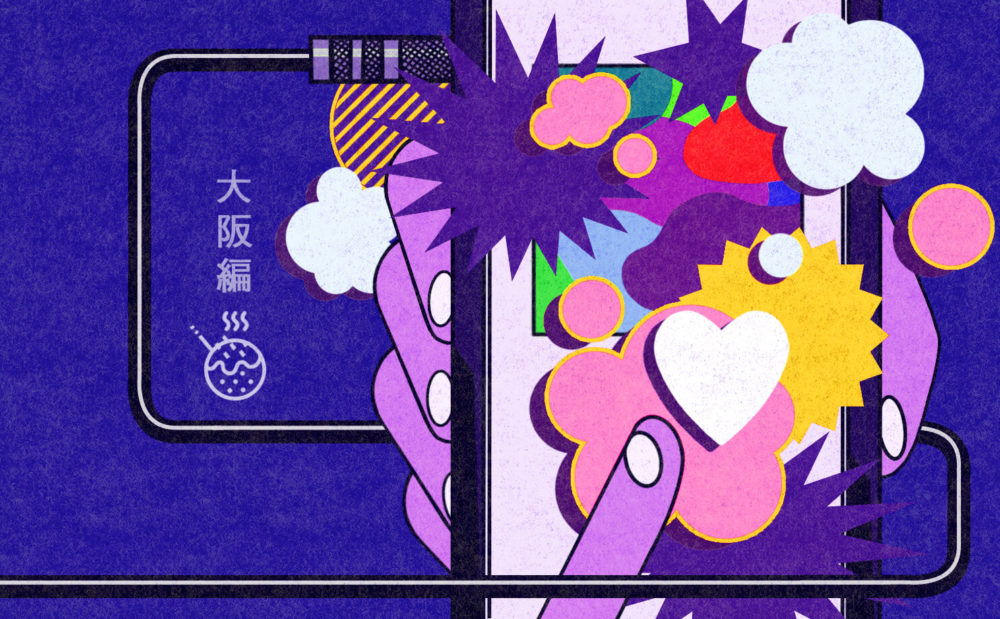ただ笑顔でいてほしい。黒沼英之が休止中の10年間で再認識した、作った曲を発表することの意味
「元気で、よかった」シンガーソングライター・黒沼英之が音楽活動を再開すると知って、初めに思ったことだ。彼のことを覚えているだろうか。2012年10月に発表されたアルバム『イン・ハー・ クローゼット』は、その切実な歌声と日常生活での感情の軌跡を独自の筆跡で描いた歌詞が、長く聴かれることを確信させる、普遍的な強度を持った作品だった。そして2013年に《SPEEDSTAR RECORDS》からメジャーデビューし、サウンド面をより押し広げた7曲入りEP『instant fantasy』、2014年にはアルバム『YELLOW OCHER』をリリースするなど、これからの活躍が期待された。しかし2014年9月に突如として音楽活動休止を発表。目まぐるしい活動ペースや華やかなセールスプロモーションにファンからも心配の声が上がっていたものの、その才能に夢中だっただけに残念な気持ちが拭えなかったことを記憶している。
それから10年間は音沙汰がなく、表舞台で名前を見かけたのは2019年、沖ちづるに“baby i love you”を提供した時のみ。それでも音楽と関わっていることに、SNSでは喜びの声も見受けられた。
状況が動いたのは2023年11月15日。SNSで「おひさしぶりです、黒沼英之です!」のコメントとともに突如として活動再開と、10年ぶりの新曲“HOPE”のリリースが発表された。アレンジに同世代のシンガーソングライター・松室政哉を迎え、ジャケット写真とMVは写真家・川島小鳥が手がける。自身の周りの人たちの力を借りながらリリースされた楽曲は、聴いてくれる人の顔を思い浮かべて歌う彼の核は変わらないまま、全編打ち込みというこれまでと違ったアプローチで作られており、紛れもない今の黒沼、等身大のポップソングだった。
10年の月日を経て、また活動する決断をした経緯はなんだろう。引いてはなぜ人は作品を作るのか、そして作ったものを発表するのか。創作を楽しむ一方で、時には辞めたくなるほど苦しみ、でもやっぱり創作する。そんな人たちにとって、自分にあった方法を見つけて活動を再開することができた黒沼の姿勢は、ひとつの希望となるかもしれない。
撮影:木下ロコ
黒沼英之

シンガーソングライター。2012年10月に『イン・ハー・ クローゼット』をリリースし、2012年11月に東京の〈WWW〉にて初ワンマンライブを開催。《SPEEDSTAR RECORDS》に移籍し、2013年6月に『instant fantasy』、2013年11月に“パラダイス”、2014年2月に『YELLOW ORCHER』等の作品をリリースした後、音楽活動を休止。2023年11月活動再開を発表、約10年ぶりとなるシングル“HOPE”をリリース。
Webサイト:https://kuronumahideyuki.jp/
X(旧Twitter):@hi_kuronuma
Instagram:@kuronuma_hideyuki
デビュー以降、しんどさを感じることが増えていた
音楽から離れることを決意した背景には、どんなことがあったのだろうか。
「当時のことはあんまりはっきりと覚えていなくて。“引退”とか書くと大げさかなと思ったので“活動休止”と書いたんですけど、自分の中ではもうやらないだろうと思っていました。『YELLLOW OCHER』のリリース以降、全然SNSを更新しなくなったので、ファンの方から心配の声も届いていて。安心させたい気持ちで“健康です”と書いたけど、とにかくこのまま続けるのは難しかった」
2013年のメジャーデビュー以降は、はっきりと理由を言語化することは難しいが、緩やかに主に心の疲労が募っていったという。デビュー前と後では、何が大きく変わったのだろうか。
「デビューまで、とにかく準備期間が長くて、15歳くらいでデモをレコード会社に送って、しばらくは育成枠として活動してたんです。デモを作っては担当者に聴かせる、ということを繰り返していました。その後《SPEEDSTAR RECORDS》が手を上げてくれたので、そこから本格的にデビューに向けた制作が始まりました。その時はいよいよか、という気持ちでとても楽しかったんです。
でもいざ曲を発表して、人にリアクションをもらうようになると怖くなって、自分がどうして音楽活動をしているのか、わからなくなったりして。レコーディングに参加していただいたバンドメンバーは第一線で活躍されているベテランのミュージシャンだし、そういう方々の音楽に対する覚悟と自分の心境を比べて気後れもありました。プロモーションでの自分の立ち振る舞いも定まらなくて、しんどかったり、複合的な要因で、これを続けていくのは難しいかも、と思っちゃったんですよね」

デビュー直前にオープニングアクトとして出演した《SPEEDSTAR RECORDS》の設立20周年記念イベントでは、斉藤和義やハナレグミ、つじあやのなどと共演したが、その時も直前でパニックになったという。
「別に誰も自分のオープニングアクトなんて求めてないんじゃないかと思っちゃいました。勝手に考えすぎちゃう傾向があって、レコード会社の期待に沿えないとか、自信がなくなっちゃったのかもしれないです。周りから見たらなんでもないことでも、自分では過剰に気になってしまう」
それまで長い準備期間をデビューに向けて取り組んできたからこそ、デビュー後に失意が続くというのはしんどいだろう。2010年代前半の当時はまだCDが主流で、まだまだアーティストとしての成功はレコード会社に拠るところが大きく、メジャーデビューを目指すのが主流だった。
「当時20代前半で、ライブハウスで共演する同世代も、みんな当然メジャーデビューを目指していました。そこが第一のゴールに近い感じですよね。だからデビューして、そこでプツンって切れちゃったのかな。助走が長すぎて、たどり着いて、無気力になった感覚でした」
視野を広げたら出会うことができた、「自分のペースで表現する」素敵な人たち
そして2014年、シンガーソングライターとしての黒沼英之像から解き放たれた彼は、出会いの間口を広げ始め、いろんな人に会いに行った。
「音楽活動を辞めたくらいから、音楽以外の分野のアーティストと会う機会が増えていきました。いろんなところに行っていろんな人と話してみようと思うようになって。今回ジャケットの写真と、MVの監督をしてくれた川島小鳥さんと会うようになったのもこの頃です。生活の一部に表現があって、自分のペースを大切に活動している人たちってすごく素敵だなと思ったんですよね」

既に世間では「自分のペースで働く」ことも認めるような動きが見え始めていたが(加速したのは無論コロナ禍である)、音楽活動を自分のペースで続けているのは、一部の成功した人か趣味と割り切っている人、というイメージがまだまだ強かった。しかし念願だと思っていたメジャーデビューを達成した後の黒沼が心惹かれたのは、語弊を恐れずにいうならば、華やかな表舞台でストイックな活動を続ける人たちよりも、自分のペースを守りながら活動している人だった。
「そういう人が本当に周りに多かったんです。“HOPE”の途中に出てくるドローイングを描いてくれた小橋陽介さんも、中心に生活がある。また別の友人の安藤智さんという画家の方は、キャリアの途中で一度絵を描けない時期があったとお聞きして、自分にも重なる部分があったので大きく影響を受けました」
そんな中で黒沼は「日々の暮らしを淡々と過ごすこともとても大切だけど、アウトプットしたいという思いがつのっていった」と語る。生計を立てるための仕事で人に喜んでもらえるよう、頑張るのも一つの生き方だろう。でもそれでは満たされない部分があったと心境を掘り下げる。
「人が感じたものごとを、自分の中で一度飲み込んで、自分なりに外に出すということが、やっぱりやりたかったんだと思います。表現をすることが生活の中に自然に並列にある友人たちと話していると、誰かと揉めたとか、恋愛したとか、仕事で嬉しいことがあったとか、もちろん辛かったとか、なんでもいいんですけど、そういう心の機微を内に留めておくんじゃなくて、アウトプットすることが、生きていく上で僕には必要なことだと改めて気づきました。
だとしたら自分にとってのアウトプットは、音楽ですることが自然で。何かあった時の帰り道に鼻歌で曲が生まれることが多いんですけど、すごく自然にやっていることだし、人の表現に憧れて無理やりやっていることでもない。いろいろ試してみたけれど、小説が書けるわけでも、写真が撮れるわけでも、絵が上手く描けるわけでもなかったから。」

黒沼は、過去作のインタビュー時に曲作りについて「帰り道とかにその日起こったことを思い出してるときにフレーズが浮かんだり、人と摩擦が起きたときに曲が生まれたり。あといい映画や小説に出会ったときに、その主人公を楽曲にしたらどんなものになるだろうって想像したり。そこで浮かんだものを、家で広げていく作業をしてます」と語っていた。そもそも、音楽でアウトプットしたくなるのはどうしてなのだろう。掘り下げると、意外な話が出てきた。
「いいカッコしいなので、仲良くなるまではいい人の振る舞いをしちゃうし、SNSとかインタビューとかだといいことを言おうとしちゃうし、ビジュアルとかミュージックビデオも、何重にもいい人を装っちゃうんです(笑)。でも本当の自分っていうのは、もっと腹黒くて、もっと汚くて、もっと自己中で。音楽ではそういう感情をそのまま出すことが不思議と全然平気で、恥ずかしくないんですよね。穂村弘さんが自身のダメエピソードを赤裸々に書いているエッセイ『世界音痴』があるんですけど、そんな感じかも。グッとくるものとして作品に昇華されていたら、一見恥ずかしいようなことも、恥ずかしくなくなりますよね。“どうしようもない”とか“ラヴソング”、“ほこり”や“やさしい痛み”とかは自分にとってそういう曲です」
同世代の仲間と一緒に完成させた新曲“HOPE”
アウトプットしたい気持ちが徐々に募る中で、新曲“HOPE”のリリース、そして活動再開を意識するようになったのは、いつからだろう。
「5年くらい前に“HOPE”の歌い出しを書いて、録音してたんですよね。曲とメロディが一緒に生まれてきていて、いいなあと自分の中に残っていて。もしいつかまた作品を出すことがあるとしたら、一曲目はこの曲にしようと漠然と思っていました。それでずっと置いておいて、完成させたのは去年の夏頃です。
ずっと音楽やりたいかも、いや、やっぱりなしかもを繰り返していて。そんな中、今回アレンジをやってくれた松室政哉くんと、偶然会う機会があったんです。それまでお互い名前を知っていたけど、会ったことはなかったんですよ。彼がメジャーデビューした2017年頃に自分はすでに音楽を辞めていたんですけど“当時めちゃくちゃ聴いてたんだよ”と言われて。それで“今は音楽やってないの?手伝えることあると思うからやろうよ”と言ってくれて。彼はすごく器用だし自分でアレンジを完結できるので、お願いしました」

メジャーデビュー当時はプロデュースに湯浅篤、河野圭、そして大久保友裕を迎え、豪華な顔ぶれのバンドをバックに歌っていた黒沼だが、今回は松室と共同プロデュース、歌以外の全てのトラックを打ち込みで完成させた。
「メジャーデビューしていたころの作品のアレンジも素晴らしいし、大好きなんですけど、今の自分にとっては、打ち込みで完結できるのは動きやすくて助かりました。当時も実はバンドサウンドに対して強い希望が合ったわけでもなくて、自然と生演奏でレコーディングする形になっていった。僕の一番の音楽のルーツに宇多田ヒカルさんがいるんですけど、特に『ULTRA BLUE』以降の彼女自身のDTMによるミニマルなスタイルに憧れていて。そういう軽やかさみたいな、ソロなんだし別に何をやってもいい、あれを足してみよう、これを足してみよう、みたいな自由度が楽しかったです。」
本作にはアレンジの松室の他、レコーディングエンジニアに川島尚己、ミキシングに土岐彩香、マスタリングを山崎翼が手掛けるなど、1989年生まれの黒沼と同世代の力を借りながら完成させた。それも新鮮だったという。
「当時は用意してもらった人たちとやっていく感じだったし、キャリアも超先輩の人たちだったので、どこか強く要望を言いづらいこともあって。でも今回は信頼できる同世代にお願いしたので、共通言語が自然と多くて、やりたいことを具体的に伝えやすい環境で、ワイワイしながら完パケまで持っていけたのが不思議な感覚でした。
でも人と何かを作るって、摩擦も生まれるし、当然大変なことも多いですよね。ものを誰かと作る時の苦しみみたいなことを久々に思い出して、あぁこれも辛かったんだよな〜!と。たった1曲だけど超大変で、かつ今回自分でいろんな人の間に立つシーンも多かったから“なんでまたこんなことやってるんだっけ?”みたいな気持ちになるタイミングもありました」
Apple Musicはこちら
届ける理由は「泣きたいときは、肩くらい貸すよ」
創作なんて極端な話、発表しなくてもできる。なのに10年間音楽を発表しなかった黒沼が、また世の中に楽曲をリリースすることを決断したのはどうしてだろうか。
「今回も、正直発表する前はめっちゃ怖くて、具合悪い感じだったんです。でも結果的にみなさんの反応を見ていて、活動再開を歓迎してくれたり、待ってくれていたことがわかって安心しました。
やっぱりすごく身勝手だけど、聴いてもらった人に救われてほしいという気持ちがあるんです。聴いて元気になってくれたり、救われたと言ってくれたりすると、自分の存在を認めてくれたみたいで安心する。やっぱり誰しも自分のことを信じたい気持ちがあるじゃないですか。自分が作ったものが褒められることは、何よりも原点な気がしていて。相手はそこまで思ってないかもしれないけど、ちょっとした“めっちゃ良かったよ”って一言が、パッと自分の景色を明るくしてくれるんです」
YouTubeにアップされている黒沼のMVには「大体悩んでる時。もしくは辛いことがあった時に聴く」「泣きたい時にめっちゃ聴きます」というコメントが並んでいた。どこか楽しい気持ちというよりは、悲しい気分の時に聴きたくなる曲であることは黒沼自身も認識している。
「自分の曲を聴いていいと思ってくれる人って、自分と似ているところがあると勝手に思っていて。考え込みがちで、自分のことを好きになりきれない人が多い気がするんですよ。そういう人に大丈夫だと思ってもらいたいのかなぁ。今回ライナーノーツを書いてくれた『青春ゾンビ』というブログのヒコさんが当時、“なんだかうまくいかなかった日の夜に聞きたいのはこんな歌なんじゃないかと思う”みたいに書いてくれて。それが当時からとてもしっくりきたんですよね」
筆者が当時高校生の頃、自分が知らない感情に出会う場所として黒沼の音楽を聴いていたことを伝えると、思い出したように話してくれたことに、黒沼の曲が誰かを救う理由があった。
「“HOPE”の制作に臆病になっていた時、確かレコーディングエンジニアの川島くんが言ってくれたんですけど、レコーディングってただその日の声の”記録”なんですよね。僕は本当に忘れっぽいので、心が動いた瞬間を録っておくことで、その感情を知らない人からしたら“そういう感情があるんだ”という気づきになるのかもしれない。またその感情が誰かの感情と重なった時に、言葉にできない感情が具現化されることで、その人の心が助かるかもしれない。身勝手かもしれないけど、そういう曲であったらいいなと思う。だから記録して外に出すことが、自分にとって大事なんです。あんまり自分のためだけに曲を書いて、誰にも聴かせないってことはないかな」
感情を置いておくことで、誰かの感情と交差する可能性は増える。そんな当たり前のことを認識すると、創作活動の真髄がはっきりと見えてくる。「サビの歌いやすさとか覚えやすさ、一回聴いて耳に残るメロディができたと思っていて、やりたいことはできました」と“HOPE”について語る黒沼がポップソングを作る理由は、誰かが彼の曲を必要とした時に、ふと思い出せることが何よりも必要だからなのかもしれない。

周りの理解も味方にして、心地よいペースを探し中
内面を掘り下げるようなソングライティングの一方で、『YELLOW OCHER』リリース時のインタビューでは「曲ごとにそれぞれのキャラクターを演じるというか。そういう意識でポップソングが書けたらいいなと考えてました」とも語っていた。ノンフィクションとフィクション、どちらも創作できる黒沼の器用さは、弱さを知っているからこその優しさに包まれたポップさも相まって、当初から本人が好きな作家として名前を挙げていた吉本ばななのようだと感じていた。“HOPE”はどちらのパターンなのだろうか。そして黒沼の意識は今どこに向かっているのだろうか。
「これまでの曲作りには2パターンあって、自分の中の恥ずかしい部分を出すパターンと、もう一つは友達の結婚式のために書いた“ふたり”みたいに、自分以外の主人公を立てるパターン。“HOPE”は切実さをそんなに感じない、明るい曲だと思っていたんですけど、実際俯瞰して聴いてみると黒沼英之として歌ってきた“後悔”とか“切なさ”はありますよね。だから、今回はどちらのパターンも混ざっているような曲。最近は曲作りにフィクション、ノンフィクションの境目はなくなってきているのかも。そのグレーさが心地いい。昔から誰の曲でも切実さが出ている曲が好きで、何かが叶う歌っていうよりも、叶わない歌に執着があります。人との摩擦や、人間関係にもがいている時に新しい曲が生まれがち。そこは10年前と変わっていないし、これからも変わらない部分だと思います」

活動再開を発表して、数々の嬉しいコメントとともに、自分のペースでの活動を応援する言葉もたくさん届いたという。レコード会社からリリースすることが一般的だった時代から10年が経ち、アーティストの活動方法も多様となった。別で仕事を持っているアーティストも一般的だし、コロナ禍以降は体調が悪いと無理を通すのではなく、公演を中止することも珍しくなくなってきた。そんな活動方法が広まっているのは若い世代だけではなく、黒沼と同じようにメジャーの活動の定型に合わなかった才能が再度自身で主体性を持って活動の場所を増やしているケースも目立つ。D.W.ニコルズも自分で会社を立ち上げたり、Analogfishもインディーズとして活動している。アーティストが自身の心地よい方法で活動することは、黒沼が落ち着いて考えている間にすっかり一般的になったのだ。
「少しずつではありますが、新曲の制作も進めていて、今年はライブもしたいと思っています。書きたいときに書いて、歌いたいときに歌うみたいなペースを生活の中で整えていくことが、今の理想なんですよね。まだまだ模索中ではありますが」
『instant fantasy』のブックレットで硬い表情をしていた黒沼とは打って変わって、柔らかい表情に出会えて安心した。”HOPE”で歌われた「あなたにただ笑顔でいてほしい」という言葉は、黒沼英之の一リスナーとして、黒沼に向けて幾度となく思っていたことだ。日々の生活で、自分のことよりも誰かのことを考えて疲れてしまう人は少なくない。少し疲れたら黒沼英之を聴いて、そして黒沼英之が歩んだ道のりと今の表情を思い出しながら、自分の方法で自分が心地よいペースでアウトプットすることが、笑顔への道のりだ。

WRITER

- ライター
-
1997年生まれ、みずがめ座。西荻窪|成城|祖師ヶ谷大蔵
OTHER POSTS
カルチャーWEBメディア NiEW(ニュー)、Musicman、ANTENNA等で執筆。