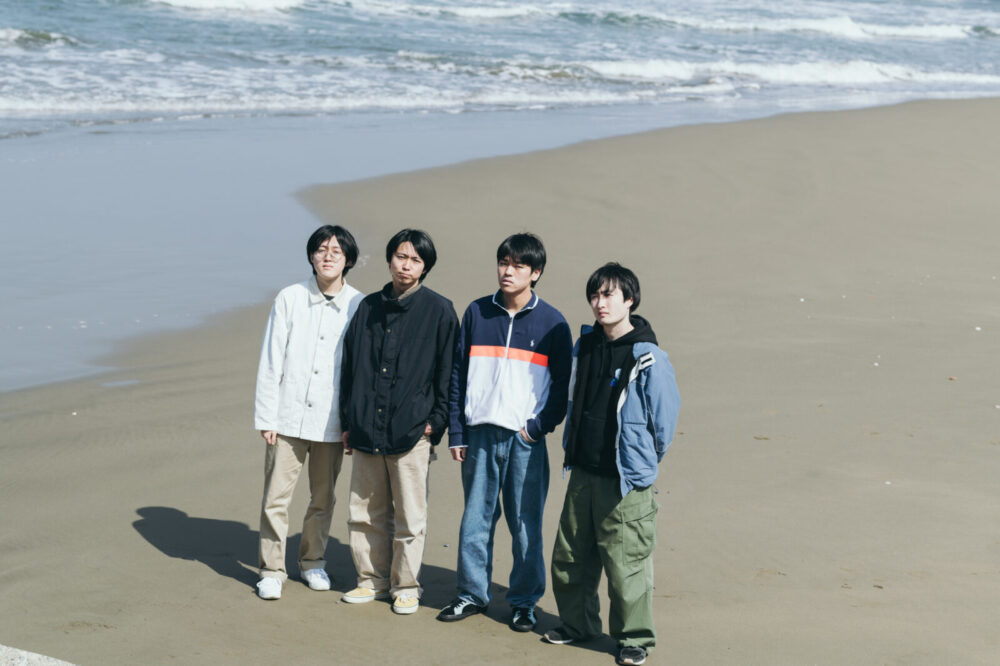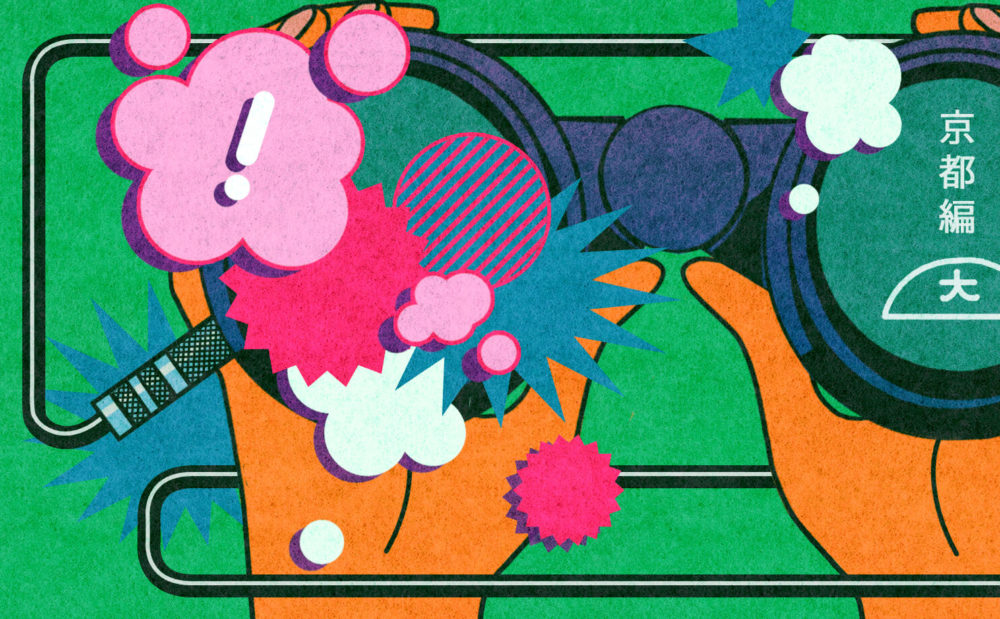“捨てる”は、あの場所にかえる動機になる? 集う人と『森、道、市場』をつなぐゴミの行方
数だけでなくスタイルもさまざまに変化を遂げた日本の音楽フェス。コロナ前の2019年には動員数295万人、市場規模は330億円(※ぴあ総研調べ)と2010年から右肩上がりの成長を続けてきた。まだ夏フェスという言葉の特別感が機能していたころは、年に一度のお祭りという祝祭的意味合いを強く感じられるものだったろうが、いまや季節でくぎる必要性などないくらいに日本のどこかで音楽フェスが行われるような状況だ。
現在のフェスの先駆けとなった『FUJI ROCK FESTIVAL』のようなイベント会社が主催するものから、『りんご音楽祭』のように実行委員会形式で地域住民が主体的に行っているもの、『京都音楽博覧会』のようにミュージシャンが主催するものなど、運営も規模も多様化。近頃では、2022年からはじまった『TOKYO ISLAND』のようにボートやカヌー、恐竜体験ツアーといった音楽以外のアクティビティを充実させた非日常的な体験ができるフェスも増え、よりレジャー化が進んでいるようにも見える。日常と非日常、ハレとケの概念が曖昧になっている現代社会のように。
そんな数多あるフェスの中で、ゴミ問題をエンタメ化することでフェスティバルとしての存在意義を提示した野外イベントがあった。それが、今年5月26日から3日間にわたり愛知県蒲郡市で開催された『森、道、市場(以下、森道)』だ。


『森道』がはじまったのは2011年。発起人である岩瀬貴己さんが三ヶ根山で偶然出会ったヤバいジンギスカン屋のことをみんなに伝えたい!という想いが発端であったこともあり、最初から音楽がメインとなっているフェスとは成り立ちが大きく異なっていた。音楽フェスと名乗るのではなく“モノとごはんと音楽の市場”という立ち位置を提示しているのもそこに理由があるといえる。そんな、一人の面白いという熱量から生まれた『森道』も回を重ねるごとに集う人たちが増え、規模が拡大。場所を変えながら2017年からは大塚海浜緑地〈ラグーナビーチ〉と遊園地〈ラグナシア〉という2つのエリアを使って開催することになり、今や来場者が5万人超え、出店は500以上となった。

人が増えると、ゴミも増える。『森道』でも他の音楽フェスと同様に、近年ゴミ問題が顕在化していた。この問題に対するアプローチとして、今年から特別企画として立ち上げたのが「生GOMIコンポスト大作戦」と「全て土に還るゴミステーション」だ。コンポストといえば、昨年『京都音楽博覧会2022』でもクラウドファンディングを募り、梅小路公園内にコンポストステーションを設置。会場で出た生ごみや余った食材を堆肥化するという「資源が“くるり”プロジェクト」が行われたという事例がある。
このケースでは、会場となる地域に住む人たちを巻き込むことで、サスティナビリティに貢献するだけでなく地域とのつながりを深め、街の活性化にも一役をかっていたように思う。運営側のくるりの想いと地域の人のアイデアがつながり実現した取り組みであったが、今回の『森道』の場合はというと、市場の出店者が主体となって運営を巻き込み立ち上がったというのだ。実際にどのような取り組みかを知るために現地に向かった。
ゴミ問題をポジティブに楽しむ「生GOMIコンポスト大作戦」のアプローチとは

今回、立ち上がったという「生GOMIコンポスト大作戦」は、会場で飲食をする来場者から出る食べ残しと、飲食ブースから出た破棄食材を「全て土に還るコンポストステーション」で回収。微生物とミミズという2つのコンポストを活用し堆肥化するという取り組みだ。『森道』終了後はコンポストの場所を移し、半年かけて堆肥をつくる。そして、完成したら野菜などの植物の種とセットにして「森道soil」としてゴミを出した来場者の手に還すことを1回目のゴールとしている。
『森道』の生ゴミが土に還るまでの流れ

微生物コンポストが担当するのは、ミミズが食べきれない生ゴミだ。これを集める拠点となる「ゴミステーション」で生ゴミを捨ててくれた参加者に手渡されるのは、土とミミズがあしらわれたシール。その裏にはこの取り組みの行方を発信するインスタの二次元コードが印字されていて、自分が捨てた生ゴミがどのように土へ還っていくのかを追跡できる仕組みになっていた。(現時点でも、“地球に土を還すプロジェクト”という名で堆肥になるまでの過程を発信中)
通常もらえるシールは小さいサイズだが、たまに大きな丸いタイプがもらえることも。そこにも遊び心を感じる
来場者の食べ残し以上に多かったのが、出店者の飲食店から出る絞った後のオレンジや野菜くずなどの廃棄食材だ。ボランティアスタッフが交代でキャスター付きのゴミ箱を使い、飲食店をまわって生ゴミを収集していたが、出店者も自ら多量の生ゴミを運んでくる。どんな仕組みなのかスタッフに尋ねると、運営が販売するゴミ袋とは違う、生ゴミ専用のゴミ袋を無料で配布しているというのだ。違いが一目でわかるように緑色のゴミ袋(トウモロコシ由来の生分解性プラスチック素材)を使用することで、不要なものが混入しないように工夫されていたことも回収の効率化につながっていたように思う。


現場で使われていたトウモロコシ由来の生分解性プラスチック素材の緑のゴミ袋(写真提供:森、道、市場実行委員会)

今回、用意された微生物がゴミを分解するために必要なる床材(もみ殻、米ぬか、落ち葉、壁土を配合したもの)は2,000L
一方、ミミズコンポストを覗いてみると、まるでアクティビティのようにスタッフの方がミミズを触らせてくれる(もちろん、触りたい人だけ)。スタッフの方は、ミミズのことを‟ミミちゃん”と呼びながら、生ゴミを食べてくれるのはシマミミズというミミズだけだということや、なんでも食べるわけでなく辛い物が苦手で甘いものが好きだという味の好みまで教えてくれた。


今回『森道』にやってきたシマミミズは約5万匹。甘党のミミズのために生ゴミが寄り分けられ、フルーツの甘い香りが漂っていた
この大作戦を実現するために集まったのは、岐阜県白川町で農業を営みながら、小農を軸とした自立分散的でタフな「小農コミュニティ」作りを目指して、農家と消費者が生ゴミ堆肥化でつながり地域資源を循環させる“BLUE COMPOST”という活動を行う五段農園の 高谷 裕一郎さん。そして、地域貢献のためにミミズコンポストの取り組みを広島で実践している土木資材を扱う光和商事株式会社。それぞれ、コンポストのプロフェッショナルが主軸となり、大学生から社会人まで、彼らの活動に共感した人たちが集まったボランティアスタッフの人たちがこの運営をサポートしていた。

ゴミ問題というとネガティブなイメージをもってしまったり、やらなければならないことと義務感で取り組んでしまうことも多いだろう。日頃より強い思いを持ち個々に専門的な活動をしていた人たちが集まった時のエネルギーはすごい。ボランティアスタッフも合わせて、そこにはゴミ問題をなんとかしようという啓蒙的な色合いというより、ゴミ問題の面白さをみんなで分かち合おうというポジティブなバイブスが滲みでていた。細やかな設計もうまく作用し、ゴミステーションにはスタッフも来場者もお互い楽しみながら『森道』のゴミ問題を共有できる場が自然と出来上がっていた。
ゴミ問題に出会うきっかけをつくる広告塔「全て土に還るゴミステーション」

この光景をカタチにしたのが「『森道』のゴミ問題をエンタメ化したい!」と『森道』で開催されたゴミをテーマにしたトークセッションで話していた株式会社りんねしゃの飯尾裕光さん(以下、裕光さん)だ。普段は農業をしているという裕光さんは、『森道』には何度も発酵食品のお店で出店してきたこの場所に集いし仲間の一人である。『森道』が最高に楽しいからこそイベントはもちろん、未来の地球のためにも何か還したいと、昨年は自身のブースにミミズコンポストを持ち込み(運営の許可は得てとのこと)、飲食店をまわって生ゴミを集めたという。一人が楽しい、面白いと思いはじめたことが伝播し、今年の大作戦につながったのだ。その動機には、このイベント発起人である岩瀬さんが『森道』を始めた理由とつながるものを感じずにはいられなかった。

入口近くにお目見えした茅葺屋根が印象的なゴミステーションをつくったのは建築集団々と株式会社くさかんむり
りんねしゃも出店する発酵居酒屋の建物と併設したゴミステーションをつくったのは庭をテーマにものづくりを行うdomus
そして、現地に赴いた私がこの場づくりに一番貢献していたと感じたのが、コンポストステーションに建てられた「全て土に還るゴミステーション」だ。遊園地と海をつなぐ入場口近くに建てられた茅葺屋根が目印のゴミステーションと海エリアには発酵居酒屋と地続きの土壁が印象的なゴミステーションがつくられていた。
先ほど事例にあげた『京都音博』のコンポストステーションは堆肥をつくるための場所として機能していたのだが、『森道』のゴミステーションの役割は違う。それ自体に堆肥をつくる場所としての機能はないが、もしこの場で朽ち果てたとしてもすべて土に還る素材を選ぶことで、今回の取り組みを言葉でなくカタチで表現するモニュメントとして広告塔ともいえる役割を担っていたのだ。
さらに、茅葺屋根のゴミステーションではインスタレーションのように『森道』の開催期間中に屋根が出来上がるという仕掛けが施されていたり、海エリアのゴミステーションでは来場者に遊び感覚で土壁を塗ってもらうことで、自然とゴミステーションに人が集まる仕組みができていた。このようなコンポストへの導線となる仕組みもエンタメ化の一役を担ってたように思う。この場所でふらりと初めてのお店をのぞくように、知らない音楽に偶然出会うように、自然と出会える設計がなされていたように見えた。そう、このゴミステーションが集めていたのはゴミではない。人の視線を集め、ゴミについて考えるきっかけをあたえる装置として機能していたのだ。


なぜ、このような試みが実現したのか。そこに込められた想いを探るため「全て土に還るゴミステーション」の制作に関わった建築集団々(のま)の野崎将太(以下、野崎さん)と株式会社くさかんむり代表の茅葺き職人相良育弥(以下、相良さん)に話を伺った。
5万人に伝えたい想いを背負った茅葺屋根の「ゴミステーション」

出店者の裕光さんが中心となり実現した「生GOMIコンポスト大作戦」だが、「全て土に還るゴミステーション」をつくってほしいと話を持ち出したのは現在、運営を一手に引き受けている山田高広さんだ。彼は2019年に急逝した岩瀬さんとともに初期からこの『森道』をつくり上げてきた人物の一人である。
「『森道』が人に影響力を与える大きなイベントとして成長してきていて、運営としても音楽と市場を楽しんでいるお客さんに、少しずつでも何を還していけるのかゴミについて考える機会をつくりたいと考えていたそうです。今回、微生物とミミズのコンポストを設置するけど、5万人の人が通る道の途中にコンポストがあるだけではお客さんに伝わらない。だから、ゴミステーションを制作してくれないかと連絡が来たんです」と運営を担っている山田さんから声をかけられたと、今回の経緯について野崎さんは話してくれた。
今や5万人も集客するイベントとなった『森道』。影響力を持ってきたらこそ『森道』として来場者にゴミに対する考え方を提案できるのではないか、それが「ゴミステーション」の制作の出発点だったという。そんな運営サイドの考えを踏まえ「生GOMIコンポスト大作戦」を企画した裕光さんから今回の制作にあたり「分解」というテーマをもらったというのだ。
「祐光さんが、コンセプトに分解というテーマをあげたんです。そこには『森道』として、生ゴミが土に分解されるということをお客さんに見せたいという考えがありました。僕がホントにすごいなと思ったのが本気度です。打合せの時に、裕光さんにどこまでやるんですかと聞くと“半年後に土とミミズと野菜の種をセットにしてお客さんに還していく”と言うんです。実際に、半年前に起こった『森道』で自分たちが出した生ゴミが土に還って送られてくる。それで家庭菜園ができたり、自分の畑に撒いたりできるところまで、初回から実現させていくって。それはすごいことだなと。コンポストチームもたくさんの人が動いているし、本気で初回から取り組むというからには、見ただけでお客さんにコンセプトを伝えるものがないと、一気に伝わらないと思いました」

裕光さんの本気の思いに応えたいと野崎さんが考えたのが今回の「全て土に還るゴミステーション」だ。この制作に至るまでにどのような思いがあったのだろうか。
「僕が“分解”というコンセプトを聞いたときに、つくったのが「全て土に還るゴミステーション」という言葉です。木材で構造を組むより竹の方が、合板を屋根にするよりも茅の方が土に還りやすい。資材も結んでいるのは縄。ビスや番線、鉄は使っていません。今回のゴミステーションの下はコンクリートですが、例えばこれが海沿いで倒れたとしてもそのまま土に還っていく。建材は統一して土に還りやすいもので制作させてもらいました」
発酵も分解も、私たちの目に見えないところで行われている。それを伝える象徴としてつくられたのが竹で組まれた茅葺屋根のドデカい櫓のようなモニュメントだったのだ。

ほかにも感覚的にゴミを知るきっかけとなっていたのが竹で編みこまれた半ドーム状のモニュメントだ。そこには「わりばしさしてね」という文字が書かれた板がささっていて、お客さんが使用済みのわりばしをさすことでモニュメントが完成していくという仕組みになっていた。面白いもので、その場所を偶然訪れただろうお客さんが列に並びながらも物珍しそうに割り箸をさしていく姿が多く見られた。この割り箸のモニュメントも、ゴミステーション自体も『森道』のイベントが終了したら、チップ機で粉砕し、微生物コンポストに入れることで文字通りすべて土に還る。これを考案したのも、野崎さんだという。
「割り箸なんで、可燃ゴミにしてしまえばいいと思うけど、分別することで感覚的にゴミのことを考えてもらいたいという思いが根源にありました。ひと手間増やすことで、ゴミに対する価値観が少しくらいは脳裏に思い出として残るかもしれない。その体験があるから、普段の暮らしも少しづつ変わっていく。また『森道』に来たら、次も楽しくみんなで分別して、気持ちいいイベントになる。そんなサイクルが徐々に『森道』で実現していくと思います」そう、強い眼差しで語ってくれた。


竹で編まれたモニュメントに割り箸をさすことで分別を促す仕組み。時間が経過するとイガグリのようなアートに変化していった
やりたいことを最大限にカタチにし、生まれたグルーヴ感

今回、茅葺屋根のゴミステーションの設営をはじめたのはイベントがはじまる4日前。櫓の土台はイベント開始前に組みあがっていたが、茅葺屋根をつくり上げる作業はイベント期間中も続けられ、27日(土)15時に完成するという流れになっていた。今や日常でなかなかお目にかかることのない茅葺屋根。今はこれをつくることができる人は限られていて、資材となる茅も、職人に受け継がれる技術も貴重なものとなっている。
「今でも、茅は一本一本を人の手で採っているんです。手でとれる範囲内を握って、鎌で切って、雑草を仕分けて、揃っているのものを選別してロープで結び、保管する。だから、すごく高価だし、手間もかかるんですよね」と相良さんは茅の貴重さについてこう話す。今回、このプロジェクトが立ち上がり、イベント当日を迎えるまでの期間は約1ヵ月。この短い準備期間で愛知県内の茅を取り寄せることは難しく、相良さんが保管していた茅を工夫して使うことになったそうだ。
「茅場は川べりにあるんですけど、愛知県は海沿いが工業地帯になっていることもあり、まとまった茅がとれる茅場がない。県内に職人さんもいない。もうちょっと時間があれば稲わらとかも使えるので、じゃあ、秋に稲わらを集めて、この時期に『森道』で使おうぜってできたんですけど……。だから、加工せずそのままのカタチであまり切らずに使うことに。これは伝統的なやり方の一つでもあるんです。それで終わったら持ち帰ることにしました」と今回の「全て土に還る」というコンセプトに沿いつつも、茅はリサイクルできる手法を選んだと相良さんが教えてくれた。短い期間の中でも、やりたいことを最大限にカタチにするためにいろいろな工夫がなされていたのだ。

そして27日(土)の15時に、ゴミステーションの完成を祝って行われたのが上棟式だ。建築現場で行われる作法にならい、茅葺屋根が完成したことを神に感謝し、関係者に酒を振舞うというこの儀式。茅葺屋根を葺くという一連の作業が終わったということを伝えるハイライトともいえる瞬間を迎えた。大きなアナウンスをしたわけではなかったが、そこにはたまたま通りかかったお客さんの人だかりが自然と生まれていた。茅葺屋根にあがった野崎さんが竹、茅、縄と全て土に還る素材でつくられているこのゴミステーションの意味について語り、その後を受けるように相良さんが自ら棟札とよばれる木に書いた口上を詠んだ。
土を作りし命の上に
納め置きます草の屋根
人の諸行は解かれて
生命の源はみな元の場所に還る
森、道、市場の緑の宴

この時、感じたことを野崎さんはこう話す「茅葺き職人と僕たちみたいな々のストリート感というか、僕たちは大工ではあるんですけど、アーティストとして集まっていて、一緒に空間をつくる仕事をしている。そういう、アーティストが集まっている二つの建築集団が一緒に存在すること。さっきの上棟式も、僕が人前で何が起こってこれをつくったかを大声で叫んで、たくさんの人に注目してもらってから、バトンタッチして相良さんに口上を呼んでもらう。普段はどちらか一人が屋根の上に立つものやし、それを同時にできたのが今日の『森、道、市場』だった。々のストリート感とくさかんむりの伝統的な仕事とのミックスは、それを見たお客さんに良い違和感を与えることができたのではないでしょうか。今回、はじめて々とくさかんむりとして仕事させてもらって、最後の棟上げの口上は最高の体験でした」


運営の思いが生んだ「ゴミステーション」が見せたかったモノとは
見事に人をひきつけ、ゴミ問題を考えるきっかけとして貢献していた茅葺屋根だが、ゴミステーションに茅葺屋根を使い、イベント期間中に完成するようにオーダーしたのは運営の山田さんだという。そこに込められた想いについて、野崎さんはこう話してくれた。
「山田さんから聞いた話なんですが、今、10代の子たちは『日本昔話』を知らないんですよ。テレビだけでなく、実際に日本の原風景もどんどん失われていっている。でも『茅葺屋根って何。見たことない』という若い子たちに、茅葺屋根の写真を見せると懐かしい感じがすると言ってくれて……。そう感じるのはもしかして、潜在的に、僕たちの遺伝子に何か入っているものがあるのかもしれない。山田さんが茅葺をやってみたいと言ったのは、みんなが忘れるべきではない原風景というものを『森道』として提案ができるのではと思ったことが大きいと思います」

現在、運営を一手に引き受けている山田さんは2019年に急逝した岩瀬さんとともにこの『森道』を長きにわたりつくり上げてきた人物の一人だ。今回、山田さんがアイデアを出した茅葺屋根に託し、彼が見せたかったみんなが忘れるべきではない原風景には、岩瀬さんがこの『森道』をはじめたきっかけともいえる面白さ、楽しさを『森道』としてここに集う共同体ともいえる仲間たちと分かち合いたいという初期衝動ともいえる想いも込められていたのではなかろうか。
今やフェスの数は膨大となり、ただのレジャーとしてとらえている人も多いだろう。しかし、『森道』は違うということを伝えるための取り組みが今回の一連のプロジェクトの一側面を担っていたように思うのだ。特別なイベントとしてその日1日で消費されてしまう非日常ではなく、日本に昔からある概念“ハレとケ”があるからこそ楽しめる祭りとしての非日常を生み出すことができる共同体を育んできた歴史が『森道』にはある。日常と地続きだからこそ毎年この1日を楽しめるそんなイベントであるということを伝えるための狼煙が「全て土に還るゴミステーション」であり、この1日を日常へと届ける役割を担うのが「生ゴミコンポスト大作戦」つくられた堆肥『森道soil』なのではなかろうか。
それを実現することができたのも、インディペンデントなイベントとして主催者の想いが出店者へ来場者へネットワークのようにつながり、楽しみを自発的に創り出す共同体ともいえるコミュニティが生まれていたからこそなのではなないか、そんな想いをゴミ問題に一端を発したプロジェクトを介して私は受け取った気がする。きっと、これからも続いていくだろうこのプロジェクト。今年の『森道』に参加した方には、あの場所で生み出されたゴミが土へ還った『森道soil』というメッセージを受け取ってみてほしい。あなたは、なにを思う?

You May Also Like
WRITER

- 編集者 / ライター
-
奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。
OTHER POSTS