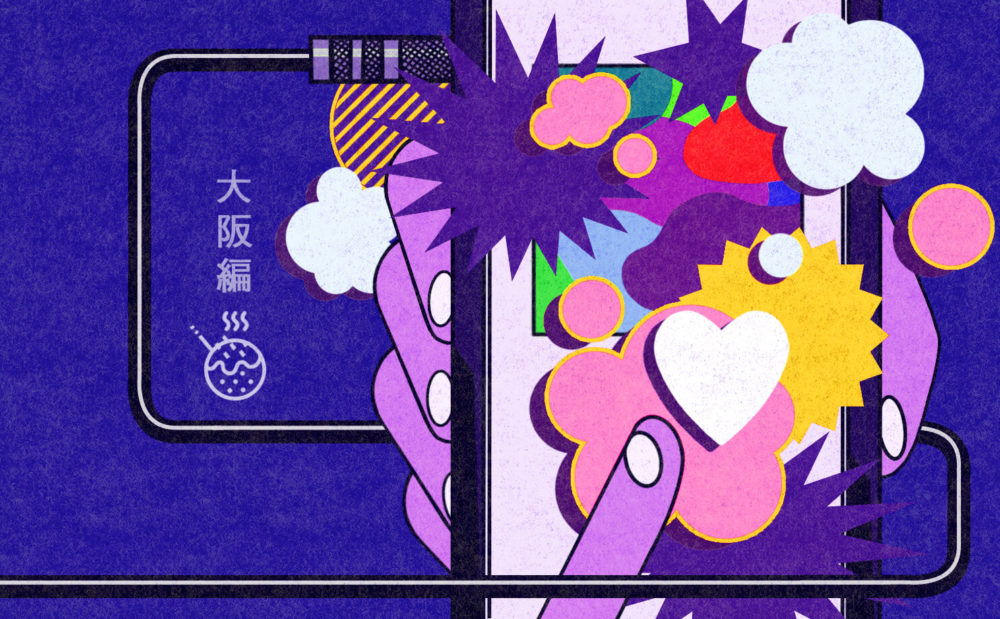京都の〈外〉から来て5年、確信とエラーで進む空間現代の現在地
東京にいた頃から交流があった劇団・地点との共作はもちろんのこと、活動の拠点を移してからは〈外〉の廊下に作品も残している詩人・吉増剛造とのパフォーマンスセッションやファッションブランド・RAINMAKERへの楽曲の提供など、これまで以上に他ジャンルとのコラボレーションを精力的に行っている空間現代。彼らはどうしてそこまで他者を求めるのか。野口順哉(Gt / Vo)にその真髄を聞くと、見えてきたのは一筋縄ではいかない右脳派・空間現代の人間くささだった。
空間現代

©細倉真弓
2006年、野口順哉(Gt / Vo)、古谷野慶輔(Ba)、山田英晶(Dr)の3人によって結成。2016年9月、活動の場を東京から京都へ移し、自身の制作および公演の拠点としてライブハウス〈外〉を左京区・錦林車庫前に開業。2021年、最新EP『Tentei』を発表。先鋭的なアーティスト達とのジャンルを超えた作品制作も積極的に行う。2019年度、京都市芸術文化特別奨励者。
コラボレーションが生む意図しない相互作用
〈外〉をつくって5年が経ちますが、京都の生活はどうですか?
自分にとっての京都は左京区周辺に限られますけど、コンパクトで満員電車もないし、東京に住んでいたときじゃ考えられない暮らしやすさです。家賃が安い木造の建物が多いからか、どこに行ってもぽつぽつと面白い店がある。中心地に近くて便利ということよりも、それぞれに違う価値観を持ってお店をやることが優先される感じがするので、「京都はいける」と思って左京区に〈外〉をつくりました。実は当初、「京都はライブハウスによって住み分けがされている」と地元の人に言われたりしていて。
ライブハウスごとの色がはっきりしています。空間現代が出ると言えば〈CLUB METRO〉か〈UrBANGUILD〉でしょ、みたいなことですよね。
実際に東京にいたときからずっと、そのどちらかにしか呼ばれたことがないんですよ(笑)。〈外〉をやるにあたっては出演してもらっている人たちを積極的に〈外〉村に囲い込むわけでも、レンタルスペースにして誰でも受け入れるわけでもない、という微妙なところを突こうと運営しています。イベントの企画は、コラボレーションと似た熱量でやっていますね。

活動初期からコラボレーションを活動の軸に置いていますね。きっかけは何でしたか?
HEADZからファーストアルバム『空間現代』を出したときに、レーベル主宰の佐々木敦さんに「ECDと一緒にやってみないか」と提案されたことです。でも当時の僕らの楽曲って、ビートとしてはあまりに変則的で。だけどECDさんは自分の持っているリリックをその都度即興的な部分も含めて僕らの楽曲に乗せてくださって、意図しない相互作用があって楽しかったんです。その流れでコラボレーションはすごく面白い、と思うようになりましたね。
佐々木敦さんとはどちらで出会ったんですか。

僕が東京の大学に通っていたときに佐々木さんが授業を持っていたんです。分かりやすくて面白いものより、「これって一体なんだ?」みたいなものを取り上げていたんですよね。音楽をやっているから音楽だけ聴いている、というのも飽きちゃった時期で、メンバーみんな演劇でも映画でも面白いものを探していたので、そういう気質とHEADZは相性が良かったですね。「音楽ってこういうものだよな」とか、「ロックと言えば」とか、言語化していないけど自分が勝手につくっている枠組みってあるじゃないですか。当時はそういう枠組みが壊されたり、外されて新しい捉え方ができるような芸術体験に惹かれていました。
鍛錬の先に起こるエラーにびっくりしたい
音楽でも、枠組みを超える、壊すような作品づくりに注力されていると感じます。
そうですね。どうやって形式を持ちながら、形式から脱臼して、ほつれが見えちゃうかとか、自分たちでもびっくりするようなことが起きるのか、ということばかり考えていました。形式をつくらずに全部即興とか、フリーインプロビゼーションは、そう簡単にはやれないという意識が自分たちの出発点としてあるんです。
どうしてですか?
聴く分には面白いし刺激を受ける一方で、自分たちがいざやるとなると見せかけだけの真似が非常にしやすく、ついそうなってしまいがちだと思ったんです。自分じゃないものと出会いたくてやるべき方法論・ジャンルのはずが、逆に自分の発露になってしまうことを恐れたんだと思います。自分が演奏するし、自分たちで作曲するんだけど、そこで私性が前面に出ちゃったらいい作品にならない。一方で、ばっちり作戦会議して作曲して、ライブではこの後何が起きるか全部知っていて、それにただ気持ちよく乗っかっていくのも押し付けがましいというか、つまらないなと。だから演奏していてもびっくりしたい、でも作曲しなきゃいけない。そういった考えから空間現代の楽曲の方向性が変わってきて、ある時期からは物理的に演奏を難しくしたいと思うようになりました。
フリーインプロビゼーションという「形式」になってしまう、ということですよね。自分たちでつくった形式に乗るわけでもなく、その形式も壊すことを試みて物理的に演奏を難しくするということかと思いますが、それはテクニックとは違いますか。
一人ひとりではできても、3人で息を合わせてやるのが非常に難しいということを試みてきました。例えば、まるでレコードの針が飛んじゃったみたいに、変なところで巻き戻るみたいな「音飛び」って言ってる手法があるんです。これがすごく難しいけど面白くて、当時はそういった方法論に邁進していました。どうしたら自分たちでもびっくりするような出来事が起きるのか、ということに興味があったんです。

〈外〉をつくって、その方法論に変化はありましたか。
本当に鍛錬して演奏しているミュージシャンのライブを見て影響を受け、エラーが起こるのは面白いけど、単なる失敗を一種の即興的要素だと開き直っているのはだめだ、という話になりました。以前はパンク的な感じがあって、うまい弾き方よりも、誰も弾いたことがない弾き方に憧れていたんです。でも今はすごく練習したり、今までやろうとしてなかったことにもトライするようになりましたね。
昨年にリリースされた『Palm』(2019)はこれまでの作品に比べて聴きやすいですね。
BGMとしてレコードが回っていても会話の邪魔にならないし、聞き流そうと思えば聞き流せる、そういった作品にトライしてみようという話になったんです。聞き流せるけど、ちゃんと聴くと何かが起きている。その両方を目指せないかと。それが転換期で、方法論で一発勝負はなくなって、純粋に、いわゆる音楽的な作り方がようやくできるようになりました。今までは逆に方法論的に斬新な理由がないと、ハイハットも叩けないし、ギターやベースも弾けない。そういった変なストイックさがありました。音楽的にかっこいいから叩けばいいじゃん、というのが普通だと思うんですよ(笑)。そういった意味で最近は、変な言い方ですけどようやく普通の音楽の作り方ができるバンドになってきました。
他に〈外〉ができて変化したことはありますか?
少し前から照明にこだわり出して、〈外〉ができてからはベースの古谷野が毎回決めています。照明も音楽と同じで、ノリでON、OFFをやるんじゃなくて、時間がきたら決められたパターンで曲の展開を無視して変えていくやり方をしています。
太陽と月みたいに、一定の法則に則って自然と切り替わるみたいな。
そうそう、そういう方が面白い。ぴったり合わせようとするとちょっと恥ずかしかったりするけど、たまたま合っちゃったら、演奏してても盛り上がるんです。それは以前コラボレーションした大橋可也&ダンサーズの照明のシステムを真似していますね。

飽くなきコラボレーションで私性と無縁の作品ができる
音楽で「形式」を壊そうとしていた試みは照明においても当てはまりますね。自分たちの形式が出来上がったら飽きて壊したくなるので、違う形式を持っている人とのコラボレーションにつながっていく。
それはあるかもしれません。全然違う価値観を持っている人と一緒に一つの作品をつくるのは、すごく勉強になります。自分たちが「こういうことしかやらないぞ」、と思っていても、それを外していいと思えるきっかけになるんですよね。
面白いと思うものの特徴で話されていたのと同じですね。
それはずっと求めていることではあります。バンドをやっている理由も同じですね。バンドって、自分以外の人と一つの曲をつくることじゃないですか。自分がかっこいいと思って弾いたフレーズも「全然ダメ」と言われたり、私性はとにかく排除されるんですよ。だから自分一人でやっていたらこういう曲になる、というのを、がんがん打ち壊されるんです。新しいものをつくるっていうことは、自分にとって新しいことは当然。でも、できれば誰にとっても新しいものをつくりたいので、自分以外の人とつくることがすごく重要ですね。「これ誰の曲?」って言いたくなるものができたら面白いと思います。
その関係が拡張したものが、さらにバンドメンバー以外と一緒にやるコラボレーションですね。
コラボレーションは最初から圧倒的な他者が一緒にいてくれるので、取っ掛かりがあって楽でもあります。バンドはドラムとベースっていう意味の他者はいますけど、ある程度似たバックボーンを持って音楽と付き合ってきた3人なので、そういう意味では他者じゃない。
関わる他者が多様になればなるほど、「自分にとって新しいもの」「バンドにとって新しいもの」、主語のスケールが大きくなるんですよね。自分にとって新しいものって、ある種自分一人でつくれるものですけど、バンドにとって新しいものっていうのは、バンドだけだと難しくて、音楽というジャンルも越境していく必要もあり、より幅広い他者が必要だと。

他者と作品をつくることによって得たフィードバックが影響して、また自分たちだけの作業のときに新しい作品ができる。それで活動が上手く回ってきたところはありますね。コラボレーションは、非常に勉強になるし、活動のモチベーションにつながっている気がします。
違う形式を持っているとか、新しい視点を得たいというのがコラボレーションする強い理由だと思うんですが、そうすると、近い価値観を持っている人とはそういった形になりづらいのかな、と思います。実験にならない、といいますか。

似たような問題意識で活動しているとか、似たような何かを求めて活動しているアーティスト同士のつながりは大切にしています。近い価値観を持っていることがコラボレーションを否定する理由にもならないです。けれども、必要以上につながりを求めるようなことを積極的にやろうとは思っていないし、お互い一緒にやっていなくてもどこかでつながっているみたいな感覚があったりもします。というか、たぶんコラボレーションは完全なる実験ではないんですよね。
どういうことでしょうか。
正直な気持ちを言えば、圧倒的に確信があります。声をかけていただいてもお断りしているものもあるし、企画段階で形にならないものもあって、それは逆に絶対にうまくいかない、という確信がある。普段の作曲においてもそうなんですけど、ルールとか方法論の話も含めて、僕たち、実はめちゃくちゃ感覚的にしかやってないんですよ。最初は絶対、なんとなくから始めるんです。だからバンドや〈外〉の運営においては、直感とか、感覚とか、根拠ない確信とか、そういうことが一番の基準になっていますね。

You May Also Like
WRITER

- ライター
-
1997年生まれ、みずがめ座。西荻窪|成城|祖師ヶ谷大蔵
OTHER POSTS
カルチャーWEBメディア NiEW(ニュー)、Musicman、ANTENNA等で執筆。