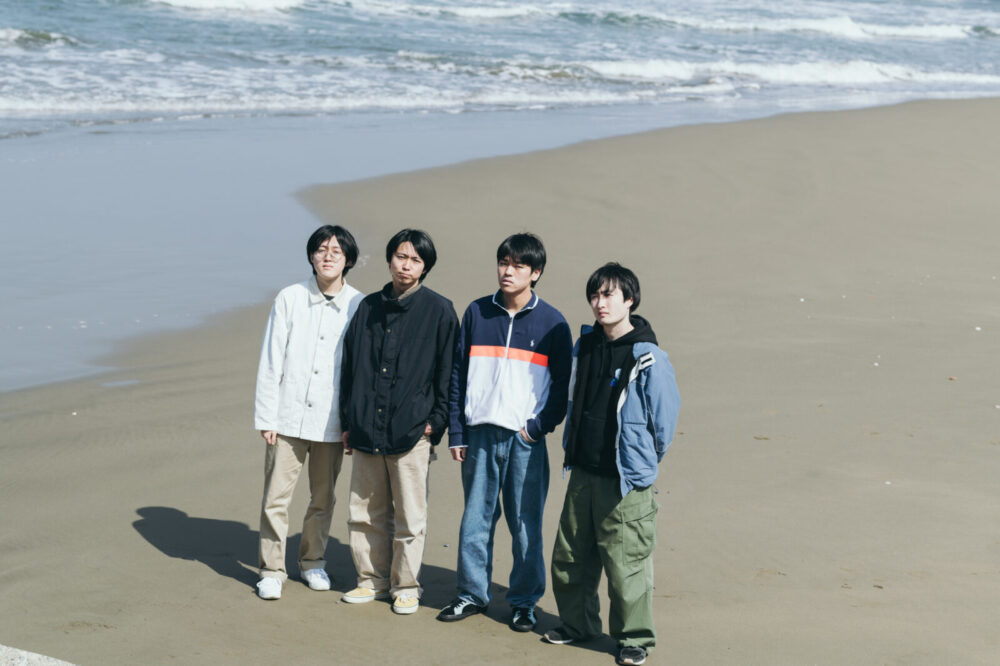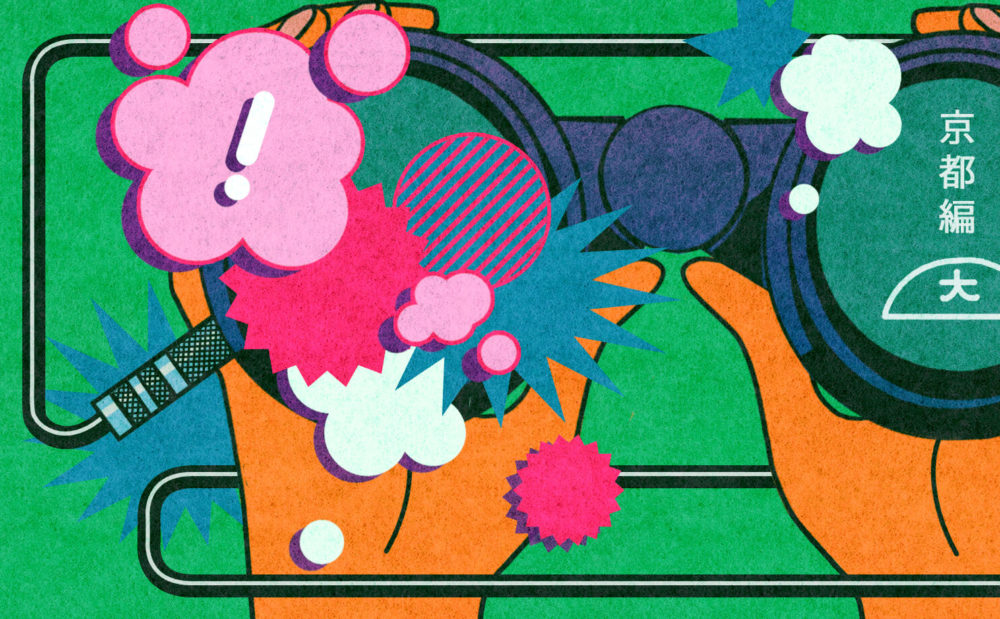ターニングポイントは『るろうに剣心』。映画のまち京都で、時代劇のつくり手と奮闘する映画祭のはなし
映画ファン、製作者、マーケットの3方向を見据え映画文化を盛り上げようという『東京国際映画祭』、山形市の市制100周年記念行事として開催され地域の文化行事として成長した『山形国際ドキュメンタリー映画祭』、アジアを中心に独創的な映画作品を紹介することを目的に運営されている『東京フィルメックス』など映画祭によってその成り立ちや目的はさまざまである。今回、京都のまちの映画祭として取り上げるのが『京都ヒストリカ国際映画祭』だ。時代劇というコンテンツに特化したこの映画祭の成り立ちにはどのような人たちが関わっていたのだろうか。
『京都ヒストリカ国際映画祭(以下、ヒストリカ)』が誕生したのは2009年のこと。2000年代から加速した時代劇の需要減少や京都をロケ地とした2時間サスペンスの相次ぐ打ち切りにより低迷した京都の撮影所の活性化が発端となっている。日本映画の黎明期から京都の映画産業の礎となってきた撮影所存続の危機に最初に声をあげたのは現京都府副知事の山下晃正さん。その後、京都の映画産業を守るべく行政が主導しつつ、京都の映像文化をアーカイブしてきた〈京都文化博物館〉の森脇清隆と〈東映京都撮影所〉の髙橋剣、〈松竹撮影所〉の井汲泰之が協力して立ち上げた映画祭である。
そんな行政や現場となる撮影所とは異なる立ち位置で立ち上げから運営に携わっていたメンバーがいる。それが今回取材を行った板倉一成さんだ。実は、京都で映画の仕事がしたいと思っていたが、受け皿となるような会社は撮影所ぐらいしかない。そこで、映画という仕事に折り合いをつけて、京都で友人とともに広告制作会社を立ち上げたという。そんな彼が『ヒストリカ』の運営に関わるようになり今年で15年になる。改めて『ヒストリカ』について振り返ってもらい話を聞く中で気づいたことは、京都にいながら映画の仕事を生み出せる余白がこの映画祭にあるということだった。

株式会社ディレクターズ・ユニブ 代表取締役
板倉一成
2008年に映像、Webサイト、グラフィックデザインなどの広告制作を手掛ける会社を京都市内に設立。京都ヒストリカ国際映画祭の運営には立ち上げから関わり、会社の事業として事務局運営を担っている。そのほかにも、京都クロスメディア推進戦略拠点の運営や2023年から実施されている京都で制作された作品や京都の映画製作に関わる功労者を賞する『京都映画賞』の事務局なども行っている。
京都の映画文化を支えた時代劇のために。つくり手に向けた映画祭を
板倉さんの立ち上げた広告制作会社は、映画とは直接的には関係のない仕事だった。なのに、なぜ映画祭の運営に参加することになったのか。そのきっかけとなった人物が〈京都文化博物館〉の森脇さんだという。
「実は『京都国際学生映画祭※1』で実行委員や事務局の仕事をしていたこともあり、学生の頃から森脇さんにお世話になっていたんです。2008年に友人と二人で広告制作会社を立ち上げることになったんですが、同じタイミングで撮影所を活性化させるために海外の人を交えて撮影所でワークショップをするので手伝ってもらえないかと森脇さんに声をかけてもらったことがきっかけで、今に至っています」
このワークショップを実施する時に参考にしたのが『ベルリン国際映画祭』が行っている若手向け人材育成プログラム「ベルリナーレ・タレンツ」である。第一線で活躍するプロから映画製作のためのノウハウを学べ、ネットワーク構築の機会を得ることができるというプログラムなのだが、これを参考に撮影所の利点を最大限に活用し、国内外の若手が時代劇を製作するノウハウを学べるワークショップを行った。
※1 京都国際学生映画祭:1997年からはじまった、京都を中心とする関西圏の大学生が主体となり企画・運営を行う日本最大規模の国際学生映画祭。学生が制作した自主映画を世界各地より集めて、実行委員が審査をし、上映する機会を作り出して、未来の映画人を担う人材・才能の発掘を目的とし、毎年2月に行われている。

京都で映画をつくってきたことで蓄積されたノウハウが撮影所にはある。それを海外に向けて発信することが時代劇にとって追い風になるのではと考えたのだ。これが現在も『ヒストリカ』で実施されている「京都フィルムメーカーズラボ※2」である。そして、このワークショップをきっかけに、翌年に映画祭をつくろうという流れになったという。ワークショップが原点ではあったが、映画祭へと形態が変わっても目的は変わらなかったと板倉さんは話す。
「前身となったワークショップもそうでしたが、(私たちは)つくり手に向けた映画祭をやりたかったんですよね。2009年から3回は、国際映画祭とは言わずに『HISTORICA』という名のイベントとして実施しました。撮影所で活躍されている技術の方に登壇してもらったり、撮影現場のようにガンガンで暖をとりながら、撮影所の助監督の方と一緒に運営もしていました。それこそ撮影所のセットを会場に、バーベキューで打ち上げをしたことなどは、今でも語り草になるぐらい最高の思い出です。あくまで、撮影所、時代劇という軸は変えず、映画制作の延長にあるような熱気が、観客だけでなくつくり手も楽しんでもらえた映画祭だったという実感があります」
※2 京都フィルムメーカーズラボ:国内外の映像制作に携わる若手が集い、一流監督・映画人の指導を受け、京都の撮影所で時代劇の短編映画製作を体験、映画関係者との交流もできるワークショップ。これまで、世界51カ国、430名の若手作家が参加(2023年8月現在)。また、『東京国際映画祭』や『ビエンナーレ・カレッジ・シネマ』との共催で多彩なゲストを講師として招聘する「マスターズ・セッション」も実施している。
時代劇のターニングポイント、2012年に国際映画祭へ
つくり手のためにはじまった『ヒストリカ』だったが、転換点となったのが2012年。この年から現在の『京都ヒストリカ国際映画祭』へと名称を変更し、会場も松竹や東映の撮影所だけでなく〈京都文化博物館〉や〈京都シネマ〉など市内の映画上映ができる文化施設へと広げていった。どのような流れで、この変化の波が起ったのだろうか。
「4回目を迎えるタイミングでもっとお客さんに向けて歴史映画をプレゼンテーションしようという動きが生まれ、より多くの海外の作品を紹介しようと考え、国際映画祭と名乗るようになりました。〈京都文化博物館〉を会場として使うようになったのもこの時からです。それまではその年にできた新しい時代劇を集めてきてみんなで観るみたいなノリでしたが、海外の新作歴史映画を上映する「ヒストリカ・ワールド」やテーマに基づいた作品を選ぶ「ヒストリカ・フォーカス」のような部門的なプログラムができて、今の映画祭のベースができたのもこの年でした」
2011年に42年間続いた国民的時代劇ドラマ『水戸黄門』の放映が終了。時代劇のレギュラーが大河だけになるという事態も、『ヒストリカ』を通じて海外へ時代劇を発信したいという動きに拍車をかけたといえるだろう。そんな時代劇にとってどん底ともいえる状態から潮目を大きく変えたのが、観客動員200万人を突破、興行収入25億円越えを記録した2012年公開の『るろうに剣心』(大友啓史監督)だ。
映画『るろうに剣心』予告編 2012年8月25日公開
「2012年に『るろうに剣心』が公開されて潮目が変わった。この作品は映画というジャンルで時代劇をアップデートし、国内外で受け入れられている好例だと思います。これまでは日本のマーケットに対して作られてきた時代劇を、正面から世界に向けて時代劇を作っている点がやはり一番大きいでしょう」と板倉は話す。時代劇映画のイメージをアップデートする作品の登場やクロスメディア的な視点から、世間の時代劇の印象も変化する中で『ヒストリカ』もプログラムも整理され、会場も街へとひろがり視点が外へと向かっていったのだ。それ以外にも、最近ではゲーム、アニメ、マンガなどのクロスメディア的な視点からも活路が見えてきたという。
「毎年20名(現在は40名)の国内外の若手のみなさんとフィルムメーカーズラボを通して交流したり、海外で歴史映画を作っている監督などを映画祭で招聘し交流する中で、改めて日本の時代劇はリスペクトされていることを感じ、若い人であれば、アニメやゲームなどに変化しつつも十分に文化として受け入れられていると感じました。最近では時代劇専用チャンネルが海外にも顧客を開拓しているのですが、これまでの日本の時代劇(日本のマーケット向けに作られていたテレビ時代劇)なども、海外でかなり受けているという話を聞くようになりました」

成長したから気づいた、若手が育っているという手応え
時代劇の大きな転換期に大きな舵をきった『ヒストリカ』は、「時代劇」をテーマに地域を巻き込みながら企画を拡張。撮影所で自分の作品企画を映像化できるコンテスト『京都映画企画市』、アニメ・漫画・ゲームなどの歴史劇コンテンツのキャラクター限定のコスプレイベント『太秦上洛まつり』、映画制作に関わる最新の手法を探求するシンポジウム『HISTORICA XR』などが連携企画として実施された。この15年、時代の流れをつかみ取りながら成長してきたように見えるが、現場を見てきた板倉さんはどのように感じているのだろう。
「時代劇のムーブメントに『ヒストリカ』がカンフル剤的な役割を担えたかという正直、僕らとしては実感がないですね。それよりも時代劇が取り巻く状況が変わってきたところに、必死でついていってるという方が強いかもしれません。一つ言えるのは、映画祭だけでなく若手育成を担っているフィルムメーカーズラボや企画市に来てくれる人たちのネットワークは広がっていて、その中から映画監督になるようなケースも出てくるようになりました。『ヒストリカ』のプログラムに『カムバックサーモン・プロジェクト』というのがあるんですが、過去のフィルムメーカーズラボの参加者がこの場所に戻ってきて、長編作品を上映するみたいな企画も行っています」
まだ道は半ばだと語る板倉さんだが、昨年は過去に『京都フィルムメーカーズラボ』に参加したことがあるという前田直樹監督の『マリッジカウンセラー』(2022年)が『カムバックサーモン・プロジェクト』の事例として上映されるなど、若手育成の手応えを感じる企画も実現している。

若手育成が撮影所と『ヒストリカ』にもたらした変化
このような若手育成の取り組みができたのも、京都に撮影所という現場があったからこそ。そして、『ヒストリカ』を行うことで撮影所にも変化があったと板倉さんは感じている。
「撮影所ってすごいハードルが高い(場所だ)と思っていたんですが、高橋さんが門を開けてくれて、入れよって言ってくれたおかげで僕らみたいな人が気軽に伺えるようになった。そういう意味では撮影所自体がだいぶオープンになったんじゃないかな。僕が撮影所に行くようになってから15年経ちますけど、〈東映撮影所〉に行くと〈VRイノベーションアカデミー京都〉というVRを学べる会社が入ってたりとか、昔では考えられないような状況になっている」
板倉さんが挙げてくれた事例以外でも、〈松竹撮影所〉の施設内に立命館の映像学部学生実習用の撮影スタジオができたりと、若手や新しい技術との接点が撮影所自体にも増えてきている。そこには、行政を含めこの地で映画産業に関わる人たちの京都の映画産業をアップデートしたいという強い想いがあるようだ。
「いろいろアップデートしているんですが、やっぱり、京都のこの苦しい状況を変えていくのって人なんだろうなと思っていています。そういう意味で、外国人の方や若手の人たちが撮影所の中の助監督の人たちと交流することでお互いに刺激になってくれたらいいなと思っています」

撮影所の変化について語ってくれた板倉さんだが、『ヒストリカ』自体の目的も「国際映画祭」を名乗りはじめた頃から変わってきているという。
「例えば、去年は上映プログラムでは三池崇史監督に来てもらって『無限の住人』の上映もしましたが、若手の人たちのディスカッションを中心のプログラムを組んだり、映画祭の見せ方も人材育成よりにシフトしていきたいと思うようになりました。今は最新の映画を上映するというよりは、若い人たちや、製作者に来てほしい。原点回帰じゃないですけど、一番最初に志してたような形に戻ってきてる感じ。映画祭としてはマーケットに良い影響が出てきたかっていうよりは、人に作用できてるような気がしていて。実際に若い人たちが育ってきてるっていう実感はこの映画祭を続けてきた中で一番の手応えじゃないかなとは思っています」
学び場としての映画祭、企業としてのこれから
ここまで『ヒストリカ』の話をしてきたが、この映画祭をきっかけに板倉さんの会社の事業にも変化があった。例えば、映画・映像の字幕翻訳についてオンラインで学べるONSTA(オンスタ)の運営や、昨年新しく発足した「京都映画賞」の事務局の運営など、広告制作以外に映画に関わる仕事も増えているという。振り返れば板倉さんにとって、映画祭は自分自身の学び場にもなっていた。
「私の会社も7月22日で15周年になります。会社を始めたときに、広告制作で生きていこうかなと思ったけど、京都にいながらでも映画の仕事ってやれることってたくさんあるなって思えるようになりました。映画祭を通して、学んだことはいろいろありますが、その一つが海外から映画を買い付けるノウハウです。一つは『ヒストリカ』の作品でもあったコロンビアの映画『彷徨える河』。そしてもう1本は、『ポップ・アイ』というタイの映画を東京の配給会社トレノバと一緒に買い付けて日本のミニシアターで公開しました。動けば映画に関われるということは、自分が働くモチベーションになっています」

そんな流れを経て、今増えている仕事が映画に関連する人材育成の仕事だという。これから事業として取り組みたいことを伺うと、人、コト、モノをつなげて、何か新しいネットワークとか価値がつくっていけるような仕事を会社としても、自分としてもやるべき仕事だと熱い思いを語ってくれた。
この街には余白がある。つくり手の街として京都発の面白い作品を
「実は、『ヒストリカ』を立ち上げる時にサウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)のような、いろいろな(業界の)人たちが集まってくれる、既存の映画祭にとらわれない映画祭にしたいという話を東映の髙橋さんとしていたことがあったんです。映画祭っていうと、敷居の高さがすごいある気がしていて……。これまでそれを下げるという試みができていなかった。もっといろんなところに拡張していけば、時代劇って関わる余白ってたくさんあると思っています」
時代劇にはまだまだいろんなジャンルの人たちと関わり合える余白があると話す板倉さんが映画祭をする上で大切にしているのは、京都という街から新しい作品を生み出すということ。
「京都的な文脈で話すと、ゲーム会社やアニメーションの会社もあったりして、映画や映像に近しい分野の人たちがたくさんいる。そういう人たちも絡みながら新しいものづくりのきっかけになるような映画祭になりたい。やっぱり、つくり手の街っていう自負はどっかにはあるんだろうなと思っていて、だからこの先10年、20年、京都から新しい作品が生み出すことができる土壌をつくれるような、映画祭であってほしいと思う」とこれからのビジョンについて話してくれた。そして今、次回の開催に向けて、映画の上映関係なしに面白そうと来たくなるゲストだったり、新たなカンファレンスやトークセッションなども増やそうと、ビジョンをカタチにすべく奮闘している。

成長を続けてきているように見える『ヒストリカ』ではあるが、映画祭だけで産業として成り立たせることは簡単ではない。例えば『広島国際アニメーションフェスティバル 』や『アジアフォーカス・福岡国際映画祭』のように運営母体の影響を受けて残念ながら幕を閉じてしまう映画祭もある。だからこそ映画祭を足掛かりに、アニメやゲームなど時代劇が接続できる異文化へと拡張しながら映画産業にコネクトできる人材を広げようとしているのだ。そしてその余白が板倉さんの仕事を生み出す原動力にもなっているようにも思えた。この余白が生まれるのも、京都という街に多種多様な文化が育つ土壌があるからなのではないだろうか。

京都ヒストリカ国際映画祭
2009年からはじまった「歴史映画」をテーマに京都にて毎年開催している国際映画祭。傑作時代劇はもちろんのこと、世界中からあつめた最新の歴史映画や、国内外の映画祭と連携した作品の上映などを行っている。
Webサイト:https://historica-kyoto.com/
You May Also Like
WRITER

- 編集者 / ライター
-
奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。
OTHER POSTS