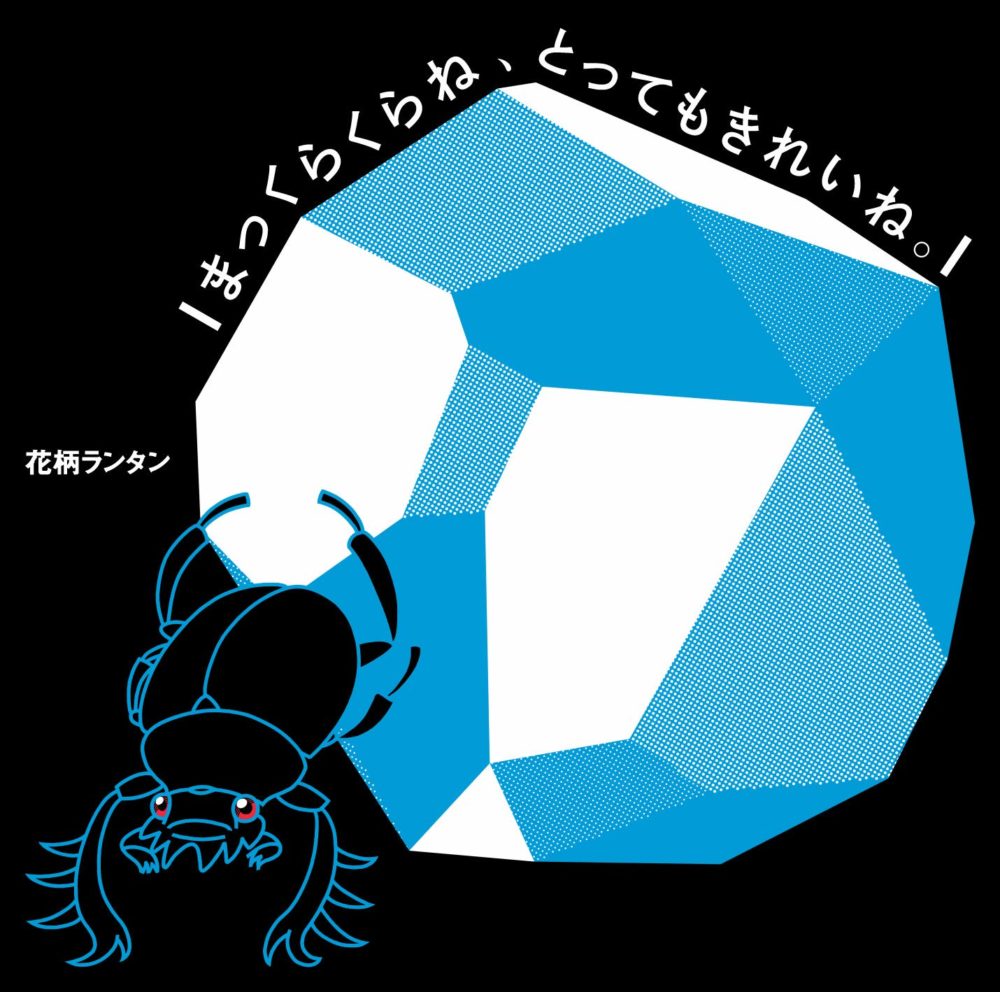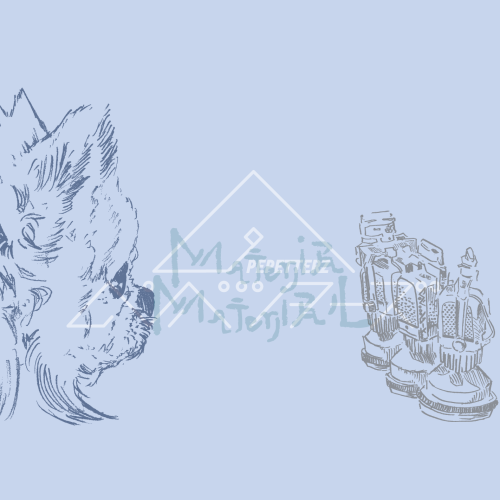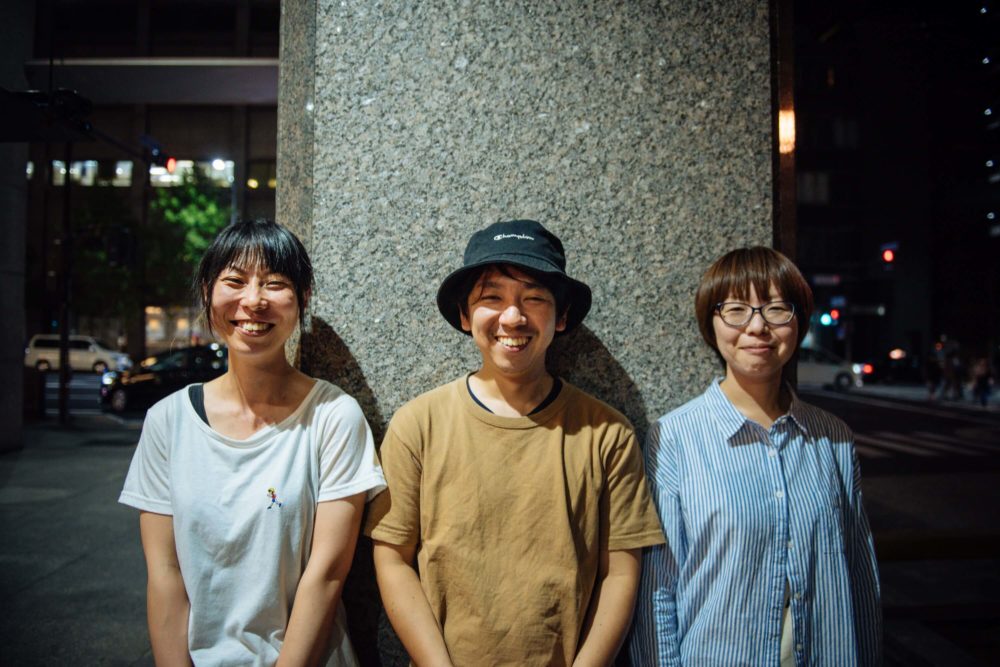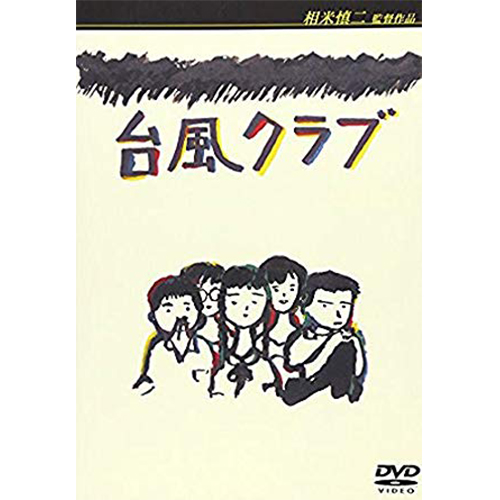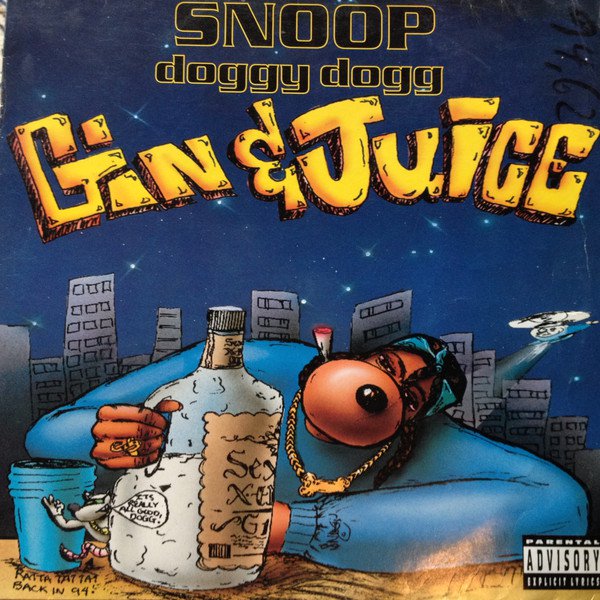マーガレット安井が見た第2回うたのゆくえ
今回で2回目になるライヴイベント『うたのゆくえ』。京都三条VOXHallで開催され、2日間で全30組以上の出演者が熱演を繰り広げ、大盛況のうちに終了した。私もほぼ全てのバンドを観たが、どのライヴも素晴らしく印象に残っている。中でも素晴らしかったのは『うたのゆくえ』2日目の大トリを飾った折坂悠太だ。
折坂悠太
メンバーにyatchi(Pf / ムーズムズ)、宮田あずみ(Ba / かりきりん、Colloid)、senoo ricky(Dr)と現地で活動するバンドマン、アーティストたちが〈重奏〉編成のメンバーとして参加し、折坂自身も京都に1週間滞在して臨んだ今回のライヴ。
まずは重奏メンバーのジャム・セッションから去年話題になった“平成”を演奏。ゆったりとしたビートから、折坂の浪曲や河内音頭を咀嚼して生まれる土俗的な節回しが心地よく会場に響く。その後、折坂のこぶしを利かせた歌とジャジーなセッションとの掛け合いが気持ちいい“みーちゃん”が演奏されたと思えば、“揺れる”ではとつとつと一語、一語をかみしめながらエモーショナルに歌う。
折坂のライヴを観るのは初めてだったが、歌声のダイナミクスの素晴らしさに舌を巻いてしまう。折坂の歌声は、どんなに張り上げてもうるさくなく、優しく語りかけても会場の隅々まで届く。だからこそ、重奏、合奏、独奏、と彼を支えるバンドの形態が違えど、会場のキャパシティが違えど、観客の胸を打つ歌を聴かせるのでは、と感じた。アンコールでは2016年のアルバム『たむけ』から“よるべ”を披露。『平成』というアルバムを出した平成元年生まれ、平成育ちの彼の歌声は、3月31日という新元号が発表される前日において、観客の心の中にいつまでも響いたに違いない。

素晴らしいライヴを見せてくれた折坂悠太だが、ライヴのMCで気になることを言っていた。
「最近、うたのゆくえについて考えるようになった。」
「うたはどこへ行くのか」なんか、今まで考えもしなかったが、いざ考えると難しい。なぜなら「うた」は私たちの心をゆさぶりながらも、目には見えない。そのため「何処で生まれ、何処に消えてしまうのか」という疑問の答えは、見えるかたちでは証明不可能だ。だけど何となく、この可視化できない“うたのゆくえ”がイベント2日間を通して分かったような気がする。
観客のゆくえ
私はよく大阪・心斎橋のライヴハウスや野外フェスに足を運ぶ機会が多いが、今回の『うたのゆくえ』に集まった観客は普段そこで見かける層とは違っていた。若者だけでなく、年齢層が高い観客も多く、ライヴハウスではあまり見かけない小さな子供を連れた家族連れも沢山みられた。
もちろん京都のライヴハウスが、心斎橋のような着飾った若者たちが遊ぶ“街の遊び場”に集合したような作りではなく、ごく一般的な住宅街やビル街にあり、場所的な敷居の高さがなく一般のお客さんにも入りやすい環境であることも原因だし、出演者がオルタナやパンクといったジャンルで集められたわけではなく“うた”という間口の広いテーマで集められたのも理由の一つであろう。
言い換えれば「うたが普段ライヴハウスへ足を向かわないお客さんを呼んだ」ともいえるし、うたはジャンルの垣根を超えて愛される存在だと言えるのではないだろうか。そんな普段ライヴへ行かないお客さんに対し「僕の音楽は特殊なんで、なれていない人は気をつけてください」とリハーサルで何度も言っていた人がいた。大阪で難波ベアーズというライヴハウスを営み、うたについてこだわり続けている人、山本精一である。
山本精一&THE SEA CAME
西滝太(Key)、Senoo Ricky(Dr)を交えた、山本精一の新しいバンド、山本精一&THE SEA CAME。新しいとは言え、この3人は以前にも山本精一&くいだおれや、山本精一&中庸フリーウェイなど名称を変えて、何度も共演していることもあり、息の合ったアンサンブルを観客に届けてくれた。
まず1曲目は山本精一2011年のアルバム『ラプソディア』から“ラプソディア”。山本の優しい歌声と緩やかなメロディーが流れる中で、その流れを断ち切るかのような山本のノイジーでエモーショナルなギター・ソロが入り、会場の観客は虚を衝かれた感覚に陥る。次に演奏した“Days”ではハード・ロックのような冒頭からスッと演奏が落ち着き、山本のやわらかな歌声が会場に響く。危なっかしさと優しさが表裏一体のバランスで演奏される山本の演奏を聴きながら、〈羅針盤時代の山本精一〉のことを思い出していた。
山本の長いキャリアの中でボアダムズの時代は世の中の不条理をノイズに託し、羅針盤ではノイズと山本の持つうたを焦点に合わせてきた。羅針盤以降はうたではなく音響(アコースティック)へ、2010年に入って今度はうたへ照準を置き始めたように感じる。ところが今回の演奏を聴く限り、必ずしもうたの方向によっていると思わなかったし、山本いわく一番ポップなアルバムである『童謡(わざうた)』(2015年)のナンバー“ゆうれい”もライヴで演奏されたが、そこには音源にはなかったノイズが薄くかぶさっていた。
「うたとノイズの融合、それは羅針盤時代の山本精一なのでは」と思った矢先に「最後に羅針盤の“ソングライン”を演奏します」と言う山本。10分近く演奏された“ソングライン”は、優しい歌声と熱量高く演奏されるバンドサウンドだ。終盤には眼鏡を飛ばしながらギターをかき鳴らす山本の姿もあり、演奏終了後には観客からの大きな拍手が巻き起こった。
ラッキーオールドサン
2日目は山本精一と折坂悠太の演奏に胸を打たれたのだが、1日目3月30日の中で最も驚いたのがトリを飾ったラッキーオールドサンだ。バンド編成のラッキーオールドサンは以前にも観てはいたが、今回は田中ヤコブ(Gt / 家主)、渡辺健太(Ba)に加え、岩出拓十郎(Gt / 本日休演)、西村中毒(Dr / 渚のベートーベンズ)とニューアルバム『旅するギター』を録音したメンバーでの出演。1曲目からアルバム表題曲“旅するギター”を演奏。以前よりもアンサンブルに厚みもまし、そこにナナの優しく純粋な歌声が会場を包む。
以降、“夜は短し”や“ワンモアチャンス!”などニューアルバムの曲が続く中で、徐々にこのバンドの新しい本質が見えてきた。以前までのラッキーオールドサンはウィルコ以降のUSオルタナティブカントリーと、日本の歌謡曲のもつキャッチーさを音楽の中に落とし込んでいた。だから彼らの楽曲はどこかなつかしく、微笑ましさが滲み出ている。しかし岩出拓十郎と田中ヤコブのツイン・ギターが参加したことによって、微笑ましさにプラスし、エモーショナルでロックなサウンドが拡充された。新しいラッキーオールドサンを観客に提示するライヴとなった。
特に本編ラストで演奏した“Rockin’ Rescue”では終盤で田中ヤコブのソロから、岩出拓十郎が呼応。それがメンバー全員に伝播し、優しくも、開放的でエモーショナルなサウンドスケープで会場を席巻。「俺たち今、凄いヤバい演奏聴いている…」と演奏がまだ終わらぬまえからザワザワと観客の声が聞こえ始め、演奏終了後には観客の歓声と鳴りやまぬ拍手。アンコール中も至る所から「ヤバい」という声がちらほら聞こえるステージとなった。

うたのゆくえ
山本精一、ラッキーオールドサン、折坂悠太。実はこの3者はあるワードで共通している。それは〈生活〉だ。例えば山本精一は羅針盤終了から5年ぶりにうたもののアルバム『PLAYGROUND』(2010年)を出した際に、インタビューで本作は「自分の部屋のなかと、半径500メートルくらいまでの範囲」を意識して作ったと語っていた。このことから考えると、生活があるからこそ山本はまた〈うた〉を歌えたと思えてくるし、『PLAYGROUND』以降の山本のうたは生活感が滲み出ていたように感じる。
ラッキーオールドサンも生活に密着している。例えば“旅するギター”のように突飛なことが起きない、生活の一場面を切り取ったような歌詞が魅力であるし、なにより彼らはバンドであり、夫婦でもある。
では〈うたはどこに向かうのか〉と疑問を呈した折坂悠太はどうか。“平成”はあるライヴでニーナ・シモン“I Loves You Porgy”に自分なりのメロディとうたを装飾して、“日付”を交えて歌った体験が印象に残っていたことから生まれた曲である。また歌詞においても“みーちゃん”では彼の姉について、“ゆれる”は東日本大震災が起きた時に考えていたことについて歌われている。つまり彼もまた自分の生活の範囲で楽曲を作り出している。

思えば今回のイベントでは自分の体験からうたを作り出してきたアーティストが多かった。小雨降る中で演奏していた石指拓朗の“武蔵野”は吉祥寺近辺の風景が目に見えるような演奏で、うたのゆくえ1日目トップバッターを飾った台風クラブはロックンロールなサウンドに合わせて、やさぐれ男の生活が抒情的にうたわれていた。また、青空の下“サンキスト”や“サマータイム”を自然体で演奏していた東郷清丸。彼の“サンキスト”は20代の頃のバイト経験から生み出された曲であり、彼もまた生活の中でのタイムリーな出来事を歌にしているアーティストであろう。
〈素直さ〉という点では、心優しき悪童である四万十川友美も忘れられない。今回はbest friendsでのライヴとなったが、時に会場中を縦横無尽に暴れ回り観客を圧倒し、時に誠意をもって会場の一人ひとりに歌を届ける姿勢に胸を打った。そしてMCの中で、昔いじめにあったことを告白し、そこから最新シングル“いじめ”を披露。明るいバンドサウンドの中で、いじめを否定せず男と女、仕事が出来る人と出来ない人、と同列でいじめる人といじめられる人、と歌われる。その歌い口は現代における多様性を歌っているようで、私の心に深く突き刺さった。




私はこのような自身の体験を歌うアーティストたちを見て、うたのゆくえは「私たちの生活」に直結するのではないかと感じた。「うたのゆくえ」に出演したバンド、アーティストたちはどれも自らの経験をうたというものに閉じ込めて、観客へ提示した。そして経験からでている以上、その言葉には嘘が見られない。谷川俊太郎がその昔に「現実を直視せず前向きな言葉ばかり使えば、歌は単なるきれいごとになる」と言ったのだが、まさにこの言葉の通り。本心から出ない言葉よりも、生活の中での体験から生み出された言葉の方が説得力が増すのだ。
では生活で生み出されたうたは、何処へ行くのか。それは私たちの耳に入り、心の中に刻み込まれ、ある時は勇気づける活力になり、ある時は悲しみを慰めたりして、生活の中でゆっくりと消費される。そして消費される中で、人によっては生活の中で新しい「うた」を生み出だすし、人によっては新しい「うた」を発見するかもしれない。つまり私たちが生活をする限り、うたは生活の中で循環していくのだし、生活が無くならない限り、うたは永遠にあり続けるものではないか。そんな「生活」と「うた」の関係性のように『うたのゆくえ』も何年でも、何十年でも続けてほしいと感じる。
You May Also Like
WRITER

- ライター
-
関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。
OTHER POSTS
toyoki123@gmail.com