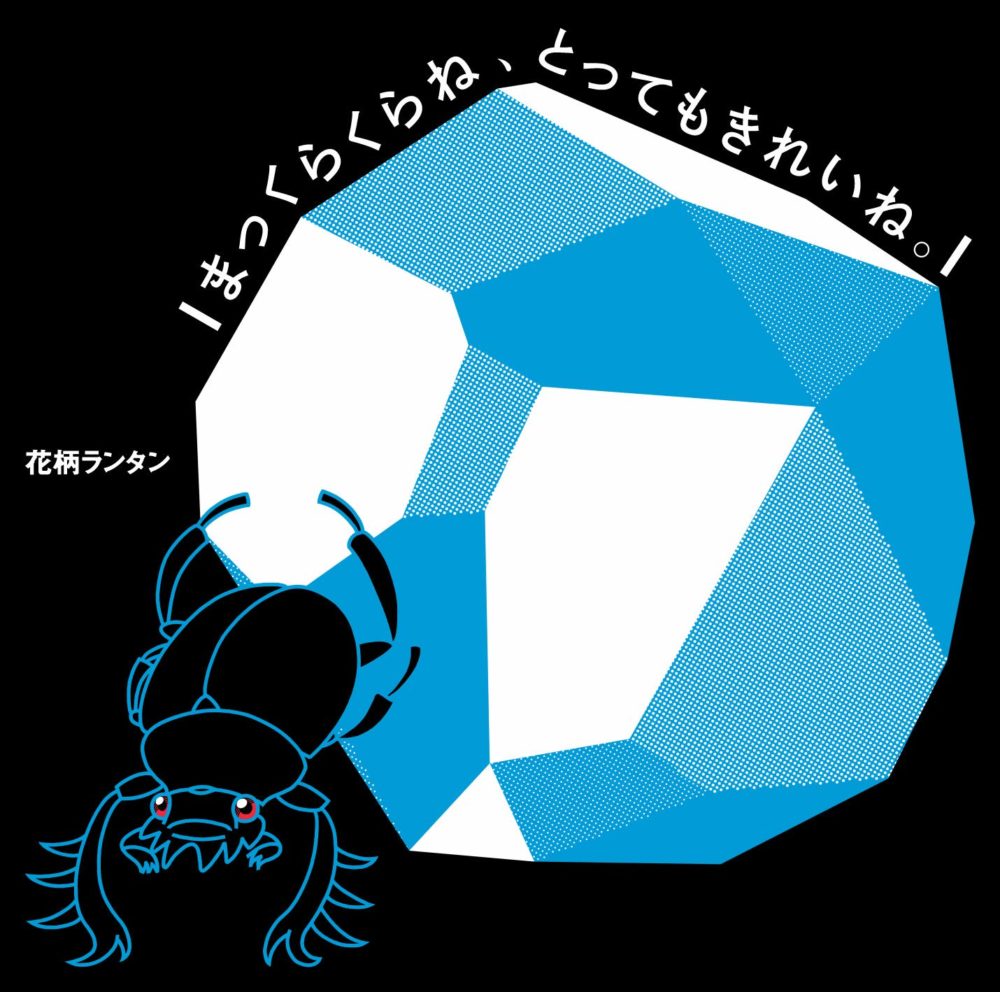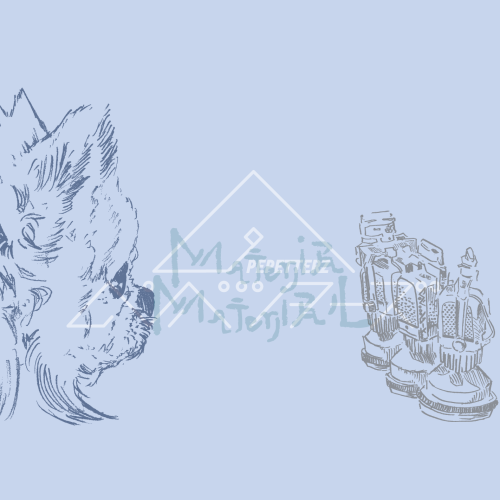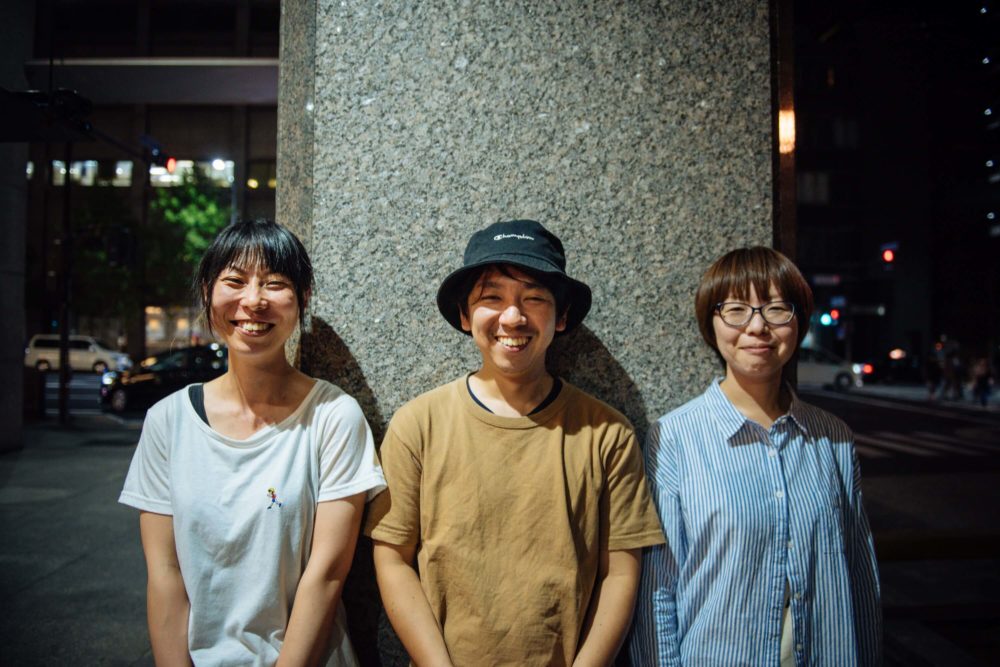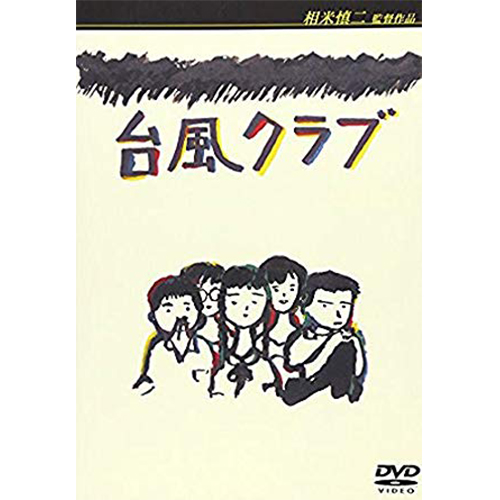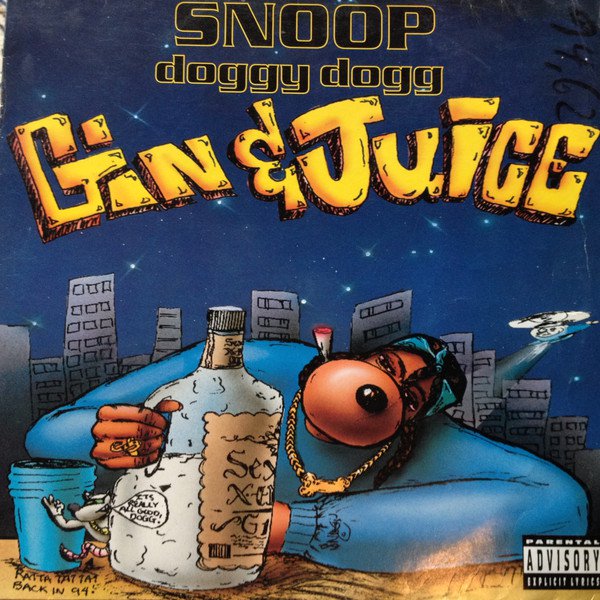ボロフェスタ2023 Day1(11/3) – 蓄積で形成される狂気と奇跡の音楽祭
今年22年目の開催を迎えた、京都のフェスティバル『ボロフェスタ』。今年は11月3日~11月5日の3日間に渡って〈KBSホール〉、また4日の夜には〈CLUB METRO〉で開催された。2014年から毎年ライブレポートを掲載してきたANTENNAでは今年も編集部あげて総力取材!ライター独自の目線でボロフェスタを綴っていく。本記事では初日の11月3日の模様をハイライトでお届けする。
トラブルさえも面白さに変えるフェス
いつも楽しみにしていた『ボロフェスタ』の名物、まーこおばちゃん※のドライカレーが今年で最後になるらしい。話を聴いたところ、どうやら来年は違うメニューを出すらしく、まーこおばちゃんがボロフェスタからいなくなるわけではないとのこと。ホッとしたのと同時に、よくよく考えるとこれだけ年月が経てば何があってもおかしくないなと感じる。〈京都大学西部講堂〉で始まった『ボロフェスタ』も、気がつけば今年で22年目。その間、東北で大きな地震が起き、元号が平成から令和へと変わり、新型コロナウイルスという未知なる病原菌が生まれた。
22年あれば何か変わる。だからこそ同じマインドを持ち続けて1つの物事に取り組むのは大変な努力がいることだ。DIYでの運営を貫き、ボランティア・スタッフが主体となり、ゲリラ的なイベントを次々と行いながら化学変化を楽しむ。アクシデントを嫌うイベント業界において、リスクを背負いながらも、それすらを面白さへと変えてやろうとする『ボロフェスタ』のマインドは狂気であり、それを22年も続けることは、もはや奇跡とも言える。

だがそれも長年、トライ&エラーを蓄積し続けたからこそできることだと考える。今年は主催者の一人であり、パーティーナビゲーターのMC土龍が『スーパーマリオブラザーズ』のマリオに扮して、『THE FIRST SLAM DUNK』ばりのフリースローをするというオープニングからスタートした『ボロフェスタ2023』の1日目。その中で「経験の蓄積」を感じられるライブを数多く観た。
※杉浦真佐子:MC土龍が店長を務める〈livehouse nano〉のオーナー
活動し続けることで得られた武器と境地(フリージアン、Superfriends)
神戸のバンド、フリージアンが『ボロフェスタ』に初見参。ライブ冒頭、マエダカズシ(Vo)が“仰げば尊し”の一節をアカペラで披露。その歌声に、彼ら目当てではなかった観客も足を止めて、ステージへと視線を向ける。そして会場いっぱいにロック・サウンドを轟かせれば、もはや〈KBSホール〉は彼らの独壇場だ。“Mayday”、“ノンアルコール”と、水を得た魚のように、瑞々しくも重厚感のある音楽が観客のもとへと届けられる。そのサウンドに感化されたのか無数の拳が挙がり、どんどんヒートアップしていく。
結成は2021年だが、メンバーのキャリアとしては10年以上の長きにわたり関西のインディーズシーンで活動しているフリージアン。今回のライブで披露された“お願いダーリン”や“悲しみの全てが涙ならば”は、マエダが10年前に所属していたバンド・逢マイミーマインズ時代の楽曲だ。だが今の方が多くの人に突き刺さっているように感じる。それは10年の間に培われた感情や技量が楽曲に反映され、より厚みのあるものへ仕上がったからだ。彼らに熱狂した観客を見ながら、活動をし続けることの重要性をひしひしと感じた。
活動し続けるという意味では、〈街の底STAGE〉に登場したSuperfriendsも忘れてはいけない。結成18年目にして初の『ボロフェスタ』出演。開始早々“Let go”、“My Donna”といったナンバーを披露する。アメリカのオルタナティブやインディーの空気をいっぱいに吸い込んだサウンドが、街の底を温かく包み込む。気負いせず、自然体のままでライブをする姿に、会場からは自然と手が上がったり、曲を口ずさんだりする観客も見られた。
ハイライトはラストで演奏された“1994”であろう。バンドのソングライターである塩原(Vo / Gt)が最も敬愛するバンド Weezerへの偏愛を詰め込んだこの曲。演奏されるやいなや歓声が上がり、シンガロングが沸き起こる。 以前塩原にインタビューした際に、Weezerに憧れてバンドをやろうとしたが目指していた音楽にならず、以降パワーポップからはみ出し続ける楽曲を作ってきたと語っていた。そんな彼らが自分の敬愛するバンドのことを、パワーポップで歌う。それもまた18年という歳月を経たからこそ、歌えているのではないかと感じた。
参照点の先に獲得した、オリジナリティー(The Slumbers、幽体コミュニケーションズ)
活動年数こそ短いが、さまざまな蓄積が音楽へと反映された若手バンドも多数登場した。その一例が〈街の底STAGE〉に出演したThe Slumbersであろう。
その音が会場になり響いた瞬間「なんて、いぶし銀のバンドなのだ!」と驚いた。“レトロカー”、“ロマンス”など次々に繰り出されるサウンドは、サザン・ロックが持つ土臭さや、オルタナティブ・ロックの壮大さを兼ね備えている。さらに佐々木智則(Vo / Gt)の昭和歌謡的なこぶしを効かせた歌唱はサウンドとマッチし、まさに「日本のロックンロール」という言葉が最高に似合う音楽へと仕上がっている。特にライブの最後に演奏された“さらば、憧れ”はその真骨頂だと感じた。
その文脈はクリエイションやザ・ルースターズなどから連なるものではある。だが先人たちよりも派手さを狙わずに、じっくり腰を据えたロックを令和に鳴らそうとする姿勢はむしろ新しささえ感じてしまう。「ロックンロール歴史の美学を集積したバンド、それがThe Slumbersである」と言いたくなるようなアクトであった。
同じ理由で幽体コミュニケーションズも素晴らしかった。“巡礼する季節”や“幽体よ”などライブが進行するにつれて、その音楽に釘付けになる。アンビエントなサウンドかと思えば、ブレイクビーツが入り、ヒップホップに変化。かと思えば、いつの間にかトイ・ポップのようなカラフルさをまとい、気がついたら再びアンビエントな音楽へと回帰する。また繊細ながら浮遊感のあるpaya(Vo / Gt)、いしし(Vo)の二人の歌声はサウンドと溶け合い〈KBSホール〉全体を包み込みこむ。観客も変化してゆく幽体の音楽に、身を委ねながら体を揺らしていく。
彼・彼女らの音楽にも参照点みたいなものはあるとは思う。フィールド・レコーディングとヒップホップをミックスする形は口ロロの『everyday is a symphony』(2009年)。カラフルなポップサウンドはceroやトクマルシューゴ。アンビエントなサウンドと生楽器をあわせるのは2000年代のコーネリアスを思い起こさせる。だがこれらの要素を掛け算した結果、そのどれにも似ていない音楽として目の前にたたずんでいる。歴史の蓄積の末に生まれた、まさに異分子というべき音楽集団、それが幽体コミュニケーションズなのだと感じた。
長年のこだわりがバンドの強みに変化(Base Ball Bear、夜の本気ダンス)
『ボロフェスタ』も中盤に差し掛かり登場したのは、Base Ball Bear。まずは“17才”、“海になりたい part.3”と立て続けに軽快なサウンドを披露する。今年で結成22年。結成当初は4人で活動していたが、2018年より3ピースで活動。“17才”も、もともとは4人編成の曲ではあるが、今ではまるで3人のためにあるかのように仕上がっている。
22年あれば「変化をしよう」または「変化をせざるを得ない」という場面にぶち当たる。逆から言えば、柔軟に変化をしたからこそ今のBase Ball Bearがあるともいえる。“Endless Etude”では本来であればもう一人のギタリストが演奏するかのようなフレーズを、ルーパーエフェクトを使用することで、三人でも演奏できる楽曲へと仕上げる。またRHYMESTERとのコラボ曲である“The Cut”のラップパートは小出祐介(Vo / Gt)がライムする。この「いない」状況を逆手に取り音楽を作るという姿勢こそ、今まで活動を続けられた強みであるとライブを観ながら感じた。
ラストナンバーは代表曲“BREEEEZE GIRL”。楽曲中盤では舞台後方のステンドグラスが登場し、観客も大盛り上がり。22年目の強さを感じるライブであった。
夜と本気ダンスもまた、「バンドの強み」を感じさせるライブを披露していた。デビュー当初から「踊る」にこだわり続けて、素晴らしいダンスナンバーを生み出してきた。米田貴紀(Vo / Gt)が開口一番「踊れる準備はできていますか、京都!」の叫びと共に“WHERE?”からライブがスタート。会場全体を踊らせたなら、“LOVE CONNECTION”、“fuckin’ so tired”と惜しげもなく代表曲を乱打する。
結成15周年、現在もロックシーンの最前線に立つ。だがインタビューにて、コロナ禍を期に「踊るとは?」という原点に立ち戻ったと語っていた。もともと00年代以降のロックンロール・リバイバルやダンス・パンクなどを軸にしてきたバンドだが、コロナ禍以降はEDMやニューウェーヴなど今まで自分たちの文脈になかった踊れる音楽も取り込んできた。今回披露された“審美眼”や、水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミが制作に参加した“ピラミッドダンス”などは、「踊るとは?」ということを考えてきた夜の本気ダンスの答えだと感じる。
同時に、これらの曲が過去曲と並んだ時に「夜の本気ダンスの楽曲」として違和感がなく仕上がっているのは、それまで培われた音楽とEDM、ニューウェーブが上手くミックスされていることを証明している。自らの軸を崩すことなく、自身の音楽性を拡張し、徹底的に観客を踊らせる。「踊る」ということに対して、強いこだわりを感じさせるライブであった。
制約からの解放 水曜日のカンパネラが作り出す、あるべきライブの姿
「『ボロフェスタ』と相性のいいアーティストは?」そう質問されたら、まず挙げるのが水曜日のカンパネラである。同フェスの面白さは「予測不可能なゲリラ的な部分」に集約される。突然開始されるアトラクションの数々や、アクシデントすら面白さへと変えるマインド。予期せぬ事態をあえて引き起こそうとする姿勢は、水曜日のカンパネラにこそ当てはまるように感じる。
「皆様どうも。前からのスタートとなりま〜す」と言い、“ティンカーベル”に合わせ、『ボロフェスタ』ではおなじみ“移動式CENTER STAGE”に乗って登場した詩羽。その登場方法に観客からも歓声が起こる。注目を引かせたら、後は彼女の独り舞台。“バッキンガム”では高速ラップを難なくこなして無数の拳を挙げさせると、“ディアブロ”では「いい湯だね!」と会場が割れんばかりのコール&レスポンスを決めていく。さらに“赤ずきん”ではオオカミも登場してダンスを披露したなら、“桃太郎”ではウォーターボールに入り、観客の頭上を遊泳していく。何が飛び出すかわからない、まるでおもちゃ箱をひっくり返したかのようなパフォーマンスで会場を圧倒していく。
詩羽になってから、水曜日のカンパネラが『ボロフェスタ』でライブするのは『ナノボロ』を含めると今回が3回目。そして過去2回はコロナ禍であったため、発声ができないなどの制約が課された。“ディアブロ”もコール&レスポンスではなく、振付で対応していた。制約が解除された今、水曜日のカンパネラは鬼に金棒。今まで以上に、観客が楽しめるパフォーマンスに仕上がっていると感じた。ラストには“マーメイド”、“エジソン”、“招き猫”と代表曲を3曲続けて披露。大きな招き猫もステージに登場し、熱狂のままライブは終了。まさに何でもありのエンターテイメントの真髄を見るかのようなステージであった。
LOSTAGEが音楽で語るロックバンドとしての生き様
「なんだこの音は!」1曲目に演奏された“巡礼者たち”の音を聴いた瞬間、そんなことを思った。今年アルバム『PILGRIM』を発表し、現在全国ツアー中の最も脂の乗った状態なのはわかってはいた。だが『ボロフェスタ』で観た彼らのライブは重厚なサウンド、力強いビート、攻撃的なギター・フレーズ、などの一挙手一投足が圧倒的すぎるのだ。まるで「最高のロックとはこういうこと」と、ライブをもって体現してるかのようである。
五味岳久(Ba / Vo)が「キャパ80人のライブハウスでも、『ボロフェスタ2023』のトリでも、いつもと同じようにを演奏します」と、土龍が運営する収容人数80名の〈livehouse nano〉にもリスペクトを捧げ、“窓”を演奏。オーラのような圧倒的なサウンドスケープが会場を侵食し、自然と歓声が沸き起こる。“平凡”では岩城智和(Dr)のビートと五味拓人(Gt / Cho)のソリッドなギターリフが絡みつき、観客を沸かせる。終盤では代表曲である“SURRENDER”も披露。あきらめずに戦い続けるその音楽は、地元奈良でインディペンデントに活動を続ける彼ら自身に言い聞かせているかのようであった。
本編ラストに演奏をされたのは最新アルバム『PILGRIM』から“瞬きをする間に”。曲のクライマックスにあわせてカーテンが開き、見事なステンドグラスが登場。演奏終了後も会場は鳴りやまず、拍手に応えて再度登場した。「いいイベントに出れて良かった」「もう一曲だけやって奈良に帰ります」と言い、イントロが鳴り始めると歓声が沸き上がる。初期の代表曲“手紙”だ。五味の叫びにも似た歌声が、この日一番の盛り上がりをみせる。「どうもありがとう、LOSTAGEでした」とだけ言い、ステージを後にした。
この1日もまた、ボロフェスタの血肉となる
他にも忘れられないライブはたくさんある。ハッピーで、心が温かくなるようなサウンドが印象的であったズーカラデル。エントランスにある〈どすこいSTAGE〉をミラーボール煌めくクラブへと変えたKENT VALLEY。シリアスなサウンドと変則的なリズムで会場を侵食したPeople In The Box。「年齢なんて、関係ねえ!」とばかりにパワフルなステージングで観客を沸かした怒髪天。挙げだすときりがないくらい、素晴らしい演奏の数々が繰り広げられていた。
そしてそれらの演奏はコピーできたとしても、生き様や人柄を内包したパフォーマンスは決して真似できるものではない。なぜなら何年もあきらめず、真摯に音楽活動を積み重ねてきたことでしか得られないオリジナリティだからだ。活動してきた年月や経験はライブでこそリアルに反映される。
22年目の『ボロフェスタ』もまたその歳月を感じさせるものだった。冒頭にも書いたがDIYでトライ&エラーを続け、ゲリラ的に観客を楽しませる姿勢は全国探しても、このフェスくらいだろう。そして今年の経験も、また血となり肉となり、次の年へと引き継がれる。パーティーナビゲーターの土龍はインタビューで「80歳になってもフェスを続けたい」と語っていたが、その未来も夢物語ではないと思えてくるのだ。

You May Also Like
WRITER

- ライター
-
関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。
OTHER POSTS
toyoki123@gmail.com