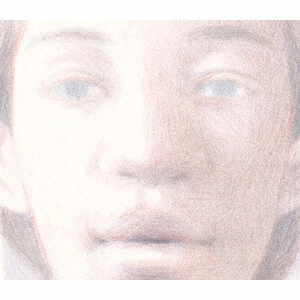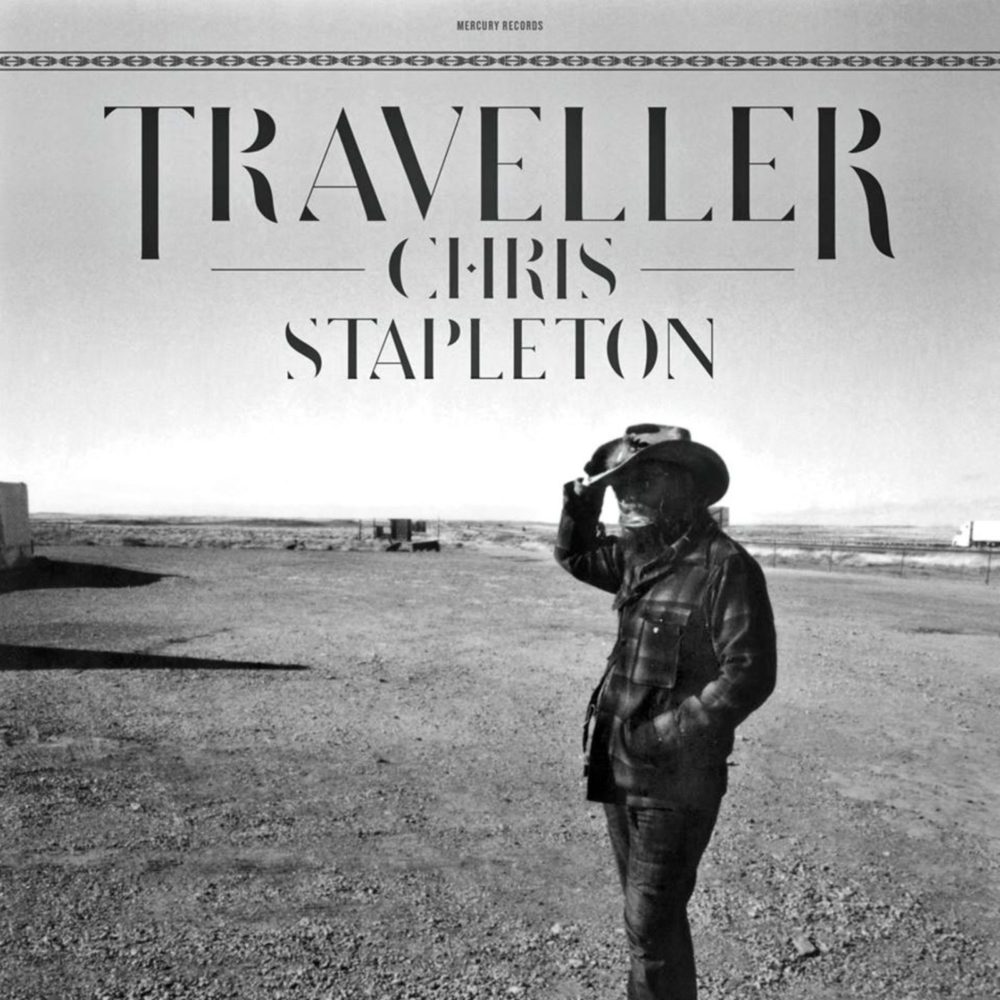峯大貴が見た祝春一番2019
今年で34回目!大阪ゴールデンウィークの名物野外コンサート
5月3日(金)~5日(日)の3日間に渡って大阪・服部緑地野外音楽堂で行われた野外コンサート・祝春一番。筆者は2013年から有志スタッフとして参加しており、今年も会場担当として動きながら現場で見ることが出来た風景を報告する。
1971年に天王寺公園野外音楽堂で第1回目が開催されてから48年、またその前身となった1970年4月の『BE-IN LOVE-ROCK』から数えると実に49年。1979年に一度幕を下ろしてから1995年に復活するまでの空白期間はあったものの、ほぼ半世紀に渡って毎年大阪のゴールデンウィークの名物として君臨している“日本のロックとフォークのコンサート”、春一番。今年で通算34回目の開催である。平成から令和に元号が変わるにあたり10連休となった2019年。時代の分岐点を迎える中でも、この場所には主催者・福岡風太が考える、70年代から変わらない野外コンサートのおもしろさ・醍醐味を表現し続けようとする意地が感じられる。いや、もはや意地だけで続けていると言ってもいいだろう。
福岡は自身が舞台監督を務めた忌野清志郎&仲井戸麗市の共演ライヴ『GLAD ALL OVER』(1994年)のジャケットを羽織り、ステージ端のマイクから1組ずつ出演者を紹介していく。するとステージ上部のめくりに名前が掲げられ演者が登場するおなじみの舞台進行だ。今回は有志スタッフのたけだあすかが傍でサポートする中で、杖を付きながら指揮をとっていた(普段はシンガー・ソングライターとして活動しているたけだあすかは最終日に急遽2曲、飛び入りで出演も果たした)。今年71歳となる福岡だが、どれだけ周りが休憩を促しても立って演奏を見つめる頑なさ、また筆者を呼び出し「あそこ。客席ど真ん中でタバコ吸うてる客おる、注意し」と常に会場全体を見渡している眼光は全く衰えていない。

3日間を彩る演者の顔ぶれにおいて、常連である小川美潮や今年のライヴは平日のみを宣言したハンバートハンバートの不在にはいささかの寂しさも感じたが、大きく変わることはない。観客の中にも常連は多く、70年代から通い詰める強者もいる。だからこそ演者は他のフェスやイベントのように代表曲を並べる自己ベスト的なパフォーマンスは許されず、1年間の活動の通信簿となるような<最新スタイル>のステージを見せる必要があるというのが他のフェスやイベントとは一線を画すところだ。特に初回から出演している大ヴェテランの中川五郎がその点を強く意識しており、ここ10年以上毎年異なった編成でのステージを貫いている。今年は多田葉子(Sax / Cl)、熊坂路得子(アコーディオン)による、<うたものシスターズ>を従えて登場。第1回の春一番でも<田舎五郎と魚>名義で演奏したというジェリー・ジェフ・ウォーカーの日本語訳“ミスター・ボージャングル”と、ブラックパワー・サリュートについて歌った20分超えのトーキング・ブルース“ピーター・ノーマンを知ってるかい?”を披露し、ここ数年またプロテスト・フォークを更新して歌わざるを得ない現代社会への怒りと皮肉をエモーショナルに観客に突き付けていた。
また演者同士が互いに入り乱れる飛び入りコラボの多さも春一番ならではである。友部正人は途中エレキギターにAZUMIを呼び込んで自身のデビュー曲“大阪へやって来た”を披露。友部が冷ややかな声を上ずらせながら歌うトーキングブルースの金字塔だが、どんどん熱を帯びていく歌とブルースハープに対して、AZUMIが絶妙の距離感を保って剛腕ギターを入れていくという珍しい共演であった。一方で友部も三宅伸治& the spoonfulのステージに呼び込まれる。近年は三宅と鮎川誠とのユニット、3KINGSでも活動を共にしている縁から、3KINGSとして友部が書いた“彼女”をコラボした。そして友部の後には金子マリを呼び込み、三宅が忌野清志郎から引き継いだ“JUMP”を交互に歌う光景はこの場所でしか見られないものだろう。また“ベートーベンをぶっとばせ”では、三宅が福岡風太の息子で舞台監督として陣頭指揮を執っている福岡嵐に肩車され、ギターを弾きながら客席中央に設営された<へそステージ>まで移動するパフォーマンスも、毎度のことながら三宅のロックスターとしての身体性に惚れ惚れしてしまう一幕だった。
様々な人の想いの受け皿となる場所―遠藤ミチロウに捧ぐ
そんなこの空間を毎年味わうことで1年間の時の流れを感じたり、年に一度この場所だけで顔を合わす人との再会を、一つの楽しみとしている者もいるだろう。演者も出番が終われば楽屋の大部屋でドリンク出店しているバー、アフターアワーズでお酒を買って、一番後ろの芝生エリアで仲間と共に飲んでいる風景があちらこちらで見られる。演者・観客・スタッフと携わる全ての人にとって単にステージだけを楽しむ以上のものを、この場所に求めているような気がする。一人一人の想いが渦巻いている空気感がなおさら祝春一番を特異な場所にしているのだ。
様々な人の想いの受け皿となっているこの場所だから、いなくなった人の残り香も感じてしまう。毎年ステージには豊川忠宏(トヨヤン)が中心となって木工作品が建造される。今年は十数本の風車が会場中に登場、その風車の絵柄の中にはイラストレーター諸戸美和子が描いた西岡恭蔵、島田和夫、そしてあべのぼるのイラストもあった。西岡恭蔵は、大塚まさじ、永井洋とのザ・ディラン時代からの春一番の看板演者で、現在は主に夕凪がこの場所で歌い継いでいる本イベントのテーマ曲といえる“春一番”の作者。島田和夫は、憂歌団のドラマーであり、90年代以降も大塚まさじや豊田勇造、宮里ひろしを始め数々のバンドで春一番のステージに出演してきた。そしてあべのぼるは、福岡と共に長らく春一番を取り仕切っていた音楽プロデューサー。3人ともすでにこの世を去っており、本コンサートの歴史において重要な面々である。

そこに加えて今年は特に遠藤ミチロウが亡くなったこともあり、追悼の意を込めたパフォーマンスが多く見られた。gnkosaiBANDは、メンバー4人がミチロウのメイクを施し登場。オカザキエミ(Syn.Cho / moqmoq)がシンセベースを担う編成になってよりミニマルに響くレゲエ・グルーヴで観客を躍らせていたが、途中にはミチロウが初ソロアルバム『ベトナム伝説』でカバーしていた“仰げば尊し”も引用し、追悼の意を込めた。gnkosai(Dr / Poet)は、実父・加川良が亡くなった2017~2018年には父親の楽曲を積極的に演奏し、バトンを引き継ぐようなステージを見せていたが、そのフェーズを超え、今年は先輩たちへのリスペクトと遊び心を自身のパフォーマンスに昇華している様子が印象的であった。
一方AZUMIはミチロウの“Just Like a Boy”をカバー。歪ませ切ったギターを鳴らしながら朗々と歌っていく。その内スーっとミチロウがAZUMIの身体の中に憑依したかのように東北訛りで話し始める。「AZUMI、ぼくな天国に行ってバンド組んだ。ギターはジミヘン、ドラムはキース・ムーン、ベースは藤井裕……」、などAZUMIがまねるミチロウの語り口は会場をしんみりとさせながらも、笑いを呼ぶ。ひとしきり話した後ミチロウは去って行き、AZUMIとミチロウがデュエットした楽曲“ホワイトソング”を披露した。次に、上野エルキュール鉄平(Dr / アフターアワーズ)を呼び込んだユニット<AZUMI with 豆パンチ>としてあべのぼるの楽曲“何も考えない”をセッション。AZUMIが吠えながら放つフリーダムな轟音ギターに対して、鉄平が何とかしがみついてドラムをシバきまくるその構図も含めて<ブルース・イタコ>AZUMIの凄みを見せつけられた。またその翌日には小谷美紗子もミチロウとの想い出をMCで話しながら、彼を知るきっかけとなった曲としてAZUMIを呼び込み、昨日に引き続き“ホワイトソング”をデュエットで披露。未だにミチロウがいるかのように歌ったAZUMIと、もうこの世にいないことを受け入れるようにミチロウの代わりにAZUMIと歌った小谷美紗子。同じ曲でも鮮やかな対比でミチロウを偲び、見送った“ホワイトソング”は今年の祝春一番のハイライトの一つであった。

余談になってしまうが、亡くなった人の残り香は何も演者だけではない。筆者が会場を巡回していると、お客さんに「この写真、ステージが見えるようにどっか貼ってくれへん?」と声をかけられた。見ると昨年亡くなった筆者も知る関係者が、春一番の会場で満面の笑みを見せている写真だった。筆者は受け取って観客席の手すりに吊るしていた有志スタッフが色紙で作った飾りにその写真をガムテープで貼り付けた。
「よお見えるな。兄ちゃんありがと」
「連れて来てくれはったんですか」
「この写真が、見たい言うてくるねんよ。ええわ、喜んでるわ」
ひとしきり写真に話しかけて自席に戻ったその男性は安心したように、赤ワインを気持ちよく飲んで酔っ払っていった。かつて共に過ごした春一番の会場に来たら、もう一度会えるんじゃないかと思って持ってきた写真なのだろうか。人が亡くなって身体が朽ち果てても、残された人たちがその人を大切に思っている間は、記憶の中では朽ち果てることなく、二度目の人生を生き続ける。ここはそんな二度目の人生を長らえる場所、歴史を積み重ねる中で大切な人を思い出す役割も背負っているのだと感じた。その時、ライターを目指そうとしていた当時大学生だった筆者の気概を買って、様々なお節介を焼き、有志スタッフにも誘い込んだ、かつての関係者受付担当だったY氏も、まもなく一周忌を迎えることに気付いた。彼の分の春一番も私は見届けている。
3日間の筋を通す存在感を見せたROBOW
話を当日の模様に戻そう。今年一番の大活躍といえば大阪で活動する4人組のアコースティック・バンド、ROBOWだろう。特にフロントマン阪井誠一郎(Vo / Gt)は<へそステージ>において、3日間違う編成でオープニングを飾るという大役を果たした。一日目は藤縄てつや(Gt)との2人編成。11時に開場となり、観客がだっと流れ込むと同時に西岡恭蔵のカバー“ジプシー・ソング”の演奏が始まる健やかな幕開け。二日目はウォッシュボード、ウッドベース、アコーディオン、クラリネット&サックスを従えたジャグ・バンド編成<阪井誠一郎とディキシー・ギャング>(福岡風太命名)として登場。高田渡の“バーボン・ストリート・ブルース”のカバーを含む陽気な演奏で観客を迎え入れた。そして二日目はライヴの中盤からオカザキエミ(moqmoq)とのコラボも含む6曲を披露。晴れやかなスマイルを絶やさすことなく、実直な歌を聴かせる阪井のボーカル・スタイルを拡張するような3日間であった。もちろん、本体ROBOWとして一日目に出演したステージでは最後に演奏した“僕の車に乗ってくれないか”で手拍子も起こり会場をゴキゲンにしては、次に登場した豊田勇造のバックバンドを引き続き務め上げる働きっぷり。またチェリー森田(P)は名古屋のシンガー・ソングライター蠣崎未来のステージにもアコーディオンで登場し、浅川マキの“それはスポットライトではない”のカバーなど蠣崎のシルキーな歌声をそっと支え、バンド全員で八面六臂の活躍を見せた。全演者の中でも中間管理職的立ち位置で今年の3日間の春一番に一つ筋を通す存在感であった。

初出演2組!ショーウエムラ、はいからはくち
今年初出演を果たしたのは2組。ショーウエムラは自身がベースボーカルを務めるアフターアワーズとしては3年目の出演となるが弾き語りのソロとしては初。一番日差しの強い13時頃、<へそステージ>に登場。木村充揮やヤスムロコウイチを思い起こしてしまうハンチングをかぶった姿は、バンドとはモードを切り替えているようだ。冒頭“突き抜けるよーな音楽”を小気味よく披露する所作と声には若干の緊張感を滲ませながらも、360度観客に囲まれるこのステージからの反応を全身に浴びながら調子を上げていく。男臭く吐き捨てるように歌う声には照れや情けなさも含まれた、哀愁のフォーク&ブルース。会場の端の方で見ていた漫談のナオユキが「めっちゃかっこええやん」と何度も言いながら、どんどんステージに近づきながら見ている姿を筆者は見逃さなかった。最後は“コーヒー&ウイスキー”。どんどん高速になっていくスリーフィンガーで魅せる、ブルース・ナンバーで締めくくった。昨年までステージ班の有志スタッフとしても春一番に関わっていたショーウエムラ。アフターアワーズ結成前から活動していた自身の原点である弾き語りシンガーとしての出演の感慨を、日差しによってどんどん顔が真っ赤になりながら噛みしめている様子がステージから伝わってきた。

そしてもう一組が大阪を拠点とする4人組バンド、はいからはくちだ。春一番にも1972年に出演しているはっぴいえんどを思わせるバンド名だが、特に片山祥希(Vo)と左利き用ギターをわざわざ逆手で使いこなしている久森楓也(Gt)のヒッピーでサイケな風貌には、むしろ相対するニューロックの雰囲気を漂わせる。ただブルースとソウルを漂わせながらもやけに人懐っこいメロディで前のめりにパフォーマンスしていく姿には村八分、憂歌団、ローザ・ルクセンブルグ、ウルフルズといった関西のロックの遺伝子を純血に受け継いでいるバンドと言えるだろう。そんな彼らだから春一番への憧れも強く、特に片山は緊張を露骨に顔に滲ませながら他の演者のステージを見て、全身で春一番の空間に耐性をつけようとしていた。しかしいざ福岡風太の紹介を受けて登場し、愛らしいフォーク・ロック曲“バカをやろう”から始める姿からは全て吹っ切れたことが見て取れた。沸点は“ダラダラのブルース”で最高潮に達した。片山が舞台を降り、<へそステージ>に駆け上がってステップを踏みながらブルースハープを吹く姿に会場が沸く。そしてステージに残された南辻凌(Ba)、アヤタ(Dr)、久森の演奏もどんどん熱を帯びてきて、離れたステージから息を合わそうとする片山が苦笑いを示す場面もあったが、見事に着地し春一番という大舞台に存分な初期衝動を見せつけるステージとなった。

関西ブルースの金字塔、大トリ有山じゅんじ
そして今年の3日間の大トリは有山じゅんじ。押尾コータローの出番にも登場した清水興(Ba / ナニワエキスプレス)と、今年古希を迎えたサウス・トゥ・サウス時代からの盟友、正木五朗(Dr)との豪華な3人編成で登場。有山が「みんなで歌える歌ばっかですわ」と言っていきなり“あこがれの北新地”を歌い始めた途端、会場中大喜びで大合唱に包まれた。“買い物にでも行きまへんか” では金子マリを呼び込んでさらに盛り上げ、“大阪へ出て来てから”、“なつかしの道頓堀”と続け、途中に“ぐるぐるぐる”を挟んで、本編最後の“梅田からナンバまで”に至るまで6曲中5曲を『ぼちぼちいこか』(「上田正樹と有山淳司」名義 / 1976年)から披露するという大盤振る舞い。有山の飄々とした佇まいはいつもと変わらずだが、とにかく全曲で会場中が大合唱しているのが春一番という場所らしいし、美しい光景だ。発表から40年以上経っても、『ぼちぼちいこか』がこの場所にいる多くの人にとって血肉となっている関西ブルースの金字塔であることを再認識した。またその大合唱はもうすぐ今年の春一番も終わってしまうことの名残惜しさの表れのようにも感じられた。
アンコールでは会場中にいる出演者全員をステージの上に呼び込み、アメリカン・フォークのスタンダードナンバー“グッドナイト・アイリーン”を披露。ふざけて歌う有山に「ちゃんとせえ!」と観客から野次が飛ぶ。はいからはくちの片山は感極まって上半身裸になっている。松田ari幸一からKOTEZへのブルースハープ・リレーや、『ぼくの展覧会』(1993年)で本曲を自身も日本語訳カバーしている友部正人が一節を歌うなど、即興ながらもたくさんの名場面を残してフィナーレを迎えた。
演者が退出し、ステージに残ったのは福岡風太、一人。鳴りやまない観客からの拍手。しかしそれは、再度のアンコールを求めるものではなく「ありがとう」という声がそこかしこから上がる、感謝の拍手だ。福岡も「これ以上は年寄り連中はキツイ。今年はこんなところで。おもろかったー!ありがとう…ありがとう…。それしか言葉ないもんな」と感極まりながら感謝を告げる。息子・嵐が声をかけ、風太が締めの挨拶「解散!」と告げる。最後の出演者のめくりとして「福岡風太」「あべのぼる」の名前が掲げられた。不思議なことに、その時あべのぼるの顔が描かれた風車だけが、ゆっくりと回っていた。まるであべが3日間をやりきった風太を始めスタッフ、演者、そして観客を労うかのようだった。

春一番は日本の野外コンサートおよび、70年代以降の関西を中心としたフォークとロックの歴史を、当時の追体験ではなくリアルタイムに更新されているものとして感じられる唯一の場所だ。だから毎年引き寄せられるように参加しているというのは筆者だけではないだろう。「また来年!」と言って帰っていく観客。「簡単に言うな~」と言い放つ福岡。彼は春一番を「演者、お客サン、スタッフ、みんなで創り上げる作品」と言う。個人的には開催前に出演者一覧が書かれたチラシを飲み屋に置いてもらいに行った時にそこの店主に「このチラシ見ているだけでね、酒飲めるんだよね」と言われたこと。また最終日終演後、会場のゴミの片付けをしていると観客から声をかけられ「今年も書きますよね?あのレポートを読むまでが春一番なんです」と言われたこと。そんな人との繋がりも含めてアルバム音源とは違い、形として残らない生ものの作品だからこそ、春一番に関わった人たちの記憶の中にはいつまでも残っていくのだろうと感じた。だから私はせめて文章として2019年の春一番の風景をこうやって今年も書き残しておく。

You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com