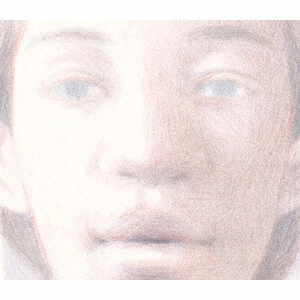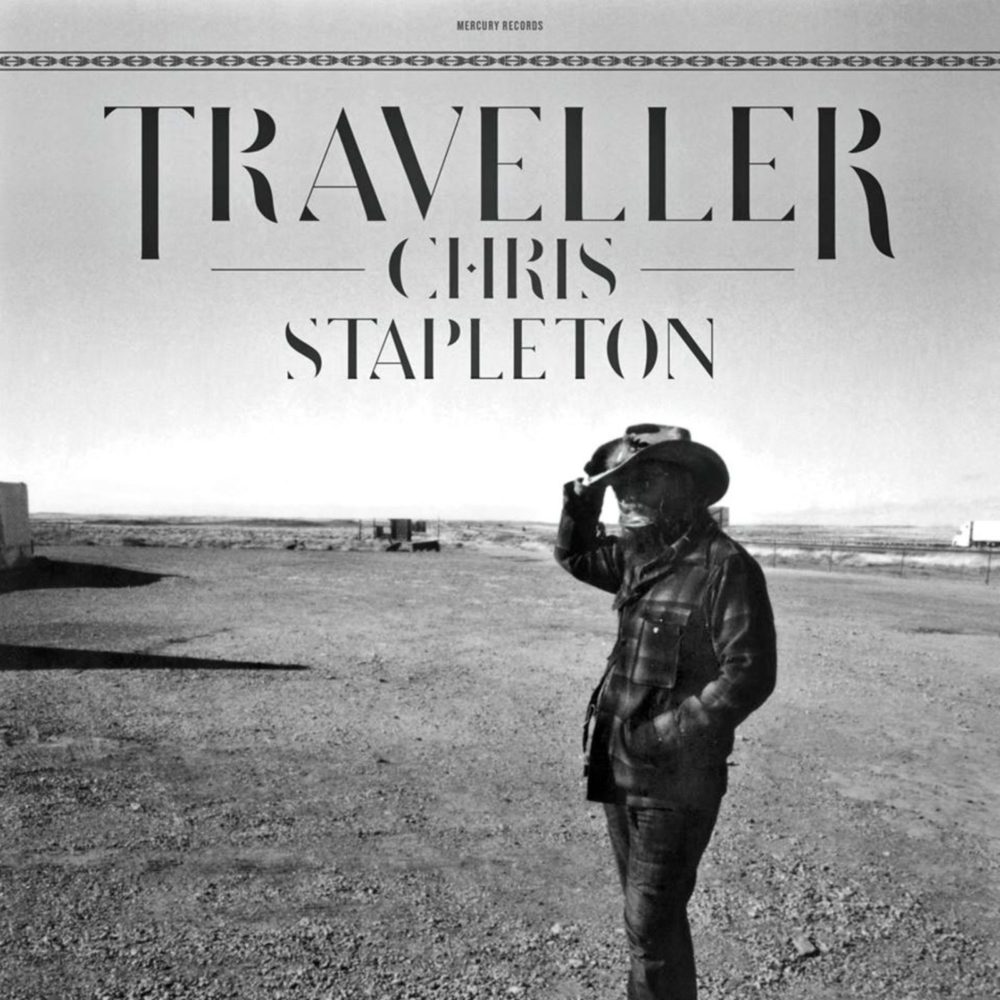ソー・バッド・レビューから続く道。 シンガーソングライター&ピアニスト / 翻訳家 チャールズ清水が目指す『FUTURE CLUES』
今から約半世紀前の1970年代中盤。関西の音楽シーンは目まぐるしく変化しながら、独自の発展を遂げ、東京と並ぶ新しい音楽の発信地として機能していた。1960年代末から起こった関西フォークのムーヴメントは曲がり角を迎え、ブルースやソウル・ミュージックに影響を受けた次の世代が台頭してきたのだ。
大阪からは憂歌団や上田正樹とサウス・トゥ・サウスが頭角を現し、京都からはウエスト・ロード・ブルース・バンドやブルース・ハウス・ブルース・バンド(後のブレイクダウン)らが続々と登場する中、ダメ押しとばかりに1975年に登場したバンドが、ソー・バッド・レビューである。「地上最大のソウルバンド」と称され、ボーカルに砂川正和と北 京一(きた・きょういち)、ギターに山岸潤史と石田長生(おさむ)、ベース永本忠、ドラムにベーカー土居、そしてキーボードに国府輝幸(現・利征)とチャールズ清水という、それぞれ関西を中心に腕を鳴らしてきた名うてのプレイヤー8人が揃ったスーパー・グループだった。ロック、フォーク、ブルース、ファンクはもちろん、コメディアンやパントマイマーの顔を持つ北も在籍したことから関西の風土を丸ごと取り込んだ圧倒的なパフォーマンスで瞬く間に話題を呼んだが、オリジナルアルバムとライブアルバムを1枚ずつ残し、あっけなく1年ほどで解散。
また彼らと足並みを揃えるように前述の主要な関西のバンドが(メンバーを変えずに90年代まで活動を続けた憂歌団などわずかな例外を除いて)次々と活動を休止し、それぞれ個別のキャリアを模索していった。そしてブルース、ソウルに取って代わりニューウェーブやポストパンク、フュージョンなどが台頭し、80年代に突入していくというのが大局的な流れである。
そんなソー・バッド・レビューが今にわかに騒がしい。1976年の未発表ライブ音源が発掘され、昨年『The Other Side of Sooo Baad Revue』として公式リリース。この実現に向けた調整役として尽力したのが、当時はまだ高校生だった最年少メンバー、チャールズ清水だ。解散後はブルーヘヴン、MYX(ミクス)などのメンバーとして活躍しながら、友部正人、三上寛、加川良、サンディー & ザ・サンセッツ、Otis Rush、Barbara Lynn、忌野清志郎&2・3’sなど数々のレコーディングに参加。デビュー当時のSIONやザ・コレクターズのアルバムでも彼の流麗なプレイを聴くことができる。
90年代以降は主に翻訳家・通訳士として膨大な実績を残してきた彼だが、今年2月、1977年に発表した唯一のソロアルバム『MINOR BLUES』のリイシューも手掛け、70年代~2010年代に至るまでのキャリアをまとめたライブ音源集『MAJOR DUES』との2枚組で発表した。また現在は新しいオリジナルアルバムの制作に着手しているという。4月にはソー・バッド・レビューの砂川正和のライブ作品『LIVE! 砂川正和』、6月にはチャールズがソー・バッド以前に在籍したアイドルワイルド・サウスのライブ作品『LIVE -BETTER LATE THAN NEVER- 』が追随して日の目を見る。再評価が進もうとしている今、再び自身の音楽を見つめ直し、未来に繋げようとしているチャールズ本人に話を聞いた。
写真:三浦 麻旅子
協力:永田 純(有限会社スタマック)
撮影場所協力:Live Music JIROKICHI
チャールズ清水
1958年大阪市生まれ。アイドルワイルド・サウスの創設メンバーとして関西の音楽シーンに登場し、1975~1976年にはソー・バッド・レビューのキーボーディストとして活躍。ソー・バッド解散後は永井“ホトケ”隆、吾妻光良らとのブルーヘヴン、山岸潤史を中心とする大型ソウルバンドMYX(ミクス)などで活動。また1977年にはソロアルバム『MINOR BLUES』を発表。セッション・プレイヤーとして70〜80年代のブルース・ロックシーンの作品にも多数参加する。著述家としても数々の記事を執筆し、1994年には教則本『ブルース・ピアノ』(リットーミュージック)を発表。2023年、『MINOR BLUES & MAJOR DUES』をリイシュー2枚組でリリースし、現在ニューアルバムを制作中。
また1981年以降は技術翻訳・著作物等の翻訳を始め、様々な業務に従事。代表的な翻訳著作物としてクラウス・シュワブ / ティエリ・マルレ著『グレート・リセット ダボス会議で語られるアフターコロナの世界』(2020年10月 初版 藤田正美 / チャールズ清水 / 安納令奈 共訳)、『ステークホルダー資本主義 世界フォーラムが説く80億人の希望の未来』クラウス・シュワブ / ピーター・パナム著(2022年8月 初版 藤田正美 / 安納令奈 共訳)など多数。
付録:ソー・バッド・レビュー、バンド変遷図(1971~1981)
少年ピアニスト、関西の音楽シーンに飛び込む
関西の音楽シーンと関わりを持つきっかけは?
心斎橋ヤマハ(現:ヤマハミュージック 大阪なんば店)に色んなミュージシャンがたむろしていて、中学1年生の時に出入りし始めるんです。そこで石やん(石田長生の愛称)やキー坊(上田正樹(注1)の愛称)とも知り合いました。確か1971年頃。
注1 上田正樹:R&Bソング・シンガーソングライター。1974年に有山淳司(現・じゅんじ)らと、上田正樹とサウス・トゥ・サウスを結成。その後、ソロに転身し“悲しい色やね”(1983年)が大ヒット。1999年以降は韓国、インドネシアなどアジア諸国にも進出し、高い人気を誇る。
そもそもピアノを弾くようになったのはご両親の影響ですか?
そうですね。地元は大阪の黒門市場で、父が中国人で母親は満州生まれの日本人。親父は日本語が片言で年もとってたから、教育はおかんがしっかりしていて。高校まで神戸のマリスト国際学校という、いわゆるインターナショナルスクールに通わせてくれました。ピアノは最初、英語のアクセントとか発音を耳で自然に覚えられるように習わせたようです。
おかんは音楽が好きやったから家ではいわゆるスタンダード・ナンバーがよくかかっていました。Paul Mauriat、Andy Williams、Pat Boone、Carmen Cavallaro、日本だと越路吹雪。あと親父が中国から連れてきた年の離れた腹違いの兄貴がジャズ好きで、車に乗ったらいつもGlenn Millerの”In The Mood”を爆音でかけていたし、「今度Count Basieが来るから観に行くぞ!」ってよくコンサートにも連れていかれました。

そこからいわゆるポピュラー・ミュージックを聴くようになるのは?
特に衝撃が大きかったのは、カウンターカルチャーの一大ムーブメントを体験させてくれた『ウッドストック / 愛と平和と音楽の三日間』(1969年)と、髭面のPaul McCartneyがピアノを弾きながら“Let It Be”や“Hey Jude”を歌うシーンが強烈に脳裏に焼き付いているThe Beatlesの映画『Let It Be』(1970年)ですね。『エルビス・オン・ステージ』(1970年)もショービジネスの一つの到達点としてすごいなと思いながら観ていました。また一人で街を出歩くようになった中学生の頃は第一次の外タレ来日ブームで、初めて一人で観に行ったコンサートは1972年のChicago。知らぬ前に警備員の制止を振り切ってステージの最前列まで行って汗だくになりながらエキサイトしたこの経験が病みつきとなって、Led Zeppelin、Elton John、Emerson, Lake & Palmer、Three Dog Night、Jethro Tull、Cat Stevens、Grand Funk Railroad、Creedence Clearwater Revival、Fifth Dimension、Ten Years After、Procol Harum……ジャンルを問わず片っ端から観に行きました。そうやって音楽を自分なりに消化することを覚えたタイミングで色んな地元のミュージシャンたちと出会うようになるわけです。
初めて学校以外のお友達ができた感覚ですね。しかもすごくやんちゃな。
そうですね。インターナショナルスクールでは米国や英国だけでなく、インド、韓国、中国、フランス、ドイツ、スイス、ブラジルやフィリピンなど、様々な国籍の友人たちには恵まれたものの、日本人の友達が逆に全然できなくて。やっと日本人の、しかも音楽で繋がれる仲間ができたのが、嬉しかったですね。
ちなみに「チャールズ清水」と呼ばれるようになったのはなぜですか?
元々の名前は「朱 達夫」といいます。「朱」は“zhū”と読むんですが、インターに通うなら英語名も付けようと親が考えて、大きくなるころにはイギリスのチャールズ皇太子が国王になっているだろう、ということで「チャールズ」と。まさか即位するのに、これだけの歳月がかかるとは思ってもいませんでしたが。
1972年には田中角栄首相の下で日本が中華人民共和国と国交を結び(日中共同声明)、中華民国(今の台湾)と断交することになりました。親は中国でも民主主義の方だったから、これを機に日本に帰化しようと。そこで「朱」から日本の名字に変えるに当たって、当時兄貴が仕事していたのが心斎橋の清水町筋、これでええやないかと。だからその職場があった通りが数本違っていたら「チャールズ宗右衛門」になっていたかも(笑)

地上最大のソウルバンド、ソー・バッド・レビューに加入!
なるほど(笑)。チャールズさんが関西の音楽シーンで存在を示したのはアイドルワイルド・サウスからでした。これもヤマハで出会った人たちの中で結成されたのでしょうか?
中心人物の松浦善博(注2)と出会ったのはインターナショナルスクールです。途中から入学してきた、数少ない日本人の友達。The Allman Brothers Bandとかアメリカ南部の音楽がやりたいと言って誘われました。活動は結構順調で、関西ではキャロルのオープニングアクトや、色んなバンドとステージを共にするようになりました。そんなある時、東大阪市にあった〈永和〉という映画館で、ダウンタウン・ブギウギ・バンドのライブの前座を務めることになったんです。でも諸事情で彼らはいつまで経っても現れない。とにかく演奏時間を延ばして何とか場を持たせようと必死にやり通したライブだったんですが、その時に観に来ていたのがベーカー土居。
注2 松浦善博:神戸市出身のギタリスト。アイドルワイルド・サウスとしてデビューし、ツイストに加入。その後はソロ、セッションミュージシャン、プロデューサー、A&Rとして活動。日本屈指のスライド・ギターの名手で山下達郎、奥田民生からも賞賛を集める。
おぉ、ソー・バッド・レビューのドラム。
ベーカーはキー坊や石やんとバンド(上田正樹とバッド・クラブ・バンド)をやっていたけど、解散後は一時期ロサンゼルスに行っていて、帰国したばかり。その頃には、ベーカーの頭の中で、後にソー・バッド・レビューとなるメンバーを集める算段ができていました。
先にパントマイムの修行でアメリカに行っていた北 京一を誘い、次に旧知の石やんと、ウエスト・ロード・ブルース・バンドを抜けて京都で自分のグループを始めていた山ちゃん(山岸潤史の愛称)に話を持ち掛けてツインギター。そしてそのグループのメンバーであったベースの永本忠とボーカルの砂川正和も口説き落とし、あとはキーボードやと。一人は国府輝幸。でもブー(国府の愛称)は久保田麻琴さんのハワイで録音するアルバム(久保田麻琴と夕焼け楽団『ハワイ・チャンプルー』)に誘われていたし、妹尾はん(注3)のバンドもやっていた。だからベーカーはもう一人キーボードを見つける必要を感じていて、このライブを観に来たんです。この日の帰り道、一緒に近鉄電車に乗っていたら「今度、遊ぼうや」と言うので、数日後、京都にある山ちゃんのアパートに連れていかれたのが運の尽き(笑)
注3 妹尾隆一郎:日本を代表するブルースハーモニカ奏者(2017年死去)。サザンオールスターズ“ラチエン通りのシスター”、山口百恵“ロックンロール・ウィドウ”、B'z“Don't Leave Me”、“BAD COMMUNICATION(000-18)”などでも印象的な演奏を聴くことができる。文中のバンドとはウィーピング・ハープ・セノオ&ヒズ・ローラーコースターのこと。
※ソー・バッド・レビュー結成にまつわる経緯やエピソードは『The Other Side of Sooo Baad Revue』(2022年)のブックレットに詳しい。

この日をきっかけに引き抜かれてソー・バッド・レビューのメンバーに加わったのですね。だからアイドルワイルド・サウスが『Keep On Truckin’』(1976年)をリリースしたころにはすでにチャールズさんはいない。
そういうことです。自分と松ちゃん(松浦善博の愛称)が共作した“台風”と“MY DADDY”だけレコーディングに参加させてもらいました。分岐点は1975年の『8.8ロック・デイ(注4)』やね。1日目にアイドルワイルド・サウスとして出演し、翌日には山岸潤史スーパーグループ(注5)でもプレイしました。
注4 8.8ロック・デイ:大阪ヤマハが主催していたアマチュアバンドのコンテスト。1973~1982年まで年1回開催され、円広志、大上留理子、清水興、菅沼孝三などその後活躍するミュージシャンたちを多数輩出した。
注5 山岸潤史スーパーグループ:この日、砂川正和と国府輝幸は不参加。サウス・トゥ・サウスの堤和美(Quncho)がパーカッションで参加している。「北京一とバッド・クラブ・バンド」を経て、ソー・バッド・レビューと名乗る。

下段:チャールズ清水(Key・1958年~)、永本忠(Ba・1954年~)、北京一(Vo・1950年~)石田長生(Gt / Vo ・1952年~2015年)
メンバー8人の中でチャールズさんは一番年下でしたが、どんな心持ちでみなさんと活動を共にしていましたか?
このバンドは面白いことに、誰一人同い歳がいない集団で、一番年上の京一と私の歳の差は8つもありました。インターナショナルスクールに通っていたからかもしれないけど、いわゆる日本社会でいうところの先輩・後輩みたいな感覚は希薄で、学年が上の人にも下の名前で呼ぶのが普通。だから年長組の北さんや土居さんにも平気で「京一」「ベーカー」と呼んでいましたし、アメリカ帰りの彼らも実に大らかで、年下の小僧である私を「おもろいやっちゃな~」という風に心広く受け止めてくれました。逆に歳を食った今の方が、向こうを立てないとって緊張しますわ(笑)
同じキーボードである国府さんとの役割分担はどうでしたか?
ブーが主にエレピとシンセサイザー、私がオルガンとソリーナ(注6)を担当することが多かったですね。彼とは身体に染みついているリズムやタイム感も多少違っていて、私はどちらかというとちょっと前ノリで、彼は後ろノリ。ギターもドライブがかかると石やんは前のめりに突っ込んでいくのに対して、山ちゃんは後ろに引っ張るタイプ。それを忠とベーカーのリズム隊がどっしり支え、全体で得も言われぬグルーヴを醸し出していました。
注6 ソリーナ:70年代後半から80年代にかけて流行したストリングス・アンサンブル・キーボード。

居場所なき人々への眼差しに、関西弁のユーモアを交えて表現していた8人の若者
唯一のオリジナル・アルバム『SOOO BAAD REVUE』(1976年)の収録曲では“ここを過ぎて悲しみの街”、“透明人間”はチャールズさんが作った曲です。どの曲を採用するかはどんな風に決まったんですか?
石やんは同じ曲を何回も納得行くまで練習することをいとわない生真面目なタイプでしたが、他のメンバーは基本的に「早よ終って、早よ遊ぼうぜ」というノリが強かったように覚えています。だからアルバムの曲作りのために〈合歓の郷〉(注7)に合宿しに行った時も、これは採用、これは却下みたいな空気は全くありませんでしたね。思いついたアイデアは誰も否定せず、ポジティブに受け止め、みんなで冗談言いながら、和気あいあいとその場で膨らませていく。私が持ち寄ったこの2曲に関しても、すんなり受け入れられて、そのままやることになりました。
注7 ヤマハリゾート合歓の郷:現NEMU RESORT。三重県志摩市にある、総合リゾート施設。当時ミュージック・キャンプというスタジオ合宿施設も併設されていた。


ではこの2曲はどんなイメージで作ったのでしょうか?
“ここを過ぎて悲しみの街”はアマチュア時代に手伝っていたWendy Soupというフォークデュオに提供した曲で、歌詞はそのメンバーの福井めぐみさんが書いています。パントマイムという言葉が出てくるから京一に歌ってもらったらいいかなと単純に考えていたんですが、今読むと太宰治から着想を得た独特のダークな世界が描かれているので、歌いこなすのはさぞかし大変だっただろうなと思います。
“透明人間”は当時の1950年代のアメリカ社会における黒人の地位や存在価値をテーマにしたRalph Ellisonの小説『見えない人間』(1952年)からインスピレーションを得て書いた曲です。メンバー全員、ブラック・ミュージックに影響を受けていたし、その音楽の背景にある黒人社会が受けてきた差別や迫害などについても憤りを感じ、「それはおかしいやろ!」って普段から話し合っていたこともありました。そうした社会的な意識を自分たちなりに代弁する曲があってもいいんじゃないかと思って書いたんです。

関西名うてのプレイヤーが集まったスーパーバンドという側面で語られがちですが、“最後の本音”、“真夜中の歌姫”、“お母ちゃん俺もう出かけるで”などはぐれ者にスポットを当てた歌が多いですし、アルバムの最後はMarvin Gayeの“What’s Going on”のカバーです。社会課題や人種差別への意識を関西弁のユーモアを交えて表現していたという点は重要ですよね。
声高に主張するのではなく、あくまでエンタテインメントであることは大事にしていましたけど、確かにカウンターカルチャーの要素は強かったですね。そこが同じ関西でも(上田正樹と)サウス・トゥ・サウスやウエスト・ロード・ブルース・バンドとは違う、我々のカラーだったかもしれません。

ソー・バッド・“ショー”ではなく、元々は時事風刺の効いたエンタテインメントという意を持つ“レビュー”としたことも頷けます。この目線は主に誰がバンドに持ち込んだものなのでしょうか?
京一はもちろんそうやし、山ちゃんと石やんもブルースやファンクの歴史を掘り下げていく中で、黒人特有のソウルフルなライブパフォーマンスの醍醐味に関心を持っていました。私はそもそも色んなアイデンティティが混ざった人間やし、そんな環境の中で砂ちゃん(砂川の愛称)とかも感化されていったように思います。
あと我々は関西フォークとの関わりも強かった。大塚まさじ、友部正人、金森幸介、西岡恭蔵、加川良、『春一番』の福岡風太(注8)に、ソー・バッドのマネージャーだった阿部登(注9)……。彼らからカウンターカルチャー的な世の中の見方を学んだ部分も大きかったように思います。ですから好きな音楽が似ているというだけで繋がっていたわけじゃなく、お笑いも問題意識も、あとどんな遊び方がおもろいと思うかも含めて、色んな部分で共鳴し合っていた。実に多彩で感受性豊かな集団だったと思います。
注8 福岡風太:音楽プロデューサー、舞台監督、大阪の野外コンサート『春一番』主催。ソー・バッド・レビューは1976年に出演しており、それ以外の年も各メンバーが様々なバンドで出演している。
注9 阿部登(あべのぼる):『春一番』を福岡風太と共に長らく率いた音楽プロデューサー。70年代にはオレンジレーベルを設立。ソー・バッド・レビューにはマネージャーとして関わり、大塚まさじ、西岡恭蔵、加川良、金森幸介などの作品にメンバーが参加している背景には彼の尽力が大きい。2000年代からは大西ユカリのマネージャーや自身のミュージシャン活動も精力的だったが、2010年に死去。

音楽、文筆、翻訳と生き方を模索していた20~30代
しかしソー・バッドから最初に脱退したのはチャールズさんでした。1976年9月と10月のライブが収録された『LIVE! SOOO BAAD REVUE』(1977年)の時はすでにいなくて、MCでは「ソー・バッド・レビュー・マイナス・ワン」と名乗っています。
そうですね。18歳で高校卒業したら留学するということは、加入する時からみんなに伝えていたことだったので。1976年4〜6月にデビューアルバムをロサンゼルスでレコーディングできるほど恵まれた環境で華々しいスタートを切り、周囲からもすごく大きな期待を寄せられていたバンドでした。だから私が8月に抜けた後も、ひのき舞台で精力的に活動を続けていくんやろなと思っていたんですけど、11月に呆気なく解散することになったので、本当に驚きました。
結果、活動期間は1年ほど。チャールズさんにとっても解散は意外だったんですか。
意外も何も、ビックリ仰天ですよ。まだメールもないし国際電話も高い時代やから、みんなから丁寧に異口同音に「スマン!」みたいなトーンで手書きした手紙をもらいました。何がきっかけで、どういう事情でバンドが終わったのかについては、その場に居なかったので真相はわかりません。多分それぞれ個が強すぎたんでしょうね。みんな血気盛んな頃でしたし。私自身はソー・バッド・レビューに嫌な思いをした記憶が全くなく、いい思い出しかありません。
ロサンゼルスに留学されましたが、ソロアルバム『MINOR BLUES』がリリースされたのは1977年。留学した翌年の作品なんですね。
1976年8月に脱退して留学、11月に解散を知り、それから一ヶ月も経たないうちに今度は親父が亡くなりましてね。おふくろ一人だけにするわけにも行かないので、日本に戻ることにしました。

たった5カ月で目まぐるしく身の回りの状況が変わりますね……。
大学の授業料も一年分は払い込んでいるので、大学二年から東京三鷹のICU(国際基督教大学)に編入することにしました。そしたら「あいつ帰ってきたらしいで」という話が下北沢あたりから広まり、ウエスト・ロードを解散して東京に出てきていたホトケさん(注10)の耳に入り、新しいバンドをやるからということで誘われたのがブルーヘヴンです。他にもいろんな人と〈下北沢ロフト〉を中心に知り合うようになっていきました。『MINOR BLUES』はそんな中で、平野悠さん(ロフト席亭)がロフト界隈の新人たちを集めたレーベルを立ち上げ、なぜか自分もその一人に選ばれて作ったアルバムです。
注10 永井“ホトケ”隆:1972年に塩次伸二、山岸潤史らと共にウエスト・ロード・ブルース・バンドを結成。現在のブルーズ・ザ・ブッチャー(blues.the-butcher-590213)に至るまで第一線で活動をつづけているボーカリスト、ギタリスト。ブルース関連のラジオDJやライナーノーツなどの執筆でも活躍している。
この頃はブルーヘヴンやソロ活動に加えて、山岸潤史さんが中心となったMYX(ミクス)に参加、またスタジオミュージシャンとしてジョニー吉永、レイジー・ヒップ、友部正人、大塚まさじ、三上寛、サンディー&ザ・サンセッツなど多数の作品に参加されています。ソロとして2作目を作ろうという野望はなかったんですか?
オリジナル曲はずっと書いているし、ソロのライブもやっていましたけど、ソロを主軸にやっていきたいという考えはあまりなかったんですよね。やっぱりバンドマン気質と言いますか。
そして大学を卒業された1981年からは翻訳や執筆の仕事も始めています。
音楽で食べていこうとするには、事務所に入ったり、いわゆる芸能界にも関わっていかないといけなかった。実際にオファーを受けたこともあるけど、簡単な仕事ではない。ヒット曲を作るために全神経集中しないといけないし、そのために魂を売るのかというせめぎ合いがありました。
それよりはもっと色んなことを経験したいなと思っていた時に、田川律さん(注11)からBruce Pollockという人が書いた『ロックンロールが最高!』(晶文社 / 1982年)というミュージシャンが主人公の小説の翻訳を一緒にやってみないかと誘ってくれました。またICUの先輩がやっていた雑誌を手伝ってくれという誘いもいただいたのが、創刊されて間もない『キーボード・マガジン』(リットー・ミュージック)。そこで記事を書いたり、海外ミュージシャンの取材ではインタビュアーとしてだけでなく、日本語に翻訳する作業も兼務するようになりました。
注11 田川律:音楽評論家、料理研究家、翻訳家(2023年死去)。関西フォークを支えた大阪労音勤務の後、1969年に中村とうようらと共に『ニューミュージック・マガジン』(現『ミュージック・マガジン』)を創刊。1970年の退社後は各種評論、翻訳、料理本の執筆、舞台監督、ミュージシャンとして活動した。

インターナショナルスクールや留学の経験を活かせる英語を使った仕事との出会いですね。
そうです。ただ自分の中では、あまり音楽・文筆・翻訳の仕事に分け隔てはなくて、拘束時間と納期、単価で打診されるのはどれも一緒。実際、歌詞や詩を読んだり、曲を作っていた経験は、文字数が厳密に決まっている音楽雑誌のレコード評を依頼された際に、どれだけ短い表現で自分が語りたいことを的確に言い切るか考える上でとても役立ちました。また翻訳を依頼されるコピーライトやプレゼン資料の見出しを作る時の単語の選び方に関しても、端的に刺さる訴求力のあるメッセージを考えるという点で、作詞に取り組む時のアプローチをそのまま適用しています。
一貫してフリーランスなんですね。そのことに不安はなかったんですか?
若い頃は将来についてあまり深く考えたことがなかった。でも1994年に娘が生まれたことが大きな転機になりましたね。初めて「このままでええんやろか」と自問自答しました。親としての責任を果たすという視点で物事を捉えるようになりますし、一人前になるまでひもじい思いをさせたくないと思うと、より安定した収入源を見つける重要性も増して経済観念も変わってきます。だから音楽やアート関連の文芸翻訳だけではなく、より需要が高まっていた実務的な技術翻訳にも挑み始めました。その産業分野での実績を積んでいくと、だんだん仕事が来るようになり、収入の浮き沈みが激しい音楽の仕事よりも翻訳業務に費やす時間の割合が自然と増えていきました。ありがたいことに、何とか子どもが大学を卒業するまで不自由なく面倒みれたのは、運が良かったとしか言いようがありませんね。
『キーボード・マガジン』での海外アーティストのインタビューからはどんなことを学びましたか?
Chick Corea、Stevie Wonder、Joe Zawinul(Weather Report)、Garth Hudson(The Band)、Gregg Allman(Allman Brothers Band)……ワールドクラスのレジェンドたちを前にすると、こんなんで自分はミュージシャンと名乗っていいんやろかと、思わされることも多々ありました。中でも中学生の時からの憧れだったRobert Lamm(Chicago)にインタビューする機会に恵まれましてね。ちょうど著書『ブルース・ピアノ』(1994年)を出したタイミングだったので贈呈したら「記念にサインしてくれない?」と言われて、目が点になりました。こんなどこの馬の骨か知れないヤツに対してもリスペクトを示してくれる彼の接し方に感銘を受けました。それは私がこのインタビュー取材の仕事で出会えた超一流アーティストにみな共通するピュアな姿勢で、直接会って体感できたのは大きな財産です。
『ブルース・ピアノ』の出版も、お子様が生まれて技術翻訳に本格的に取り組むようになった1994年ですよね。これまでのブルース・ピアノの知見を詰め込んだような教則本ですが、音楽のキャリアを総括するような意図があったのでしょうか?
意図はしてなかったですが、結果的にその時点までのブルースピアノについて研究したことや、周りから教わったりしたことを凝縮した内容になっていますね。確かにこの本を制作するタイミングは、自分自身の生き方のべクトルが変わる境目であったことは間違いないです。また偶然にも娘が生まれた翌日に、ソー・バッド・レビュー十数年ぶりの復活ライブがあり、私にとって新しい門出を祝う一大イベントになりました。

歌い続けてきた彼がつかんだ未来の手がかり
しばらく技術翻訳の仕事の比重が高まる時期が続きますが、また音楽活動に取り組むようになったのは何かきっかけがあったのでしょうか?
2013年に娘に誘われてSnarky Puppyのライブを〈ブルーノート東京〉に観に行ったんです。そしたら座席ボックスの後ろの従業員用の通路に立ったまま、めっちゃのっているおっさんがいたんですよ。そしてそのおっさん、アンコールになったら急にステージに上がってきて、よく見たら山ちゃんやった(笑)。次の日にChickenshack(注12)としてライブするから観に来ていたことが後で分かりました。
注12 Chickenshack:土岐英史(Sax)、山岸潤史(Gt)、続木徹(Key)の3人を中心とした1986年に結成されたフュージョンバンド。1991年に活動休止するものの、2012年にリユニオンを果たし、これまでアルバム10枚を発表。
おぉ!その時は久しぶりの再会だったんですか?
1994年の復活ライブ以来だから約20年ぶり。終演後、路上でタバコ何本も吸いながら久しぶりに喋り倒しました。その時の生存確認(笑)が一つの引き金になって、翌2014年の『FUJI ROCK FESTIVAL』にソー・バッドで出演する話が現実味を帯びていったのかもしれません。

2015年に亡くなる石田長生さんと最後の共演になったステージですね。『FUJI ROCK』の直前には〈渋谷duo MUSIC EXCHANGE〉でも公演を行ないました。
あのライブはキーボードが私一人だけだったので、ブーが担当していたパートもなるべくカバーする必要があって大変でした。でも前日練習で石やんが「バッチリやな~」と声をかけてくれた時、とても気が楽になったことを覚えています。この〈渋谷duo〉と『FUJI ROCK』が一緒に過ごす最後になるとは。
また、この2014年の復活ライブでは、懐かしい旧友たちとたくさん再会できました。その一人が昔、ローラーコースターでベースを弾いていた永田純(音楽エージェント / プロデューサー)です。これを機に連絡を取り合うようになり、未CD化だった『MINOR BLUES』を再発する話が持ち上がりました。その過程で1976年に〈高円寺JIROKICHI〉でやったソー・バッドの未発表音源が見つかり、それもアルバム化する話も浮上して、どちらも実現することになりました。
2作品ともリリースされた今は『MINOR BLUES』以来となる、ソロアルバムを制作中と伺いました。
はい。19歳の時にリリースした『MINOR BLUES』に、現在に至るまでのライブ音源をまとめた『MAJOR DUES』を加えた2枚組をリリースすることが今回できました。このプロジェクトはこれまでの自分の歩みを総括することに主眼を置いたものです。またこの2枚組の次に繋がるものとして、翻訳の仕事が多かったここ2~30年の間もずっと曲は作っていたので、今度は現在から未来につながるニューアルバムの制作にマインドを切り替えるタイミングがとうとう来たという感覚で今はいます。

現在から未来につながるとは、具体的にどんな作品にしようと思っていますか?
シニア世代に分類されるようになると、これまで自分が受け継いだものを次の世代に渡したい気持ちも大きくなってきています。だから今の自分を提示する方法も、これまで培ったものの集大成にするというよりは、若い人たちからも教わり、刺激を受けながら、自分一人では想像できなかったようなサウンドやアイデアを形にしてみたいです。そのアプローチを生涯貫いたMiles Davisはやはり本当に凄いと思っているんですよ。
また少し翻訳の話に戻りますけど、最近は機械翻訳の進化が目覚ましく、翻訳者は存亡の危機に瀕しています。存在価値が問われる今の時代、マシンが作る冷徹な文章に、どれだけ血を通わせ、行間から醸し出すニュアンスをうまく表現して命を吹き込めるか。いかにして、translationからtranscreationに移行できるかが、ヒューマントランスレーターの大きな命題になっています。
それと同じように、音楽の創作プロセスについても「デジタルリテラシーが進む中で、どういうツールや手法を使って、心を打つ音楽を作ることができるか?」「年齢や世代を超えても、「おもろいな~!」と言い合えて、一緒に感動できるのはどんな音楽?」という問いに対する手がかりみたいなものを見つけたい。そんな想いから、次作のタイトルは『FUTURE CLUES』にすることにしました。『MINOR BLUES』『MAJOR DUES』『FUTURE CLUES』と語呂が合うタイトルにすることで、この三作を私の過去・現在・未来を映し出すトリロジーにしようと考えています。
先日の〈高円寺JIROKICHI〉でのライブ(注13)では『MINOR BLUES』に入っている“続ける”を歌ってらっしゃいましたが、10代の頃に作ったこの曲を60代になったチャールズさんが歌っていることに、すごくグッときました。紆余曲折ありながら、ずっと音楽を続けている。当時と変わらぬ純粋さと、あの頃から格段に増している説得力と意味合いを感じたと言いますか。
注13:2023年4月2日開催 Charles Shimizu presents…Minor Blues & Major Dues 発売記念ライブ
出演はチャールズ清水(Vo / P)、吾妻光良(Vo / Gt)、永本忠(Ba)、松本照夫(Dr)、永井“ホトケ”隆(Vo)、飛び入りゲストに迫水泰裕(アイドルワイルド・サウス初期のボーカル)、北京一、大野えりと旧知のミュージシャンが集まった。
曲を書き続ける
風の音から ひろいあつめて
詩を書き続ける
だれでも 考える事を
リズムを取り続ける
不安定でも自分の物で
心で泣き続ける
みんなと同じように
苦労し続ける
みんなといても一人で
さけび続ける
それでおちつけるなら
しんぼうし続ける
光が見えなくとも
笑い続ける
一人さみしい時でも
なんであろうと いつまでも
続ける 続ける
形が変わろうが すじを通して
続ける 続ける
チャールズ清水 “続ける”
19歳の時に、よくこれだけ言い切れる勇気があったなと今になって思います。怖いもの知らずだったから、躊躇なくここまで書けたんでしょうね。弱気や消極的になったり、やる気が薄れたりする時に、自分に言い聞かせてもう一度奮い立たせるカンフル剤のような役割を果たせるモチベーション・ドライバーになってくれたらいいなと思っています。

またチャールズさんのタッチの強さも含めて記名性が強いプレイだなとも、改めてこの日のライブを観て思いましたね。
この時、ホトケさんから「やっぱ独特の音色あるな」って言われて、社交辞令うまいなぁと思いましたけど(笑)、素直に嬉しかったですね。「すごいなぁ……。こんなん俺には弾かれへん」と思わせてくれる刺激的な存在は昔も今もたくさんいますが、自分の場合は、古くはNat King ColeやRay Charles、ニューオリンズ系ではFats Domino、Dr. John、Professor Longhair、スタンダードジャズ系ではLes McCann、フュージョン系ではGeorge Duke、弾き語り系ではRandy NewmanやBen Sidran、それにシンガーソングライターという言葉を初めて強く意識させてくれたElton Johnや幸運にもインタビューする機会にも恵まれたStevie Winwood、Billy Preston、Leon Russell、Michael McDonaldやDonald Fagenなど、歌いながら鍵盤を叩くアーティストたちから受けた影響が大きいです。
歌の伴奏をするのも大好きですし、ソロを弾く番が回ってきても、ベラベラと早弾きすることにはさほど興味がない。常に歌えるようなメロディラインやフレージングで構成するプレイを心がけています。とは言っても、気分が高揚して、ガンガン弾き倒したい衝動に駆られる時は、とことん行っちゃいますが(笑)

MINOR BLUES & MAJOR DUES

アーティスト:チャールズ清水
仕様:CD
発売:2023年2月22日
価格:¥3,883(税込)
収録曲
CD1『MINOR BLUES』
1. MINOR BLUES
2. ある愛の詩
3. JAPANESE LONELY BROTHER
4. 透明人間
5. 大阪 ― LOS ANGELES
6. MY DADDY
7. 続ける
8. MINOR BLUES (REPRISE)
CD2『MAJOR DUES』
1. ブルー・ヘヴン / MINOR BLUES [1980年3月 渋谷屋根裏]
2. アイドルワイルド・サウス / MY DADDY [1999年 神戸チキンジョージ]
3. アイドルワイルド・サウス / 台風 [1998年5月 新宿パワーステーション]
4. チャールズ清水 / 座椅子オバアチャン [1980年 吉祥寺のろ]
5. 友部正人 with チャールズ清水 / 西の空に陽が落ちて [1987年9月 有楽町読売ホール]
6. ブルー・ヘヴン / I HEAR YOU KNOCKING [1980年3月 渋谷屋根裏]
7. ブレイクダウン feat. チャールズ清水 / WELCOME TO BOURBON HOUSE [1986年6月 梅田バーボンハウス]
8. ブレイクダウン feat. チャールズ清水 / I CAN’T PLEASE YOU [1986年6月 梅田バーボンハウス]
9. 砂川正和&ブレイクダウンwith チャールズ清水 / IN THE MIDNIGHT HOUR [1979年12月 高円寺次郎吉]
10. 大塚まさじ with チャールズ清水 / エピソード [2000年5月 服部緑地野外音楽堂”春一番”]
11. ソー・バッド・レビュー / 透明人間 [2014年7月 渋谷duo MUSIC EXCHANGE]
12. ブルース・ジャム / MINOR BLUES [1979年2月 高円寺次郎吉]
You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com