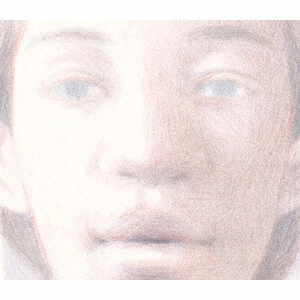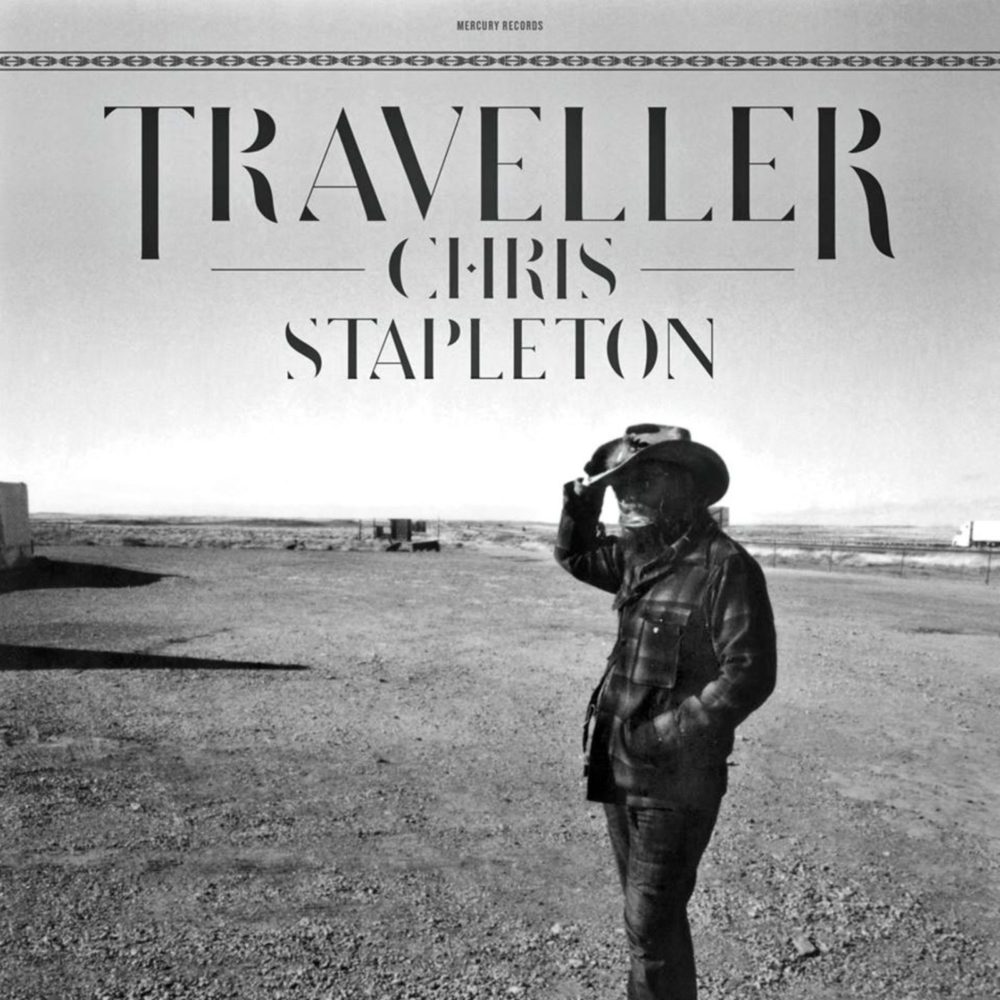あがた森魚による音楽集会『タルホピクニック』とは何だったのか?
今年デビュー52周年を迎えるミュージシャンのあがた森魚が、2024年6月16日(日)に東京都北区・王子の〈飛鳥山公園〉でフリーコンサート『ラストタルホピクニック』を開催した。コロナ禍などの社会状況への問いかけとして2020年6月から毎月開催してきた音楽集会『タルホピクニック』が「ラスト」と銘打ったその意図とは?またライブイベントでも、デモ集会でもない『タルホピクニック』とはそもそもなんなのか?当日のレポートとあがた森魚へのインタビューで解き明かす。
第1部:パレードはいつまでも終わらない -『ラストタルホピクニック』レポート

6月16日、筆者はJR王子駅に初めて降り立った。まぶしいくらいの日差しにクラっとするが、気温は30度を少し超えるくらい。どちらかと言えば昨日の雨による湿度の高さが、うだるような暑さをもたらしていた。とはいえ梅雨のこの時期に見事晴天に恵まれてしまう、音楽家・あがた森魚の神通力ったら。
『タルホピクニック』とは、あがたが王子駅近くにある〈飛鳥山公園〉で行っている月例音楽集会だ。あがたが敬愛しており、作品や彼の発言にも度々登場する作家・稲垣足穂(1900年~1977年)の月誕生日である26日の前後に、楽器を持ち寄った参加者たちと演奏しながらパレードをしている。
コロナ禍に突入した2020年6月に「ギターを背負って歩く練習」と称して始めてから、丸4年。第49回目となる6月16日の開催は『ラスト』と称し、〈飛鳥山公園〉にある野外ステージ「飛鳥舞台」でのフリーコンサートと併せて開催されることを発表した。あがたによるステートメントでは「丸4年、毎月、行ってきた『タルホピクニック』をひとつの区切りとして6月16日を未来への展望とする」と、余白を残しながら。
事前にアナウンスされていたこの日のスケジュールは、13時30分に〈飛鳥山公園〉の麓に集合。1時間ほどかけて公園中を練り歩き、飛鳥舞台に到着して30分ほどフリーコンサートを行うというもの。予定している演奏曲、楽器は各自持ち寄り、曲を知らない方も途中参加、途中離脱自由、観覧フリーという注釈は、他の音楽イベントと一線を画している。

予定されている13時30分。集合場所に到着するともぬけの殻で、数10m先の方に、ひと際にぎやかな群衆がいる。どうやらあがたが予定より早く歩き始めたらしい。この時点で50人近くはいるだろうか。常連の参加者に聞くと普段の倍以上はいるとのこと。それぞれ持ち寄る楽器はギター、ベース、パーカッション、ラジオ、アコーディオン、バイオリン、一番数が多いのはあがたが特に熱を入れているアフリカの民族楽器、シェケレだ。あがたが演奏を先導。循環するコード進行が参加者たちに伝播し、波紋のように広がっていくことでメロディとグルーヴを形成していく様は今まで感じたことのない音楽体験だった。


群衆はあがたを先頭に王子駅から上中里駅方向へと行進を開始した。JR京浜東北線と〈飛鳥山公園〉に挟まれた「飛鳥の小径」をゆっくりと進む。あじさいの名所で知られるこの道だが、この日が今年一番の見頃であり、あがたはどうしてもこの日にやりたかったそう。写真を撮りにくる一般の通行人も多く、通行スペースの確保を徹底してパレードしていく。群れから長い長い一列になることで徐々に先頭の演奏は、後方まで届かなくなり、ずれていく。そのうち公園に入る階段を登り、跨線橋を渡りながら折り返すことで、列の先頭が後方と再び出会い、また演奏がジャストになっていく。このパレードしながらアンプラグドで音を出すことによる、グルーヴの伸縮、音のうねりこそが『タルホピクニック』の音楽的特徴の一つだと言えるだろう。


公園内に入り、再び列は大きな一群となり演奏は一体感を取り戻す。あがたは時折、参加者の一人に目くばせし、ソロパートを取らせていく。一般の公園の利用客は何をしているのか不思議な眼差しを向けるものもいれば、気になって付いてくるものもいれば、「あがたさんがまたやっている」とすっかりこの公園での日常の風景として見る家族連れもいる。児童エリアに展示されている都電6080の保存車両を通り抜け、噴水広場までたどり着きパレードはいよいよクライマックス。あがたはシェケレを持った参加者10人ほどを集め、全員が一斉に振り出し、“ブリキ・ロコモーション”の演奏を開始した。1980年代前半にあがたが「A児」と名前を変えて取り組んでいたニューウェイヴ・バンド、ヴァージン VSとして発表された楽曲だ。「シュワットベイビー・ロコモーション」と歌詞を繰り返しながら、目指す先は飛鳥舞台。あがたを待ち受けるように、今回のイベントの実働面をサポートしている《Waikiki Record》のサカモトが率いるバンド、ELEKIBASSを中心としたメンバーが続々とステージに並んでいく。そこにあがたもゆっくりと到着。3カウントで、PAを通した大音量での“ブリキ・ロコモーション”が始まる。シームレスにフリーコンサートへとなだれ込んだのだ。

驚いたのは、ここまでパレードしてきたシェケレを始めとする楽器隊も演奏に加わり続け、プロアマ問わず20~30人がステージ上に結集していること。演者と観客、コンサートとピクニックの垣根をにじませ、この場所に集った人全員を表現者にしてしまうアートフォームに感動してしまった。飛鳥舞台周辺まで視野を広げるとざっと見る限り150人ほどが集っていた。
その後も“MEZCAL (はじめに歌ありて)”、“俺の知らない内田裕也は俺の知ってる宇宙の夕焼け”とコールアンドレスポンスや観客と一体となって歌う賑やかな楽曲が続いていく。その後、代表曲である“赤色エレジー”では楽器隊は一度ステージを降り、“春の嵐の夜の手品師”では大きな紙を持ち出しパフォーマンスをするなど、あがたの指揮により、コンサートはさらに厳かな雰囲気を醸す。終始MCは控えめであったが「今日の『タルホピクニック』は一応ラストとしているけど……また来月ここに来てみればわかる!今日はありがとう!」とその真相は濁しながら、“大道芸人”と“太陽がくれた海の日々”を披露して約45分ほどのフリーコンサートを終えた。

……が、しかし『タルホピクニック』はまだ終わっていない。「これからこっちの楠の森の方に去っていくからさ、時間がある人一緒に来て!最後は音無川の方までいくかもしれない」と言って、“太陽がくれた海の日々”の演奏を続けながら、ステージを降りて再びパレードに戻る。小休憩を挟みながら、飛鳥山を飛び出し、歩道橋を渡り、都電荒川線を挟んで向こう側に位置する〈音無親水公園〉まで、さらに40分ほど練り歩き続けたのだ。
この今まで味わったことのない音楽体験での気づきは大きく二つ。一つはこの日の暑さも伴って最初から最後まで見届けるだけでも筆者はすっかりバテてしまったが、前後のパレードとコンサートを悠然とやり切ったあがたの強靭なバイタリティだ。そもそも1972年に“赤色エレジー”で旋律なデビューを飾り、本曲やこの日披露された“大道芸人”が収録された『乙女の儚夢』(1972年)を始め、先鋭的なコンセプトアルバムを50作以上も世に放ってきた、日本音楽界の巨人である。今年76歳を迎える今なお、大勢の有志たちを巻き込んで、まだ目の当たりにしたことのない光景を作り出そうとする実行力と体力に魅せられてしまった。
そしてもう一つ、『タルホピクニック』はこの日「区切りをつけた」だけで恐らく続くだろう。ただどう続くかはまだあがたの胸の内にのみある、いやそれすらないかもしれない。ではなぜ今、このタイミングで『ラスト』と銘打ったのだろうか、そもそも『タルホピクニック』をあがた本人がどのような考えを持って続けてきたのか、聴いてみたくなった。
第2部:あがた森魚が総括する『タルホピクニック』
『ラストタルホピクニック』から3日後。あがた森魚本人から話を訊く機会を得て、彼が20年以上住まう埼玉県川口の街に赴いた。杖をつきながらゆっくりと取材場所に現れた彼の顔には、大きなイベントを終えたことによる安堵と、まだ少し残る疲労がうかがえた。
しかし、ひとたび今回語ってほしかった「『タルホピクニック』とはなんだったのか?」について質問を投げかけると、熟考しながら、大きく横道に逸れながら、タイトルにも冠した作家・稲垣足穂の言葉を借りながら、洪水の如く語ってくれた。まるで話しながら、今もまだ答えを探っているかのように。
今なおフレッシュなアイデアでアルバムや映画の製作を続け、昨年にはヴィム・ヴェンダース監督『PERFECT DAYS』にも俳優として出演するなど、多作で多面的なあがた森魚の世界。その50年以上を誇るキャリアの中で、2020年代というディケイドに色濃く刻み込まれた、運動?デモンストレーション?ギターを背負って歩く練習?である『タルホピクニック』について、本人と総括を試みた。

コロナ禍に始めた個人的な営みから、人が集い、パレードへ
『ラストタルホピクニック』の開催前、スタッフに向けて「今年と来年は自分にとってすごく重要になる」と仰っていたそうですが、なぜそう捉えているのでしょうか?
自分がキングレコード傘下の《ベルウッドレコード》の第1弾アーティストとしてデビューしたのは1972年。この年は既存のポップスや歌謡曲、演歌に当てはまらないフォークやロック、後のニューミュージックを手掛けるようなレーベルがメジャーレコード会社の中にもできてきた重要な年です。でも決して自分自身でデビューを狙っていたわけではなく、1971年にたまたま『全日本(中津川)フォークジャンボリー』で“赤色エレジー”を歌っているところを見た、ベルウッドのプロデューサー三浦光紀さんが面白がった。あい前後してはちみつぱいとも出会い、早川義夫さんとも出会い、いろいろなことが偶発的に起きたことで世に出るようになり、もう50年以上経ちます。だから今年や来年が重要だと感じるのも、何かの機運に吸い寄せられているところはある。もちろん、現実的に僕の実年齢からくる焦りみたいなものも、ないわけではない。
あがたさんは今年76歳を迎えます。先日の『ラストタルホピクニック』に私も参加させていただきましたが、炎天下の中で約3時間に渡るパレードとステージの演奏をこなされていて、その体力とバイタリティに驚きました。
そのことは記事の中で触れてほしい(笑)。でも健康状態や、いろいろな考え方やスタイルの人がいるからね。ただバイタリティやクリエイティビティがずっとあって、活動を続けていればいいわけではない。ずっと迷いながらやっています。僕もライブのMCでは「後期高齢者になりました」ってネタっぽくいったりするけどさ。
制作においても、2011年から10年間は毎年アルバムを出す計画をされていましたが、2020年代に入ってもペースは衰えず、多作傾向は現在も続いています。
欲深いというか……ずっと達成感がないんですよね。だから今回、4年ほど続けてきたこの『タルホピクニック』を「ラスト」と一区切りをつけたのも、たとえ小さくてもエポックになるような達成感が欲しかったのかもしれない。

『タルホピクニック』は2020年6月に始動。あがたさんの創作にも影響を及ぼし続けている作家・稲垣足穂さんの月誕生日である26日前後に開催されてきました。毎月続けてきたものを「ラスト」としたのも達成感を得たかったのが一番の理由だったのでしょうか?
このままの形で月1回、ずっと続けてもいいはずなんです。そもそもはコロナ禍が来て、ライブも何もかもできなくなった現象に対する問いかけとして、「ギターを背負って歩く練習」という一個人の営みとして始めました。そこから徐々に人が集まって、円盤少女やThe Rollsのメンバーがしょっちゅう来てくれたり、みんな楽器を持ってくるようになって、演奏しながら練り歩くようになる。徐々に『タルホピクニック』が僕の中でのコロナ禍における表現の母体になっていって、大きなテーマであり課題にもなっていった。それがうまくやりくりできなくなっていったという部分もなくはないです。
行動制限があったコロナ禍での活動として始まりましたが、制限が撤廃されたここ1~2年は、その意味合いも変わったのではないでしょうか?
仰る通りです。おわかりいただきにくい話かもしれませんが、ロックが政治とも宗教とも、経済、商業、テクノロジーとも切り結び、また切り離されていた、1960年代のウッドストックやヒッピーイズム、サマー・オブ・ラブにも通じるような……自分たちの生きている証みたいな独自の運動形態ですよね。つまり『タルホピクニック』はリアルタイム性を持ちながら、自分たちらしい営みを行う一つの拠点である、とは言えると思います。
ただ2020年6月に始まり、数ヶ月〜半年~1年、そしてコロナが明けて3年、4年と続く中で、もっと様々に展開していく可能性もあった。でも割とコロナ禍に確立された範囲の中で継続してしまった感じもある。それは悪いことではない。今ではどんな時でも毎回数10人は集まるんだから。ギャラが出るわけではないのに、『タルホピクニック』の持つ魔力に惹かれて集まってくれる。なんて贅沢なことでしょう。ただ僕も70代後半~80代のここから何ができるのか考えて、自分の中の妄想も広げたときに、『タルホピクニック』をどうしていくか。ひとまず出した小さな結論として一区切りをつけようと思ったんです。

『タルホピクニック』とは社会と向き合いながら、自分らしく生きていく中で表出するグルーヴ
実際にパレードや野外ステージでのライブを観て印象に残っているのが、演者と観客、コンサートとピクニックの垣根がまるでなかったところです。客席からステージを観るという構図のライブハウスやコンサートホールでは実現できない、フレッシュな音楽表現だなと感じました。
観客は演奏者である僕たちを見ている。でも僕たち演奏する側にとっては、観客という存在をなくしてしまっても問題ない。その状態が『タルホピクニック』なんです。ここに集まった私とあなたで生み出されるものであり、観客という概念がないことで成立していると言ってもいい。別にエキセントリックでダダイスティックでシュールな表現がやりたいわけではない。コロナやいろいろな社会情勢の中で、キャリアやテクニック、どんな人かも関係なく、シェケレを振って、ギターを鳴らして、トランス状態になっていることに、それぞれがどんな意味を見出すのかが重要。
各々がシェケレや、パーカッション、ギター、ベース、アコーディオン、ラジオまで持ち寄ったり、たまたま遭遇した人も「これはなんのデモですか?」と気になって自然とパレードの列に交じっている。とことん自由なのに空気を乱す人がいなくて秩序が保たれているのがまた素晴らしいです。
それ自体はどこかのお祭りでも、ジャムバンドやセッションイベントでもよくあることなのかもしれない。僕が作りたいのは、観客にシェケレ渡して「あなたもこれ振って」と巻き込むのではなく、気が付いたら観客も演奏者もわけわかんなくなって一体になっている状態なんです。この前の「ラスト」はそれに近い状態が実現できていたのかもしれないね。パラドキシカルな幸福をあの場所にいるみんなと分かち合えた。
そもそもシェケレは『タルホピクニック』を象徴する民族楽器ですが、注目したのはなぜですか?
20年くらい前に、久保田麻琴からブラジルに行こうと誘われて、カーニバルの時期を目掛けて2年連続で行ったんです。彼はその時ブラジル音楽のノルデスチのルーツを探求していました。ノルデスチのサウンドにはシェケレが大きな役割を担っていて、ある地域の祭りに行ったら、30人以上の女性たちがシェケレにもついているビーズの文様の服を着て、ターバン巻いて、一斉に振ってグルーヴを作っていました。シェケレはこうやって首を持つようにして振るんだけど、僕にはそれが子どもを抱いてあやしているように見えたんですよね。単なる演奏ではなく、この地域に住まう方たちの有様を表現しているようで、すごく感銘を受けました。これをいつか自分もやってみたいと常々思っていて、ようやく『タルホピクニック』が合致したんです。

あがたさんが意識的に持ち込んだものだったんですね。
そうなんです。だから本当は『タルホピクニック』でもみんなで一体感のある衣装を着て、もっとシェケレの人数を増やして、あの時体感したグルーヴを自分たちだったらどう作れるか、というところまでもっとためしたかった。自発的にそういう機運が生まれたらいいなと。でもあくまでこの営みは「今日は時間があったから遊びに来ました」というだけでもいい。コロナや社会情勢と向き合う時に、いろんな情報があるけど、最後に判断を下すのは自分です。人間の朗らかさ、愚かさを感じたり、考え方の違う個が群れになる時の混乱もありながら、自分たちらしく生きている中で表出するグルーヴ。それが『タルホピクニック』なんだから。
あがたさんが旗を振っている営みだけれども、決してあがたさんの求める表現をみんなで実践するプロジェクトではない。あくまで「僕はこうするけど、あなたはどうするの?」と投げかけて、それぞれがどう反応・判断するかで成り立っている。あがたさん自身が『タルホピクニック』の頭数の一人であるとも言えますが、ご自身の活動にはどのようなフィードバックがありましたか?
それはいい質問だね……。僕は歌い手だからあくまで「音楽」として表現したいんです。ノイズもあっていいけど、複雑すぎないもの。これだけの人数でシェケレを振ったり、いろいろな楽器を鳴らせば、倍音でうねりが生じる。なぜうねるのか、そのうねりとは何なのか確認しようにもわからない。自分の出す音に集中しながら、普段の自分から解放されながら、第三者とどう向き合うのか考えながら。スコア通りの演奏ではない、様々な可能性がある中で行う、このジャムセッション、インプロビゼーション、アドリブ……。これは今の非常に危うい世界情勢や社会に対する、僕たちなりの音楽を用いたデモンストレーションになるんじゃないかという期待は持っています。古典的な言葉を使えばアナーキー(無政府状態、自己決定)で、偶発性を残したまま、「音楽」を鳴らす。これは僕にとってすごく大事な経験になった。
実は今回「ラスト」と銘打つにあたって、さらにいろいろな人に声をかけて来てもらおう思ったけど、できなかった。気おくれしたんです。自分が飛鳥山というお山の大将になってどうするんだという問いかけもあった。でもそれをしなくたって、今回は非常に不特定多数の人が集まって、本当に有意義な時間だった。もっと自信を持たないといけない。
常に偶発性を残し、自分の判断で参加を募っていた『タルホピクニック』だったからこそ、豪華なゲストに声をかけて華々しくやるのではなく、これまでの延長線上で開かれて多くの人が集まった特別な回になったのは、非常に全うで誠実な「ラスト」だったと思います。
そう理解してくれることはとてもうれしい。『タルホピクニック』はこの4年間で培われた強力な軍団によるデモンストレーションではない。常にありのままに流動していることを忘れないようにしなければならない。そのことによって集権化された権力や、人々を悲惨なことに巻き込んでいく現在への抵抗や問いかけでもあるんです。

やめるでも続けるでもなく「区切り」を付け、あがたはまた次の旅に出る
今後の『タルホピクニック』について、ステージでは「また来月ここにくればわかる!」と仰っていていました。あくまでも「区切り」であり、続く可能性も示唆されていましたが、どのように考えていますか?
どうなるだろうね……。これっきりにするのか、『タルホピクニック・アゲイン』をやっていいのか、はたまた違う場所でやるのか。やるならやっぱりブラジルのノルデシチでやりたい。じゃあカーニバルにあわせて来年の2月か(笑)
2020年に「あがた森魚」名義での作品制作を辞めることを宣言し、「あがた森魚るびぃ」名義に移行していましたが、昨年12月の『遠州灘2023』から再び「あがた森魚」に回帰しました。全国各地を旅しながら、様々な変化や決断をしながらも、その時々の成り行きに身を任せているのが、あがたさんなので、いつの間にか『タルホピクニック』が復活しているのも十分ありうるし、少なくとも今回参加した人たちはその覚悟ができているとは思います(笑)
ソロシンガーは解散できないからね。ヴァージンVSで「A児」と名乗っていたこともあるけど、変身したり区切りをつけたくなる時期はくるんです。とにかく今は『ラストタルホピクニック』を終えて、この4年ほどやっていたことはまんざらなことではなかったと知ることができた。飛鳥山で行われる小さなデモンストレーション、シェケレによるグルーヴ、稲垣足穂の世界観などいろいろな要素が融和している欲張りな営みでした。もっと盛大に、もっと自分が考えていたテーマが届くようにしたかった気持ちもなくはない。でもこの規模でも十分だった。ともかく不特定多数の人々が集まって音のグルーヴをたしかめあう。その体験が貴重だった。すごく満足しています。
このあがたさんが始めた営みから何か受け取った人が、次の『タルホピクニック』的な何かが生まれてくるような気すらします。
今まで関わってくれた人が何かの気配を察知したり、次の表現や行動に繋がるかは確かに重要ですね。先にやったからすごいというわけじゃなくて、でも50年後、100年後、こういう形のものがもっと面白くなって存在しているかもしれない。まさに稲垣足穂の『美のはかなさ』的であり、吉田兼好の徒然草にも通じる未来系デジャブ感(既視感)です。

Photo:高梨はるの
あがた森魚のキンダーロック
| 日時 | 2024年10月1日(火) |
|---|---|
| 会場 | |
| 出演 | あがた森魚 |
| 料金 | 一般 ¥5,500(全席指定)/ 小学生以下¥1,500 |
| チケット |

You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com