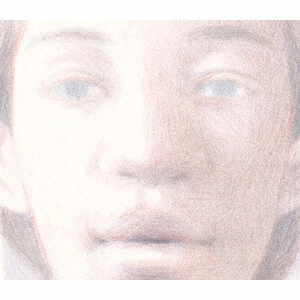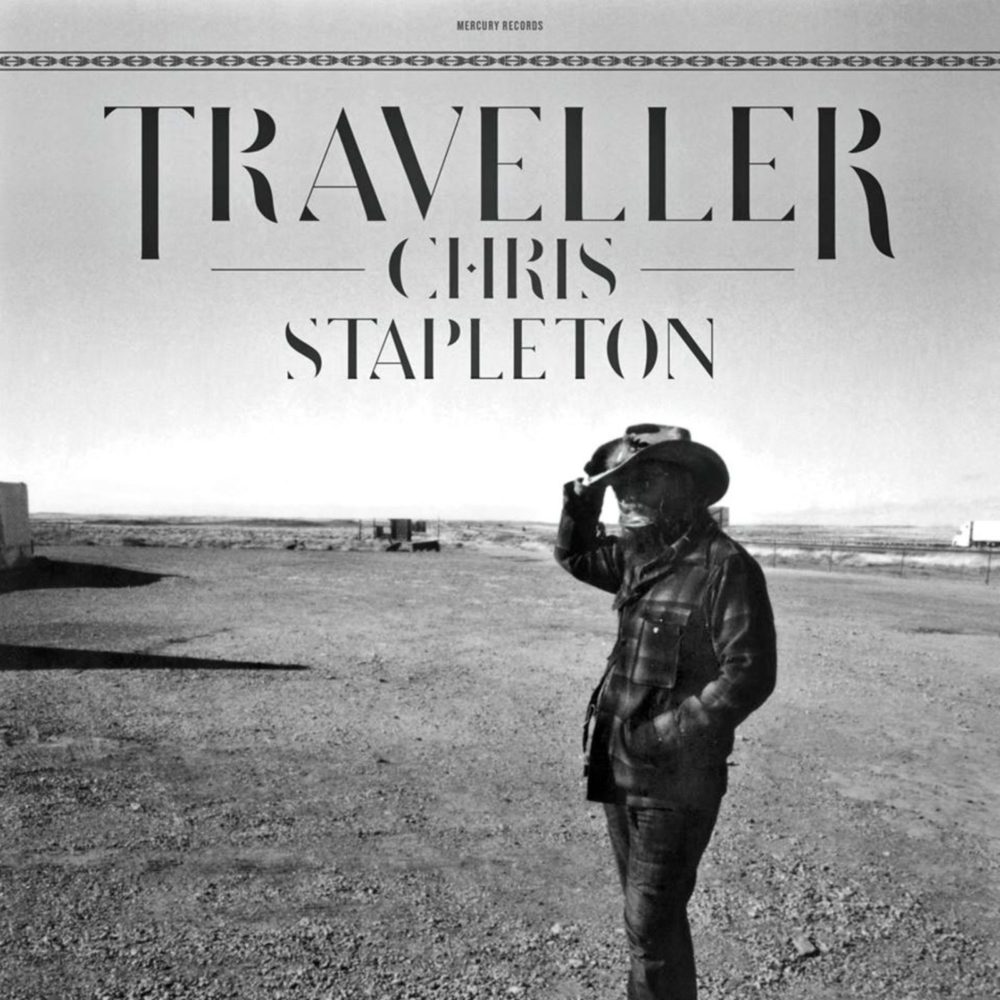「おせっかい」な京都のスタジオ、マザーシップ。エンジニア野村智仁が語る、人付きあいと音作り
先に公開したCHAINSの記事の取材場所となったのはニューアルバム『decades on』のレコーディングも行った、ラリー藤本(Ba)が営む京都・烏丸十条からほど近い音楽スタジオ〈マザーシップ・スタジオ〉。2002年のオープン以降、ここで生まれた名作を挙げ出したら数限りない。ゆーきゃん with his best friends『sang』(2007年)、山本精一『ラプソディア』(2011年)、世武裕子『リリー』(2010年)、キツネの嫁入り『俯瞰せよ、月曜日』(2012年)、Turntable Films『Small Town Talk』(2015年)、騒音寺『百歌騒乱』(2018年)、ラッキーオールドサン『旅するギター』(2019年)、バレーボウイズ『雨があがったら/セレナーデ』(2019年)……。
そんなこのスタジオでチーフ・レコーディングエンジニアを務めているのが野村智仁さんである。ちょうどこの日の取材時にも在席しており、少しお話を聞かせていただくことに。彼の音楽づくりに関わる姿勢や、エンジニア視点でのCHAINS『decades on』について語ってもらったミニインタビューをお届けする。
CHAINSのインタビューはこちらからご覧ください。
野村さんがマザーシップスタジオに携わるようになった経緯を教えてください。
自分が働き始めたのは2002年の営業開始からです。自分がまだ大阪のビジュアルアーツ専門学校の音響芸術学科にいた時、あるバンドのアルバム制作にレコーダーを操作するアシスタントとして関わらせてもらいました。そのバンドのベースがラリーさんで、そこからの繋がりです。このレコーディングのあと、ラリーさんが京都で新しくスタジオを立ち上げることとなり、ちょうどエンジニアを探していたので声をかけていただきました。当時レコーディングに関しての知識はまだまだ乏しかったのですが、機材の選定やスタジオワークの進め方は結構最初から任せてもらったのがありがたかったです。
初めてレコーディングをするという学生バンドから、大ベテランまで様々なミュージシャンが利用されていますが、京都にもいくつか音楽スタジオがある中で、マザーシップの特徴と言えるものはどこにあると考えていますか?
マザーシップは元々あった一軒家を改装してできたスタジオなので、演奏ブースやコントロールルームは防音・整音施工されているのですが、建物内のあらゆるところに「普通の家」を感じると思います。この「普通の家」感に他のスタジオとは少し違う居心地のよさがあるのではないでしょうか。
その一方でスタジオワークとしての特徴はいい意味で「おせっかい」です(笑)。特にレコーディング初心者の方の中には、例えばパート楽器間で不協和音があったり、シンコペーションが統一されていないということも多々あります。レコーディングの時にこの部分を一つ一つ修正していくのは時間がかかりますし、限られた時間を有効に使ってもらうため、事前にデモ音源を聴かせてもらって、問題になりそうな箇所があればレコーディングまでに検討してもらうようにお願いすることもあります。
またまれにその内容によってはアーティストの創作領域に踏み込む事になる局面もありますが、そういう場合は丁寧にコミュニケーションをとって相談するようにしています。こういうことは割と初期の頃から自然と行って来ていますが、アーティストとの距離感が近いアットホームな雰囲気の〈マザーシップ〉故に出来てる事なのかなと思っています。

では一人のレコーディングエンジニアとして野村さんが大切にされていること、こだわっているところはどこでしょうか?
なるべくいい音でレコーディングするのはもちろんですが、いいテイクを残すためにはコミュニケーションもすごく重要だと思っていて。特にブース内にいる時に演者と交わす会話はテンションに直結しますので、その時々の状況に合わせてリラックスさせたり、テンポよく進めたり、私の方で場の空気やレコーディングの進捗をコントロールすることは大切にしています。
野村さんが手掛けた作品の中にも名盤は数多くありますが、中でも気に入っている作品はありますか?
ワイルド・フラワーズ(The Wilde Flowers)やキャラヴァン(Caravan)などでも活躍したキーボード奏者のデイヴ・シンクレアさん(Dave Sinclair)のソロアルバムは思い入れがありますね。『HOOK-LINE & SINCLAIR』(2021年)、『OUT OF SINC』(2018年)、『THE LITTLE THINGS』(2013年)という近年の3作品にエンジニアとして参加させていただきました。特にミックス作業が特徴的で、非常に細かな音量バランスを求められるんです。一般的なミュージシャンでは0.5dB以下のボリューム変化は気が付かないことも多いのですが、最終工程ではこのレンジ以下でのボリュームの上げ下げまで慎重に吟味される。私がうっかり音量操作をし忘れると、すぐに気づいて指摘をもらいました。全ての音に対してかなり神経を行き届かせた作品なので、気に入っています。

エンジニアとしてお仕事をされてきた中で、特に学びになったり、影響を受けた方はいますか?
山本精一さんとの作品作りは非常に影響を受けましたね。『プレイグラウンド』(2010年)や『ラブソディア』(2011年)をはじめ、歌もの作品を中心に多数のアルバム制作に関わらせてもらいましたが、最初の頃はレコーディングのスタイルに毎回びっくりしていました。通常はベーシックといわれるリズムと主要なコード楽器を録音、次にダビングという他の音を重ねていく進め方が一般的です。でも精一さんの場合は、ある時はギターの1フレーズから、ある時はサンプリングしたノイズからと、決まった手順がないんです。だけど徐々に見事な音楽が構築されていくので驚きの連続。自分のセオリーが狭く不自由だったことを学ばせてもらいました。また、即興性を重視されるので、サウンドチェックからレコーダーを回しておく習慣になりました。それに伴って音作りやレベル設定を判断するスピードは格段に上がったと思います。
Apple Musicはこちら
Apple Musicはこちら
今回CHAINSの新作アルバム『decades on』にもレコーディングとミックス・マスタリングを担当されていますが、エンジニア視点で特に意識したポイントはどこでしょうか?
CHAINSの作品に関わるのも初めてではありませんので、特にバンドからの細かいオーダーはなく任せてもらえました。でも音にこだわりが無いわけではなく、メンバーそれぞれに実はかなりあると思っていて(笑)。メンバーそれぞれの好みや志向性を見極めつつ、それを録り音にどう反映させていくのかがポイントだったかと思います。
中でも歌を大切に扱うバンドですので、新村さんのボーカルやコーラスを含めた声の処理には細心の注意を払いました。またスネアの音色が歌声と干渉するので、録音の時から入念に調整するのが重要。楽器の選定からピッチ、ミュート具合まで曲ごとにベストな音色を探っています。
あと今回はマスタリングまで担当していますが、新録の7曲だけではなく2018年、2020年と既に配信リリースされている曲を含めてのアルバム制作なので、ある程度の制作期間を経ているぶん全体の統一感を出すのは少し苦労しました。最終的には細かな違いも含めてマスタリングだけでも3バージョン用意して、みなさんに決めてもらったものを最終マスターとして採用しています。
最後に普段一緒にお仕事をされているラリーさんをはじめ、CHAINSとの付き合いも長い野村さんから見た、CHAINSの魅力について教えてください。
普段CHAINSのメンバーはものすごく口数が少ないんです。レコーディングの休憩中とかも心配になるくらい静か(笑)。でも、演奏が始まると全員が音でコミュニケーションをとり始めるんです。この絶妙の間合いでなり立っているところが、バンドとしての魅力になっていると思いますね。

マザーシップスタジオ
| 住所 | 〒601-8031 |
|---|---|
| ご予約・お問い合わせ | 075-681-3836 【電話受付12:00〜23:00 】 |
| Webサイト |
You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com