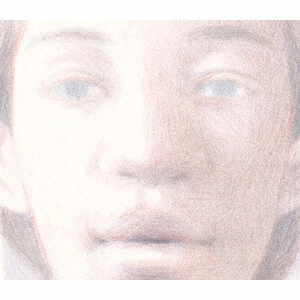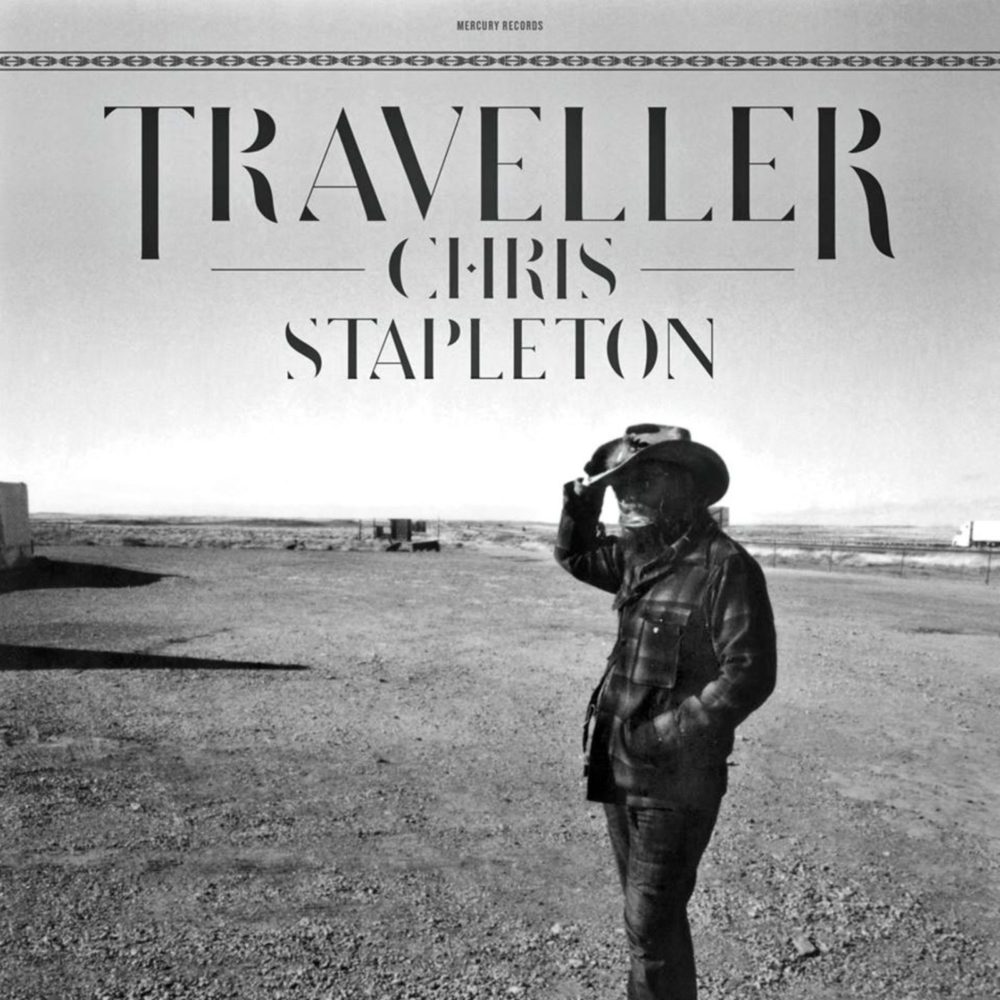発令!アジアに向けた日本からの開国宣言-BiKN shibuya 2023 クロスレポートNo.1
アジア音楽を照らす日本発ショーケース・フェスティバル『BiKN shibuya 2023(以下、BiKN)』が2023年11月3日(金・祝)に開催。アジアの人気アーティストたちと、日本からも世界を射程に見据えた面々が全35組が東京・渋谷で一堂に会する全く新しいライブ・イベントだ。ANTENNA編集部2名がそれぞれの視点で当日の模様をレポートする。
Cover photo:渡邉隼(落日飛車Sunset Rollercoaster)
今まで味わったことのない渋谷の空気
今回が初回の開催となった『BiKN』だが、このフェスティバルを立ち上げた経緯については、開催前に公開した実行委員であり《THISTIME RECORDS》社長の藤澤慎介さんのインタビューをぜひ読んでほしい。X(旧Twitter)でもいくつか反響をいただいたが、印象的だったのは「音楽シーンにおいてアジアの国々が連帯を結んでいる中で、日本が取り残されていることへの危機感」に対する共感が多かったことだ。『SYNCHRONICITY』の主催者である麻生潤さん、韓国在住で現地から音楽情報を発信しているライターの山本大地さん、今回の『BiKN』でもタイのアーティストの招聘に尽力したGinnさんをはじめ、それぞれ日本とアジアをつなぐ取り組みを行っている要人たちからの反応は、藤澤さんが話していた日本の課題に対して、さらなる説得力と、事態の深刻さや切迫していることを痛感することになった。
そこからも『BiKN』は単にアジアの人気インディー・アーティストが多数来日するイベントではないことがわかる。その「単に日本に呼ぶ」ことができなくなるかもしれない状況に、ギリギリで「待った」をかけようとする開国宣言の発令という意義を持って開かれるのだ。
〈Spotify O-EAST〉をメインとした渋谷・円山町周辺の6会場を周遊するサーキット・イベント自体は決して物珍しいものではない。しかし付近に到着した途端、様々な言語が飛び交っており、今まで味わったことのない空気を察知した。アジアのインディー音楽が好きで「こんなイベントを待ち望んでいた」という人はもちろん、出演アーティストはほぼ知らないがこの機会に新たな出会いを求めようとする人も多く、前のめりではあるがロック・フェスティバルの熱狂とはまた異なる、成熟した熱量の高さが心地よい。
そして日本人だけではなく、日本に滞在しているアジア出身者、この日のために日本を訪れたであろう旅行者、その中にはアジアだけでなく欧米から来たと思しきオーディエンスも多数。しかし「異国感」や「人種の坩堝」、「文化的モザイク」なんて言葉はちょっとそぐわない気がした。日本と海外、本国も異国も、どちらがメインでどちらがゲストもない。ただこの場所に大音量で流れる音楽だけは確かに全員が共有している、『BiKN』というフラットで新しい空間としか言いようがないのだ。この一言では表せない気配や体感を、一日中会場を往来しながら観たステージの模様を通して、少しでも伝えられればと思う。
魚とシャボン玉が彩るラウドな演奏、拍謝少年 Sorry Youth
筆者がこの日一番心を掴まれたのは〈O-WEST〉に登場した台湾南部の高尾出身の3ピース、拍謝少年 Sorry Youthだったかもしれない。9月に日本ツアーを終えたばかり。これまでも『SUMMER SONIC2015』『森、道、市場2019』への出演や、the band apartとのオンライン対バンライブの開催など、日本と積極的に交流を結んできたバンドだ。ライブは“你愛咱的無仝款(君は比類なき僕らが好きさ)”からスタート。グランジやポストパンク、エモを経由したヘヴィでラウドな演奏と、魂をぶつけるような歌はeastern youthを思わせるが、実際メンバー3人共通のフェイバリットだそう。また全員がイーブンに担う歌唱も特徴的だが、台湾での公用語である中国語(台湾華語)ではなく、使用人口が減少傾向にある台湾語を用いた歌詞にもこだわりを持っている。MCでは「日本に呼ばれてうれしいです。私たちは違う言葉だけど、音楽で国の壁を超えられます。ロックンロールのライブをしばし聴いてください」と、このために練習してきただろう日本語での挨拶に拍手が沸き起こった。
その後は“歹勢中年(Sorry No Youth)”や“暗流”など腹の底から力が漲るような代表曲を力強く演奏していくが、中盤からは彼らのアイコンである台湾の魚「虱目魚(サバヒー)」を被った屈強な男が登場。客席前方に位置する彼らのファンにとっては「待ってました!」とばかりに会場の熱量が数段吹き上がる。また初めてライブを眼にする観客にとってはカルチャーショックほどの衝撃があったのか方々で声が上がっていた。さらに虱目魚男は延々とバブルマシーンで会場中をシャボン玉で満たすという、ライブハウスでは珍しい光景が広がる。終演後に隣にいた二人組が「めっちゃよかった!でも後半シャボン玉に気をとられてしまった……」と話していたのには、こっそり吹き出してしまったが、観客の記憶には間違いなく刻み込まれたライブだっただろう。
拍謝少年のステージが終了した時、向かいの〈O-EAST〉ではちょうどCody・Lee(李)のライブが始まっていた。この二組は昨年11月の『Emerge Fest. Japan』で共演してから交流があり、高橋響(Vo / Gt)はMCでもタイムテーブルがかぶって拍謝少年が観られないことを悔やんでいた。そしてなんと彼らのナンバー“歹勢中年”を演奏し始める。そしたら中盤から拍謝少年の3人が飛び入りでステージにあがり、ぴょんぴょん跳ねながら二組で大合唱。最後には高橋が自分のギターを維尼(ウェニー、Vo / Gt)に渡してソロを促したのも幸せな一幕だった。
フィリピンのポップ・アイコンとして日本に帰ってきた、ena mori
この時点で15時ごろ。12時にスタートしてしばらくは快調に会場を回っていたが、徐々に観客は増え続け、これくらいの時間になるとどこも大盛況。特にアコースティック系のアーティストが並ぶ〈7th Floor〉は以降最後までステージが見えないほどにごった返していた(そんな状態でも鄭宜農 Enno Chengのアコースティックギターと甘く澄んだ歌が素晴らしく、人に埋もれながらもうっとりしてしまった!)。出演する全35組はいわゆるロックバンド形態のアーティストが主力ではあるものの、出身国はもちろんジャンル・編成などはほどよくバラエティに富んでいる。
その中でも〈clubasia〉に出演した日本とフィリピンをルーツに持つena moriは、稀有なポップ・アーティストとしての存在感を放っていた。バンドメイトであるTim(Key)、Cairo(Dr)とステージに登場。アルバム『DON’T BLAME THE WILD ONE!』(2022年)の1曲目でもある“there’s a fire in my kitchen up it goes I’m to blame”がオープニングテーマとしてかかり、“VIVID”からはエネルギッシュに飛び跳ねながら、眉から足の指先まで意識を及ばせ、躍動していくステージングがたまらなくキュートだ。加えてTimもキーボードから時折ギターやカウベルを持ちだし、enaとともにステージを華やかにしていく。MCでは15歳で日本からフィリピンに留学し、現地での音楽活動を続けてきた彼女にとって、バンドセットによる日本でのライブは今回が初めてで、夢が叶ったと語っていた。そして唯一日本語を含むレパートリーである日本のDJ・音楽プロデューサーTomgggとのコラボ曲“いちごミルク”を披露。弾けるようなポップ・チューンではあるが、丁寧に歌う彼女の姿は感慨に浸っているようにも見て取れた。
この日から6日後の11月10日、フィリピン最大の音楽賞『Awit Awards』の受賞者が発表され、ena moriは前述の『DON’T BLAME THE WILD ONE!』で「ALBUM OF THE YEAR」を受賞した。名実ともにフィリピンのアイコンとなった絶好調の時期でのパフォーマンス。このタイミングでもう一つのルーツである日本で披露したという点でも意義のあるステージだった。
ena mori(Photo:Masushi Watanabe)
スターダムを駆け上がる最中のSilica Gelでブチ上がれる至福よ
そろそろクライマックスが見えてきた19時。ヘッドライナーである落日飛車 Sunset Rollercoasterが登場する〈O-EAST〉以外の5会場ではトリのライブがスタートしていく。その横並びがShe Her Her Hers〈O-WEST〉、THREE 1989〈clubasia〉、FORD TRIO〈O-nest〉(橋本薫(Helsinki Lambda Club)とのコラボ曲“เปล่าเลย (Plao Loei)”の生披露に会場が大いに沸いたそう)、Tomii Chan〈7th Floor〉(急遽優河が登場し『ティファニーで朝食を』の主題歌“ムーン・リバー”をコラボしたらしい!)と、なんと酷な選択を迫られるものだ……。
四方八方に後ろ髪を引かれながらも、今勢いに乗っており特にライブパフォーマンスが凄いと評判を聞いていた、韓国の4人組ロックバンドSilica Gelを選び〈duo MUSIC EXCHANGE〉に到着した。丁寧にサウンドチェックを行っている姿さえも、すでに観客はうっとりした様子で見つめており、少しイントロを鳴らすだけで歓声が上がる。そして“Sister”から本編が始まると、悲鳴にも似た熱狂が沸きだす。アルバム『Silica Gel』(2016年)に収録されている本曲だが、サイケやシューゲイザーを経由しながら、やたらと前のめりなテンポでドライブをかけていくアレンジはデビューEP『Pure sun』(2015年)の方に近い。しかし最後にはアルバムテイクだけに入っている「今日の晩ご飯は何がいい?~栄養を取ろう 栄養を取ろう」と日本語のセリフの仕掛けもしっかり見せてくれる複合型の“Sister”だった。そこから一拍おいて彼らを一躍トップ・バンドに押し上げた昨年のヒット曲“NO PAIN”になだれ込んだ時の高揚感よ!サビでは大合唱が起きるし、キム・ハンジュ(Key / Gt / Vo)は手拍子を煽る。この日一番の一体感がもたらされたシーンだった。
そして間髪入れず“Budland”、“Realize”とキム・チュンチュ(Gt / Vo)の鋼のように硬質なギターリフがフィーチャーされた、昨年以降に発表された楽曲が並ぶ。この流れの極めつけとばかりに披露されたのが“Tik Tak Tok”。キャッチーなメロディに対して、曲の後半はキム・チュンチュのハードなギターソロパートに占められる、今の彼らのスタイルにおける極北みたいな楽曲だ。その場にいる観客全員の心を打ちぬくソロは約4分半に渡り、終わった後もしばらく拍手が鳴りやまないほど。新時代のギターヒーローっぷりを見せつけた。
最後はファンキーなギターポップ・パートとドリーミーなパートを行き来する“Everyday Does”で明るく終演を迎えたものの、観客の声援が収まらずに急遽再登場。キム・ハンジュのところに集まり、みんな一つのPC画面を見つめて相談するのもまた微笑ましい光景だ。会議の結果“9”を披露し、たっぷり50分以上のステージを見せてくれたSilica Gel。今回の来日は5年半ぶりだったが、2018年の時とは編成もパフォーマンスも自身を取り巻く環境もガラッと変わった。インディーニューカマーというより、もはや韓国を代表するバンドとして、あまりに堂々たるステージだった。
Silica Gel(Photo:木下マリ)
あらゆる役目を引き受けるステージ、落日飛車 Sunset Rollercoaster
残るは出演者は落日飛車 Sunset Rollercoasterのみ。この日〈O-EAST〉の前の出番でもあったOGRE YOU ASSHOLEと2016年に台湾で共演したことを皮切りに、日本のバンドとのコラボレーションや、頻繁に来日公演も行なってきた。今年は『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演という快挙も成し遂げた台湾を代表するバンドである。主催・藤澤さんも「彼らの出演によって僕たちの本気度が伝わればいい」とも言っていた、今回の『BiKN』の象徴を担う存在だ。
開始10分前でオーディエンスは後方まで埋まっているが、他の会場から移動してくる人の流れはまだまだ落ち着きそうにない。会場BGMが消え、静寂の中でメンバーが登場し、盛大な拍手に包まれながら“Burgundy Red”からライブがスタート。雄大なビートとロングローンのシンセとギターフレーズが織りなす、なんて厳かなパフォーマンスだろうか。昨年発表された“Little Balcony”から、まだアジアン・オリエンティッド・ロック(A.O.R)のスタイルが開花する前のデビューアルバム『BOSSA NOVA』(2011年)収録のブリットポップやガレージが効いた“No Man’s Land”や“Little Monkey Rides on the Little Donkey”まで、全てのキャリアからいいとこ取りの大盤振る舞いなセットリスト。私的には2019年のコンセプトEP『Vanilla Villa』から“Vanilla”と“Viilla”を一連の流れで堪能できたのがたまらなかった。
そろそろ終演も予感する中、会場のボルテージがさらに一段階上がったのはKuo(Vo)が観客からの声援に返答し、一呼吸おいて「Every time you lie in my place……」と歌い出した瞬間。問答無用の代表曲“My Jinji”である。そこかしこから「Whoo!」と声が上がり、次第に誰しもがうっとり身体をただ揺らしていた。駆け上がるフレーズはシンプルながら、絶妙に拍子をずらし、いつまでも聴いていられるアウトロもたっぷりの、7分間の甘いアバンチュール。その後のアンコール“I Know You Know I Love You”まで、70分を超える雄大なパフォーマンスは、この場所に居合わせた全ての人々に向けたエールのようだったし、Elephant Gym、Mong Tong、落差草原WWWW、百合花Liliumなど、今回は名を連ねていない、台湾が世界に誇るバンドたちを背負っているような覚悟すら見えた気がした。
落日飛車Sunset Rollercoaster(Photo:渡邉隼)
BiKNという名の運動がやっとスタートを切った、渋谷11.3
これまで観ることができなかったアーティストのステージになるべく足を運ぼうとしたあまり、日本のアーティストをあまりじっくり観ていないことに後から気づいてしまった。会場を訪れるまで、このフェスティバルにおける日本組の存在感という視点は、今回のレポートで重要だと想定していたが、すっぽり抜け落ちていたことを告白しておきたい。今まで味わったことのない空気、大盛況の会場と、観客の心地いい熱量に感化されて、一日過ごすうちにただ純粋な音楽に対する好奇心だけで行動していた。まとまった休憩や、フェスティバルのもう一つの醍醐味とすら思っていた腹ごなしの時間も取らず、できる限りたくさん観たいという気持ちが最後まで続いたのはいつぶりだろう。あまりに深みや捻りもない結論に帰着して小っ恥ずかしいのだが「まだ知らない音楽の世界に出会えることは喜びだ」と再確認させてくれた。
そこに至る遠因としては、全出演者に40~50分の時間が与えられていたことも重要だったと思う(落日飛車のみ70分)。大量の出演者がギチギチのタイムテーブルの中で、せめて自己紹介やハイライトとなるようなパフォーマンスをし、オーディエンスも自身の嗜好とのマッチングを主目的としてテイストを把握していくようなイベントも散見される昨今だ。その中でじっくりそのアーティストの表現に浸ることができる大よそアルバム1枚分ほどの時間を設けたことは、「よさそうだった」で終わるのではなく、この日からどっぷりファンとなってしまうのにも十分だった。
終演後、公式Webサイトにはステートメントが更新されていた。『BiKN』の想いを受け止めた全ての人への感謝を綴った後、「一度灯したこの熱を絶やさず、輝かせ続けられますように!!」と次への期待を込めて締めくくられている。おそらく主催の藤澤社長や実行委員会の方たちは、今回の成功に胸を撫でおろしながらも、冒頭に記した日本の課題に対して、なんとか土俵際で踏ん張ることができたと思っているのではないだろうか。おそらくすでに次なる試みに向けた動きを始めているだろうし、また今回この場所に感化された人たちによる新たな動きも待ち望んでいるはず。『BiKN』という名のアジアに向けた日本からの開国運動はまだスタートを切ったばかり。このムーヴメントが広がっていくことを心から願っているし、筆者も一人の音楽ライターとして行動で示していきたいということを、ここにそっと宣言して本稿を締めようと思う。

You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com