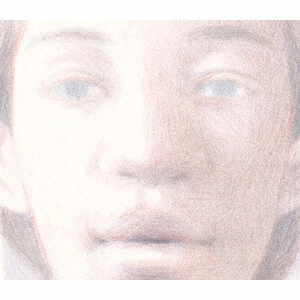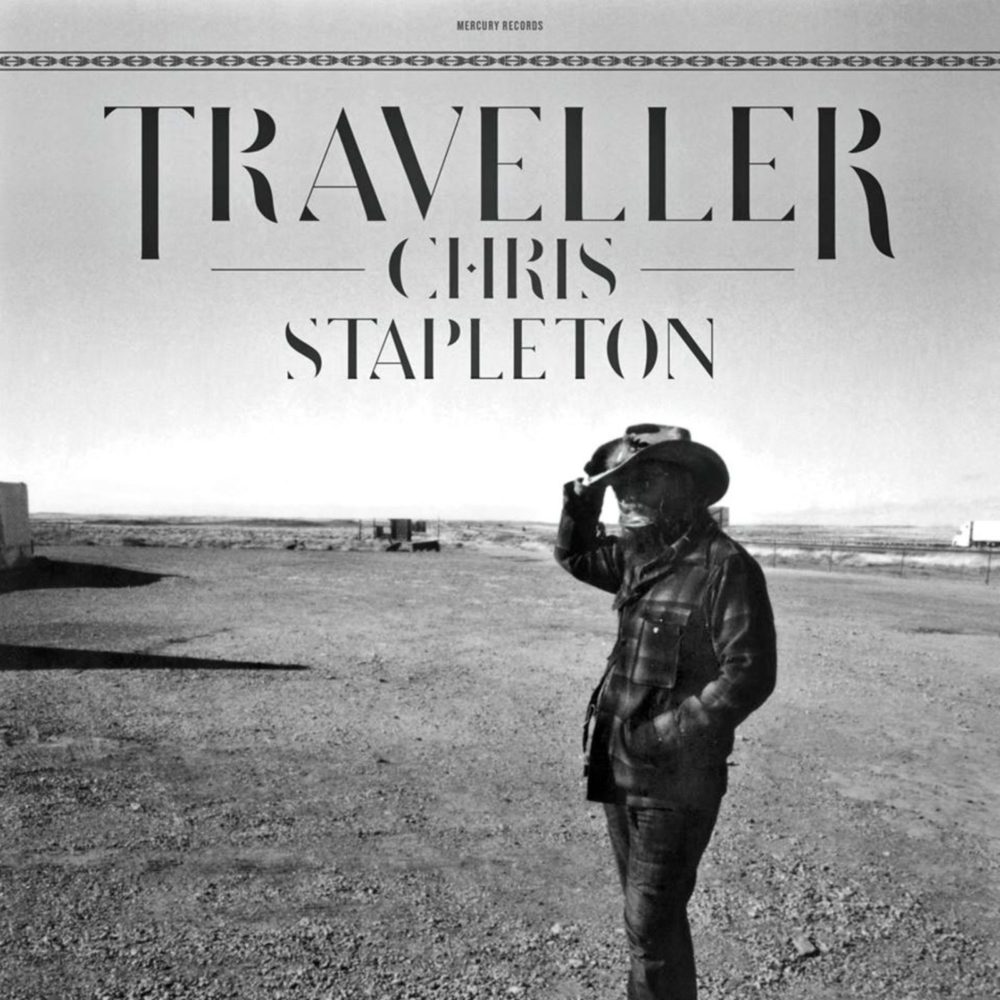台湾インディーバンド3組に聞く、オリジナリティの育み方『浮現祭 Emerge Fest 2024』レポート(後編)
2019年から台湾・台中市で開催され、今年5回目を迎えた『浮現祭 Emerge Fest』。本稿では2月24日(土)~25日(日)に行なわれた現地レポートを2記事に渡ってお届けする。後編では2日目に出演した、ANTENNA的注目台湾インディーバンドである老王樂隊 Your Woman Sleep with Others、SHOOT UP、拍謝少年 Sorry Youthの3組にバックステージで少し話を聞くことができた。
『BiKN shibuya』から受け取ったバトンを携え『浮現祭』へ
そもそも今回このフェスティバルの取材に行くことになったのは、台湾のメディア・プラットフォームTaiwan Beatsからのコラボ・オファーが発端だった。2015年に設立され「台湾音楽の世界発信」をテーマに現地の音楽やカルチャーをインターナショナルに発信している。Webサイトは日本語対応しており、SNS(X・Instagram)の日本版アカウントも定期的に更新されている。また自身のメディアだけではなくQetic、音楽ナタリー、Mikikiなどとのコラボレーションや、ミュージック・マガジン2020年4月号の特集『台湾音楽の30年』にも協力するなど、これまで日本のメディアを通じて台湾の音楽カルチャーを伝える活動を行ってきた。
筆者はANTENNAで昨年11月に開催された日本発ショーケース・フェスティバル『BiKN shibuya』の取材を行い、台湾から出演した鄭宜農 Enno Cheng、淺堤 Shallow Levée、拍謝少年、落日飛車 Sunset Rollercoasterのステージをこの時初めて目の当たりにした。国内インディーアーティストを中心に長らく執筆活動を続けてきた私にとって、未開拓であったアジア各国のインディーカルチャーを浴びる経験は新鮮そのもの。そんな興味・関心の熱が冷めやらぬ中でのオファーだ、台湾に行くしかなかった。
今回の取材に際してTaiwan Beatsは、『浮現祭 Emerge Fest(以下、Emerge Fest)』とのやりとりや、現地の案内・通訳まであらゆる面でサポートしてくれた。さらには事前リサーチで、このフェスティバルを通して台湾インディーを語る時に軸となるだろうといくつか挙げていたアーティストの中から、2日目に出演した3組に対して、対面で話を聞かせてくれる機会まで。そこで、ライブや会場の様子を通して『Emerge Fest』全体を現地レポートした前編に対して、この後編ではインタビューを実施できた3組にグッとフォーカスし、彼らの音楽の魅力に主眼を置きたいと思う。1日目をフルで体感したことで体力は削られながらも、日本と違う環境で過ごすことにも身体が慣れてきたこの日。めくるめく台湾インディーバンドの森のさらに深いところまで突入だ。

変化の渦中にある台湾式フォークロア、老王樂隊 Your Woman Sleep with Others
事前に出演アーティストをリサーチしている中で、最も独自性を感じていたのが、2015年結成の5人組バンド、老王樂隊だった。直訳すると「あなたの女性が誰かと寝る」という官能的なアイロニーを持ったバンド名に対して、台湾の若者が抱える現代的なメッセージとシンプルなバンドアレンジでアウトプットされたフォークロアなサウンドが特徴だ。
特筆すべきはチェロ奏者である邵佳瑩(シャオ・チアイン/通称、ステラ)の存在だろう。ときにはアンサンブルの先頭に立つようなフレーズを担い、ときには低音でサウンド全体のムードをじんわりと敷いていく。昨年台湾のインディー音楽アワード『金音創作奨(Golden Indie Music Awards)』の最佳民謠歌曲獎(ベストフォークソング賞)のノミネートを果たした“我在愛情的盡頭看見了你和我”での、心の琴線に訴えかける叙情的なチェロの音色はたまらない。先日発表されたKaty Kirbyの2ndアルバムに収録された“Party of the Century”でのチェロの存在感と相似形を見ることもできるし、Big Thief以降の欧米含めたインディーフォークロックの潮流の中に彼らを位置づけることも容易だ。

……とここまでが事前に楽曲を聴いた印象。
5人が〈浮現舞台〉に登場したのは14時20分ごろ。馮會元(フォン・ホイユアン)(Dr)がハイハットで16ビートを刻み出す。そして廖潔民(リャオ・チーミン)のベースとステラのチェロが不穏さを醸す低音フレーズで掛け合うセッションパートからライブはスタートした。バンドの中心人物である張立長(チョウ・ジョシュア)(Vo / Gt)のアコースティックギターの音色にこそ、事前のイメージと地続きなものを感じられるが、童偉碩(トン・ウェイ・シュオ)(Gt)によるテクニカルなギターソロもダメ押しとばかりに放たれ、ほぼハードロックかヘヴィメタルに手をかけた楽曲だった。あとから聴くに、この1曲目は現在制作している新曲で、常にフォークとロックの間で自分たちのスタイルを探してきたが、次作はこれまでで最もロックに寄ったものになるかもしれないとのことだった。


そもそもボーカルのチョウこそ、自身のフェイバリットとして張懸(現名義:安溥)や日本のアーティストではカネコアヤノも好きというシンガーソングライター志向がうかがえたが、ギターのトンとベースのリャオはX JAPANからの影響が大きいと語り、ドラムのフォンは小さい頃からキリスト教の音楽に親しんできたという。全員の共通言語となるようなリファレンスは「ない」と言い切るところが興味深い。
現在のこの編成に辿り着いたのも、当初はメンバーが流動的でベースの不在時にチェロ奏者の前メンバーを誘ったことがきっかけだそうだ。その後再びベースが加入したが、チェロもそのまま残ることに。周りのグループにはいなかったこの編成で自分たちのオリジナリティを目指すようになったという。明確に狙いがあったわけではなく、自然と行きついたスタイルだったのだ。


しかしこのアンサンブルは紛れもなく最大の強みだ。活動していく中で、ベースは5弦を用いるようになり、チェロもアコースティックからエレクトリックに持ち替えたことで、低音を担う二つの楽器も役割の幅を広げていった。またステラによれば、チェロはギターと交差しながらリードを担うこともあるので、リズムとメロディどちらにも出ていける存在だと、自身の役割を捉えている。またロックバンドの中にチェロがいるというスタイル自体は、隱分子 Infancy Bandという先輩格のバンドもいるので参考にしたとも語ってくれた。
この日のライブに話を戻すと、ハードな新曲群に対して後半は代表曲を中心に雄大な世界を描いていく。やはり“我在愛情的盡頭看見了你和我”のチョウとステラのダブルボーカルと美しいオーケストレーションにはこみ上げるものがある。そしてラスト2曲“安九”、“我還年輕 我還年輕”では観客は大合唱だ。染み入るようなミディアム・チューンなのに、会場のあちこちでサークルモッシュが起こっていた。

ボーカルのチョウ、ギターのトン、ベースのリャオの3人は台中出身とあって、この地で開催される『Emerge Fest』には思い入れもひとしおのようだ。緊張感溢れるハードな新境地から、穏やかにリラックスした雰囲気の台湾式フォークロアへ。そんな今日のライブをチョウは「抜罐(吸い玉療法、カッピング)みたいだったね」と独特すぎる例えで総括してくれた。

自分たちのスカパンクの完成形を見せつけたSHOOT UP
続いて訪れたのは前編でも触れた、観音廟の真向かいに建てられた〈清水紫雲巌 QINGSHUI STAGE〉。何度見てもこの位置関係でライブをすることに驚いてしまうが、到着したタイミングの直前まではアイドルグループの出演が続いており、ゆるめるモ!がパフォーマンスしていた。会場の脇にはアイドルとの交流に並ぶファンの長蛇の列ができている。観音廟の麓でアイドルの握手会。これもまた今まで見たことのない光景だ。
ステージに登場したのは一転してヤンチャでアッパーな大人たち。台中を拠点とするバンドSHOOT UPである。昨日OC experimentを観た時のスムースな空気とは正反対で、リハーサルの時から最前列を陣取る観客の熱狂がとにかく激しい。この日を待ち望んでいたと言わんばかりに本編が始まる前から「SHOOT UP! SHOOT UP! SHOOT UP!」とコールが起こる。何でもこの日が2024年初のライブパフォーマンスであり、かつトランペットの吳極(ウー・ジー)とサックスの柯達(コダック)が加入して初のステージだそう。


彼らが標榜するスタイルはスカパンク。新メンバーと、終始ゴキゲンな振る舞いが見ていて楽しいトロンボーンの花澤愷も加えた3人のホーン隊が重なる分厚いサウンドは強力だ。ステージ後に話を聴くと「自分たちのやりたいスカパンクができる体制が整った。ようやく完成形になったんだ」と、このメンバーでの初ライブにしっかり手ごたえを感じている様子。実際、2012年の結成当初はストレートなパンクバンドであり、冒頭に披露された“25”などはスカよりもメロコアやポップパンクの要素の方が強い。メンバーの増減はありながら結成から10年以上経ってようやく理想に近づいた喜びを爆発させたパフォーマンスだ。
会場は常時モッシュ状態。こんなに街のど真ん中でダイブが起こっている光景も初めてだった。あっけらかんとした曲調だが稼ぎが少ない生活の悲哀が歌われた“Good night my friends”で見事なフィナーレを飾り、メンバーは大勢の観客と観音廟をバックにステージから写真撮影を行うが、すぐさまアンコールが起こった。まだ後にも出演アーティストが控えているが、ボーカルの阿嵐(ラン)が感慨深そうに引き受けて“川流”を披露。この曲も、うだつのあがらない自分を叱咤しながら、最後には「Drink beer !(喝吧)」と繰り返す歌だ。彼らの歌には常に労働者としての哀愁が滲んでいて思わず心に刺さってしまう。曲が終わっても2回目のアンコールが鳴りやまない観客に向けて両手を合わせて何度もお礼を告げ、ステージを後にする彼らの愛されっぷりに感動してしまった。

台湾では数少ないスカパンクのスタイルだが、ランによればバンドの数は関係なく、自分を常に前向きにさせてくれる青春時代から大好きなこの音楽を、本気でやれることに幸せを感じているという。RancidやNOFX、日本のバンドの中でもHEY-SMITHには大きな刺激を受けたそうだ。ドラムの邱凡宸(キュウ・ボンシン)は一時期日本の学校で音楽を学んでいたということで、日本語も堪能。メンバーと私たちの通訳も率先してやってくれた。
最後に次の目標を聞くと、アルバム制作と国外でのライブツアー、「もちろんまずは日本でやるよ」と再会を誓ってインタビューを終えた。とびきりハッピーでなぜかグッと来てしまうSHOOT UPのスカパンク。理想のメンバーが揃ってすごいライブができるのだから、あとは名盤を作るだけだ。彼らの活躍が台湾外に轟く日はもう間近に迫っている。

台湾インディーの精神的支柱としての堂々たるステージ、拍謝少年 Sorry Youth
前述の筆者がアジアのインディーバンドたちに興味を持つきっかけになった『BiKN shibuya』で一番心掴まれたのが、高雄と台中で生まれ育った3人によるバンド、拍謝少年だった。あの渋谷の〈O-WEST〉で観た、ヘヴィでラウドな演奏と、3人全員の魂をぶつけるようなボーカル、そして彼らのアイコンである台湾の魚「虱目魚(サバヒー)」を被った男のゲリラ的なパフォーマンスは、シンプルなのにとびきりセンセーショナル。だからこのフェスティバルの取材企画が持ち上がった時の最初の動機は、出演ラインナップを見て「Sorry Youthの台湾現地のライブはぜひ見てみたい!」だったことを告白しておきたい。

『Emerge Fest』には2019年の初回から出演している常連であり、薑薑(ジャンジャン)(Ba)と宗翰(ゾンハン)(Dr)は台中出身。「最初はもっと都心部ではじまったけど(2019年は台中市にある台中インターコンチネンタル野球場が会場)、年々街の特徴を活かすフェスティバルに変化しているのが嬉しい」とジャンジャンが語る。2005年の結成から台湾の音楽フェスティバルの勃興を演者として見届けてきた台湾インディーシーンの精神的支柱的存在でもある彼らが、メインである〈浮現舞台 EMERGE STAGE〉と双璧を成している、2番目に大きなステージ〈光景舞台 SCENE STAGE〉の大トリとして登場した。隣の〈浮現舞台〉ではヘッドライナーのずっと真夜中でいいのに。(ZUTOMAYO)を待つばかりの状況だが、こちらにもどんどん熱いファンが詰めかけてくる。


この日は、孩子王 Kid Kingや淺堤の作品にも参加しているプロデューサーのEasy Shen(イージー・シェン)をサポートギター・キーボードに加えた4人編成。“你愛咱的無仝款(君は比類なき僕らが好きさ)”からスタートしたが、彼らともなればどの曲でもAメロからオーディエンスは大合唱。しかしなんとこの大きな会場でこそ映えるスケールの大きな楽曲たちだろうか。代表曲である“歹勢中年”のようなギターをかき鳴らしながら、声をあわせて歌うことの喜びを詰め込んだようなパワーポップ・チューンは言わずもがな。“踅夜市 Nightmarket”みたいに感傷に訴えかけるノスタルジーに溢れたパーソナルな楽曲や、この日ラストに披露された10分を超えるプログレッシブな構成を持った“兄弟沒夢不應該(男は夢を捨てるな)”でも、思わず手を上げたくなるスタジアム・ロックとして聴こえてしてしまう。
彼らの歌詞は台湾の公用語である中国語(台湾華語)ではなく、使用人口が減少傾向にある台湾語(台湾閩南語)を用いている。案内してくれたTaiwan Beatsのチェ・シーからすると、田舎の祖父母が話していたような懐かしい感覚を受けるのだそうだ。台湾の人の遺伝子に刻み込まれた郷愁が彼らの楽曲をさらに親しみやすく、さらにはアンセムとしても響くのかもしれない。この日は『BiKN shibuya』で観た虱目魚男が現れることはなかったが、ライブが進むごとに観客から彼らのグッズである虱目魚タオルが掲げられ、会場中が魚だらけの幸せな光景が拡がっていた。


日本から来たことを彼らに伝えると、『THE FIRST SLAM DUNK』は3人で観に行って思わず青春時代に帰った気分になったことや、維尼(ウェニー)(Gt)は『細野晴臣 録音術 ぼくらはこうして音をつくってきた』(鈴木惣一朗 著)が昨年台湾語に翻訳出版されたから、今は一章ずつ読んで細野作品を研究していることも話してくれた。
現在は2021年作『歹勢好勢(Bad times, Good Times)』以来となる通算4作目のアルバムを制作中。目指しているのは「原点回帰」だそう。結成当初は3人が住んでいたアパートで日々練習と制作に励んでいて、あまりの騒音に苦情が来ながらも1stアルバム『海口味 Seafood』(2012年)を完成させた。そんな彼らが言うところの「ノイズアパート時代」を思い起こすような、ラウドで初期衝動に溢れたパーソナルな作品に取り組む時期に来ているらしい。イギリス・ブリストルのIDLESを始めとする近年のポストパンク・リバイバルの流れも大きな刺激になっているそうで、新たな扉を開こうとしている台湾インディーロックバンドの雄の今年の動きは注目しておきたいところだ。
台中に音楽を集める場所であり、日本と台湾の音楽を繋ぐ場所でもある『浮現祭』
2日間『Emerge Fest』の会場を周り、3組に話を聞いて感じたのは、2000年代後半から2010年代にかけて一時代を築いた透明雑誌や、欧米でも人気を博している落日飛車の次世代を担う台湾インディーバンドの群雄たちは確実に生まれているということ。一方でこのフェスの中だけではキャリアや活動拠点、サウンド志向の近しいバンドたちがシーンを形成するような動きはあまり感じ取ることができなかった。
今日出ているアーティストの中でのおすすめや仲がいい人はいるかなどもインタビューの最後に聞いてみたりもしたが皆一様に「一緒に切磋琢磨している存在だから、一組に絞れなくてみんなおすすめ」といった具合。それはバンドたちが共通して集うようなライブハウスの数の少なさもあるだろうし、その周りに影響されにくい環境が現在はオリジナリティと多様性を育むポジティブな方向に作用しているのかもしれない。
だからこそそんなインディーバンドたちを、台北よりさらにライブをする場所が少ない台中で一堂に会する、『Emerge Fest』というフェスティバルの意義は今後ますます大きくなってくるだろう。拍謝少年 の3人に別れを告げ、会場に戻るとずっと真夜中でいいのに。が紫のスモークが立ち昇る中で大歓声と大合唱を巻き起こしていた。Open Reel Ensembleによるオープンリールを含んだセッティングも大がかりかつ特殊なもので、このパフォーマンスを実現させるための関係各所の創意工夫や気概を感じる。日本の音楽を台湾に伝える役割においても、『Emerge Fest』は奇特な場所であることを痛感した二日間だった。

You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com