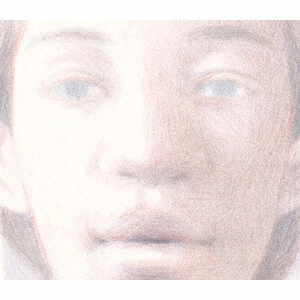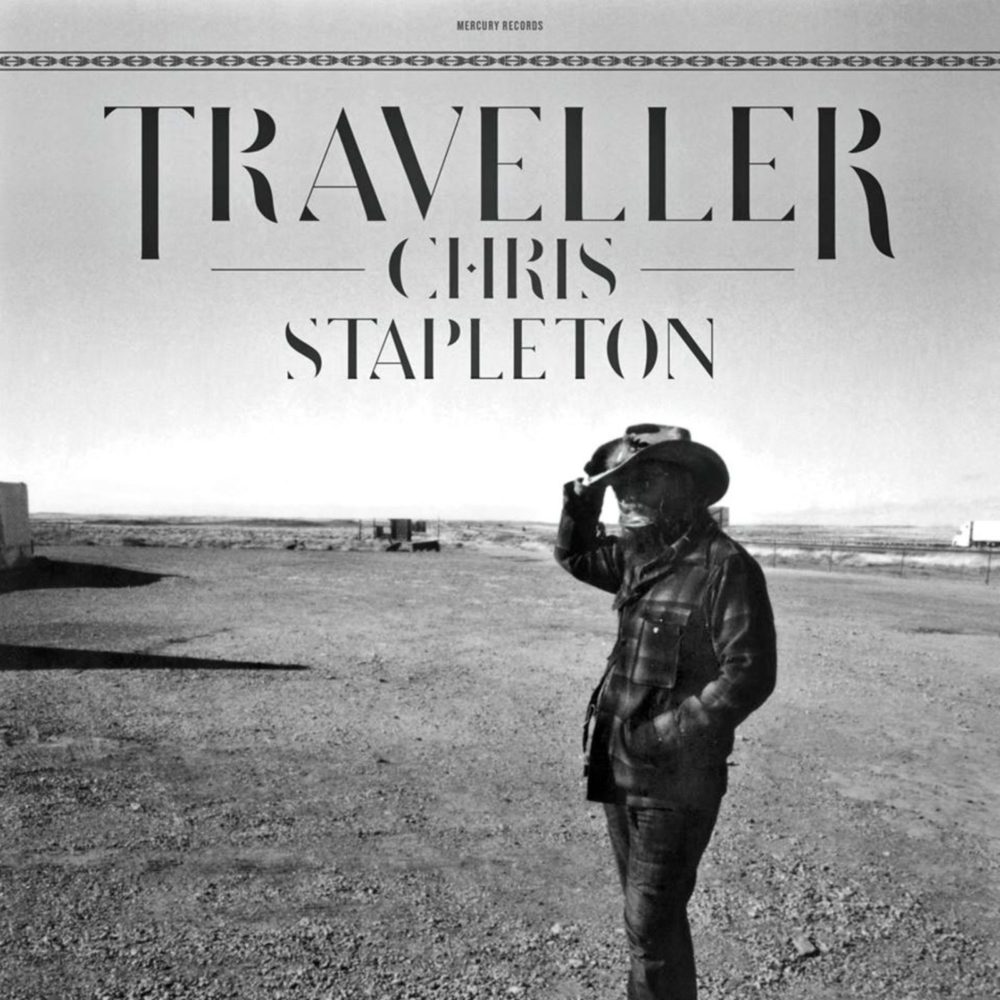ボロフェスタ2022 Day4(11/6)- クリープハイプ、リベンジ。過去2年を取り戻す気概の最終日
今年21年目の開催を迎えた、京都のフェスティバル『ボロフェスタ』。今年は11月3日~11月6日の4日間に渡って〈KBSホール〉で、また4日の夜には〈CLUB METRO〉で開催されました。2014年から毎年ライブレポートを掲載してきたANTENNAでは今年も編集部あげての総力取材!各日1名のライターによる独自の目線でボロフェスタを綴っていく、全4記事のクロスレポートをお届けします。本記事では最終日の11月6日の模様をハイライト。
〈KBSホール〉を訪れるのは昨年の本イベント以来ちょうど1年ぶり。観客として、もはや秋の恒例行事となっているため、久しぶりに来た感慨よりも、毎年のルーティンとして気合いを入れて臨む気持ちの方が当初は強かった。しかし一度ホールに足を踏み入れると、昨年とは違う空間に、2019年以前の感覚が呼び起される気がした。中止となった2020年、ステージや収容人数を制限した開催となった2021年というイレギュラーを乗り越えた、本来のボロフェスタの姿だ。去年はなかった〈街の底 STAGE〉に漂う、湿気が充満し酸素が薄くなるような地下ならではの熱気。メインのホールステージから否応なしに漏れてくるバカでかいサウンドに、観客も一緒になって対抗していくようなロビーに位置する〈どすこい STAGE〉を包む不思議な一体感。この空気を形成しているのはなにより、昨年と比べ物にならないスタッフとお客さんの数の多さだ。
でもこの光景は決してコロナ以前のノスタルジーだけじゃない気がしている。昨年20周年を迎え、新たなディケイドの突入となる今年。「ボロフェスタの本寸法」をフルカスタム状態で行うことから、改めて先に踏み出そうとしているように思えた。何が起こるのかわからない仕掛けや、この場所でしか見られないという特別感よりも、度々このフェスが掲げている「いつでも誰でも戻ってこられる場所」としての包容力を例年より強く感じた気がする。そんな最終日の様子を振り返っていこう。
ULTRA CUBに漂う、ボロフェスタ直系バンドとしての自覚
まずは京都のバンドであり、ボロフェスタでもスタッフを務めるULTRA CUB。昨年に引き続いてトップの出番となったが、このフェスティバルを自分事に捉えながら、熱量吹き上げるような彼らのステージは現在のボロフェスタの精神を最も直系で体現しているバンドと言ってもいいかもしれない。5回目の出演となる今年は、カーミアタアキ(Vo / Gt)の歌からじっくり始まるミディアムテンポの“別の世界”からスタートすることで少し趣を変えていた。徐々にギアをあげていきながら、MCではこの日に向けてどのように準備してきたかをスタッフ目線で語ることで、観客にこのイベント独特の姿勢や味わい方を周知していく。最終曲の“八月のアリア”ではステージを飛び出し、ウルトラマンを模した櫓を駆け上って歌い叫ぶ様は、自分の役割を強く意識しながら観客の心をぐっと引き寄せていて、主催バンドとしての立ち振る舞いが光っていた。
Photo:渡部翼
Black petrol、空音、ニューリーが形成する新世代のシーン
同じ京都のバンドと言えど、エクスペリメンタル・ヒップホップ・バンドBlack petrolの盛り上げ方は対極と言えるものであった。1曲の中でテンポがスムースに移行していくジャズ・ファンクな演奏。ギター、ベース、ドラム、サックス、キーボードがグルーヴだけを共有し、突かず離れずテクニカルなフレーズをかましていく。そこにMCのSOMAOTAがラップしていくスタイルだ。もう一人のMCであるONISAWAがこの日欠席だったため、よりSOMAOTAが演奏陣を指揮しながら、観客の身体を心地よく揺らしていく臨機応変さが際立つ。またクールな演奏中とは一転し、SOMAOTAが喋り出すと丁寧に自分たちを紹介したり、観客に水分補給を促すところには行き届いた心づかいが伝わってきた。後半には飛び入りゲストとして空音を呼び込んで、コラボ楽曲“STREET GIG feat. Black petrol”を披露。この日の出演者に二組が名を連ねているということで、期待しているファンも多かっただろう。歓声をたっぷり受けながら、二人のMCのラップがスリリングに掛け合っていく光景はこの日ならではのものだった。
そしてその空音も自身のステージでは、〈街の底 STAGE〉で出番を終えたばかりのニューリーをベーシストとして呼び込み“all date”、“CIRCUS”をコラボする場面も印象的であった。二人は同じ事務所Broth Works所属とあって、心通わせながらも、ギラついた対抗意識も漂わせながら、ラップとベースソロを絡み合わせていた。Black petrol、空音、ニューリーと互いのステージを行き来する姿は観客にも新時代のシーンの概形をおぼろげながら示していたように思える。
Photo:岡安 いつ美
観客との対峙の仕方に滲み出るそれぞれの美学
ステージを渡った美しい連なりという点で言えば、THE NOVEMBERS、春ねむり、ROTH BART BARONという夕方の時間のホール内ステージのバトンを繋いだ3組も見物であった。いずれもボロフェスタにいることを放念してしまうような、ただ目の前で鳴っている音楽に没入していく風光明媚なサウンドスケープ。特に春ねむりは歌、ラップ、ポエトリーリーディングに、スクリームを行き来しながら、観客の胸に訴えかけていく。MCでは「私の音楽って必要ない人には本当に必要ない。でも必要と感じる人がいればちょっとだけでも何かを渡したい」という発言に建前なしのリアリティがそこに立ち昇ってきた。会場全体は一つじゃない。その場にいる観客一人一人と対話していくような、求心力を放っていた。
Photo:渡部翼
Photo:岡安 いつ美
Photo:渡部翼
それ以外も櫓のウルトラマンをいじりながらリハーサルも本番も関係なしに歌いまくり、一度MCとなればふにゃふにゃと。極めつけには加山雄三の“君といつまでも”を熱唱する奇妙礼太郎の姿には、とびっきりの色気と同時に木村充揮(憂歌団)の影を思い起こしたこと。待望のボロフェスタ本祭のステージを踏むこととなったアフターアワーズは、入場規制がかかる街の底ステージに登場。小さな室内の熱気をさらに焚きつけるように上野エルキュール鉄平(Dr / Vo)が滝のような汗を流していたこと。しかしその中で披露した“ニュータウン”でショーウエムラ(Vo / Ba)が飛びきりの感慨を受けながら歌う「あの瞬間を覚えておくよ 今日の景色を忘れないよ」がたまらなく染み入ったこと。そんなアフターアワーズが終わってロビーにあがると、〈どすこい STAGE〉のクリトリック・リスが後方のカーテンを開けて、〈KBSホール〉のステンドグラスの開帳を模していて、そのなんとも言えないショボさに観客から大きな声援とヤジをくらいまくっていたこと。
Photo:岡安 いつ美
Photo:岡安 いつ美
様々な光景を観ながらエンドロールに向かっていく。例年夜が更けていくにつれてゆるやかに観客は減っていくことが多かったが、この日はむしろ人が増えていった。それは大トリのクリープハイプへの期待かもしれないし、最後に流れるエンドロールを観るまでがボロフェスタという楽しみ方の理解が進んだことによるものなのかもしれない。これまでにない混雑具合だったため、終盤の転換時に櫓をフロアの中央まで運んでウルトラマンが踊るダンスタイムはボロフェスタらしいバカ騒ぎだったが少し危険を感じたし、大トリの出番前に主催であるMC土龍が緊迫した様子で、観客の配置を整頓するアナウンスをしていたことには驚いた。街の底ステージには60人ほどの入場制限、ホール内も転換時の入退場を規制するタイミングを設けるなど、人の流れをコントロールする仕組みを例年以上に敷いていただけに、惜しい課題が残ることとなった。
畜年の想いが覇気となった大トリ、クリープハイプ
舞台は整い、改めて土龍の紹介でクリープハイプのライブが〈ORANGE SIDE STAGE〉で始まる。昨年も出演が決まっていたものの直前に尾崎世界観(Vo / Gt)の体調不良でキャンセル。冒頭、尾崎の独白と謝罪からライブはスタートした。「ライブを飛ばすってのは本当にダサい。本当に恥ずかしくて、悔しくて、情けない。そんな……“思わず止めた最低な場面”」と“ナイトオンザプラネット”になだれ込む。噛みしめるように進んでいく演奏は激しいはずなのに、曲と曲の間では息をのむような静寂が漂う。“社会の窓と同じ構成”のサビ前のブレイクでは「拍手するならしてくれ」と尾崎が添えるほどに、その佇まいからは覇気みたいなものが伝わってきて、観客をロックオンしていたのだ。ボロフェスタのステージを踏むのは2017年以来。メジャーデビュー前には土龍が店長を務める〈livehouse nano〉にも出演していたという縁もあり、この場所にも並々ならぬ思い入れがあることを尾崎は語っていた。「nanoから大阪城ホール2 daysまでいきました」「メジャーデビューして10年。土龍さんやりましたよ……」とつぶやくと、「やったねぇ」と土龍がしみじみと応答したシーンはこの日のハイライトだ。最後に“ねがいり”を披露し、ステンドグラスが開帳する。そして演奏を終えると、ゆっくりと去っていくクリープハイプの4人。アンコールもなし。最後に最高潮の熱狂を見せるのではなく、会場にいる全ての人を穏やかに日常へと返すような締めくくりであった。
Photo:渡部翼
散らばった星たちを再び星座にしていく事始めの年
クリープハイプの演奏中。全ての出番が終わった隣の〈GREEN SIDE STAGE〉で土龍が座ってライブを眺めていた。そして自分の持ち場がひと段落したスタッフもぞろぞろとステージに上がり、三角座りでライブを楽しんでいる。まるで間もなく終演を迎えようとしていることを称え、土龍がスタッフたちに特等席を用意したかのようだった。そしてエンドロールの映像がスクリーンに流れ始め、全ての演者とスタッフ、関係者が紹介される。ここまでは例年通りだが、映像が終わると土龍の掛け声と共にスタッフがステージ上で一礼し、観客から盛大な拍手を浴びながら、終演となったのが印象的だった。そこには新しいスタッフたちにボロフェスタをやることの他には代えがたい面白さを伝え、観客にはボロフェスタはスタッフ「も」主役であることをエンドロールと合わせて丁寧に理解してもらおうという、主催メンバーたちの思惑も伺えた。

2022年のボロフェスタを総括するなら、コロナに耐えた20周年を後にして、散り散りになった星たちを再び星座として結んでいこうとするその事始め、といったところだろうか。クリープハイプのリベンジがまさに象徴しているところだが、イレギュラーだった過去2年を取り戻すかの如く「〈KBSホール〉を再びフルに使い、とにかくいいライブを魅せる環境づくり」に特化していた気がする。しかしこの場所は「元に戻る」だけでは黙っていられないはず。ここからまた物語は始まり、面白くなっていくのだろう。安心、安全、でもカオス。そんな混沌としながら成熟していくボロフェスタに来年以降は期待している。
You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com