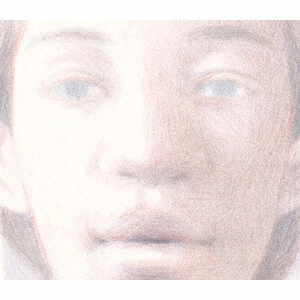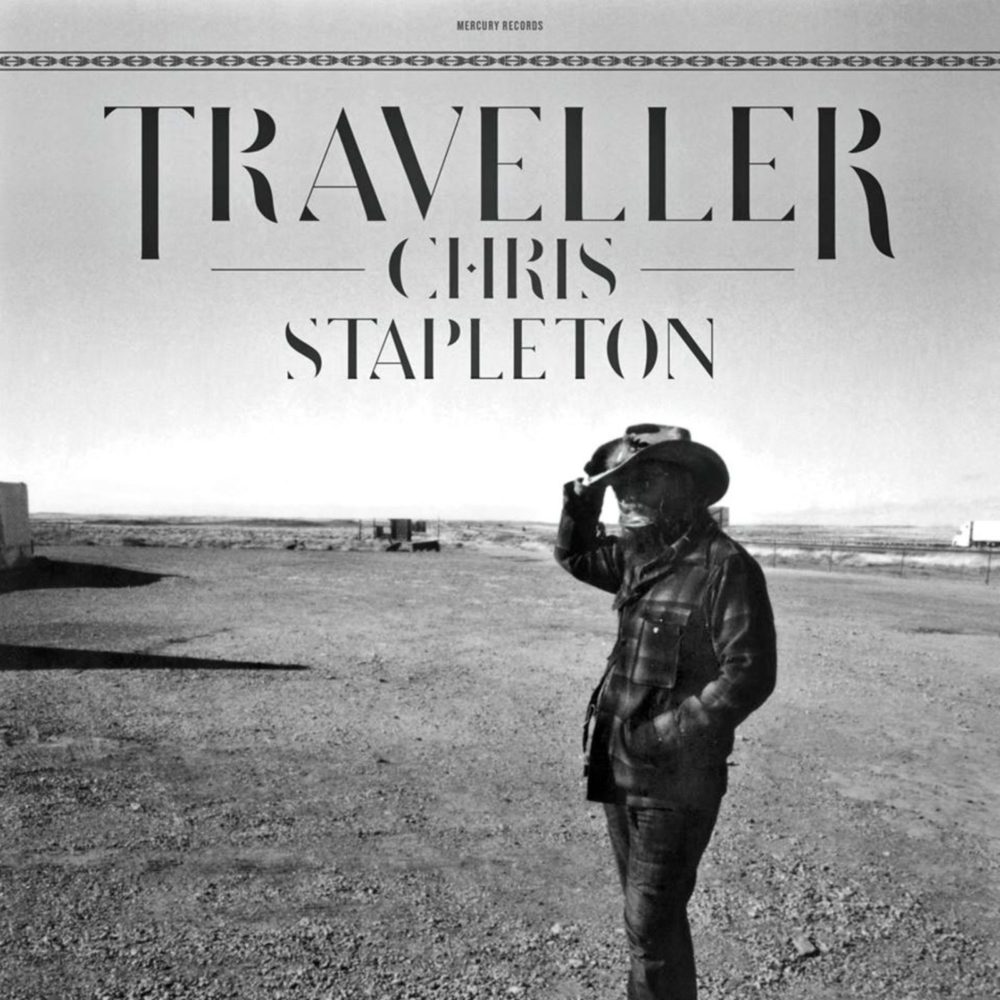峯大貴が見た第2回うたのゆくえ
2019年3月30日~31日に京都・三条VOXHallで行われた『第二回 うたのゆくえ』。東西名うての〈うたうたい〉たちが集結したこのイベントの背景や目的は、事前に公開した主催者 須藤朋寿インタビューに譲るが、結論2日間共に大盛況となった。メインステージであるHALLはもちろん、一階下がったキャパ50人程度のスペース〈十八番(おはこ)〉もステージに立つ演者と観客がゼロ距離で対峙し、終始ぎゅうぎゅうで熱狂のライヴが繰り広げられていた。そしてもう一つの弾き語りステージである屋上の野外ステージも、観客みな三角座りで真っ昼間の空の下、吉田省念や東郷清丸、mmmら(いずれも2日目出演)がゆるりと弾き語りを披露。1日目は曇天模様で西洋彦の出番時には本格的に雨が降り出してきたが、傘に当たる雨音も身近な生活の営みを描く、西の歌の背景となるような特別な光景だった。またその次の屋上出番であった牧野ヨシは雨の影響で、急遽3階のこぢんまりとしたバー風のパーティースペースでの演奏となったが、ノンポリ風情でしっぽり歌う牧野の歌がこの空間にたまらなく合う。予期せぬ事象も歌の力でご愛嬌とし、3会場それぞれの個性が観客を楽しませていた。


うたで選りすぐられた精鋭たちの競演
多くのフェスやイベントで見られるジャンルレスで多様性を持たせたラインナップとは真逆の〈日本語によるうた〉で選りすぐられた精鋭たちの競演。そのため演者はもちろん観客にとっても、互いの音楽性に共通項を見出だしやすく、1シーンのような一体感でもって楽しめる顔ぶれと言えるだろう。一方それがゆえに演者は〈この顔ぶれの中で自分たちはどういう役割を担うのか〉という問いへの回答をステージで課せられているような、どこかヒリヒリとした空気も漂っていたのが印象的であった。
その問いに、ひと際アグレッシブな演奏で答えていたのが最近4人組となった家主(1日目 / 十八番)だろう。やるせない歌と泥臭くジャリっとしたバンドアンサンブルの中で、無邪気に唸り続ける田中ヤコブ(Vo / Gt)のギター。あらゆる生活の中のペーソスを熱量に昇華していくような演奏には、曲が終わるごとに観客からため息が漏れ聞こえてきた。そんな中、最前で感動に立ちすくんでいる様子だったのはバレーボウイズ(1日目 / HALL)のネギ(Vo / Gt)。出番以外は絶えずステージを周り、観客以上に楽しんでいた様子だった。バレーボウイズの出番はまもなく夜に差し掛かろうかという時間。メンバー6人それぞれのエモーショナルを大合唱でスパークさせるパフォーマンスは在りし日の姿だ。この日は特に“ひとのこ”、“ひがしのまち”、“タイトルコール”といった静かに情動掻き立てる楽曲に重心を置き、ドシっとした演奏とハーモニーが冴えわたる。これまでのステージの熱狂に覚悟を決め、開催地・京都のバンド代表としての役目を引き受ける気概を感じた。


前述のヒリヒリした空気というのが最高潮に達したのはバレーボウイズの後のHALLに登場した、1日目のトリであるラッキーオールドサン(1日目 / HALL)だろう。渡辺健太(Ba)、西村中毒(Dr / 西村中毒バンド)、岩出拓十郎(Gt / 本日休演)、田中ヤコブ(Gt / 家主)という新作『旅するギター』の録音メンバーによるバンドセットで登場。それぞれフロントマンとして自身のバンドでも本イベントに出演する東西のプレイヤーを3人も抱えた、トリにふさわしいドリームチームだ。特に後半“Rockin’ Rescue”では岩出とヤコブが周りを振り切るかのようなギターバトルを展開していき、全員が追い付こうとして高まる熱量に会場が沸いた一幕はこの日のベストシーンだ。このバンドのアンサンブルは決して篠原良彰(Vo / Gt)とナナ(Vo)の2人の歌をしっかりバックバンドが支えるような構図ではない。どうやってもブレない歌の掌の中で演奏陣が心置きなくローリングストーンしていって、結果ラッキーオールドサンの楽曲の度量の広さが際立つような演奏であった。

〈音楽の業を肯定する〉ステージの数々
今回の出演者の共通点について主催者 須藤朋寿は「しいて言うならば」と付け加えた上で「自分たちの思想や生活から生まれた想いとかをどうしても歌わずにはいられない人たち」と答えた。現状を変えるため、売れるため、名曲を作るため……何かの目的意識ではなく、ただ歌いたくて、メッセージがあって、ことばとメロディにして歌い続けている。言い換えると〈歌うことをやめてしまうのを恐れている〉とも言えるだろう。
時系列としては遡ってしまうが、1日目のトップバッターを飾った台風クラブ(1日目 / HALL)の石塚淳(Vo / G)は「もう解散してしまったバンドと、いつか解散してしまう俺たちに送ります」と言って久々の新曲“火の玉ロック”を演奏した。「名も無い別れ道が 後ろに去って行く」の部分に象徴される諦めにも似た自身の行く末を案じる歌詞が、哀愁漂うミドルテンポに乗せて開演直後から満員の会場を満たしていく。彼らの立ち振る舞いにかつてのバンド仲間たちの分まで……という勇みはない。むしろ仲間たちに取り残された虚無感が台風クラブの演奏をなおさら愛おしくさせる。そんな今も足を洗うことが出来ない愛すべき音楽不良たちの姿を示していた。

また台風クラブの直後に屋上ステージに登場したのは石指拓朗(1日目 / 屋上)。かなり久々の京都ライヴだと言って、自分を奮い立たせるかのように“朝”から始める。「こんなはずじゃなかったなんて 言わないでおくれよ」と、現在の不安と未来に待ち受ける後悔から逃れようと懸命に今を生きる繊細な心象風景は、石指の歌い手としてのドキュメンタリーそのものだ。MCでは「うたのゆくえって、どこにあるんでしょうね」としばらく自己問答し、“春と夏と秋と冬について”を歌い始める。朗々と巡る季節を綴っていく石指の姿には、年中曲を作って色んな街を行脚し、歌うことを繰り返していくフォーク・シンガーとしての所業が伺えた。

台風クラブや石指拓朗もそうだが、ここのイベントに集められた演者はみな、〈うた〉や〈音楽〉を自身の業であると信じ抜いているようだ。常識も非常識も、立派だろうがカッコ悪かろうが、歌うことが明確だろうが、ぼんやりとさまよっていようが、とにかく理性によって制御できない心の働き(=業)をうたにして、どうにか肯定しようとする様がライヴ・パフォーマンスに表れている。
倉内太はしばらくシンガー・ソングライターとしての表舞台から退いていたが、昨年から再び姿を現し、今回は新バンド・ウエル(1日目 / HALL)で降臨した。ジャケット・スタイルでボーカルに徹し、冒頭“eetto”でバンド名を連呼するその姿はリアム・ギャラガーやスタイル・カウンシル時代のポール・ウェラーを思わせる佇まい。石川真平(Gt)、岡山健二(Dr / classicus)、関口萌(Gt)、のもとなつよ(Ba / Solid Afro、ex.昆虫キッズ)という強力な個性を放つ演奏陣による軽薄と重厚の間を行き来するアンサンブルと混ざり合い、どんどん倉内は邪悪な輝きを纏っていく。最後には上半身裸になりながら、甲高い声を放っていた。ただそこにいるだけで自己表現になってしまうこの日の倉内太の立ち振る舞いには、どうやったってまた歌に戻ってくるしかなかった、という業を感じた。

〈音楽の業を肯定する〉。その姿勢を今最も体現しているバンドといえば、アルバム『二枚目』(2018年)が福田喜充(Gt / Vo)による「今、俺、音楽しかしたくない!」という叫びで幕を開ける、すばらしか(2日目 / HALL)だろう。中嶋優樹(Dr)が欠席によりサポートドラムでの出演であったが、福田がメンバーに手ぶりで指示を出し、加藤寛之(Ba)がバンドのグルーヴを取りまとめていくようなセッション主体の演奏を展開していく。連続性を持たせたステージの中で一区切り置いて始めたのは、直前に訃報が流れた萩原健一のカヴァー“お元気ですか”のみ。荒々しい演奏の中にも律儀なリスペクトを覗かせる点にもロックバンドとしての美学が感じられる。またこの日は林祐輔(Key / Vo)が福田とほぼイーブンにボーカルを取っており、彼の詞曲による“嘘は魔法”は当初のアレンジからどんどん発散していき、徐々にスライ&ザ・ファミリー・ストーン“Thank You”と見境が付かなくなっていく。ロックの首根っこをつかみ、サイケを従え、ファンクを泣かせる孤高のうたを観客に叩きつけていた。

まだまだあるぞ素晴らしいうたの風景
これまで挙げてきた以外にも印象に残っている光景は数えきれない。Easycome(1日目 / 十八番)のちーかま(Vo / Gt)のすごい顔ぶれの中に自分たちがいることの喜びを爆発させながら、今日を焼き付けるように観客一人一人の目を真っすぐ見つめながら歌う愛らしい姿ったら。唯一タイムテーブルがmmmとかぶっていたマーライオン(2日目 / 十八番)は出番前にせっせとチラシを配り、ステージではiPhoneで流したトラックに載せて“アウトレイジ”や“茶道クラブ”などニヤニヤしてしまうような屈託のないラップ披露する。最後は一転ギター弾き語りで素朴な名曲“ばらアイス”を披露する、その突拍子もない二面性をポップに丸め込んでしまう、その愛嬌ったら。


京都在住のフォーク・ギター弾き語り小川さくら(2日目 / HALLオープニングアクト)は初アルバム『日々』収録の楽曲を中心に生活を俯瞰する眼差しの歌が、開演を待つ観客をじっと聴き入らせる。ラストにはなぎら健壱やディランⅡも取り上げた春歌“満鉄小唄”をそぼそぼと歌うところに感じた、硬派なフォーク・シンガーの遺伝子ったら。前回の『うたのゆくえ』ではひとりキイチビールとしての出演だったキイチビール&ザ・ホーリーティッツ(1日目 / HALL)のもどかしく屈託のない歌の魅力は損なわずとも、2回分のバンド・エモーション!とばかりに放つその音圧ったら。6人バンド編成で登場した姫路の至宝、ゑでぃまぁこん(2日目 / HALL)の砂浜を徐々に濡らすアシッドの波のような細やかな演奏と、コーラスで参加していた井手健介の声の確かな存在感ったら。
これからの日本のうたのゆくえを左右するカネコアヤノ、中村佳穂、折坂悠太
そんな素晴らしいうたの風景が2日間絶えず繰り広げられていく中でそれに加えて、やはり今回大きな存在感を放っていたのは2日目のHALLのラスト3枠を飾ったカネコアヤノ、中村佳穂、そして折坂悠太という並びだろう。昨年3月に行われた前回の『うたのゆくえ』に出演していた演者はいずれも、この1年の間に着々と活動を積み重ねていったが、中でもこの3組は2018年にリリースしたアルバムが日本の音楽シーン全体の中で広がりを見せ、新星として評価を得ることとなった。それに伴って今から振り返ると前回の第1回は結果的に〈2018年の日本の音楽トレンド〉を予言していたともいえる。しかし今回の2回目にあたって『うたのゆくえ』はそんなブレイク&ネクストブレイクたちのショーケース・イベントになってしまうことを頑なに拒んだ。それゆえに2日間へと拡大し、山本精一、吉田省念、ゑでぃまぁこんといった、他の演者ともしっかり繋がって〈うたの系図〉が見えるような世代上の演者も招集、今一度コンセプトを研ぎ澄ませて説得力を持たせた。そうした上で名実ともにこれからの日本のうたのゆくえを左右する存在となったカネコアヤノ、中村佳穂、折坂悠太を大看板として迎え入れる舞台を用意したのだ。
カネコアヤノは盤石なバンドセットを従えて登場。マイクに向かう姿は勇ましい。新曲“愛のままを”、“セゾン”も含めて誰の心の中にもある感情の機微を捉えた言葉で綴られる歌は、ゆえに鋭利なほど真っすぐな力を持つ。鋭い眼光ともに観客一人一人の心にうたを突き刺していくような力強いステージであった。続く中村佳穂は、客が全然いない頃からVOXhallに出演してきたホームグラウンドへの凱旋ということで、リハから観客のご機嫌を伺いながらサービス精神満載で盛り上げていく。深谷雄一(Dr)を引き連れた2人セットで、“アイアム主人公”ではタイマンを張るようにヒートアップし、一転最近できたという新曲ではノートを見ながら演奏する中村を深谷が静かに支えるなど、阿吽の呼吸で自在の組手を見せていく。さらに後半ではDaichi Yamamotoを呼び入れ、即興でラップをフィーチャリングするなど大盤振る舞いだ。会場の歓声に主催者 須藤朋寿から「時間あるからもう1曲」との指示を受け、急遽予定になかった“口うつしロマンス”も披露するなど、このイベントのお祭り騒ぎを一層華やかに盛り上げるステージを見せた。

そして大トリは折坂悠太。約10日間ほど京都に滞在し、yatchi(Pf / ムーズムズ)、宮田あずみ(Ba / かりきりん、Colloid)、senoo ricky(Dr)という京都で活動するミュージシャンたちとの〈重奏〉編成での初演奏となった。ラジオのノイズを流して今日の日付をポツリと呟き“平成”を始める折坂の歌と、音数は最小限に絞られた〈重奏〉のアンサンブルは、この場にいる一人一人が自分が生きた時代に対する想いを投影する隙間を残すかのように、研ぎ澄まされていた。ここ数年パーマネント・バンドとしていた〈合奏〉編成は、多様な音楽性の抱擁と新たな歌の可能性へのトライアルを実現させてきた〈重奏〉編成はそこから趣を変えて、折坂の歌の響きを最大限に拡張することに重きが置かれている。イベントのコンセプトである東西のうたをつなぐ意味も携え、この日を新たな試みのスタートとした折坂のステージは、立ち会った人々と共に平成という時代にとどめを刺すようであった。
それは平成の最後を飾るスポットライトなんかじゃない。この2日間は、ここからそれぞれの〈うたのゆくえ〉を探していこうと、次の時代に向けて決起するスタートラインになったんだ。古くから言われる〈うたは世につれ、世はうたにつれ〉をこれから体現していくのは、あの日、あの時、あの場所にいた、私たちからだ。

You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com