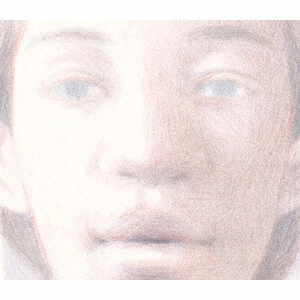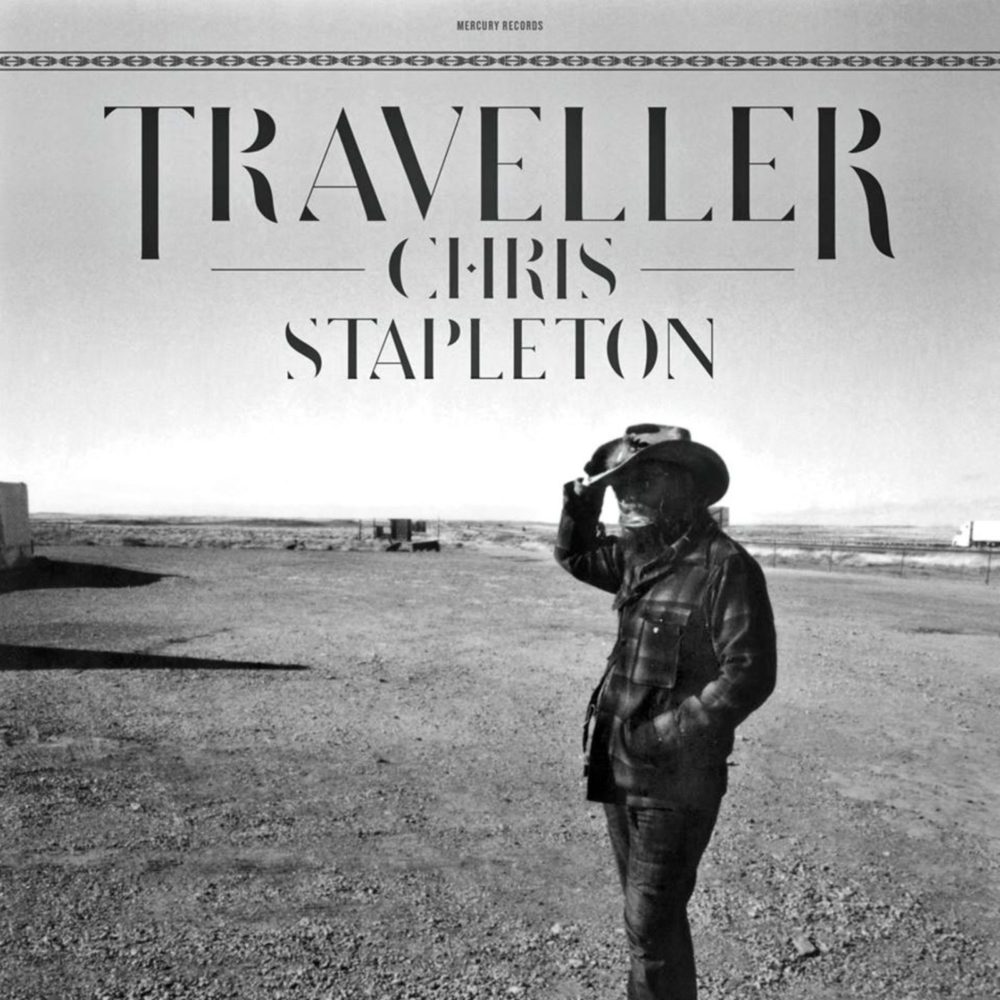休日に音楽を続ける人たちのドキュメント-松ノ葉楽団3rdアルバム『Holiday』リリースインタビュー
「松の葉につつむほどのわずかなもの」という意を示す、贈り物の添え書き。そんな言葉を冠した松ノ葉楽団は京都を中心に活動する4人組である。彼らの音楽はバンド名の如く、心配りに溢れながらも、ちょいと人の心の茶の間にお邪魔し、謹製のグッドタイム・ミュージックをお届けするようだ。2008年の前身バンド結成から、メンバーの入れ替わりや音楽性の大きな転換も経たつづら折りの道のりは、昨年10周年を迎えた。その結果たどり着いたのはアコースティック楽器を主体として、スウィング・ジャズやジャンプ・ブルースをゴキゲンに鳴らしていくスタイル。しかしあくまでど真ん中に据えられているのは松葉ケガニ(Vo/Gt)の歌なのだ。強いメッセージを込めるでも、ドラマチックなストーリーテリングを担うわけでもなく、まるで純文学のように訥々と言葉を並べていく。細やかであっけなくって、でもそこに滲む生活の匂いと感情の機微こそが松ノ葉楽団の音楽の本質なのだろう。
約2年に渡る松葉のフランス・パリでの移住期間を挟み、3年ぶりのアルバムとなった3作目『Holiday』は、全8曲を通してある休日の1日を描いている。それは同時にそれぞれ仕事や家庭もある生活の中で、どうしようもなく音楽に興じてしまう、彼ら自身のドキュメントでもあるのだ。
初のメディア・インタビューとなる今回は、ライヴハウスを飛び出して、いたるところで演奏を展開する特異なスタイルと音楽性に至った経緯、そして最新作『Holiday』に宿る曲作りの美学について松葉ケガニと松岡亮(Gt/ウクレレ)に話を聞いた。何を隠そう松葉は昨年までアンテナ・メンバーとして連載『ブンガクの小窓』を中心に数々の記事を作ってきた同胞だ。今は違う道を歩む彼の今の姿を捉えることは、アンテナの現在地を確認する作業のようにも感じた。音楽や文学は常に交錯し、越境することでなお輝きを放っていく。
残された3人がたどり着いた、スウィングとブルース
バイオグラフィー上では松葉さんを中心に2008年に前身バンドPLANETZを結成。当初は全く違った音楽性だったとのことですが、メンバーの入れ替わりや紆余曲折は公式サイトに10周年コメントとして詳細に書かれておりました。なのでこのインタビューではまず、今のアコースティック編成でルーツ・ミュージックに根差した歌ものをやるという音楽性に至る経緯から伺えればと思います。
PLANETZの頃はジャンルに限定せず、ポップなものからオルタナティブ・ロックや、ソウルまで色々やっていて。そこから歌詞の文字数を減らして、使うコードの数を減らして、一番簡単な方法で、一番いいと思うものを実現したいと思うようになったんです。色んな要素を取り除いて好きな音だけを残していったら、ジャイブ、スウィング、ジャンプが残っていきました。
元々松葉さんはロック・バンド的なサウンドよりもそちらの方が音楽のルーツにあったということでしょうか?
ブルースは中学の時から好きでしたね。中学の時に来た教育実習の先生がエリック・クラプトンの“Tears In Heaven”を弾き語りしてくれて。その時にかっこええなと思ったんです。今思ったらだいぶ変わった先生ですね。でも両親も音楽が好きでレコードが流れている家でしたし、それでクラプトンの原曲を聴いたり、家にあったブルースのスタンダード・ナンバーが入っている30枚組のCDボックスを片っ端から聴いていったりしていました。
なかなか当時ブルースで話が合う人やバンドはいなかったでしょうね。
そうですね。でもジャズは大学でサークルにも入っていて、スウィング・ジャズをビック・バンドでやっていました。カウント・ベイシー楽団やデューク・エリントンは好きでしたし、スモール・コンボでニューオーリーンズ・ジャズをやるインスト・バンドは周りにいましたね。だからバンドでスウィングを取り入れることに関しては、そこまで変なことをやっているという意識はなかったです。

ではロック・バンドのスタイルをとっていたところから、自分のルーツに近い方向へとそぎ落としていく、きっかけはなんだったのでしょうか?
当時先輩にザ・ベクトルズがいて、Superfriendsや、ザ・ルージーズのような3~4ピースのエレキギターが主体のかっこいいバンドが周りにいたから、こうでなきゃという固定概念がありました。でも自分がやっている内に土龍さん(Live House nano)に「松葉はアコギの方がいいんじゃない?」とアドバイスをもらって。Superfriendsの塩原さんには「おじいちゃんみたいな声だからアコギの方が合うよ」と言われたり(笑)。
松葉さんのルーツや素養が見抜かれていたんですね。
あと外的な要因も大きいです。当時のドラムが上京して脱退してしまって。ドラムレスのバンドは出来るジャンルも限られてくるじゃないですか。なので徐々にスウィングや、ブルースに集中し始めたというのもあります。
それが松ノ葉楽団に改名して直後の6年前くらいですね。ドラムが抜けて、ベースも仕事が忙しくてなかなか参加が出来なくなっていった。それで残った松葉君と、自分とかんじょうさん(かんじょうえみ、Pa / ピアニカ)と3人でやることが多くなって、今のような音楽になっていった部分もあるかもしれないです。
松岡さんはちょうど音楽性が変わりつつある時期に加入されたようですね。
自分は今も並行してやっているthe pumpkinsというバンドで、3ピース時代だったPLANETZと対バンした時に知り合いました。当時から松葉君の歌詞はフォークぽくって深みがあるなと思っていたんです。そこから2年ほど間が空いて、久々に見たら今の松ノ葉楽団がやっているようなスタイルになっていて、その頃からサポートで関わるようになりました。
「アルコールの匂いのする生活の歌」とか言い始めていったのもその頃からで。そうするとライヴハウスが主戦場じゃなくなっていったんです。居酒屋、ラーメン屋、串カツ屋、インド料理屋、銭湯、お寺、路上……。
今の音楽性になって、活動の場がぐっと広がりましたね。プラクドしなくていいし、マイクがなくても楽器と体だけ持って行ってどこでもやりますよと。

歌詞をそぎ落としていく曲作りのこだわり
確かに音楽性という意味でもそうですし、一人欠けると演奏が成り立たないロック・バンド編成から脱したことで、極端な話、欠員が出ても対応できる懐の深さと柔軟性が松ノ葉楽団の音楽には感じられます。でも基本的には松葉さんの歌がど真ん中にあるじゃないですか。そういうスウィングやブルースをどのように消化していったのでしょうか?
僕は元々12小節のブルースしか認めないようなハードコアなブルース・ファンだったので、メロディやコード進行においては、ジャンルのフォーマットに乗っかって作るのは難しい。だけどスウィング・ジャズはドミナント・モーションなどの基本的な動きがあれば、転調やコード進行も自分にとってはすごく自由な音楽で。だから曲が絶対的なものとしてあって、合う要素をかいつまんで取り入れていくという感じですね。
だからジャズもブルースもフォークも特化している人たちにとっては、ルーツ的ではないと思われるかもしれません。でも極端に言えば松葉君の歌詞と曲さえあれば、松ノ葉楽団の音楽になるんですよ。あとは自由でこんな感じかなと肉付けしていく作り方ですね。
まずは歌詞と曲ありきということですが、松葉さんの曲作りのこだわりはどういうところにありますか?
数えきれないほどありますが……。一番は初めてライヴを見た人に歌が聴き取れてしっかり伝わること。だから音節の区切り方とか単語の選び方はかなり考えていますね。なので英語も使わないようにしています。でもスウィングやシャッフルのリズムに日本語って乗りにくいんですよね。不自然に聴こえがち。そこは吾妻光良さんの詞はやっぱり天才で理想的やなと思います。あと関西のブルースとかソウルをやっている人たちのグルーヴの乗せ方も見事。関西弁の言語の力でねじ伏せているところもあるんですかね。
確かに。上田正樹とサウス・トゥ・サウス、憂歌団とか、ウルフルズなんかもそんな感じする。
あと文字数を極力少なくしたいんです。AメロとBメロだけで出来ていて、サビすらないような小さい曲が好き。俳句を作るみたいに6文字を何とかして5文字に収めようとする歌詞作りも好きでこだわっていますね。
なぜそこまで歌詞や曲の構成をそぎ落とすことに美学を持たれているのでしょうか?
うーん……。そこまで多くのことを1曲で伝えられると思っていないんですかね。本当のことを言うと、最初のAメロ8小節くらいで言いたいことは言っちゃっている。そんな曲の方が印象に残るというか。そんなに大げさなことは言いたくないんですよ。
ではどういうことを歌いたいと思っているんですか?
短編集を読むのが好きで。芥川龍之介、川端康成、志賀直哉とか。読み込んでいると、ちょっとした心の動きが陳腐じゃなく表現されているところがあって、そういうところを曲にしたいです。物語やメッセージよりも、日常にある心の動きを言語化したい。あとは高田渡さんが好きな詩人が好きです。生活詩人と言われる人たち。
“ごあいさつ” や “アイスクリーム” なんて短い曲の極地ですもんね。高田渡が取り上げた詩人で言うと山之口獏や、金子光晴でしょうか?
そうです、そうです。でも金子光晴の詩は長いのも多いですよね。石原吉郎、添田唖蝉坊、山之口獏とか。山之口獏で確か自分の下駄を娘が履いていっちゃったと、ただそれだけの詩があるんです(ミミコの独立)。自分に娘はいないですけど、あの短い表現で、同じ気持ちになれるのがいいなと思います。
今回の作品『Holiday』は今までの作品にも増して、1曲の時間が短いですよね。ほぼ3分以内で、ラスト2曲のM7“Girl In A Poster”、M8“Midnight Special”も3分台。
詞のサイズ感がそれで完結しちゃうから自然と曲も短くなった。
やはりテーマと曲の長さって比例するべきで。そこを無理やりふくらますと不自然さがバレてしまうんですよね。なんでもっとみんな短い曲を作らないんですかね?
物語を描きたいんじゃないでしょうかね。あとはメロディや楽曲の構成を先に作って、詞を乗せるという工程だと、それに応じて長くなる。
あーなるほどなぁ。
ロックとかポップスだと曲の中に山と谷を描く必要があるから、歌詞以外のところでボリュームが出てきてしまうんでしょうね。でも短い方がいいよね。ライヴでも曲数いっぱい出来るし(笑)。
自分は聴いていて、そんなあっけなさこそが松ノ葉楽団の魅力だと感じました。今作の中ではM4 “あかりがつけば” が一番好きなんですけど、松葉さんの朴訥な声で「長い映画のような 恋はおわりさ」と歌われて、サッと過ぎ去っていく。このキレがよくって取り残されたような心地がたまらなく切ない。
この曲のメロディは松岡さんが作っているんです。純文学とか、ブルースの歌詞もそうなんですけど、しんどいことを表現していても湿っぽくならず、カラっとさせたくって。大げさじゃない表現は目指していますね。
NEXT PAGE
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com