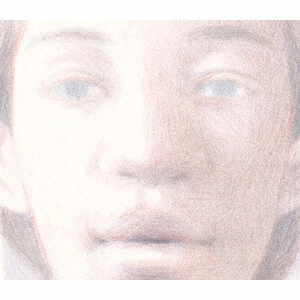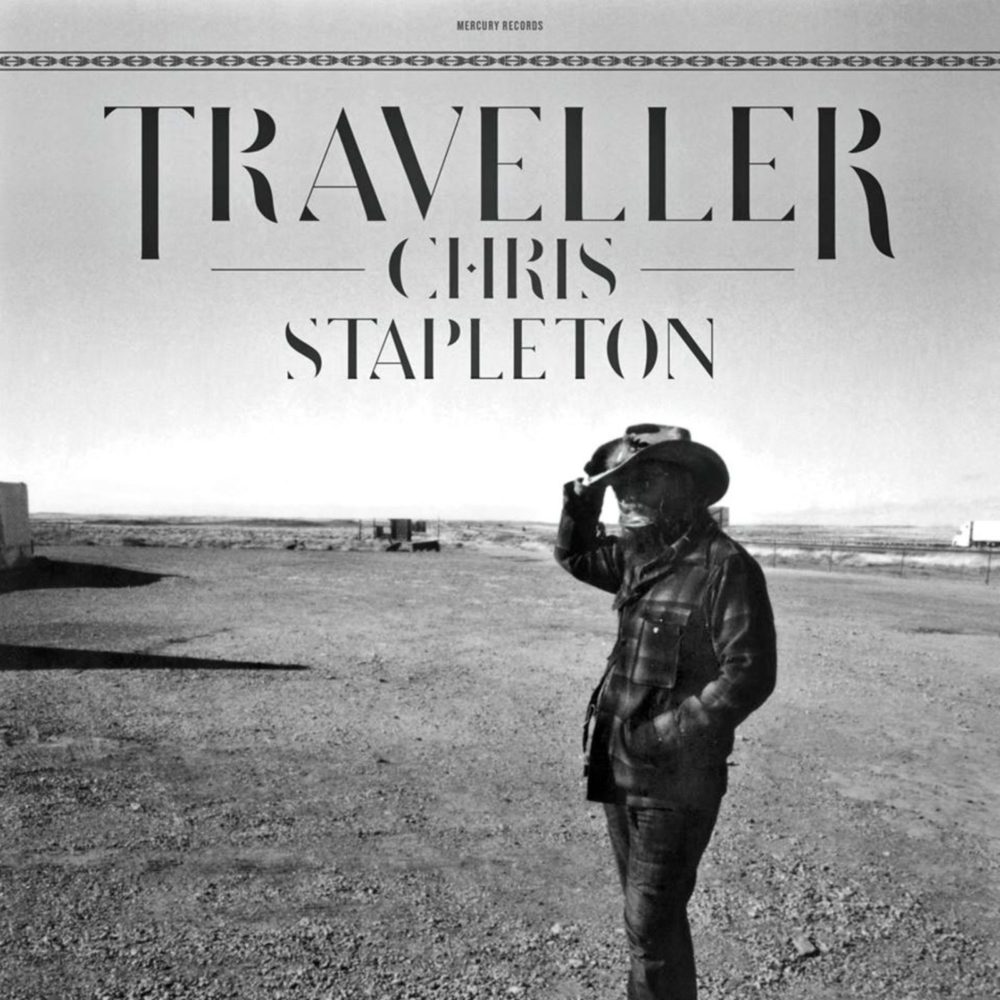峯大貴が見たボロフェスタ2021 Day3 – 2021.10.31
20周年を迎えた、京都のフェスティバル『ボロフェスタ』。新型コロナの影響もあり、2年ぶりとなった今年は、2週連続6日間に渡って開催されました。2014年から毎年ライブレポートを掲載してきたANTENNAでは今年も編集部あげての総力取材!全6日間の模様を各日1名のライターによる独自の目線で綴っていきます。本記事では10月31日の模様をハイライト。
KBSホールに入ったところにあるロビーにも、ステージが設置されるようになったのは2013年から。今までにこの場所ではトークショーが開かれたり、スカートや中村佳穂、折坂悠太、眉村ちあきといった今ではすっかり人気者の面々が立っていたり、またある時は高座となって落語家の立川吉笑が上がったり、そしてなにより演者と観客の見境をなくすカオスなパフォーマンスでボロフェスタのインディペンデント精神を体現し続けている2人、クリトリック・リスとボギーが一番輝く場所でもあった。入り口からホールへの導線にあることで偶然の出会いがあったし、ちょっと休憩がてらで観ることができるなど、ホールや地下ステージとまた違う重要な役割を果たしてきたのだった。
しかし地下ステージと共に取りやめとなった今年。このロビーには過去20年のフライヤーと名場面の写真が掲示されていた。でんぱ組.incは2012年に初出場していたのか。2013年のソウル・フラワー・ユニオンと非常階段とBiSが合体し、紙吹雪や笹蒲鉾が撒かれたカオスなステージは本当にすごかったなぁ。くるりが初めて出演したのは2015年ともう6年前なのか……とこの日観る演者の過去の出演を振り返りながら、一息つくのも20周年ならではの楽しみ方だ。今回の6日間の中でも、積み重ねてきた歴史が織りなすつながりや縁にひと際溢れていた心地がしている10月31日のハイライトをお届けしよう。

今年はなき、地下ステージから愛を込めて
まず目を引いたのがハンブレッダーズからTHE FULL TEENZにつながる美しいバトン。2019年にも両者は出演しているが、同日かつ出番が並ぶのは初。それぞれのフロントマンであるムツムロアキラ(Vo / Gt)と伊藤祐樹(Vo / Gt)は中学の同級生として出会い、長らく交流のある間柄だ。虚空を貫くように澄み切った蒼さと思春期のきらめきを鳴らしているという点でも、同じ目線を感じる二組である。ハンブレッダーズは見据える視点が一昨年よりも一段階上がったような風格をまとい、メインのORANGE SIDE STAGEがひと際お似合いなバンドとなっていた。楽曲の届く範囲はメジャーデビューも経験して広がれど、常にハンブレッダーズの歌の主人公はリスナーやこの場にいる観客に据えられているところに魅力が詰まっている。中でも新曲として披露された“再生”は「BOROFESTA NEVER DIE」という今年掲げられたボロフェスタのテーマと見事に呼応していたし、“不特定多数に向けられた歌に興味はないよ/僕の感動とお前の「エモい」を同じにすんな”という歌詞はこのステージを見ている人しか味わうことができないリアルな感動を見事に言い当てていた。そして最後に演奏した“ライブハウスで会おうぜ”でもこの場にいる一人ひとりの感動と孤独を歌い上げる。この曲のMVやジャケットにも〈livehouse nano〉が登場しており、ボロフェスタという居場所を再確認するような演奏と歌唱で、GREEN SIDE STAGEにつなげた。
そんなバトンを生粋のnano育ちであるTHE FULL TEENZが2マンライブのように引き受ける形で、疾走していくようなショート・チューン“Sea Breeze”から始めていく。3人の鳴らす「蒼さ」は伊藤祐樹が自分の青春期に語り掛けることで色彩が帯びていく心地がする。だから2014年以降、幾度もボロフェスタのステージに立ってきたが、年を経るごとにその「蒼さ」はどんどんまぶしく輝いていくのだ。まだ発売が決まっていないという『メモリーレーンep』からの新曲も複数披露。最後に伊藤が「ずっとボロでいてください」と言って締めたところには、この場所で育ったものとしての役割を果たせた満足感すら感じられた。
ハンブレッダーズもTHE FULL TEENZもこのボロフェスタで最初は地下ステージから出演を果たし、その後も出演を重ねるごとにホール内のステージへと這い上がって来た。TENDOUJIもその内の一組で、MCでは地下ステージを「独房ステージ」と表現し、ひどいながらに上手く言い当てていた。でもそれは、あの息もしにくい熱気むんむんの場所が今年ないことに対する寂しさの裏返しのようにも思える。だからこそ京都の地元バンドである踊る!ディスコ室町が、一昨年の地下ステージから遂にホール内でのステージに初出演を果たしたのも感慨深かった。6人のメンバーに加えて、パーカッションとホーンを加えた豪華9人編成。常に密接に身体を寄せ合う地下では出来なかっただろう大所帯による豊かなサウンドと前のめりなファンキー・グループからは少しの緊張と、気合いがひしひしと伝わってくるようなステージを魅せていた。
笹蒲鉾で更新されるBiSとソウル・フラワー・ユニオンとの縁
BiSも2011年から幾度となく出演しているが、第3期の現体制となっては2度目のボロフェスタ。ロビーに設置されたスタッフお手製のボロッター(Twitterを模したコメントブース)には京都出身のメンバー、トギーの凱旋を祝福するメッセージが溢れ、また出番前にはフレディ・マーキュリーに扮した土龍の合図で開いたくす玉から「KBS武道館ビス」と書かれた垂れ幕が現れるなど、ウェルカムなムードで登場。4人の全力パフォーマンスはすっかりこの場所の重要因子となっている。
BiSの終演後、ボロフェスタ代表の飯田仁一郎がステージに上がり、宮城県女川町のかまぼこ店「蒲鉾本舗 高政」から笹蒲鉾が送られてきたので、次の出番のソウル・フラワー・ユニオン終了後にホール前で配布することがアナウンスされた。この蒲鉾は2013年のソウルフラワーBiS階段のステージでも観客に撒かれたもの。そもそもは2011年に東日本大震災が起こり、ソウル・フラワー・ユニオンの中川敬(Vo / Gt)が女川町を訪れた際に、瓦礫に埋まったターンテーブルを偶然見つけ、Twitterにその写真をアップした。そのターンテーブルの持ち主が高政の社長であり、ソウル・フラワーの大ファンでもある高橋正樹だったのだ(ソウル・フラワー・ユニオンはこのエピソードを元にした楽曲“キセキの渚”を同年に発表している)。その縁で2011年にソウル・フラワー・ユニオンがボロフェスタに出演する際に高橋もトークショーに出演することとなり、その際に見たBiSに衝撃を受けたという流れがある。そこから2013年の伝説のコラボ・パフォーマンスを経て、この度ボロフェスタ20周年を祝し、笹蒲鉾が寄贈されたということだ。
そして満を持してソウル・フラワー・ユニオンがリハーサルも兼ねたヘヴィなサイケ・ロック、“グラウンド・ゼロ”から幕が上がる。LIKKLE MAI(Cho)が「ANGER IS AN ENERGY!」と書かれたプラカードを掲げると早速そちらこちらで観客の拳が突き上がった。中川敬はこの場所ではほぼ最年長であることをMCで嘆きつつ、なるだけたくさんの曲をやるべくいつもの雄弁を引っ込め、矢継ぎ早に演奏が続いていく。そして中盤に呼び込んだのはオリジナル・メンバーの伊丹英子(三板 / Cho)。ここ15年以上、ソウル・フラワー・ユニオンのライブの最前線からは退いているものの、最近また頻繁に飛び入りゲストとして登場しているバンドの精神的支柱だ。そして中川がここばかりは丁寧に伝えなければと阪神・淡路大震災が起きた時のエピソードを話し“満月の夕”を披露した。その後も代表曲“海ゆかば 山ゆかば 踊るかばね”や“風の市”、これほど率直なステイトメントはないというほどの抗う人々の歌“ダンスは抵抗”など、力強い楽曲を披露し、あっという間に終焉。何も制約がなかった頃のようにシンガロングもお囃子も本当は思いっきり入れたかっただろう。しかし手をひらひらとさせながらステージに目線を送る観客の光景に彩られた、ソウル・フラワーのステージもまた格別だった。
また2013年のソウルフラワーBiS階段は経験していない、第3期のBiSメンバーも新鮮に楽しんでいる様子が会場の後方で伺えた。そしてその後、ホール前で配られる笹蒲鉾に行列を成す研究員や観客。女川町の復興から繋がったソウル・フラワーとボロフェスタ、そしてBiS。東日本大震災からちょうど10年経った今また思い出す機会となった二組がつなぐ笹蒲鉾のバトンは、縁という意味ではこの日最大のハイライトだった。
いつかは僕たちも離れ離れになるのだろう?
そしてトリにはくるりが登場。岸田繁(Vo / Gt)、佐藤征史(Ba)に加え、松本大樹(Gt)、野崎泰弘(Key)、石若駿(Dr)の5人がリハーサルで“太陽のブルース”を披露し、一度退場する際には拍手が起こった。いつもは演者に対する情感をたっぷり込めて紹介する土龍も、今年は制限のあるルールを敷いた中で存分に遊んでくれた観客に対する詫びと感謝、そして来週も続くことを告げた後、「くるりの登場です」とシンプルに紹介した。迎え入れる際の拍手はくるりに対するものだけでなく、ここまで無事に1週目を終えることが出来たねぎらいの意味もあるような気がした。そして祝辞はウェットな言葉ではなく演奏や振る舞いで示していくもの、と言わんばかりに岸田が「おめでとうございます。よろしくお願いします」と軽くあいさつしたのち、飄々と“コンチネンタル”からスタートしたのがたまらなく粋だった。“watituti”など『天才の愛』収録曲を核としつつも、“花の水鉄砲”や“アナーキー・イン・ザ・ムジーク”など、この5人によるとにかく固くて獰猛なアンサンブルで再解釈された楽曲が演奏される。途中には新庄剛志が日ハム監督に就任したことを受けて、まるで予言のような曲になったというエピソードが語られ“野球”を披露したが、緊張感を持続させたまま淡々と演奏を続ける謹製のくるりがそこにいる。しかし後半には“ばらの花”から“ハイウェイ”と代表曲が連続で披露されると徐々に興奮とそろそろ終わってしまうんだなという寂しさが沸き上がってきた。
この日ステンドグラスが開いたのはアンコールの“HOW TO GO”のイントロのリフがなったとき。くるりの中でも演奏者のグルーヴがぶつかり合い、バンドのロマンと色気がここぞとばかりに発揮されるという意味で、荘厳に光り輝くステンドグラスに一番合う曲を選んだようにも思える。そんな京都のロックバンドと京都のフェスティバルの思惑が重なり、見事な終演を迎えた。
電車で帰路についている最中。(30日のレポートの冒頭で触れた)2019年の開催が終わった後に感じた「ボロフェスタに行くのは最後になるかもしれない」という気持ちと、2年ぶりにこの場所を体験した感覚を照らし合わせながら、会場で販売されていた20周年記念のZINEを読んでいた。そこでの主宰者座談会で飯田仁一郎が語っていた言葉がすっと私の胸に飛び込んだ。
“僕は、やりたい人は来たらいいし、出たい人は出て行ったらいいと思っているんですよ。どっかで忘れずにいてくれたらそれでいいぜ、いつでも間口は開いているぜ、みたいな”
読んだ瞬間、ボロフェスタという場所にこだわり続けることも、行くのは最後とピリオドを打つ必要もないのだと腑に落ちた。またどうせ来年のこの時期になったら〈KBSホール〉に足を向けたくなってしまうのだろう。ましてや今年はこの31日の参加で切り上げてしまった私だ。翌週のLimited Express (has gone?)も、ボギーも、クリトリック・リスも、そしてエンドロールだって見れなかったんだから。しかし今年、どんなかたちになってもボロフェスタを続けていくという覚悟は十分に受け取った。その姿勢に「また次の一年」と背中を押してもらったような気がしている。
You May Also Like
WRITER

- 副編集長
-
1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。
OTHER POSTS
ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。
過去執筆履歴はnoteにまとめております。
min.kochi@gmail.com